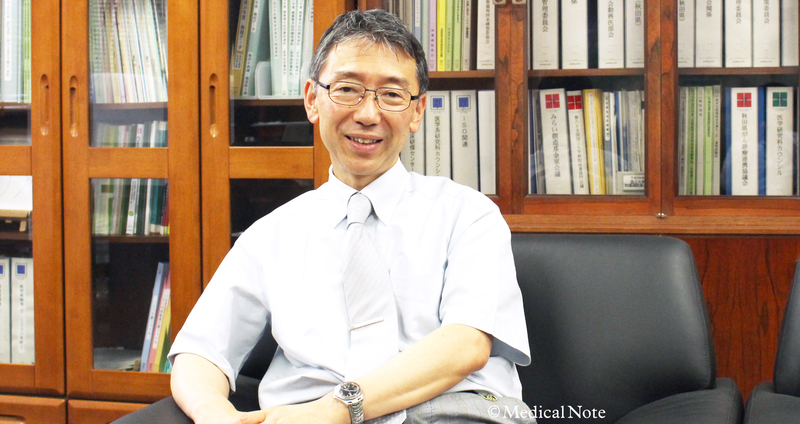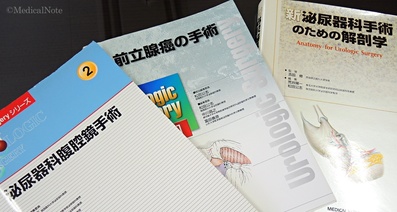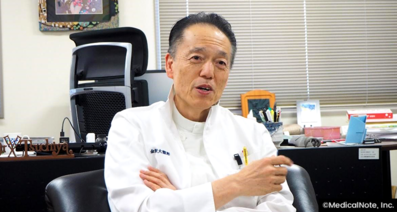

加齢とともに発症頻度が増える腎臓がんは、人口の高齢化や人間ドックなどの普及に従い、日本で増えているがんのひとつです。どのようなリスク因子を持っている場合、腎臓がんになりやすいのでしょうか。また、治癒を目指せる早期段階で自覚できる症状はあるのでしょうか。知っておきたい腎臓がんの基礎知識について、秋田大学医学部附属病院泌尿器科科長の羽渕友則先生にわかりやすくご解説いただきました。
腎臓の機能-どこに位置し、どのような役割を持つ?

腰のやや上に、左右一つずつ位置する腎臓は、次のような役割を担う臓器です。
老廃物を尿中へ排出する
腎臓は、「フィルター」としての役割を持っています。血液によって運ばれた尿素窒素などの老廃物は、腎臓で濾過され、余分な水分とともに尿として体外へと排出されます。
イオンバランスと血圧の調整
体を巡る体液のなかには、ナトリウムやカリウムなどのイオンが含まれています。腎臓はこれらのイオンバランスをコントロールしており、結果として血圧が正常に保たれます。
そのため、腎機能が低下してしまいナトリウムが過剰になると血圧が上昇してしまい、高血圧になるリスクが高まります。
また、血流を確保するために、腎臓からは血圧を上昇させる物質であるレニンが分泌されています。
造血ホルモン・エリスロポエチンの分泌
赤血球を増やすための造血ホルモン、エリスロポエチンを分泌するのも腎臓の役割です。エリスロポエチンが骨髄にアプローチすることで、赤血球がつくられます。
ビタミンDを活性化し、カルシウムを調整する
摂り込んだ飲食物などに含まれるビタミンDは、腎臓で活性化されます。活性化されたビタビンDは、小腸におけるカルシウムの吸収を助けます。
また、尿に排出されたカルシウムの再吸収も、活性化されたビタミンDの作用です。
左右の腎臓はそれぞれ同じ役割を持っている
左右の腎臓はそれぞれ同じ機能を1:1の比率で担っているため、片方を摘出しても、残った腎臓の機能が正常であれば、QOL(生活の質)に大きな影響は生じないという特徴があります。
両腎の機能を合計で100%としたとき、25%が残っていれば通常の日常生活に大きな支障は出ないともいわれており、実際に腎臓がんなどにより片腎を摘出された患者さんでも、これまで通りの食事や運動を楽しみながら過ごされています。
※腎臓摘出後の生活については、記事2『腎臓がんの手術治療と術式ごとの入院期間や再発率』で詳しくお話しします。
腎臓がんの種類-淡明細胞型腎細胞がんが最も多い
腎臓に生じる腎細胞がんは5つの種類にわけられますが、そのなかでも最も多いのは、淡明細胞型腎細胞がんです。淡明細胞型腎細胞がんの性質はさまざまで、肉腫様変化を伴うものは治療が難しくなる傾向があります。
次いで多いのは乳頭状腎細胞がんですが、割合は全腎細胞がんの約15%と高くはありません。
なお、尿道上皮(腎臓でできた尿を運搬する腔)にできる腎盂がんは、腎臓の実質にできる腎細胞がんとは異なり、腫瘍の性格や治療法も全く違います。
増える腎臓がんの患者数、その理由
腎臓がんは60~70歳代に多い
日本における腎臓がんの患者数は増加傾向にあります。この理由は、大きく3つ挙げられます。
一つ目の理由は、腎臓がんが60~70歳代で発症しやすいがんであり、高齢化と共に罹患者数自体が増えているためです。
もう一つの理由は、検診制度の普及です。職場などで腎臓の超音波検査が実施されるようになったことで、過去にはみつからなかった腎臓がんが発見されるようになったことも、患者数増加の一因と考えられています。
また、食生活の西欧化・肥満者の増加なども関与している可能性があります。
腎臓がんの3大リスク因子

腎臓がんのリスク因子は、(1)肥満、(2)高血圧、(3)喫煙といわれています。
肥満と腎臓がん-脂肪細胞から分泌される物質が関与
腎臓がんと肥満の関係については、世界で研究が行われています。現時点では、脂肪細胞から産生されるアディポカインが、腎臓がんの発症を促進するのではないかと考えられています。
肥満と相関関係があると考えられる腎臓がんは、他の腎臓がんに比べ大人しい性質を持っており、同じ病期(ステージ)で発見されたとしても治療成績がよくなる傾向があるとされています。
高血圧と腎臓がん-酸化ストレスが関与
高血圧により動脈硬化が生じ、腎機能が悪化することが関係しているといわれています。また、高血圧が酸化ストレスを亢進させ、遺伝子に傷がつくことで腎臓がんを発症するとも考えられています。
腎臓がんは女性に比べ男性に多いがんですが、この理由も、男性のほうが酸化ストレスが多いことに起因しているのではないかと考えられます。
喫煙と腎臓がん
肺がんや膀胱がんほどの相関関係はないものの、喫煙も発症に関与していると考えられています。
現時点でわかっている腎臓がんのリスク因子は、上記の3点です。ただし、非喫煙者で痩せている女性など、上記すべてに該当しない場合でも、腎臓がんを発症することはあります。
腎臓病と腎臓がんは関係している?
末期腎不全の場合は腎臓がんのリスクが上がる
腎炎などの腎疾患があったとしても、それにより腎臓がんになりやすくなるわけではありません。
ただし、透析治療が必要な腎不全に至っていると、乳頭状腎細胞がんを発症しやすくなるといわれています。そのため、透析治療を受けている患者さんに対しては、1年に1度CT検査を行っています。末期腎不全患者さんの腎臓にがんがみつかった場合は、腎全摘出術の適応となります。
※腎全摘出術については記事2『腎臓がんの手術治療と術式ごとの入院期間や再発率』をお読みください。
腎臓がんと遺伝の関係
遺伝の影響は比較的少ない
乳がんなどは遺伝子異常が大きく関わるがんとして知られていますが、腎臓がんと遺伝子の関係はそれほど強くありません。
人種差をみると、アジア人に比べ欧米人に多くみられますが、この原因は解明されていません。
ただし、難病のひとつであるフォル・ヒッペル・リンドウ病の患者さんの約5割は腎臓がんになるといわれています。フォル・ヒッペル・リンドウ病は、常染色体優性遺伝という遺伝形式をとる遺伝疾患であり、この場合に限り、腎臓がんと遺伝は強く関係するといえます。
腎臓がんの自覚症状
初期症状はほとんどない
過去には、血尿や鈍痛、手で触ってわかるほどの腫瘤(しゅりゅう)が、腎臓がんの患者さんの代表的な主訴として認識されていました。しかし、これらはがんが進行してから現れる症状であり、検診が普及した現在では、上記3つの主訴を訴える患者さんはほとんどみられなくなりました。
このほか、発熱や原因不明の倦怠感、食欲不振なども、進行腎臓がんの症状として挙げられます。
職場の検診をきっかけにみつかることが多い

多くの患者さんは、職場の超音波検査で腎臓に異常がみつかり、無症状の段階で腎臓がんの診断を受けるに至っています。また、他の異なる病気で腹部エコー検査を受けたときに、腎臓がんが発見されるというケースも珍しくありません。
腎臓がんのステージ分類
腎臓がんのステージは、腫瘍の大きさや転移の有無により、以下4期に大別されます。
- T1:腫瘍が7cm以下で、転移していない
- T2:腫瘍が7cmを超えており、転移はしていない
- T3:腫瘍が腎静脈や下大静脈などの血管内に浸潤している、または腎周囲の脂肪に浸潤している。
- T4:周囲の臓器に浸潤している。
進行した腎臓がんは肺転移、骨転移することが多い
なぜ、離れた肺に転移するのか?
腎臓がんの場合、特に転移しやすい部位は、肺と骨です。腎臓からは離れた肺への転移が起こりやすい理由は、腎臓が血流豊富な臓器であり、がん細胞が血液の流れにのって移動するためです。これを、血行性転移といいます。
なお、腎臓がんがしばしば骨転移する詳しい理由は、現時点ではわかっていません。
腎臓がんの検査と診断
腎臓がんは、生じた位置にもよりますが、画像検査により発見に至ることが多い疾患です。超音波検査などで疑わしい所見がみられた場合、当院ではCT検査で精密検査を行い、確定診断をつけています。
腎臓にできる腫瘍の約9割は腎臓がんであるため、診断の際に組織を採取する腎生検は原則として行いません。また、良性の腎腫瘍と悪性の腎腫瘍の違いも、CT検査により判断できることがほとんどです。腎臓がんとの鑑別が必要な良性の腎腫瘍には腎血管筋脂肪腫(AML)がありますが、これもCT検査とMRI検査により診断することができます。
また、播種(はしゅ)や出血のリスクが大きいことも、診断時に腎生検を実施しない理由のひとつです。播種とは、がん細胞が周囲に飛び散ってしまうことを指し、転移や局所再発のひとつの原因となりえます。
このような理由から、当院では既に転移がみられる進行腎臓がんに対し、どの薬が効きやすいかどうかを調べるときにのみ、腎生検を実施しています。
次の記事2『腎臓がんの手術治療と術式ごとの入院期間や再発率』では、腎臓がんの手術とステージごとの生存率、病院の選び方などについてお話しします。
秋田大学大学院医学系研究科 腎泌尿器科学 教授、秋田大学医学部附属病院 前病院長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
羽渕 友則 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
頻尿治療について教えてください
一週間ほど頻繁に尿意と微熱があり 近くの泌尿器科で見てもらいました (前立腺肥大の持病はあります) そのときのデータ ・白血球50-99/HPE 赤血球5-9/HPF 細菌3+ 細胞質内封入対1-9/LPF ・左右腎臓には結石を認められるも 今回の症状とは関係なし ・膀胱の残尿量も多くはなし 結果 臓器に細侵入侵入している ということで ・レボフロキサシン500mg 1錠/夕食後 7日分 処方していただき服用して4日経過しましたが 微熱は収まりましたが尿意は当初の状態と変わりません (尿意は尿道出口でムズムズ痛かゆい感じ) 質問 ①このまま7日間抗生物質を飲み終えるまで我慢し 様子を見るしかないでしょうか?
一月ほど前から喉の違和感が続いています。
一ヶ月半ほど前から、右側耳の下辺りに違和感があり、ゲップをすると小骨が刺さった様な違和感があります。 耳鼻咽喉科を受診し、逆流症の疑いありとのことで薬を処方されていますが、痛みは治らず、三日ほど前から、右側舌の付け根が痛み始め、声のかすれや痰が絡む症状が出ています。 咽頭がんや舌癌が不安なので、精密検査を受けたいのですが、どの病院に行けば良いのでしょうか?
クレアチ二ンの数字の件
前立腺PSA検査と並行して、血液の他の項目の値でクレアチニン1.06、赤血球数590、Ht52.6、尿素窒素15.6、アミラ-ゼ65、Hb17.4などから脱水かなと言われました。今まで糖尿病外来の毎月の検査でも10年程、クレアチニンは高くても0.95程度でした。急に腎臓が悪くなったのかと心配です。夏程水分はとってなかったのですが、夜中にトイレの回数も減り、水分不足かなと思うところもあります。右の腎臓は萎縮してます。実際に一時的な脱水でこのようなクレアチニンの値になるのでしょうか、また1.06という数値はどの程度なのでしょうか。よろしくお願いします。
肺炎について今後の治療方針や転院について相談
現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「腎臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。