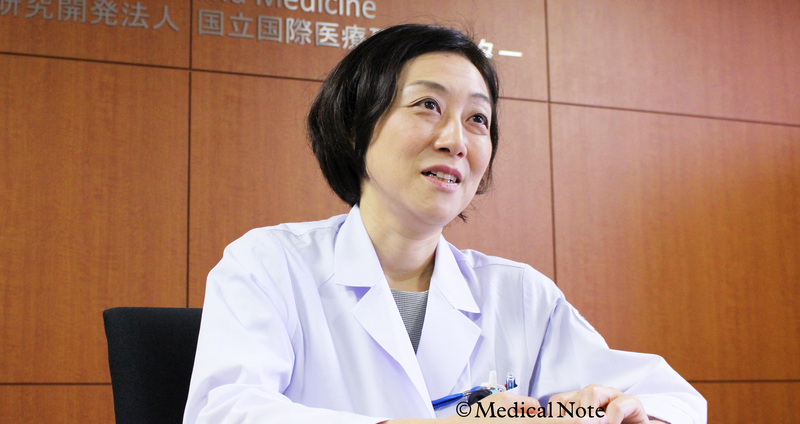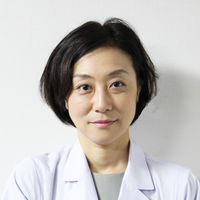乳がんの薬物療法には、主にホルモン療法、抗がん剤の化学療法、分子標的療法があります。このうち、どの治療法を選択するかは、主に患者さんのがんの性質によって決定されます。薬剤にはさまざまな種類があり、副作用の内容や頻度は、使用する薬剤や患者さんの状態によって異なります。
上手に薬とつきあっていくために、患者さんは薬物療法を行っている期間に「現れる症状を記録する」ことが大切であるそうです。それはなぜなのでしょうか。
今回は、国立国際医療研究センター病院 乳腺腫瘍内科の清水 千佳子先生に、乳がんの薬物療法の概要と上手な薬とのつきあい方についてお話しいただきました。
※「国立国際医療研究センター病院」は、 2025年4月より「国立国際医療センター」に名称変更しています。
乳がんの薬物療法とは?
乳がんで行われる薬物療法の種類には、主にホルモン療法、いわゆる「抗がん剤」の化学療法、そして分子標的療法があります。

ホルモン療法
ホルモン療法とは、乳がんの患者さんのなかでもホルモン受容体が陽性の方に効果が期待できる薬物療法です。ホルモン受容体が陽性である乳がんは、女性ホルモン(エストロゲン)の影響を受けてがん細胞が増殖すると考えられています。そのため、ホルモン療法では、エストロゲンのはたらきを抑えることによって、がん細胞の増殖を抑制します。
ただし、ホルモン受容体が陽性であっても、ホルモン療法が必ずしも効くわけではありません。ホルモン抵抗性乳がんの場合には、もとからホルモン療法が効きにくい場合もあります。
分子標的療法
また、分子標的療法とは、がんを増殖させる特有の分子を抑える治療です。たくさんの薬の種類がありますが、代表的なものがHER2と呼ばれる分子のはたらきを抑える薬です。
この薬は、HER2陽性の乳がんの患者さんに適応されます。HER2陽性の乳がんには、HER2タンパクやHER2遺伝子を過剰にもつという特徴があります。これらの因子は、がん細胞の増殖を促進するはたらきがあると考えられており、薬によってこれらの因子を抑える効果が期待できます。
薬物療法はどうやって決定される?
患者さんのがんの性質によって決定
ホルモン療法、抗がん剤の化学療法、分子標的療法のうち、どの薬物療法が選択肢となるかは、患者さんのがんの性質によって決定していきます。先述したように、ホルモン受容体が陽性であればホルモン療法が選択されますし、HER2陽性であれば分子標的療法が選択されるケースが多いでしょう。
実際には、がんの性質だけではなく、患者さんのがんの病状や身体の状態、薬物療法によってどれくらいの効果がみこまれ、どんな副作用が起こるのかなどを踏まえ、複数ある選択肢のなかから患者さんと相談しながら最適と思われる薬物療法に決定します。
薬による治療を開始した後も、副作用が重い場合には、副作用による症状を和らげるための治療を組み合わせたり、薬の量を加減したりすることで対応するケースもあります。がんがその薬でコントロールできていない場合、つまり薬を使っているにもかかわらず、がんの進行が抑えられていない場合には、薬の変更を検討します。
術前・術後の化学療法の役割
小さながん細胞を攻撃する効果がある
術前・術後に行われる抗がん剤による化学療法には、飲み薬であっても点滴であっても、血液の中を流れていき、見えないレベルの小さながん細胞を攻撃する効果があります。
患者さんと相談の結果、先に手術を行うこともありますし、先に化学療法を行うこともあります。ただし、抗がん剤による化学療法は、術前でも術後でも「がん細胞をなくす」という目的は同じです。
実際に、手術後に抗がん剤による治療を行った患者さんは、再発率が少ないことがわかっています。また、術前に腫瘍が小さくなれば、切除範囲が小さくすむ可能性があり、たとえば全摘ではなくて、乳房の温存につながることもあるでしょう。
乳がんの薬物療法で起こりうる副作用
化学療法では脱毛・吐き気などが起こることも
化学療法では、脱毛や吐き気、白血球の減少に伴う感染症などの副作用が起こることがあります。また、手足のしびれや全身のだるさなどが生じることもあるでしょう。ただし、こうした副作用は、すべての化学療法で起こるわけではなく、薬の種類や投与量によっても異なります。
化学療法と比べると、ホルモン療法の副作用は現れにくいといわれていますが、全身のほてりなど更年期症状のようなものが現れることがあります。また、分子標的療法には、副作用が強くないものもありますが、化学療法と似たような副作用が起こったり、化学療法にはみられないような症状が比較的強く起こったりするものもあり、さまざまであることがわかっています。
乳がんの薬との上手なつきあい方
副作用を記録して医師に伝えてほしい
薬の副作用をうまくコントロールしていくには、薬物治療を行っている間に現れる体の症状を記録することが大切だと思います。そして、その症状を医師や薬剤師、看護師に伝えてください。医師は、実際にいつどんな症状が起きたのか、それに対して患者さんがどのように対応したのか、という事実に基づき、それに対する対応法を考えます。
頭の記憶だけに頼ってしまうと、すべての症状を正確に伝えられないこともあるでしょう。また、受診時に緊張してしまい上手に伝えられない方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合にも、毎日の記録が残されていれば、伝えやすくなるのではないでしょうか。当院の乳腺センターでは、化学療法中の患者さんの体の症状や投薬の記録のための手帳を配布し、活用していただいています。

周囲に治療を受けていることを理解してもらうことも大切
また、ご本人だけでなく周りの方に、どのような治療を受けているのか理解しておいていただくことも大切になるでしょう。
お仕事をされている方であれば、職場に薬の副作用によって調子が悪くなる可能性があることを伝えておくことも重要です。職場の上司や同僚に理解しておいてもらうことで、仕事の内容や働き方なども配慮してもらえるようになるでしょう。
2018年9月現在、国もがん患者さんの就労サポートに力を入れています。がん対策基本法と共に、企業もがん患者さんをサポートする体制を築きつつあります。治療と仕事の両立で何か問題が起こったとしても、早まって退職することなく、社会福祉士の方に相談するなど、両立の道を模索していただきたいです。
たとえば、当院では、患者さんの就労相談の日を設けています。このような病院の相談窓口を利用することもおすすめしたいと思います。
乳がんの患者さんがうまく病気とつきあえるように
トータルでサポートできる体制がある
当院の乳腺センターでは、各診療科や相談支援センターなどとの連携が実現されています。たとえば、私たち乳腺腫瘍内科の医師も、緩和ケアチームや相談支援センターの相談員と日頃から密接にコミュニケーションをとっており、何かあれば連絡しあう体制が築かれています。さらに、入院している患者さんに関しては一緒にカンファレンスを実施し、治療法の共有や相談を行っています。
妊娠の可能性を残す「妊孕性温存」にも対応

若年で乳がんを発症し、抗がん剤による治療を行うと、薬の影響で妊娠が難しくなる可能性があります。当院では、生殖医療も行っているので、産婦人科の医師と連携しながら妊孕性温存*の治療にも対応しています。
生殖年齢にあたる乳がんの患者さんに対して薬物療法を行う場合、治療の副作用についてお話しするときに、妊孕性温存にご興味があるか確認します。その際に患者さんのご希望があれば、妊孕性温存の治療をご案内するようにしています。
妊娠の可能性を残すため生殖機能を温存すること
複数の病気を抱える方の治療も
近年では、高齢化が進行し、患者さんが抱える病気が複数であることも少なくありません。たとえば、乳がんの患者さんのなかには、糖尿病や、腎臓や肝臓の病気などを抱えている方もいます。
当院では、そのように複数の病気を抱える患者さんの治療にも取り組んでいます。ほかの診療科との連携によって、複数の病気を抱える場合であっても、院内ですべての治療を完結できる場合も多いです。
清水千佳子先生から患者さんへのメッセージ
一緒に治療を考えていくので何でも相談してほしい

私たち国立国際医療研究センター病院の乳腺センターは、患者さんにとって最適ながん治療ができる場であると考えています。
患者さんの病気の状態はもちろんのこと、将来の希望やライフスタイルなどによっても、適する治療は異なってくるでしょう。記事1『転移再発乳がんの特徴と治療』でお話ししたように、私たちは、「shared decision making」という理念を大切にしています。これは、患者さんと医療従事者が共に治療方針を決めていくという考え方です。
何がベストな選択か、患者さんと一緒に考えていくことができます。そのうえで、トータルでサポートする体制が築かれていますので、まずはどんなことでもご相談いただきたいと思います。
国立国際医療センター がん総合診療センター 副センター長、乳腺・腫瘍内科 医長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
「乳がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
本ページにおける情報は、医師本人の申告に基づいて掲載しております。内容については弊社においても可能な限り配慮しておりますが、最新の情報については公開情報等をご確認いただき、またご自身でお問い合わせいただきますようお願いします。
なお、弊社はいかなる場合にも、掲載された情報の誤り、不正確等にもとづく損害に対して責任を負わないものとします。
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。