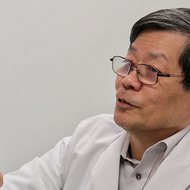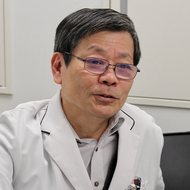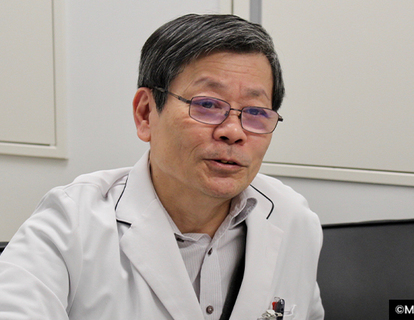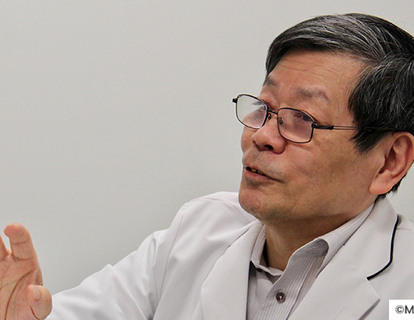概要
急性白血病とは、“血液のがん”である白血病のうち、急激に進行するタイプを指します。白血病は、血液細胞ががん化して無制限に増殖する病気で、がん化した血液細胞が増えることで正常な血液細胞が減り、貧血や感染症を起こしやすくなるなどの症状が見られます。
白血病は進行のスピードによって急性白血病と慢性白血病に分けられ、急性白血病も病気の発症機序によって、さらに急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病に分けられます。
急性白血病は子どもから高齢者まで幅広い世代で見られますが、特に子どもがかかる小児がんの中ではもっとも多い病気です。
種類
急性白血病は、血液が作られる過程のどこに異常が生じているかによって、大きく急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病に分けられます。
急性骨髄性白血病
骨髄(骨の中心部にあり、血液を作る組織)で血液を作る過程でできる骨髄芽球と呼ばれる細胞に異常が起こることで発症する白血病です。急性骨髄性白血病の中には、骨髄芽球が少し成長した段階でできる“前骨髄球”ががん化する急性前骨髄球性白血病と呼ばれる病気もあります。
急性リンパ性白血病
白血球の一種であるリンパ球が未熟な状態でがん化し、無制限に増殖することで発症する白血病です。リンパ球ががん化する病気はいくつかありますが、がん化した細胞が骨髄で増殖するものを急性リンパ性白血病と呼びます。子どもがかかる白血病でもっとも多いタイプです。
原因
血液は造血幹細胞と呼ばれる細胞からスタートして、形を変えながら赤血球、血小板、白血球、リンパ球などの血液成分に成長します。このような成長の過程を“分化”と呼び、白血病は血液の分化の過程のどこかに異常が起こり、異常な血液細胞が無制限に増殖することで発症します。
分化のどのタイミングで異常が見られるかによって分類が異なります。骨髄芽球と呼ばれる成分が作られるタイミングで異常が起こるものを骨髄性、リンパ球と呼ばれる成分が作られるタイミングで異常が起こるものをリンパ性と呼びます。
急性骨髄性白血病の一部は、過去に抗がん薬治療や放射線治療を受けたことにより発症する場合があり、これを二次性白血病と呼びます。しかし、そうでない場合に急性白血病を発症する詳しい理由は、急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病のどちらについてもよく分かっていません。
症状
急性白血病の主な症状は造血機能の障害によって起こるものと、白血病細胞が臓器に浸潤(周りの臓器に広がること)することで起こるものがあります。
急性白血病は病気の進行が早く、突然症状が現れ、短期間で悪化する場合が多いことが特徴です。
造血機能の障害
急性白血病は、未熟な血液細胞が正常な機能を持たないまま無制限に増殖します。そのため正常な血液細胞が減って本来の機能がはたらかなくなり、以下のような症状がみられることがあります。
- 赤血球が減る……動悸、息切れ、倦怠感などの貧血症状
- 白血球が減る……発熱などの感染症状
- 血小板が減る……あざ、点状の出血斑、鼻血などの出血症状
白血病細胞の浸潤
白血病では、白血病細胞が周りの組織に染み出すように広がる浸潤と呼ばれる現象が見られることがあります。浸潤が起こり、周りの臓器に白血病細胞がたまると、以下のように部位に応じて腫れや痛みなどの症状が見られるようになります。
- 肝臓や脾臓にたまった場合……お腹の張りや腹部のしこり、痛みなど
- 歯肉にたまった場合……歯茎の腫れや痛みなど
- 骨にたまった場合……腰痛や関節痛など
また、急性リンパ性白血病では脳や脊髄といった中枢神経系に浸潤しやすく、頭痛、吐き気、嘔吐といった症状が出ることがあります。
検査・診断
急性白血病が疑われる場合は、血液検査で血液細胞の増減の様子を調べ、骨髄検査で確定診断を行います。
骨髄中の未熟な細胞や成熟した細胞の割合を調べ、骨髄中の芽球と呼ばれる細胞が20%以上であれば、急性白血病と診断されます。さらに、骨髄中の芽球についてペルオキシダーゼ染色と呼ばれる検査を行い、陽性の芽球が3%未満であれば急性リンパ性白血病、3%以上であれば急性骨髄性白血病と診断されます。
また、急性骨髄性白血病や急性リンパ性白血病には特徴的な染色体異常や遺伝子異常が現れていることがあります。予後や治療法に影響することから、これらを調べるための染色体検査・遺伝子検査を行うこともあります。
このほか、周りの臓器への病気の広がりを調べるため、腹部超音波検査や腹部CT検査を行うこともあります。
治療
急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病のどちらも、薬物治療を中心とした治療が行われます。薬物治療だけでは十分な効果が得られないと予想される場合は、造血幹細胞移植が行われることもあります。
薬物治療
抗がん薬や分子標的薬(がん細胞に特有の分子を標的とした薬)などを用います。通常はこれらの薬物を複数の種類組み合わせて、症状や検査結果から血液中にがん細胞が確認できない“寛解”と呼ばれる状態を目指します。このような状態を目指して最初に行われる治療を寛解導入療法と呼び、寛解が得られた後もその状態を維持し、治癒を目指して治療を続けることを寛解後療法と呼びます。
用いられる薬の種類は、急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病の分類や、年齢、全身状態、合併症の有無などから判断されます。
造血幹細胞移植
造血幹細胞とは、骨髄中で血液を作る元となる細胞のことです。抗がん薬治療などの強力な薬物治療や放射線治療を行った後に、患者自身やドナーから事前に採取した造血幹細胞を点滴で投与することで、正常な造血機能の回復を目指します。
造血幹細胞移植はそのほかの治療法に比べて強い副作用や合併症を起こすリスクがあるため、抗がん薬治療で十分な効果が得られない場合や、造血幹細胞移植を行ったほうがよりよい治療効果が期待できる場合など、この治療のメリットが大きい場合に考慮されます。
「急性白血病」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「急性白血病」に関連する記事
 白血病の初期症状や受診の目安をチェック~急性白血病と慢性白血病の違いとは?~佐賀大学医学部附属病院 内科学講座 血液...木村 晋也 先生
白血病の初期症状や受診の目安をチェック~急性白血病と慢性白血病の違いとは?~佐賀大学医学部附属病院 内科学講座 血液...木村 晋也 先生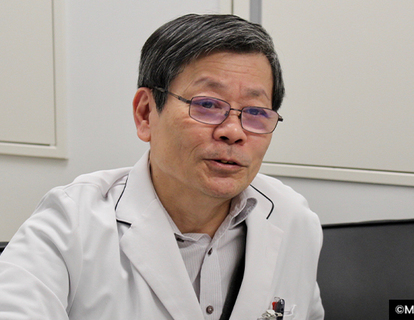 急性白血病(AML:急性骨髄性白血病、ALL:急性リンパ性白血病)の検査、診断の重要性と治療内容大阪暁明館病院 血液内科部長小川 啓恭 先生
急性白血病(AML:急性骨髄性白血病、ALL:急性リンパ性白血病)の検査、診断の重要性と治療内容大阪暁明館病院 血液内科部長小川 啓恭 先生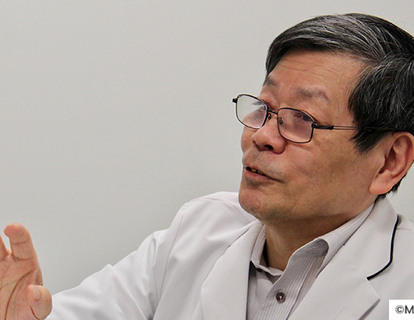 急性白血病とは? AML(急性骨髄性白血病)とALL(急性リンパ性白血病)の違いや原因、症状大阪暁明館病院 血液内科部長小川 啓恭 先生
急性白血病とは? AML(急性骨髄性白血病)とALL(急性リンパ性白血病)の違いや原因、症状大阪暁明館病院 血液内科部長小川 啓恭 先生 骨髄移植のドナーと方法―造血幹細胞移植の進歩広島市立広島市民病院 血液内科 部長 兼...西森 久和 先生
骨髄移植のドナーと方法―造血幹細胞移植の進歩広島市立広島市民病院 血液内科 部長 兼...西森 久和 先生 造血幹細胞移植とはなにか広島市立広島市民病院 血液内科 部長 兼...西森 久和 先生
造血幹細胞移植とはなにか広島市立広島市民病院 血液内科 部長 兼...西森 久和 先生