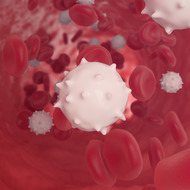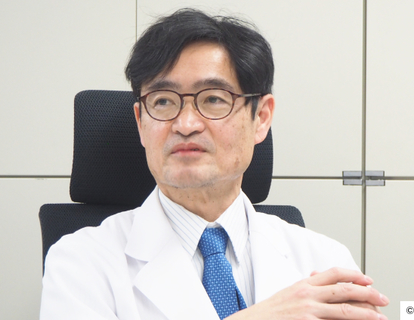概要
白血病とは、血液中の細胞の一種である白血球ががん化する病気のことで、いわゆる“血液のがん”と呼ばれるがんの1つです。
白血病にはさまざまなタイプがあり、白血病という1つの病気を指すのではなく、がん化した白血球などの血液細胞が無制限に増殖する病気の総称を指します。
現在、白血病の治療薬が飛躍的に発展したことにより、かつてと比べて白血病患者の治療成績は大きく向上しています。しかし、白血病は乳幼児から高齢者まで幅広い年代で発症する病気であり、治療の効果が得られないケースでは命を落とすことも少なくありません。
種類
白血病には、突然発症してさまざまな症状を引き起こすタイプの“急性白血病”や、重篤な症状はないものの数年にわたって進展するタイプの“慢性白血病”があります。また、白血病は血液細胞の基となる骨髄中の造血幹細胞のうち、骨髄系幹細胞由来の細胞によって引き起こされる“骨髄性白血病”と、リンパ系幹細胞由来の細胞によって引き起こされる“リンパ性白血病”に分類されます。
そのほか、白血球だけでなく赤血球や血小板など、ほかの血液細胞の生成にも異常が生じる骨髄異形成症候群も白血病の一種と考えてよいと思われます。
原因
血液中の細胞の一種である白血球ががん化し、がん化した細胞が無制限に増殖することで引き起こされます。
白血球の基になるのは、骨髄の中に存在する“造血幹細胞”と呼ばれる細胞です。この細胞は白血球のほかにも赤血球や血小板などの細胞に分化する能力を持ちます。白血球はさらに顆粒球、単球、リンパ球という3つの種類に分類され、顆粒球と単球は造血幹細胞から分化した骨髄系幹細胞に由来する細胞であり、リンパ球はリンパ系幹細胞に由来する細胞です。
このように、造血幹細胞は分化の過程でさまざまの段階の前駆細胞を経て、最終的に白血球などの血液細胞を生成しますが、何らかの遺伝子異常が白血球に成熟する前段階の細胞に生じることで、白血病を引き起こすと考えられています。
現在のところ、その遺伝子異常を引き起こす原因が判明しているタイプの白血病もありますが、多くの種類の白血病では解明されていません。ただし、ダウン症候群など特定の病気を発症している人は白血病になりやすいことが分かっています。また、放射線やたばこなどに含まれる化学物質、ベンゼン、トルエンなどの有機溶剤の影響で白血病が引き起こされるとの報告もあります。
そのほか白血病の中でも成人T細胞白血病と呼ばれるタイプのものは、“ヒトT細胞白血病ウイルスI型”に感染することによって引き起こされることが分かっており、何らかのウイルス感染が発症に関与するケースもあると考えられています。
症状
白血病の症状は病気のタイプによって差はありますが、一般的には正常な白血球の産生が阻害されることで、発熱などの感染症症状が出やすくなります。また、骨髄が白血病細胞によって占拠されることで、赤血球や血小板の産生に支障を生じ、貧血や出血しやすくなるといった症状が現れるようになります。
進行すると、白血病細胞が全身の臓器に行き渡ることで、肝臓や脾臓の腫れ、歯茎の腫れ、骨の痛みなどが現れることもあります。さらに白血病細胞が脳や脊髄を包む髄膜にまで及ぶと、頭痛や吐き気などの症状が引き起こされることも少なくありません。
そのほかリンパ系幹細胞に由来する白血病では、リンパ節や胸腺などの腫れが見られることもあります。
一般的に、急速に発症して進展するタイプの“急性白血病”は重篤な症状が現れやすいですが、ゆっくりと進行するタイプの“慢性白血病”は初期段階では自覚症状がほとんど現れず、健康診断などで偶然発見されるケースも少なくありません。しかし、発症から数年ほどで急速に症状が悪化する場合もあるので注意が必要です。
検査・診断
白血病が疑われる場合には、次のような検査が行われます。
血液検査
白血球の数や異常な細胞の出現などを調べるために血液検査が必要となります。また、白血病は種々の臓器障害、感染症などを引き起こすこともあるため、単に白血球の状態を調べるだけでなく、全身の状態を把握するためにさまざまな種類の検査を行います。
遺伝子検査・染色体検査
慢性骨髄性白血病などのように原因となる遺伝子の異常が判明しているタイプの白血病では、確定診断のために遺伝子検査や染色体検査を行う必要があります。これらの検査は採血によって行うことも可能ですが、白血病の状況を正確に把握するためには、以下に述べる骨髄の細胞を用いて行うことが必要です。
骨髄検査
骨盤(腸骨)などの骨に針を刺し、内部の骨髄液を採取する検査です。採取時に瞬間的な痛みを伴う検査ですが、採取した骨髄細胞を顕微鏡で詳しく観察したり、遺伝子や染色体の異常の有無を調べたりすることで確定診断を下すことが可能となります。
画像検査
肺炎などの合併症の有無、白血病によるリンパ節、肝臓や脾臓の腫れの有無を調べるため、CTやMRIなどによる画像検査が行われます。
治療
白血病の治療方法は病気の種類によって大きく異なります。
急性白血病
急性白血病には急性骨髄性白血病と急性リンパ性白血病があります。ともに、治療方法としては抗がん剤による化学療法が行われます。急性骨髄性白血病の予後不良例や難治例に対しては、造血幹細胞移植が検討されます。急性リンパ性白血病の場合は、同様に抗がん剤治療が先行して行われますが、その後の治療として、造血幹細胞移植やCAR-T細胞療法などの治療が検討されます。
抗がん剤による化学療法
急性白血病に対する化学療法では、複数の抗がん剤を併用することによって白血病細胞を攻撃します。このような治療方法を多剤併用療法といいます。多剤併用療法は数日~1週間程度にわたって行われた後、休止期を挟んでまた繰り返されます。
薬の投与によって、白血病細胞とともに正常の血液細胞も一時的に作られなくなってしまいますが、白血病細胞より正常の血液細胞のほうが早く回復します。この時間差を利用して、白血病細胞を減らすことが可能です。正常の血液細胞が回復した後、再び多剤併用療法を行うというサイクルを繰り返すことで、白血病細胞を段階的に減らしていきます。初回の化学療法の治療目標は“完全寛解”ですが、これは、骨髄検査を含む通常の検査では、白血病細胞を見つけられず、健常な骨髄と区別のつかない状態を指します。1~2サイクルの治療で完全寛解になれば、順調に治療が進んでいることを意味します。通常、最初の1~2サイクルの多剤併用療法で、80%前後の患者が完全寛解に至ります。2サイクル投与後も完全寛解にならない場合は、治療内容を変更するか、以下に述べる同種造血幹細胞移植を考慮することになります。
完全寛解になっても、白血病細胞が微少なレベルで存在している可能性が高く、これを微小残存白血病と呼んでいます。したがって、完全寛解が得られた場合でも、治療をやめると、その後再び白血病細胞が増加し元の状態に戻ってしまいます。そのため、寛解到達後は微小残存白血病の量をさらに減らし、真の治癒を目指して、化学療法が継続されます。また、中枢神経など、薬の行き渡りにくい部分に直接治療薬を注射したり、放射線治療を追加したりする場合もあります。
急性リンパ性白血病の80%はB細胞性です。このB細胞性急性リンパ性白血病の患者で、治療薬が効きにくい(難治性)場合や再発した場合は、新しく開発された分子標的薬のブリナツモマブや抗がん剤のイノツズマブが使用されることがあります。
ブリナツモマブはB細胞性急性リンパ性白血病の白血病細胞の表面に現れる抗原(CD19)と、正常なT細胞*の表面に現れる抗原(CD3)を結合させることでT細胞を活性化させ、白血病細胞を効率よく攻撃するように工夫された薬です。
イノツズマブはB細胞性急性リンパ性白血病に現れる抗原(CD22)を標的としたモノクローナル抗体**に抗がん剤を結合させた薬です。これにより、白血病細胞に抗がん剤を届けて細胞内に取り込ませることができ、特異的に白血病細胞を死滅させます。ミサイル療法とも呼ばれる分子標的薬です。
*T細胞:白血球の1つで、白血病細胞など体内の異物を攻撃する役割をもつ。
**モノクローナル抗体:体内の異物(抗原)に対し、特定の目印にだけ結合して攻撃するよう人工的に作製した抗体。
必要に応じて造血幹細胞移植やCAR-T細胞療法が検討される
病気の種類や実際の治療の効き具合によっては、化学療法だけでなく造血幹細胞移植やCAR-T細胞療法が検討されます。
造血幹細胞移植とは、血液を作るもととなる“造血幹細胞”を健康な人から採取し、それを患者に移植する治療方法です。この治療を行う場合には、前述した寛解状態を得た後、化学療法や全身放射線治療で、患者の体内に残存する白血病細胞を正常細胞もろとも攻撃したうえで、健康な造血幹細胞を移植します。
移植される造血幹細胞は、自分のものを使用する“自家移植”と自分以外の人のものを使用する“同種移植”があります。急性白血病の場合には“同種移植”が行われることが一般的ですが、同種移植を行うためには健常人ドナー(提供者)の協力が必要です。基本的には、ヒト白血球型抗原(HLA)が合致する人からの提供が必要ですが、血縁関係にない人との間で合致する確率は、数百〜数万分の1といわれているため、より合致する確率の高い兄弟姉妹への依頼が検討されます。
ただし、兄弟姉妹であってもHLAが合致する確率は、1人のドナー候補につき4分の1です。兄弟姉妹にHLAが合致するドナーが得られない場合は、骨髄バンクや臍帯血バンクから、造血幹細胞の提供を受けることが可能です。さらに、最近は移植技術が進歩して、HLAが半分だけ合致した血縁ドナー(HLA半合致ドナー)からの移植も、可能になっています。親子間はHLA半合致ですし、兄弟姉妹では1/2の確率でHLA半合致になりますので、血縁内に高い確率で移植可能なドナーが見つかります。
一方、B細胞性急性リンパ性白血病の難治例に対しては、条件が整えばCAR-T細胞療法を行うことが可能です。CAR-T細胞療法は、B細胞性急性リンパ性白血病細胞が持つ抗原(CD19)を標的にした免疫療法の1つで、白血病細胞を特異的に攻撃するよう患者のT細胞を遺伝子医療技術で改変したものです。
T細胞は白血病細胞を認識し、白血病細胞を攻撃する能力を持った白血球の1つですが、難治性白血病の患者はその能力を十分に発揮できません。CAR-T細胞療法では、採血で取り出した患者のT細胞に白血病細胞を認識・攻撃する遺伝子“CAR(キメラ抗原受容体遺伝子)”を導入して、T細胞を改変します(CAR-T細胞)。CAR-T細胞を増やした後、患者の体内に戻すことで、白血病細胞を攻撃するように工夫されています。
CAR-T細胞療法は有効性が高いものの、治療費用が高価でCAR-T細胞の培養に数週間かかる点、サイトカイン放出症候群(cytokine release syndrome:CRS)*、神経系事象**、腫瘍崩壊症候群***などの重篤な副作用が生じる可能性があるという課題があります。
*サイトカイン放出症候群(cytokine release syndrome:CRS):サイトカインは細胞間の情報伝達を担うタンパク質のこと。中でも炎症性サイトカインは様々な炎症反応を引き起こす働きを持つ。CAR-T細胞は標的を攻撃するほか、増殖・活性化して炎症性サイトカインを過剰に放出することから、CRA-T細胞療法を受ける患者はCRSのリスクが高まるとされる。CRSの主な症状は発熱や低血圧、低酸素症、呼吸困難、心不全など。
**神経系事象:脳症や振戦(自分の意思に反して手や頭、声帯などに規則的な震えが生じること)、錯乱状態、記憶障害、幻覚などの症状がみられる可能性がある。
***腫瘍崩壊症候群:抗がん剤治療や放射線治療によって腫瘍細胞が大量に死滅し、腫瘍細胞から核酸やカリウムなどが放出されることが原因で生じる症状。高尿酸血症、カリウムなどの電解質バランスの乱れ、代謝性アシドーシス(血液の酸性化)、尿量の減少といった症状が現れる。
慢性骨髄性白血病
慢性白血病も慢性骨髄性白血病と慢性リンパ性白血病に分けられます。このうち、慢性骨髄性白血病の場合には、分子標的薬による薬物療法や造血幹細胞移植が検討されます。
分子標的薬による薬物療法
慢性骨髄性白血病は、造血幹細胞レベルでBCR-ABLという融合遺伝子が形成され、それが原因となって、白血病を引き起こします。この病気は、“慢性期”、“移行期”、“急性転化期”と病期がしだいに進展していきます。通常、無症状の”慢性期”で診断されることが多いですが、この時期であれば、“イマニチブ”、“ ダサチニブ”や“ニロチニブ”などの分子標的薬で治療が開始されます。
これらの分子標的薬はBCR-ABL遺伝子が作るたんぱくに直接結合することによって、そのはたらきを抑える効果があります。続けて服用することによって、白血球や血小板の数を正常化させ、BCR-ABLを有する異常な幹細胞を徐々に減少させます。治療効果は、BCR-ABL遺伝子を標的にした定量的なPCR検査によってモニタリングされ、判定は、BCR-ABL遺伝子産物の減少あるいは消失をもって評価されます。
ただし、服用を中止すると元に戻ってしまうため、生涯服用し続けることになりますが、治療が奏功した一部の患者では、服薬中止が可能と報告されています。
これらの分子標的薬は副作用が少なく有効性の高い治療薬ですが、服用を続けていると作用するたんぱく側に変化が生じて薬が効きにくくなる場合があります。そのため、効かなくなってきたときには、“ポナチニブ”や“アシミニブ”という別の分子標的薬が使用されます。
造血幹細胞移植
分子標的薬を使用しても病状がコントロールされない場合、薬が効きにくくなって再燃してきた場合や、急性転化(急性白血病のように芽球が増加する)を起こした場合には、患者の年齢が若く全身状態がよければ造血幹細胞移植が検討されます。造血幹細胞移植を行えば治癒が期待でき、以後治療薬の服用が必要なくなることもあります。
慢性リンパ性白血病
慢性白血病の1つである慢性リンパ性白血病は、成熟したBリンパ球が増殖する白血病です。進行すると多くは肝腫、脾腫を伴います。しかし、大きな変化がなければ治療が行われないこともあります。ただし、病気が進行している場合には抗がん剤による化学療法などを用いた治療が検討されます。
慢性リンパ性白血病は現状の治療では治癒が難しく、病状改善のために化学療法が行われます。この病気に関しても新規薬剤が数多く開発されていて、従来からのフルダラビン、シクロホスファミド、ベンダムスチンに加え、リツキシマブ、オビヌツズマブ、イブルチニブ、アカラブルチニブなどの分子標的薬が単独あるいは併用の形で投与されます。繰り返し投与することによって異常リンパ球数を減少させます。ただし正常なリンパ球も減少させてしまうため、治療中は免疫状態が低下しやすく、感染症などにかかりやすくなるといわれています。上記の薬物療法で、病気がコントロールできなくなった場合には、同種造血幹細胞移植も考慮されます。
予防
白血病の多くは原因が分かっていないため、確立した予防方法もないのが現状です。しかし、上述した成人T細胞白血病は原因ウイルスが判明しており、母乳から乳幼児に感染することが分かっています。そのため、現在では妊娠時にウイルス感染の有無を調べ、母親が感染者である場合は母乳育児を控えるよう指導が行われます。
「白血病」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「白血病」に関連する記事