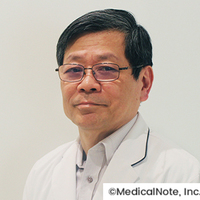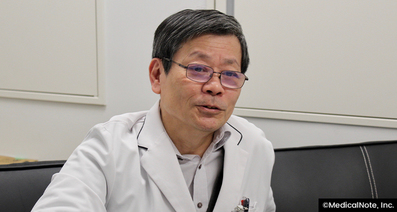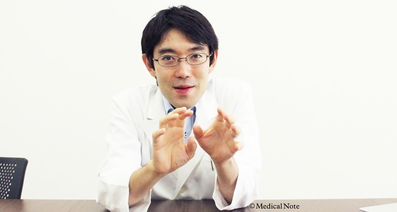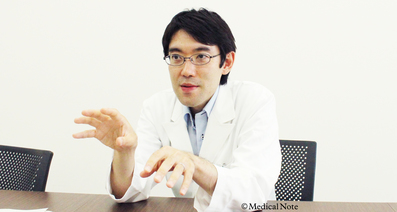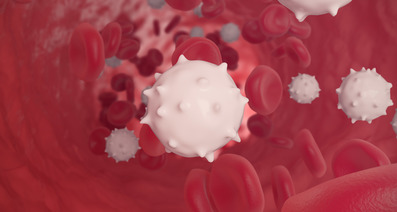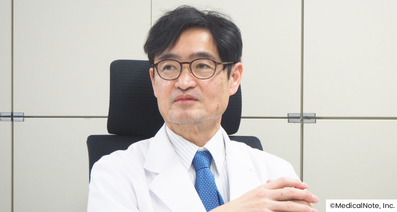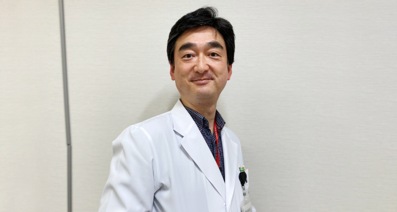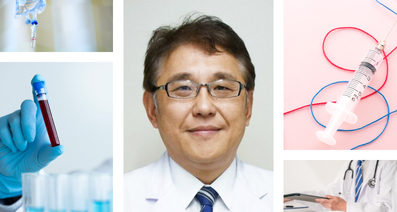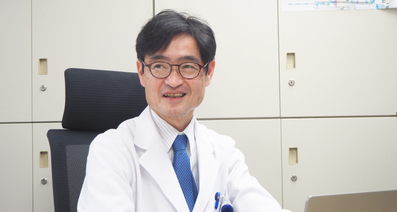骨髄異形成症候群は、赤血球、白血球、血小板など血液中の細胞が減少する病気です。これは、骨髄の中にある“造血幹細胞”の遺伝子異常によって引き起こされます。高齢者によく見られる病気で近年では高齢化の影響により患者数は増加しているとされています。
血液中の細胞は私たちが生きていくうえで重要なはたらきを担っているため、骨髄異形成症候群では全身にさまざまな症状が現れます。命に関わる重篤な病気と考えられることも多い病気ですが、実際はどうなのでしょうか。今回は、骨髄異形成症候群の特徴と共に発症した場合どのような経過をたどるのかについて解説します。
骨髄異形成症候群とはどのような病気なの?
骨髄異形成症候群は、血液中の細胞のもととなる“造血幹細胞”に異常が生じ、正常な白血球や赤血球、血小板が作られなくなる病気です。
以下では好発年齢や症状など、骨髄異形成症候群の特徴について詳しく解説いたします。
有病率と好発年齢
日本での骨髄異形成症候群の有病率は、厚生労働省が全国的な調査を行った1991年の時点で10万人あたり2.7人です。全ての年代で発症する可能性がある病気ですが、中高年に発症するケースが多く、欧米での調査では70歳前後の患者がもっとも多いとの報告もあります。近年、日本では高齢化が進んでいるため、骨髄異形成症候群の患者は増加傾向にあるとされています。
症状
私たちの血液中には赤血球、白血球、血小板の主に3つの細胞が存在しています。赤血球は全身に酸素を送り届けるはたらきがあり、白血球には体内に侵入した細菌などの異物を攻撃して排除するはたらきがあります。そして、血小板は出血を止めて傷を治すはたらきを担います。
赤血球、白血球、血小板は骨髄の中の“造血幹細胞”から作られる細胞です。つまり、この3種類の細胞はもともと同じものからできています。骨髄異形成症候群では、“造血幹細胞”に異常が生じるため、正常なこれらの血液細胞が作られなくなります。
その結果、息切れ、動悸、だるさ、疲れやすさ、顔色不良などの貧血症状が見られる、風邪や感染症にかかりやすくなったり、些細な原因で出血やあざが生じやすくなったりするといった症状が見られるようになります。
また、骨髄異形成症候群は同時に3つ全ての血液細胞が減少していくケースもあれば、特定の種類の血液細胞のみが減少するケースもあります。このため、症状の現れ方が非常に多様であり、以前は“前白血病状態”や“治療困難な貧血”などと考えられていたこともありました。
白血病に進行することもある
骨髄異形成症候群には、造血幹細胞がそれぞれの血液の細胞に変化するどの過程に異常が生じるかによって8つの種類に分けられます。その中には、急性骨髄性白血病に移行する可能性が高いものもあるので注意が必要です。
骨髄異形成症候群の生存率
骨髄異形成症候群は、血液中の細胞が減少する病気です。そのため重篤な病気と思われがちですが、一般的ながんのように急激に病状が進行することはありません。ゆっくりと症状が現れるため、発症に気づかないことも少なくありません。また、上で述べたような症状が現れたとしても、即座に命に関わるわけではありません。症状とうまく付き合いながら生活している患者も多く、病気の種類と発症年齢によっては診断されてから10年後も生存している率が80%を越えるものもあります。
しかし、骨髄異形成症候群の中には急性骨髄性白血病に移行するものもあり、このような場合は白血病に移行しなくても血液の細胞が著しく減少するのが特徴です。そのため、診断されてから1年以内に半数近くの患者が亡くなると報告されています。
骨髄異形成症候群の生存率を決める因子
骨髄異形成症候群には上でも述べたように、造血幹細胞が血液の細胞に変化するどの過程に異常が生じるかによって8つの種類に分けられます。そのうち、造血幹細胞から血液の細胞に変化する際に生じる“芽球”という未熟な細胞が多く見られる場合、発症に染色体の異常が関与している場合、血液の細胞が著しく減少している場合は急性骨髄性白血病に移行するリスクが高いとされています。
骨髄異形成症候群の経過は緩やか
骨髄異形成症候群は急性骨髄性白血病に移行する場合を除いて、緩やかに進行していくのが特徴です。このため、自覚症状がまったくなく、たまたま受けた健康診断などで血液細胞の減少を指摘され、発見されるケースも少なくありません。
このように自覚症状がないケースや軽度な症状のみが見られるケースでは特別な治療をせずに、定期的に血液検査を行いながら経過を見ます。
しかし、骨髄異形成症候群を根本的に治す方法は、現在には残念ながら存在しません(2019年12月時点)。このため、血液細胞の減少による症状が強い場合には輸血や抗生剤などを用いてそれぞれの症状を改善する治療が適宜行われます。
一方、急性骨髄性白血病に移行しやすい場合の骨髄異形成症候群は予後が悪く、造血幹細胞移植や化学療法など白血病に準じた治療を行います。しかし、このような化学療法による長期生存を得ることは難しく、同種造血幹細胞移植が治癒が期待できる唯一の治療です。
早期発見・治療が大切
骨髄異形成症候群は血液の細胞が減少する病気です。発症しても症状が現れることなく一生を終える患者もいれば、急性骨髄性白血病に移行して診断から1年以内に亡くなる場合もあります。同種造血幹細胞移植が治癒の期待できる唯一の治療です。いずれにせよ、発症した場合はできるだけ早く診断を受けて適切な治療や経過観察を続けていくことが大切です。早期の段階では症状がない場合が多い病気のため、定期的に健康診断を受けて体の状態をチェックするとよいでしょう。
大阪暁明館病院 血液内科部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
小川 啓恭 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
おへその中や周りのチクチクした痛みやつっぱり感
1週間くらい前からおへその中やおへそのすぐ外側にチクチクした痛みや突っ張り感が出るようになりました。 寝返りをした時や朝起きた時に伸びをした時、動き始める時に感じることが多いです。 同じ頃から下痢や軟便になり今は便秘3日目です。おへそのすぐ上あたりに何かが詰まってるような苦しさがあり食後にひどくなります。食後苦しくて吐きたいという気持ちになります。 元々、機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群があるため、胃腸が張ったり苦しくなったり、下痢や腹痛はよくあるのでその影響かと思っていたのですが、いつもは胃のあたり全体、下腹部全体に症状が出ておへそ周りピンポイントでというのはあまりなかったので気になっています。便秘もたまにはあるけどいつもは快便な方だと思います。 3ヶ月前に虫垂炎になり腹腔鏡手術を受けています。その時退院してから1ヶ月以上、おへそ周りだけ筋肉痛のような痛みやつっぱり感があり、今の症状と似ていて場所も同じです。私の体感は手術後いつの間にか消えていた症状が、何かのきっかけでまた出始めたという感覚です。 手術後3ヶ月以上経つので今頃傷がどうこうというのはないかと思うのですが、他の2箇所の傷はしっかり残っているのでたぶんおへその傷も残ってると思います。見た感じおへその窪みが深くなって縦に細くなったような気がします。 腹腔鏡手術でも癒着はするし腸閉塞になることもあると聞いているので、その不安もあります。 虫垂炎発症前2ヶ月くらい、ひどい便秘が続き手術後に快便に戻ったという経緯もあり、便秘とお腹周りの変化に敏感になっています。 おへそ周りのチクチクやつっぱり感で考えられることって何かあるでしょうか? 仮に癒着してたとして何か症状を自覚できるものなのでしょうか? 機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群の影響というのもあるでしょうか? また、どのくらい症状が続いたりどんな症状が出たら受診した方がいいとか、受診するなら何科に行けばいいのかも教えて頂きたいです。
貧血傾向にあります
去年の7月の健康診断で ヘモグロビンの値が11、8 とでました。 昨日半年後の血液検査を行い、 値が下がっていたら 更に検査が必要といわれました。 このような場合どういう 病気が予想されるのでしょうか?
手の痺れ、だるさ
現在の体の不調は 両手の痺れ、腕のだるさ、足の痺れ、左右の顔の痺れ、肩凝り、首痛、頭痛、目の奥の痛み、めまい、です。 今年の2月頃から、肩凝りがひどく、そこから 頭痛、目の奥の痛みが出ました。 その時は目が原因だと思い眼科に行き目薬をもらいました。 4月に入り首も痛くなり、1週間程前から 痺れも出てきました。 痺れは片側の痺れが強くなったり弱くなったり無くなったり様々です。 3日前に整形外科に行ってレントゲンを撮ったのですが、骨には異常はなく、牽引と薬で様子見という事になりました。 でも、ネット調べていると、 首のヘルニアだったり、自律神経失調症、脳梗塞などの症状にも当てはまります。 なので、別の病院(神経や脳など見れるような所)にも行くべきなのか、先生に言われた通り薬で様子見をするべきなのか迷っています。
1週間前からの息苦しさ、左胸の痛み
1週間前から息苦しさがあり、その2日後、37.6の熱が2日間続いた。すぐに熱は下がったが、息苦しさは変わらず続いていた。気になって内科を受診したが、酸素濃度も、肺炎の症状もみられなかったため、精神的なものだと診断された。(風邪症状もほぼなし。)念のため喘息用の漢方薬を処方していただき、3日ほど服用。本日から左胸の痛みがある。生理中。 新型コロナではないかと心配だが、心臓も何度か健診でひっかかったことがあるので不安がある。どの病院に行った方が良いか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「骨髄異形成症候群」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。