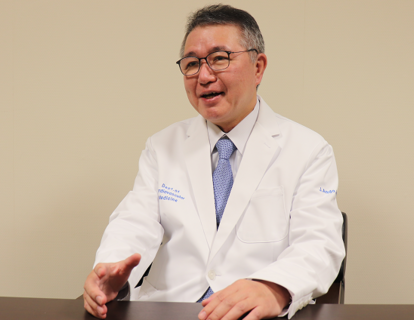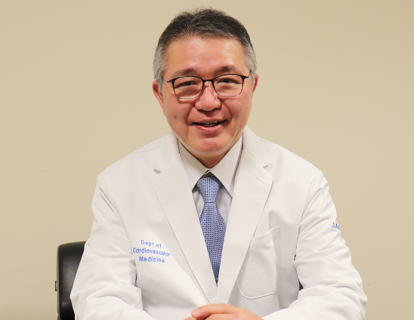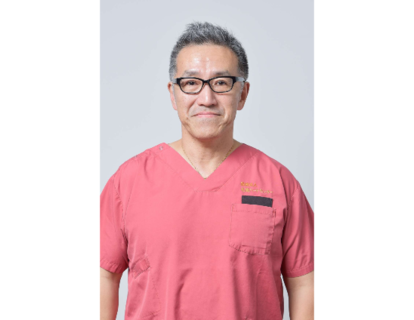概要
虚血性心疾患とは、冠動脈が狭くなったり、閉塞したりすることで血流障害を起こす病気です。冠動脈は心臓の筋肉に酸素や栄養を送り込むはたらきをしています。虚血性心疾患は高血圧や糖尿病、肥満などにより冠動脈が動脈硬化を起こすことを原因として発症し、労作性/安定狭心症と急性冠症候群(急性心筋梗塞症)に大きく分類できます。
虚血性心疾患を発症すると、胸痛や息苦しさなどが現れます。狭心症の場合、症状は短時間で改善しますが、心筋梗塞を発症すると症状は持続し、命にかかわることもあります。虚血性心疾患の発症には日々の生活習慣が大きく関わっており、規則正しい生活が発症予防につながります。
原因
心臓は筋肉で構成されている臓器で、絶えず全身に血液を送り続けています。心臓が適切に働くには非常に多くの酸素・栄養が必要です。冠動脈は、心臓に十分な血液を送るという重要な役割を果たしています。
冠動脈は大動脈から分岐しており、大きく3本の枝によって心筋全体の血流を保っています。しかし、高血圧や糖尿病、脂質異常症、肥満などが存在すると、冠動脈の動脈硬化が進行し、徐々に冠動脈が狭くなってしまいます。冠動脈の内腔が狭くなると血液が流れにくくなり、結果として、酸素・栄養が不足してしまいます。この状況を虚血と呼び、虚血に関連して発症する心臓の病気を虚血性心疾患と呼びます。
虚血性心疾患に含まれる病気には、大きく労作性/安定狭心症と急性冠症候群(急性心筋梗塞症)があります。動脈硬化性病変の程度の違いにより症状の出方は異なり、労作性/安定狭心症では心筋細胞が死んでしまうことはありません。しかし、急性冠症候群(急性心筋梗塞症)では冠動脈が完全に閉塞してしまうため、血液供給が途絶えてしまい心臓の細胞が死んでしまいます。
なかには冠攣縮性狭心症と呼ばれる病気もあります。これは冠動脈が痙攣性の収縮を生じることで起こります。日本人に多く 、安静時に症状が出ることが特徴です。また、子どもの病気である川崎病の後遺症や、大動脈弁膜症が原因となる狭心症もあります。そのほか、心臓の表面を走っている冠動脈の狭窄や収縮を原因とするのではなく、心筋の中を走る細い血管の異常で起こる微小血管狭心症もあります。
症状
虚血性心疾患の症状は、胸痛や息苦しさが代表的です。運動時は特に多くの酸素を必要とするため、運動に伴い症状が現れやすいです。また血管の狭窄が強くなったり、動脈硬化性病変が不安定になったりすると、安静時にも胸痛が出るようになります。もっとも危険な急性冠症候群では胸痛が持続し、ときに意識消失をきたすこともあります。
検査・診断
虚血性心疾患の検査では、心電図検査、心エコー検査、血液検査、心筋シンチグラム、冠動脈CTやMRI、血管造影検査などが行われます。
狭心症は安静時に症状が現れない場合が多いため、運動負荷をすることで狭心症発作を誘発することがあります。心エコー検査は心電図同様簡便な検査であり、虚血に陥った心筋の運動低下を確認します。心筋シンチグラムでは血流低下を描出することができ、CTやMRIを行うことで、冠動脈病変や心筋虚血の状況も確認できます。最終的には血管造影検査にて、冠動脈の狭窄をより正確に描出して診断します。最近は、冠動脈CTが初期診断に有効とされてきています。
治療
高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙などが基盤となり発症するため、内服薬や生活スタイルの是正など原因に応じた治療が必要です。とくに、禁煙はとても、重要な要因となります。また冠動脈の内腔が狭くなっているため、血液の流れをよくする抗血小板薬を使用します。
虚血性心疾患のなかでも心筋梗塞は発症すると命にかかわる危険性もあるため、緊急対応が必要とされます。検査の項目で記載したような血管造影検査で冠動脈の病変を評価し、カテーテル治療(細い管を用いた血管内治療)で狭くなった冠動脈に対して介入します。この治療を行うことで血管を広げ、途絶した血流を再開させることができます。
この際、発症してから少しでも早く再灌流(再度血流が回復すること)を得られるよう、来院してからの操作は迅速に行われる必要があります。再灌流後は抗血小板薬や脂質異常症の薬、硝酸薬の内服や、抗凝固薬や硝酸薬の点滴による治療も並行して行われます。早期の回復をめざし心臓リハビリテーションも行われます。心筋梗塞になるまえにカテーテルで治療が可能であれば、入院は一泊ですみますが、心筋梗塞症になるとそれに見合うリハビリの入院期間が必要となります。
「虚血性心疾患」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「虚血性心疾患」に関連する記事
 虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術――国立国際医療センターにおける手術の特徴国立国際医療センター 心臓血管外科 医長...田村 智紀 先生
虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術――国立国際医療センターにおける手術の特徴国立国際医療センター 心臓血管外科 医長...田村 智紀 先生 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の種類と症状――みぞおちの上の痛みは受診を国立国際医療センター 心臓血管外科 医長...田村 智紀 先生
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)の種類と症状――みぞおちの上の痛みは受診を国立国際医療センター 心臓血管外科 医長...田村 智紀 先生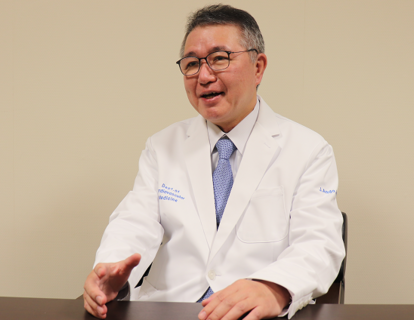 虚血性心疾患が疑われたら――診断の流れと治療の選択肢NTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生
虚血性心疾患が疑われたら――診断の流れと治療の選択肢NTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生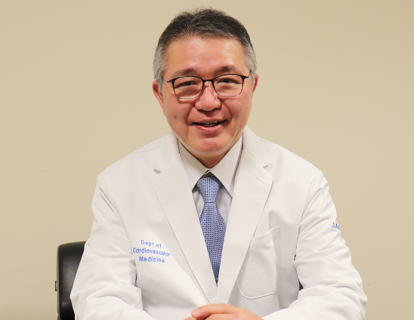 虚血性心疾患の原因と注意すべき症状――自覚症状があればすぐに受診をNTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生
虚血性心疾患の原因と注意すべき症状――自覚症状があればすぐに受診をNTT東日本関東病院 循環器内科 部長安東 治郎 先生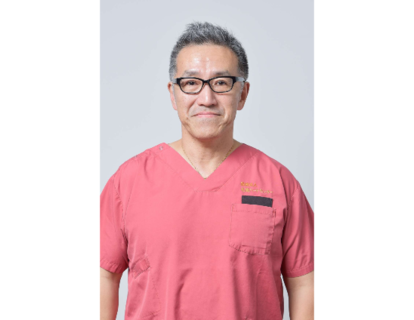 虚血性心疾患の治療を遠隔で行う“ロボット補助PCI”の可能性医療法人 札幌ハートセンター 名誉会長藤田 勉 先生
虚血性心疾患の治療を遠隔で行う“ロボット補助PCI”の可能性医療法人 札幌ハートセンター 名誉会長藤田 勉 先生