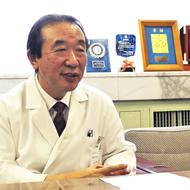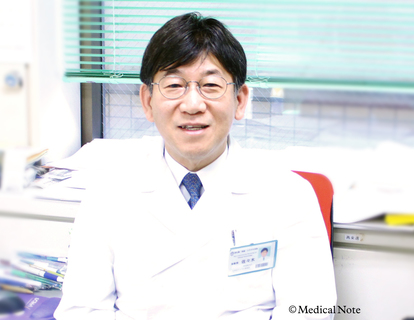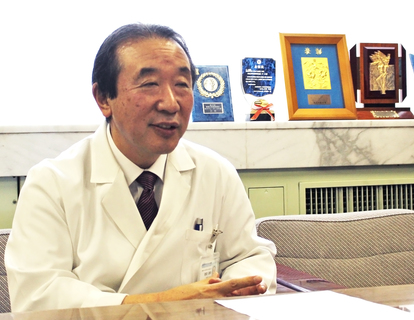概要
ウイルス性肝炎とは、ウイルスが原因となって肝臓に生じた炎症性疾患のことを指します。ウイルスの種類に応じて、A型、B型、C型、D型、E型、非A〜E型、その他(サイトメガロウイルスやEBウイルスなど)、の7つに分類されます。
原因となるウイルスに応じて感染経路(経口感染や血液製剤による感染など)や臨床経過が異なります。臨床経過によっては急性期の症状のみで治まることがある一方、慢性化し肝硬変や肝細胞癌など、より重篤な病気が発症することもあります。
原因
ウイルス性肝炎は、A型、B型、C型、D型、E型、非A〜E型、その他(サイトメガロウイルスやEBウイルスなど)、といったウイルスを原因として発症する、肝臓に生じる炎症性疾患です。この中でもいわゆる「ウイルス性肝炎」として認識されることが多いのは、A型、B型、C型、D型、E型の各種肝炎ウイルスです。
A型肝炎ウイルス・E型肝炎ウイルス
発症様式と肝炎の臨床経過を考えると、A型肝炎ウイルスとE型肝炎ウイルスは共通している点が多いです。両ウイルスともに、糞口感染で感染が成立し、急性肝炎として発症します。糞口感染とは肝炎ウイルスに汚染された食べ物や水・氷を口から摂取することで感染が成立することです。さらに、A型肝炎であれば魚介類(カキ)、E型肝炎であればイノシシなどが特徴的な感染経路として知られています。
B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルス・D型肝炎ウイルス
B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルスは血液や体液などで感染し、慢性化しやすいという共通した特徴があります。血液製剤を介した感染経路は、以前に問題となったことがありますが、原因となるウイルスが同定されて以降、徐々にこうした感染経路は少なくなってきています。
しかし、これらのウイルスは体液中にも分泌されることが知られており、性感染症としての感染成立が増加してきていることが問題視されるようになってきています。
また、D型肝炎ウイルスは血液を介して感染することが主になりますが、B型肝炎ウイルスと同時感染することが知られています。この場合は急性肝炎の症状が重篤化するリスクが高まります。
症状
ウイルス性肝炎では、急性症状を引き起こすことや、慢性化し肝硬変から肝癌の発生に至ることがありますが、多くは原因となっているウイルスによって症状の経過が異なります。
A型肝炎ウイルスやE型肝炎ウイルスでは急性肝炎として発症することが多いです。急性肝炎を発症すると初期の症状としては、食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛、気分不快、肝臓の腫大にともなう腹痛などが生じます。さらに、肝炎により一層特徴的な黄疸の症状が急激に出現しはじめます。具体的には、皮膚や眼球の白い部分が黄色くなることに加え、尿の色が暗色になることもあります。
一部の症例においては急性肝炎の症状がさらに増悪し、劇症肝炎を発症することになります。劇症肝炎に陥ると、肝臓へのダメージが重篤なものとなるため、肝臓が本来持つ機能が保てなくなり、意識障害や腹水・胸水、全身のむくみ、出血傾向等、肝不全にともなう症状が出現するようになります。特にE型肝炎ウイルスによる劇症肝炎は、妊婦さんにおいて発症リスクが高いです。
B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスでは経過が慢性化するリスクを伴います。特にC型肝炎ウイルスでは感染による慢性肝炎発症のリスクが高いです。慢性肝炎の状態では急性肝炎ほどの特別な症状を呈することは少なく、徐々に肝障害が進行します。慢性肝炎が進行すると、お腹が膨れる(腹水がたまる)・黄疸がでるといった症状が出てくるのですが、このような症状は疾患がかなり進行した時点で現れます。つまり、その時にはすでに肝硬変・肝臓がんといった疾患に移行してしまっているケースが多いのです。
検査・診断
ウイルス性肝炎の診断では、肝臓の機能を評価することに加えて、原因となっているウイルス検査が行われることになります。各種ウイルス肝炎に感染すると、ウイルスに対応した抗体が体内で産生されることになります。これらの抗体を血液検査で測定することで間接的にウイルスに感染していることを証明します。ウイルスの種類によってターゲットになる抗体はさまざまであり、疑われるウイルスに応じた抗体を検査することになります。
また、肝炎ウイルスを血液や糞便などを用いて、直接同定することもあります。この目的のためには、リアルタイムPCRを用いてウイルスに特異的な遺伝子を同定します。肝炎の炎症の程度を判断する指標としては、血液検査にてASTやALT、ビリルビン、ALPなどの肝臓に関連した検査項目を行います。
また、肝臓のタンパク合成機能を評価するために、コリンエステラーゼや凝固因子(血液を固めるのに必要な物質)、出血傾向の指標を検査することもあります。
治療
A型肝炎ウイルスとE型肝炎ウイルスに対しての特別な治療方法は存在せず、安静を保ちつつ急性肝炎症状をモニターすることになります。途中、劇症肝炎を発症したときには、肝移植を含めた積極的な治療方法が選択されることもあります。なお、A型肝炎ウイルスに対しては、ワクチンを用いた予防接種が可能です。
B型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスについては、ウイルスに特化した治療をおこないます。B型肝炎には、インターフェロンや核酸アナログを用いた抗ウイルス治療があります。これらの治療により、ウイルスを制御しウイルスの量を減らすことができますが、完全にウイルスを排除することはできません。核酸アナログの場合は、服薬を長期に継続していくことが必要です。
C型肝炎に対しては治療薬の選択肢がここ数年大きく広がってきています。2014年7月に認可された内服薬である「ダクラタスビル」「アスナプレビル」の2剤併用療法を皮切りとして、2015年には「レジパスビル/ソホスブビル」が、2015年末には「オムビタスビル/パリタプレビル」が登場しています。近い将来には、さらなる改良が加えられ、より短期間での治療実現が可能になると期待されています。
「ウイルス性肝炎」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「ウイルス性肝炎」に関連する記事
 肝機能障害の改善は可能? 新たな治療戦略とは大阪大学 大学院医学系研究科 消化器内科...竹原 徹郎 先生
肝機能障害の改善は可能? 新たな治療戦略とは大阪大学 大学院医学系研究科 消化器内科...竹原 徹郎 先生 肝機能障害とは? 肝機能低下を引き起こす原因と症状大阪大学 大学院医学系研究科 消化器内科...竹原 徹郎 先生
肝機能障害とは? 肝機能低下を引き起こす原因と症状大阪大学 大学院医学系研究科 消化器内科...竹原 徹郎 先生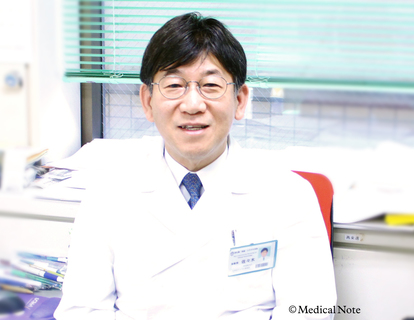 「C型肝炎ウイルスは治療で治る!一生に一度はウイルス性肝炎の血液検査を」札幌医科大学 医学部消化器内科学講座 准教授佐々木 茂 先生
「C型肝炎ウイルスは治療で治る!一生に一度はウイルス性肝炎の血液検査を」札幌医科大学 医学部消化器内科学講座 准教授佐々木 茂 先生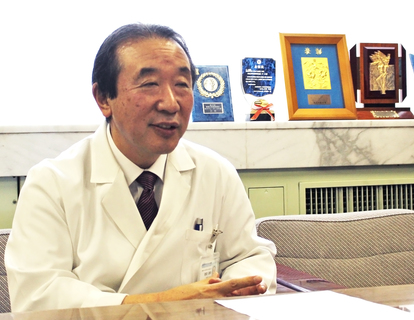 原因はウイルス? C型肝炎やB型肝炎など肝炎の種類・症状・治療方法概論横須賀市立総合医療センター 副病院長 消...池田 隆明 先生
原因はウイルス? C型肝炎やB型肝炎など肝炎の種類・症状・治療方法概論横須賀市立総合医療センター 副病院長 消...池田 隆明 先生 C型肝炎の症状とは?-C型肝炎のウイルスは性交渉を通じて感染することもプライベートケアクリニック東京 院長尾上 泰彦 先生
C型肝炎の症状とは?-C型肝炎のウイルスは性交渉を通じて感染することもプライベートケアクリニック東京 院長尾上 泰彦 先生