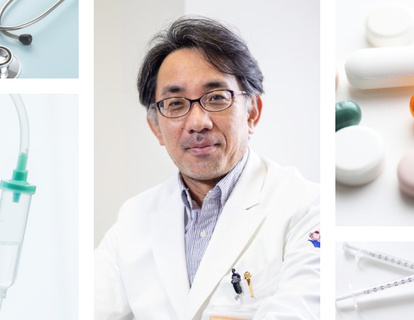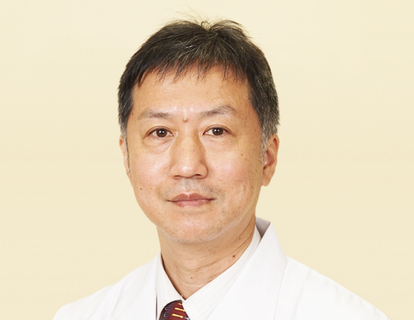概要
低侵襲心臓手術とは、体の負担を少なくした心臓手術のことです。人工心肺装置を使わない、もしくは胸骨を全切開しない手術のいずれか、または両方を行う場合を低侵襲心臓手術と定義されています。
心臓の手術では、一般的に胸骨を縦に全切開して心臓にアクセスし、心臓を止めて肺や心臓の代わりになる人工心肺装置を用いて全身に血液を循環させながら手術を行います。
しかし、近年では医療の進歩に伴い胸骨を切開することなく(あるいは部分切開のみで)、また人工心肺装置を使わずに手術を行うことが可能になりました。このような方法はMICS(ミックス:Minimally Invasive Cardiac Surgery)とも呼ばれ、従来の方法よりも体への負担が少なく、術後は早期に社会復帰することができます。最近では手術支援ロボットを用いた手術も行われていますが、低侵襲心臓手術は高度な技術と特殊な手術機器が必要なため、実施可能な医療機関は限られています。
目的・効果
低侵襲心臓手術は、患者の負担を少なくすることを目的とした手術です。
従来の開胸手術では、胸骨を全切開するため出血量が多くなるほか、骨や傷の感染によってまれに縦隔炎という重篤な合併症が起こることがあります。また、人工心肺装置を用いる場合、大動脈を使って全身に血液を送るために大動脈破裂や大動脈解離、脳梗塞などの合併症のリスクが少なからずあります。
低侵襲心臓手術では胸骨を全切開せず、このようなリスクを回避あるいは軽減できます。また、小さな傷口で済むため、術後の痛みも少なくより早い社会復帰を目指すことができるほか、傷あとが目立ちにくいという特徴も挙げられます。
種類
病気ごとに細かな手技は異なりますが、低侵襲心臓手術の方法には大きく“オフポンプ手術”と“ミックス・ロボット手術”があります。
オフポンプ手術
心臓を止めて人工心肺装置を使用する従来の手術をオンポンプ手術、人工心肺装置を使用せずに心臓を動かしたまま行う手術をオフポンプ手術といいます。
心臓は常に動いていて心臓内に血液を充満させています。心臓手術を行うにあたって、通常は心臓の拍動を止めて心臓内に血液がない状態にしなければなりませんが、心臓を止めると全身に血液が送られなくなるため、人工心肺装置を用いて血液循環を補います。しかし、心臓を止めて人工心肺装置を使うことで、ごくまれに脳血管障害や腎臓障害をはじめとする合併症が発生する可能性があります。
オンポンプ手術に対して、人工心肺装置を用いない冠動脈バイパス術のことをオフポンプ冠動脈バイパス術(オプキャブ:OPCAB)と呼びます。心臓に血液を供給する冠動脈は心臓の表面を走行していることから、オフポンプ手術といえば一般的に冠動脈バイパス術を示します。
冠動脈バイパス術では、狭くなった血管の先に新たな血管(バイパス)を作ります。近年、スタビライザー(吸盤がついた固定具)などの特殊な機材が開発され、操作が必要な血管部分だけを持ち上げ固定して手術が行えるようになりました。
オフポンプ手術は、心臓を動かした状態で手術を行うため高度な技術と時間を要しますが、患者の体にかかる負担を抑えられ、早期の社会復帰が期待できるといわれています。
ミックス・ロボット手術
心臓手術では、一般的に前胸部にある胸骨を縦に全切開し、胸を開けて手術を行います。それに対してミックス・ロボット手術では胸骨を全切開せず、肋骨と肋骨の間から内視鏡を挿入して手術を行います。
通常の心臓手術のように人工心肺装置を用い、左右の足の付け根からカニューラという管を挿入して駆動させます。
胸骨を全切開すると前胸部に約20~30cmの傷ができますが、肋骨と肋骨の間を利用して手術を行うことで肋間に約3~8cmの傷と、足の付け根の小さな傷で済みます。
リスク
低侵襲心臓手術は少ない負担で手術ができるという大きな利点がありますが、その反面、少なからず欠点があります。
たとえば手術時間の延長です。手術に特殊な器具を用いるなど技術的な難しさから、通常の心臓手術よりも手術時間が長くなる傾向があります。
また、肋間から手術を行う際は手術中に肺を潰した状態にする必要があるため、術後に肺が潰れることがまれにあります(再膨張性肺水腫)。
手術中の合併症への対応が難しいため、手術中の出血やそのほかの合併症に対処するために、必要に応じて胸骨正中切開に切り替えることがあります。
適応
現在のところ低侵襲心臓手術が適応となる病気は、弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症・大動脈弁閉鎖不全症・大動脈弁狭窄症・三尖弁閉鎖不全症)、心房中隔欠損症、不整脈、狭心症、心臓腫瘍(左房粘液腫など)などです。
ただし、このような病気であっても必ずしも低侵襲心臓手術が可能なわけではありません。胸郭が薄い人、高度の動脈硬化がある人、肺や心臓の機能が低下している人などは、適応とならない場合があります。
治療の経過
低侵襲心臓手術では手術時間が長くなる傾向がありますが、体への負担が少ないため、早期の退院・社会復帰が可能です。
退院までの期間は病気の種類、患者の年齢、合併症の有無などによって異なりますが、一般的に通常の心臓手術では2~3週間になるのに対して、ミックス・ロボット手術では1週間程度で退院となります。
費用の目安
低侵襲心臓手術を受けるにあたって、入院費用や手術費用が通常よりも高くなることはありません。通常の心臓手術と同様に各種保険が適用されます。
また、一般的に心臓手術の医療費は数百万円となりますが、1か月の医療費が高額になる場合には高額療養費制度を利用できます。
手術内容と所得によって費用負担が異なりますが、高額療養費制度を利用すれば多くの場合で自己負担額は10~20万円程度になるでしょう。
「低侵襲心臓手術」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください