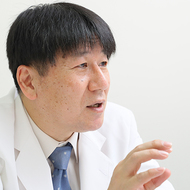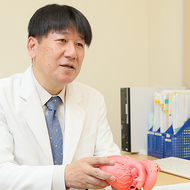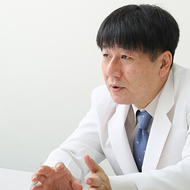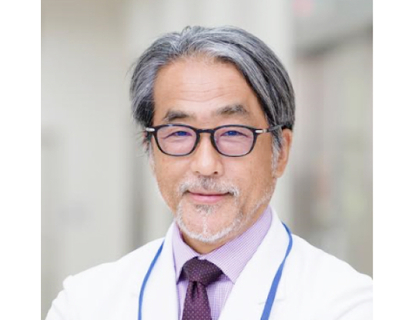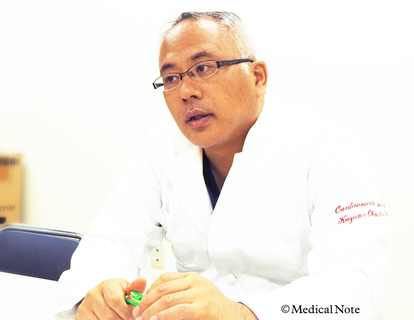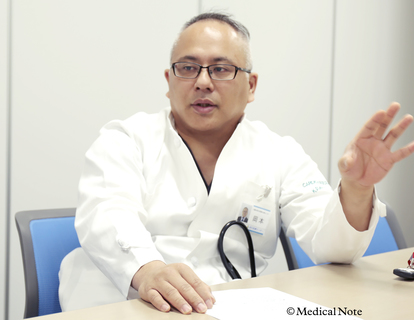概要
僧帽弁閉鎖不全症とは、主に動脈硬化や心筋梗塞、リウマチ熱などを原因として発症する、僧帽弁の閉まりが悪くなった状態です。僧帽弁は、心臓の弁の1つで、左心房と左心室の間に位置します。僧帽弁の機能が悪くなると、左心房から左心室に送り出された血液の一部が左心房に逆流してしまいます。
軽症の場合には無症状であり、健康診断で心雑音の指摘を受けて診断されることもあります。進行すると運動時の息切れなどの心不全症状が現れたり、心房細動という不整脈が現れて動悸を自覚することもあります。さらに、心房細動にともない心臓内に血栓(血の塊)が形成され、脳梗塞を引き起こす危険性もあります。
治療方法としては、心不全や不整脈、血栓に対しての内科的な治療があります。また僧帽弁の逆流を解除するためには、手術やカテーテル治療などが行われます。
原因
心臓は、全身や肺に血液を送るポンプとしての機能を果たしています。心臓には4つの部屋が存在していますが、左心房は、肺から戻ってくる豊富な酸素を含んだ血液を受け入れる部屋です。左心房に戻ってきた血液は左心室へと送られ、その後、大動脈を介して全身に血液が送られます。
僧帽弁閉鎖不全症とは、この弁が何かしらの原因で機能不全を起こし、左心室から左心房へ血液が逆流してしまう病気です。その結果、肺うっ血と呼ばれる状態を引き起こします。
僧帽弁閉鎖不全症は、僧帽弁そのものが傷むことで起こる一次性僧帽弁閉鎖不全症と、虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞など、心臓に血液が十分行き渡っていない疾患)や心筋症などが原因で左心室が傷むことにより、結果として僧帽弁の動きが悪くなる二次性僧帽弁閉鎖不全症とに分けられます。また、一部の僧帽弁閉鎖不全症は、バーロー症候群と呼ばれる先天性の疾患により起こることが分かっています。バーロー症候群とは、生まれつき僧帽弁がふやけたような柔らかい形状をしている病気です。
症状
軽症の僧帽弁閉鎖不全症では、特に症状を感じることはありません。しかし、進行すると階段や坂道の昇り降りで息切れを感じるようになります。さらに進行すると、平地を歩くだけでも息切れを感じるようになり、やがて安静にしていても息切れするようになります。これは病気が進んでいることを意味します。
さらに進行すると、夜寝たとき急に息切れが起こる夜間発作性呼吸困難や、横になっただけで息苦しくなり、常に体を起こした姿勢でいるしかなくなる起座呼吸と呼ばれる状態に陥ることもあります。重症例では、激しく咳き込み、ピンク色の泡状の痰が出るようになります。この場合ただちに医療機関を受診したほうがよいとされています。
また、僧帽弁閉鎖不全症は、心房細動と呼ばれる不整脈を併発することがあります。心房細動は、発症直後のほうが自覚症状が重くなる傾向があります。具体的な症状としては、動悸・胸部不快感・胸痛・立ちくらみ(めまい)・全身倦怠感などです。また、脈を計ると脈が速いあるいは遅い・不規則になっている、ということが確認できます。
心房細動が慢性に経過すると、左心房内に血栓と呼ばれる血の塊が形成されることもあります。血栓が左心室から全身の血液の流れに移動すると、脳梗塞を引き起こすこともあります。
検査・診断
治療方針を決定するためには胸の音を聴く聴診、採血などの一般的な検査だけでなく、さまざまな画像検査を行います。
経胸壁心エコー
経胸壁心エコーは、最初に行われる検査のうち、もっとも大切な検査です。超音波を使って、弁の逆流の原因を調べ、心機能を含めて定量的に評価します。胸に小さい装置をあてて、胸郭の中にある心臓を画像化し計測します。
経食道心エコー検査
経食道心エコー検査では、胃カメラのような機械を口から入れて、食道から心臓を観察します。この方法により、明瞭な画像による詳細な診断が可能となります。経食道心エコー検査は、経胸壁心エコー検査では十分に心臓を観察できない場合や、よりよい治療方法を選択するために行われます。
僧帽弁閉鎖不全症に合併する心房細動に伴い、左心房内に血栓が形成されることもあります。心エコー検査では血栓の状況についても評価することが可能です。
その他の検査
心電図検査で心房細動を合併していないかどうかを評価します。
血液検査では全身臓器の状況に加えて、心不全の程度(BNPなど)も評価します。
そのほか、心臓カテーテル検査を行い、僧帽弁閉鎖不全症の原因として冠動脈狭窄がないかどうかを評価したり、逆流の程度を評価することもあります。
治療
僧帽弁閉鎖不全症は、急性と慢性で治療の流れが異なります。
急性の場合
急性の場合は、多くが急性の心不全を発症します 。ただちに入院し、心不全に対しての集中的な薬物治療を開始します。その後、原因疾患に応じた治療が選択され、必要であれば適切な時期に手術を行います。
慢性の場合
慢性の場合、まずは逆流の重症度を判定します。
軽症の場合
外来で経過観察をおこない、薬も必要ないこともあります。
軽症と重症の間の中等症である場合
薬物を用いた内科的治療を行いながら経過観察し、逆流が増えたり心機能が悪化したりすれば手術を行います。
重症の場合
外科的治療を行います。利尿薬や血管拡張薬などの薬による内科的治療も行いますが、これらは心不全に対しての対症療法であり、問題となっている僧帽弁そのものを修復することはできません。僧帽弁の修復をおこなうためには外科的治療による介入が必要です。手術方法には大きく分けて弁形成術と弁置換術とがあります。手術方法は状況に応じて適宜検討されます。
心房細動を合併している場合は、血栓に対する治療薬が併用されます。
僧帽弁閉鎖不全症でお悩みの方へ
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
受診前に
医師に治療・手術の相談ができます!
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
受診前に
医師に治療・手術の相談ができます!
こんなお悩みありませんか?
- 治療すべきか迷っている
- 治療費について不安がある
- 通院する前にまずはオンラインで相談したい
受診前に
医師に治療・手術の相談ができます!
- お問い合わせフォームで無料相談
岡本 一真 先生 (静岡県)
国立大学法人 浜松医科大学 外科学第一講座 教授
「僧帽弁閉鎖不全症」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください