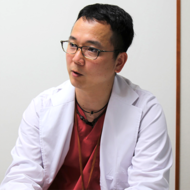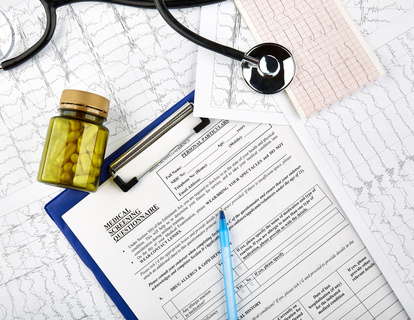概要
心房細動とは、本来は一定のリズムの電気活動で動く心房が、無秩序に電気活動をしてけいれんしている状態を指します。そのため、規則的な脈ではなく、不規則な脈となってしまいます。心房細動を発症すると、動悸やめまいなどの症状を自覚することがありますが、似た名前を持つ心室細動のように突然死のリスクと直結することはほとんどありません。
しかし、心房細動を発症すると脳梗塞を引き起こす危険性が高くなります。心房細動に関連した脳梗塞は、心原性脳梗塞と呼ばれるタイプのものであり、脳梗塞のなかでも、脳の広い範囲に障害を引き起こす可能性のある危険な脳梗塞です。
そのため、心房細動の治療では、不規則な脈をコントロールするという点以上に、脳梗塞発症を予防するという点が重要になります。また、似たような病気として、心房粗動も知られていますが、発生のメカニズムに異なる点があります。
原因
心臓には、大きく分けて心房と心室の2種類の部屋があります。心房と心室は、それぞれさらに右と左に分けることができ、全体でみると左心房、左心室、右心房、右心室、の計4つの部屋に分かれています。心臓はこれら4つの部屋が規則正しい電気活動を介して適切に活動をすることから、全身や肺に血液を送るポンプとしての機能を果たすことができます。規則正しい電気活動は右心房に存在する洞房結節と呼ばれる部位から発生しており、心房から心室へと一方通行で電気が伝わっています。健康な人の脈拍数はおよそ1分間に60〜100回とされており、これは洞房結節が1回興奮することで、それに対応して心室が1回収縮することを示しています。
心房細動を発症すると、洞房結節以外に心房内などで電気興奮が起こります。そのため、洞房結節を起源とする電気活動が機能せず、心房全体でバラバラに電気活動を起こします。心房で生じたバラバラな電気活動がランダムに心室に伝わることで、心室の脈拍も不規則になります。
心房細動そのものは比較的よくみられる不整脈ですが、心房細動を引き起こす病気は多岐に渡ります。加齢に関連した弁膜症や虚血性心疾患などの病気により発症することがあり、高血圧や生活習慣との関わりも指摘されています。若年の人であっても、たとえば甲状腺機能亢進症やストレスを抱えている人などでは発症する可能性が出てきます。
心房粗動との違い
心房細動と似たような病名に心房粗動があります。両者とも心房の運動が活発になっている状態ですが、両者には明確な違いがあります。
心房細動では心房と心室が不規則に活動していますが、心房粗動では規則的に活動をします。つまり心房粗動では、心房と心室の収縮回数は3対1や4対1といったように一定であり、正常よりも早い心拍数でありながらも心室は規則的な脈を示します。両者の治療方法は類似していますが、脳梗塞の発生リスクや動悸などの症状は心房細動でより多くみられる傾向にあります。
症状
無症状の人もいれば、動悸や不快感などの症状が現れることもあります。
心房細動を発症すると心室の収縮は不規則にはなりますが、一回あたりに全身へ運び込まれる血液量は十分なこともあり、失神や直接的に突然死を引き起こすといったことはほとんどありません。しかし、心原性脳梗塞、心不全のような心房細動に関連した合併症・併存症が起こる可能性はあります。
検査・診断
心電図による電気活動の確認と、超音波による血栓の確認が重要になります。
心電図検査
標準12誘導心電図
もっとも基本的な検査です。体への負担が少なく、簡単に検査できるとされており、そのほかの循環器疾患と同様に必須の検査となっています。
心房細動が起きているときに検査を行えば、心電図検査で心房細動の診断が可能です。しかし発作性心房細動の場合は、不整脈発作が起きていないときに検査を行っても異常が検出できないため、この検査で異常がなくても心房細動が否定できるわけではありません。無症状でも、定期検診の心電図検査で偶然発見されることもあります。
ホルター心電図
胸にいくつかの電極を貼り付け、携帯型の心電図装置に日常生活の心電図を24時間記録する検査です。日常生活のなかで心電図を記録できるため、心房細動の発作をみつけやすくなります。
イベント心電図
小さな記録装置を持って、日常生活の中で動悸などの自覚症状が起こったときに装置を胸に当てて心電図を記録するといった仕組みで心房細動を検出することができます。
心臓超音波検査
超音波により、心臓の収縮力、心拡大/心肥大の有無や心臓の弁の状態を確認することができます。また、心房の中に血栓ができていないかも確認が可能です。体への負担が少ないため、基本的な検査としてよく行われます。
しかし、血栓ができやすい左心房は体の表面から遠い位置にあるため、通常の超音波検査でははっきりと確認することが難しい場合があります。そのような場合には、経食道心エコー検査という、胃カメラのようなエコー装置を口から飲み込み、心臓を体の内側から観察することで、血栓の位置や大きさを確実に診断する検査が検討されます。
治療
薬物治療とカテーテルによる治療に大きく分かれます。一般的には、まず薬物治療を行います。
薬物治療
血液をサラサラにして脳梗塞を予防するための抗凝固薬と、脈拍を整える抗不整脈薬があります。
抗凝固薬
心房細動のもっとも大きな合併症の1つである脳梗塞を予防するため、血液をサラサラにする抗凝固薬を内服します。高齢の患者や高血圧症・糖尿病などの基礎疾患を持っている患者では脳梗塞を引き起こすリスクが高いとされており、その場合には内服の適応となるでしょう。副作用として出血をしやすくなることがあるため、適切な服薬指導も重要です。
抗不整脈薬
脈拍を整える抗不整脈薬を内服する目的は、(1)心房細動を止めて正常な脈に戻すこと、(2)心房細動は止めずに速い脈を遅くすること、という2つに分かれます。
前者の目的のためには、心臓の細胞の興奮を抑制するタイプの薬剤が用いられます。後者の目的のためには、交感神経(自律神経の1つで興奮時にはたらく神経)のはたらきを抑制するβ遮断薬や、心房と心室の電気伝導を抑制するカルシウム拮抗薬がよく用いられます。
心筋細胞の興奮を抑える薬剤であるため、副作用として心臓の機能が低下し心不全を起こすこともあり、そのほかには細胞の興奮が不安定となり重症な不整脈を起こす可能性があります。適切な服薬指導や薬剤の適切な見直しが重要です。
カテーテル治療
薬物治療で不整脈が停止しなかった場合は、カテーテル治療(高周波カテーテルアブレーション)を検討します。高周波カテーテルアブレーションとは、足の付け根の太い血管からカテーテルと呼ばれる細い管を心臓まで持っていき、心房細動を引き起こすきっかけとなる異常電気信号や心筋細胞を焼灼治療する手術です。そのほかにも昨今はバルーンカテーテルを用いたカテーテルアブレーションの有効性や安全性も確立されています。
カテーテルアブレーションの合併症として、カテーテル挿入部の出血や血腫(血液がこぶ状に固まった状態)、感染のリスクがあります。また、まれではありますが、心臓に傷がつき心臓周囲に血液がもれてたまる心タンポナーデという重篤な合併症を引き起こすことがあります。
カテーテルアブレーションは、10-40%程度の患者で再発してしまうことがあり、再度カテーテルアブレーション治療が必要になる場合もあります。
- よりよいアブレーション治療――戸塚共立第2病院における治療選択や多職種連携の取り組み戸塚共立第2病院 循環器内科眞壁 英仁 先生
高齢化に伴い増えている病気の1つである心房細動。心房細動に対するアブレーション治療は、技術の発展とともに治療成績や安全性の向上につながっている...続きを読む
- アブレーション治療により不整脈の根治を目指す戸塚共立第2病院 循環器内科眞壁 英仁 先生
不整脈の治療は年々進化しています。中でも、カテーテルアブレーションは、低侵襲(ていしんしゅう)(患者さんの体への負担が少ない)治療でありながら...続きを読む
 心房細動の治療法について医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管ク...北井 敬之 先生
心房細動の治療法について医療法人札幌ハートセンター札幌心臓血管ク...北井 敬之 先生心房細動は、脳梗塞(のうこうそく)や心不全などの合併症が起こる前に治療を行うことが重要です。心房細動の治療にはどのようなものがあり、何を目的と...続きを読む
「心房細動」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください