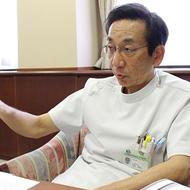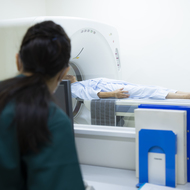概要
腎臓で作られた尿が通る道は、尿路とよばれます。尿路には、腎臓、尿管、膀胱、尿道が含まれ、尿路のどこかにミネラルや有機物を含む結石ができる病気を尿路結石といいます。
尿路結石の患者数は世界的に増えていて、食生活の変化や地球温暖化の影響があるのではないかと考えられています。尿路結石になりやすい年齢は、日本人の男性では40歳代、女性では50歳代が多いです。
結石のできた場所が腎臓や尿管の場合には上部尿路結石と呼び、膀胱や尿道の場合には下部尿路結石といいます。日本人では、尿路結石のうち95%以上が上部尿路結石であるといわれています。症状は結石の大きさや結石ができた場所によってさまざまですが、背中やわき腹の痛み、吐き気、血尿、頻尿などがよく起こります。
治療は、小さい結石の場合には飲水や運動などの生活指導のみのこともありますが、結石が大きく自然に排出されることが期待できないときや痛みが繰り返し起こる場合などには、入院して積極的な治療を行います。尿路結石は再発の多い病気なので、予防のために水分摂取量や食事内容に気を付けるとよいでしょう。
※編集部注:こどもの尿路結石についてはこちらをご覧ください。
原因
尿路結石には、複数の要因が影響していると考えられています。具体的には、尿の流れの停滞、尿路の感染、内分泌や代謝の異常などが挙げられます。
尿が濃縮されると結石ができやすくなるといわれています。尿の流れの停滞は、生まれつきの腎臓や尿管の異常や、前立腺肥大症、がん、寝たきりなどによって起こりやすいです。内分泌や代謝の異常の例としては、甲状腺や副甲状腺の病気、高尿酸血症、がんなどが挙げられます。内分泌や代謝の異常によって、尿中のカルシウムやシュウ酸の排泄量が多くなると結石ができやすくなると考えられています。
症状
結石が小さい場合には、無症状のこともあります。しかし、結石によって尿の流れる道が閉塞してしまうと背中やわき腹、下腹部に痛みが起きます。痛みの持続時間は2~3時間のことが多く、痛みの強さに波があるのが特徴です。結石の刺激で血尿が起きることもあります。感染を伴う場合には発熱があることや、痛みとともに吐き気を自覚する場合もあります。
下部尿路結石の場合、これらに加えて膀胱が刺激されることによる頻尿や残尿感がみられることもあります。
検査・診断
尿路結石の多くは、検査をしなくても症状や痛みの場所などによって診断することが可能といわれています。身体所見では、結石の存在する部分の痛みや軽く叩いたときに誘発される痛みを認めることが多いです。結石の大きさや成分、結石の存在する場所によって、適した検査方法があります。
具体的に行われる主な検査は以下のようなものです。
尿検査
尿路結石では、目で見て分かる血尿だけでなく、顕微鏡で確認すると分かるような血尿を認めることがあります。膀胱の結石では膿尿や細菌尿を認めます。
血液検査
採血によって、腎機能や尿酸値、カルシウム値、リン値、炎症反応などの異常がないかを確認します。尿路結石では、腎機能低下や感染を伴うことがあります。血液中の尿酸値やカルシウム値、リン値が高いことは、尿路結石が起きやすい原因の1つになります。
単純X線写真(腎尿管膀胱撮影)
尿路結石のうち、約90%は単純X線写真で確認できるといわれています。2mm以下の小さい結石、X線写真では写らない尿酸結石などは確認することが難しいので、ほかの検査も行います。
超音波検査
結石が尿路の一部を閉塞すると、結石より上方の部分が拡張することがあります。超音波検査は、拡張した部分や結石の存在を確認するために行われます。膀胱にある結石も超音波結石で確認できます。
排泄性腎盂尿管撮影
単純X線写真で結石が確認できない場合や結石が尿の流れにどのように影響しているか調べるときに、排泄性腎盂尿管撮影が行われます。この検査を行うことにより、単純X線写真で確認できない小さな結石や下部尿路結石の診断に役立てることができます。
CT
単純X線写真で写らない結石や小さい結石、結石による腎臓の形の変化などを確認することができます。
結石分析
結石の成分として、シュウ酸カルシウム、リン酸カルシウム、尿酸、リン酸アンモニウムなどがあります。結石の成分は、治療法を選ぶときの参考になります。
治療
結石の大きさ、感染の有無、腎機能低下の有無などによって治療法が決まります。自然排石が期待できる結石の場合には、飲水や食事指導、運動などの日常生活指導や内服薬によって経過を見ます。しかし、結石が大きく自然排石が期待できない場合、痛みの発作を繰り返している場合、尿路感染を合併している場合、腎機能低下の可能性がある場合などは結石を砕いて排出させる積極的な治療を行います。
尿路結石に対する積極的治療には大きく分けて次の3つがあります。
経尿道的尿管砕石術
尿道から細い内視鏡を挿入し、尿管に存在する結石をレーザーなどで砕く根治治療です。全ての尿路結石で主に用いられます。全身麻酔が必要な治療法です。
体外衝撃波結石破砕術
体の外で発生させた衝撃波を結石に収束させることによって砕く治療法です。切開の必要がありません。結石発作の初期など限られた状況で行われます。
経皮的腎砕石術
背中から直接腎臓に内視鏡を挿入して、レーザーなどで結石を砕く治療法です。腎結石のうち体外衝撃波結石破砕術で砕けないような硬い石や大きい石が対象になり、全身麻酔が必要です。
予防
尿路結石は再発しやすいため予防が大切です。尿路結石の予防法の基本は、飲水量や食事内容に気を付けることです。飲水量は1日2L以上が目標で、水や麦茶、ほうじ茶などがよいといわれています。また食事の量や内容、食事の時間も大事です。一般的に、夜遅くに塩分とたんぱく質、炭水化物を多く取る方に多い傾向があります。したがって尿路結石の発作が出た方は糖尿病のリスクが高くなります。また食事時間が早いのも特徴的です。野菜や海藻をまず食べ、ゆっくり食事することを心がけましょう。
「尿路結石」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください