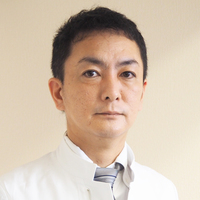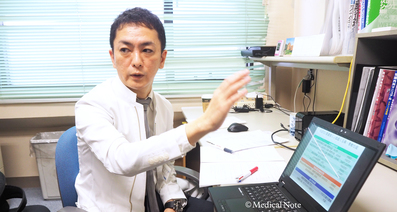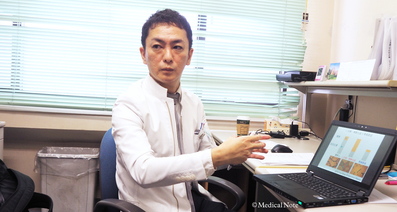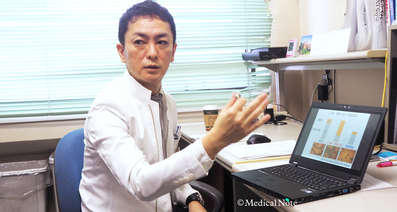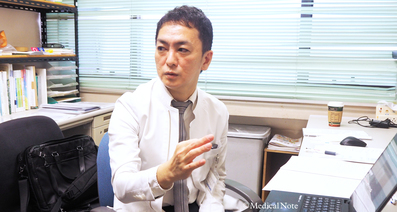
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症とは、遺伝子の変異により生まれつき発症し、骨の痛みや変形などの症状が現れる、指定難病のひとつです。非常にまれな病気と言われていますが、骨粗しょう症やビタミンD欠乏症などの他の病気に間違えて診断されている方もいるのではないかと想定されており、診断のためには詳しい検査が必要だと考えられます。
今回は、ビタミンD依存性くる病・骨軟化症とはどんな病気なのか、東京大学医学部附属病院 伊東伸朗先生にご解説いただきました。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症とは?

生まれつき発症する骨の病気
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、遺伝子の変異によって、ビタミンDが体内で使えるような状態にならない、または、体内でうまく使うことができない病気です。骨をつくる過程で重要なはたらきを担う栄養素であるビタミンDが正しくはたらかないことで、「くる病・骨軟化症」の症状が現れます。
くる病・骨軟化症とは、骨の石灰化が妨げられて、本来は石のように固いはずの骨が柔らかくなってしまう状態(石灰化障害)がみられる病気です。
「くる病」と「骨軟化症」の違いとは?
「くる病」と「骨軟化症」は同じ病気ですが、発症時期により分類されています。子どものとき(骨端線*が閉鎖する前)に発症すればくる病、大人になってから(骨端線が閉鎖した後)発症すれば骨軟化症といいます。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、くる病として発症し、子どもの頃から骨の変形などがみられます。その後、成長して骨端線が閉鎖した後も同じ状態がみられるため、大人の患者さんの場合は骨軟化症と分類されます。
骨端線…子どもの成長にかかわる、長い骨の端に存在する軟骨組織。
患者数の報告は100例程度
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の患者さんは、世界で100例程度であると報告されています。しかし、軽症~中等症の患者さんは発見されていない、あるいは誤診の可能性があり、実は発症頻度がもっと高いのではないかと想定されています。
実際に、ビタミンD欠乏症と言われていた患者さんに遺伝子の変異が発見され、本当はビタミンD依存性くる病・骨軟化症であることが分かったという報告もありました1)。
ビタミンD欠乏症とは?
体内におけるビタミンDが欠乏している状態です。ビタミンDとは、カルシウムやリンとともにバランスよく摂取することで、骨の代謝(古い骨が新しい骨に入れ替わるしくみ)に重要な役割を果たす栄養素です。日光にあたることによりヒトの体内でつくられますが、食事から摂取することもできます。そのため、外出しない期間が長く続いたり、ビタミンDを含む食べ物を全く摂らなかったりすると、ビタミンD欠乏症の状態になり、骨の痛みなどが引き起こされる可能性があります。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の原因

遺伝子変異
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、ビタミンDの「活性化」、もしくはその受け手となる「受容体」に関連する遺伝子の変異によって発症します。
体内に取り込まれたビタミンDは、2段回の過程を経て「活性型ビタミンD」という形に変化する(活性化する)ことで初めて、骨の形成など、体内における重要な機能を果たします。
そのため、ビタミンDの活性化に関連する遺伝子に変異が起こることにより、骨や関節のさまざまな症状が現れると考えられます。
一般的に、発症と食事の内容には関連性がない
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の原因は遺伝子の変異であるため、小児期の重症例の発症には、日光を浴びる時間や食事からのビタミンDの摂取量は関連性がないとされています。
ただし、成人の軽症例(活性化酵素や受容体の機能低下が軽度の患者さん)では、ビタミンDの摂取が少なくなることを契機に発症する症例があると予想されています。
親の育児放棄が疑われることも?
私がオーストラリアで診療した患者さんは、生後14か月で腓骨や中手骨などの骨折が生じていたことから、親の育児放棄による栄養失調(ビタミンDの欠乏)や、ひいては幼児虐待も疑われていました。しかし、血液のデータからこの病気を疑って遺伝子診断を行ったところ、遺伝子の変異を発見し、ビタミンD依存性くる病・骨軟化症であることが判明しました2)。
患者さんの子どもが同じ病気を発症する可能性は低い
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、常染色体劣性遺伝形式で遺伝するため、患者さんの子どもが同じ病気を発症する可能性はほとんどないと考えられます。
常染色体劣性遺伝形式とは?
遺伝形式(遺伝する法則)のひとつです。病気にかかっていない両親のどちらも、同じ病気を引き起こす遺伝子の変異を、2つ存在する遺伝子の片方にもっている場合、生まれてくる子どもは4分の1の確率でその病気を発症します。
近親婚(結婚した相手が血縁者の場合)などでは、このような常染色体劣性形式の遺伝子疾患が発症する確率は高くなると考えられます。
一方、常染色体劣性遺伝形式の病気を発症している患者さんの子どもが同じ病気を発症する確率は、非常に低くなります。血縁者同士の結婚でない限り、結婚の相手が同じ遺伝子の同じ変異をもっていることはまれであるためです。
複合ヘテロ、de novo変異について
近親婚でなくても、常染色体劣性遺伝形式の病気の子どもが生まれることはあります。たとえば、両親がそれぞれ、同じ遺伝子の異なる場所の変異をもっている場合です(複合ヘテロ)。
また、病気にかかっていない両親の一方のみが、常染色体劣性遺伝形式の病気を引き起こす遺伝子の変異を、2つ存在する遺伝子の片方にもっている場合でも、新規(de novo: デノボ)変異発症によって発症する場合があります。すなわち、遺伝子変異をもっているのは両親のどちらかだけという、一般的には発症しないように思われる場合でも、片方の変異は親から受け継ぎ、もう片方は受精卵の段階で突然変異(デノボ変異)が起こるという状況により、病気の遺伝子対がそろって発症するケースです。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の病型

ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、原因ごとに5種類の病型に分類されています(2018年6月時点)。基本的に症状は共通しています。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症1型
1型は、体内で活性型ビタミンDをつくりだせないことにより、くる病・骨軟化症を生じる病型です。
先にお話ししたように、ビタミンDが体内ではたらくようになるためには、2段回の過程を経て活性型ビタミンDへと変化する(活性化する)必要があります。この病型では、ビタミンDが活性化する過程に関わる酵素*をコードする(指定する)遺伝子に変異が起こります。
また、1型は、原因ごとに1A型と1B型に分類されており、どちらも症状と経過は共通しています。
酵素…タンパク質などに作用し、別のタンパク質などに変化させる作用を持つ。
1A型の原因とは?
1A型は、ビタミンDを活性化させる作用をもつ「1α水酸化酵素」がうまくはたらかなくなる遺伝子変異により発症します。この病型では、ビタミンDが活性化する過程の2段回目に異常が生じ、活性型ビタミンDを十分な量つくりだすことができません。
この2段階目の反応は、以前は腎臓でしか起こらないと考えられていました。しかし、近年では、腸管や骨などの、活性型ビタミンDがはたらく場所ごとで起こっていると考えられています。
1B型の原因とは?
1B型は、ビタミンDの活性化に関連する「25水酸化酵素」がうまくはたらかなくなる遺伝子変異により発症します。この病型では、ビタミンDが変化する過程の肝臓での1段回目に異常が生じ、2段回目の変化である活性化に進むことができないため、最終的に活性型ビタミンDも必要量つくりだすことができません。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症2型
2型は、活性型ビタミンDが体内でうまく作用しない(使うことができない)ことにより、くる病・骨軟化症を生じる病型です。1型に効果を示すビタミンDの製剤を投与しても、2型の症状は改善しにくいことがあります。
また、2型は、原因ごとに2A型と2B型に分類されており、症状や経過には差がみられます。
2A型の原因とは?
2A型は、活性型ビタミンDが体内(腎臓や腸管、骨)で作用するときに情報の受け手となる部分である「ビタミンD受容体」がはたらかなくなる遺伝子変異により発症します。つまり、この病型では、体内に十分量の活性型ビタミンDが存在してもうまく使うことができません。
2B型の原因とは?
2B型は、ビタミンD受容体のはたらきが、hnRNPというタンパク質の異常な発現(つくられること)により阻害されてしまう病型です。そのため、ビタミンD受容体の反応性が低下し、やはり活性型ビタミンDをうまく使うことができません。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症3型
3型は、ビタミンDが活性化する過程でつくられる物質(25水酸化ビタミンD*と活性型ビタミンD*)が肝臓で異なる物質に変わるはたらきが強まってしまうことにより、くる病・骨軟化症を生じる病型です。薬などの異物を代謝する酵素をつくる遺伝子(CYP3A4)の変異によって発症します。また、この病型は2018年5月に初めて報告されました。
25水酸化ビタミンD…体内に取り込まれたビタミンDが活性化する過程の肝臓での第一段階でつくられる物質。
活性型ビタミンD…体内に取り込まれたビタミンDが活性化する過程の腎臓や腸管、骨、副甲状腺などでの第二段階でつくられる物質。1,25水酸化ビタミンDと同義。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の症状

くる病の症状
子どもの頃(骨端線閉鎖前)に起こる可能性がある症状としては、
- X脚、O脚
- 脊柱の湾曲
- 低身長
- 肋骨念珠*
- 関節腫脹
などが挙げられます。
肋骨念珠…肋骨が変形して節くれ立った形になること
骨軟化症の症状
大人になってから(骨端線閉鎖後)も起こる可能性がある症状としては、
- 骨痛
- 偽骨折
- 骨折
- 筋力低下
- 虫歯
などが挙げられます。
生まれつき発症する病気ですが、成人してからも骨の柔らかい状態は続くため、ひびのような骨折(偽骨折)や、本当の骨折を起こしやすくなります。骨に痛みが出て日常生活に大きく影響したり、未治療では寝たきりになったりする可能性もあります。
また、症状が長期にわたって続くと、靭帯の石灰化や関節症などが起こり、症状の改善が困難になる場合があります。
低カルシウム血症、低リン血症
ビタミンDには、カルシウムやリンの吸収を助けたり、カルシウムの尿への排泄を抑えたりするはたらきがあります。ビタミンD依存性くる病・骨軟化症を発症すると、リンとカルシウムの吸収が障害され、また尿中へのカルシウムの排泄が増加します。それにより、血液中のリンとカルシウムの濃度が低下します。
低リン血症とは?
血中のリン濃度が低下すると、強い骨を形成する「ハイドロキシアパタイト」という、骨の石灰化にとって重要な成分が不足します。このとき、本来であれば石のように固いはずの骨が、細胞成分が多く柔らかい骨になってしまいます。
低カルシウム血症とは?
血中のカルシウム濃度が低下すると、カルシウム濃度を上昇させるために副甲状腺*から副甲状腺ホルモンが分泌されます。それによって、カルシウムの排泄を減らす作用と、骨を溶かしてカルシウムを血液中へ送る作用が起こります。これらの作用が過剰になると、骨粗しょう症を引き起こす可能性があります。
また、低カルシウム血症が起こると、テタニーと呼ばれる反応を伴うことがあります。テタニーとは、血液中のカルシウムが不足することにより、筋肉が刺激に対して過敏になる状態のことです。症状としては、けいれん、「トルソー兆候」という特徴的な手の状態(手位)などがみられます。症状が重くなると、体中の筋肉が動かしにくくなる場合もあります。
副甲状腺…甲状腺の近傍にある小さな組織。
2A型では禿頭を伴う
2A型の一部の患者さんでは、髪が生えにくい状態を指す禿頭を伴います。2A型で禿頭を伴う理由は、ビタミン D 受容体の存在が毛髪の発生に関与するためだと考えられています。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の検査、診断

受診のきっかけは歩行の遅れ
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、多くの場合は歩行の遅れがきっかけで発見されるでしょう。一般的な子どもの成長過程ではおよそ1歳頃に歩行が可能になりますが、この病気では、骨の痛みが強い、骨が柔らかいといった理由からしっかりと立てず、歩行障害を生じます。そのため、1歳半から2歳半頃になっても歩行ができず病院につれていったときなどに、発見される可能性があります。
小児期には発見されない可能性もある
軽症であるために、小児期には症状がはっきりせず、成人になってから骨折や偽骨折を起こしたことをきっかけに病院を受診するケースも存在すると考えられます。ただし、このような症例では骨粗しょう症やビタミンD欠乏症などの他の病気と誤って診断されてしまう可能性が高いと思われます。
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の発症が考えられる場合、病院では以下のような検査が実施されます。
血液検査
血液検査では、基本的には、補正カルシウム(血中のカルシウムの値を血液中のアルブミン*値で補正したもの)とリンの値を測定します。
低リン血症の原因を明らかにするためには、最初に、血液中のリン濃度を調節するFGF 23というホルモンを測定することが有用と考えられます(2018年6月時点では保険適用外)。
また、ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の診断や、病型を明らかにするためには、25水酸化ビタミンDと、活性型ビタミンDの測定を行うことが重要です。活性型ビタミンDの測定が必要である理由については、次の項目で詳しく解説します。
アルブミン…肝臓で合成されるタンパク質。
遺伝子検査
ビタミンD依存性くる病・骨軟化症は、ビタミンD欠乏症という別の病気と血液検査のデータと症状がある程度共通しています。そのため、遺伝子変異によって生まれつき発症しているビタミン D 依存性くる病・骨軟化症と、ビタミンDの摂取不足によるビタミン D 欠乏症を見分けるためには、最終的には遺伝子検査を行う必要があると考えられます。
記事2『ビタミンD依存性くる病・骨軟化症の治療と経過、病院の取り組み』でもお話しするように、症状に気づいたら詳しい検査を行うことが望ましいでしょう。
医師にも啓発したい、ビタミンDの欠乏を調べる正しい検査について

医師の間でも勘違いされている、ビタミンD欠乏症の診断
先にお話ししたように、ビタミンD依存性くる病・骨軟化症と症状が類似する病気として、ビタミンD欠乏症が挙げられます。鑑別するためには正しい検査を行うことが重要です。
多くの医師の間ではこれまで、ビタミンDが欠乏しているビタミンD欠乏症の診断のために、誤って活性型ビタミンD(1,25-ジヒドロキシビタミンD3)の濃度が測定されてきました。しかし、活性型ビタミンDの測定は、腎臓でのビタミンDの活性化効率をみる指標に過ぎず、ビタミンD欠乏症の診断には利用できません。
ビタミンDは、全身ではなく局所で活性化すると考えられている
以前は、体内に取り込まれた(または皮膚で産生された)ビタミンDは肝臓で25水酸化ビタミンDに変化したあと、腎臓で活性型ビタミンDになり、全身に作用すると考えられてきました。
しかし実際には、ビタミンDは肝臓で25水酸化ビタミンDに変化したあと、腎臓や腸管、骨、副甲状腺などの、ビタミンDが作用する臓器で活性型ビタミンDになり、その場所で作用して骨の形成などに関わることが、最近ではおおよそ証明されています。
ビタミンD欠乏症の診断には、25水酸化ビタミンDの測定が必須
血液中に出てくるのは腎臓で活性化したビタミンDだけであるため、血液中の活性型ビタミンDの測定では、腎臓でのビタミンDの活性化効率を知ることしかできません。一方、活性化される前の段階である25水酸化ビタミンDの血中濃度は、骨の健康状態とよく関係する事が分かっています。
そのため、今日では、ビタミンD欠乏症の診断には25水酸化ビタミンDを測定することが必須とされています。
【参考文献】
1)Arnaud Molin, et al. The Journal of Bone and Mineral Research.2017;32(9):1893-1899.
2)Nobuaki Ito, et al. The Medical Journal of Australia.2014;201(7): 420-421.
東京大学医学部附属病院 難治性骨疾患治療開発講座 特任准教授、骨粗鬆症センター 副センター長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
東京大学医学部附属病院 難治性骨疾患治療開発講座 特任准教授、骨粗鬆症センター 副センター長
伊東 伸朗 先生日本内科学会 総合内科専門医・内科指導医日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・内分泌代謝科指導医・評議員日本糖尿病学会 糖尿病専門医・糖尿病研修指導医日本人類遺伝学会 臨床遺伝専門医日本骨粗鬆症学会 認定医・評議員日本骨代謝学会 評議員
糖尿病、高血圧や内分泌疾患全般を診療しているが、その中でも骨粗鬆症や原発性副甲状腺機能亢進症、くる病・骨軟化症といった骨代謝疾患の診療を専門としている。特に生理的なリン濃度調節因子であるFGF23が関連する疾患に関しては世界に先駆けた臨床研究・基礎研究を行っている。
「東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 内分泌骨ミネラル代謝研究グループホームページ」
https://plaza.umin.ac.jp/bone-mineral-lab/伊東 伸朗 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
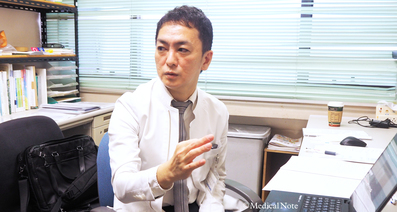
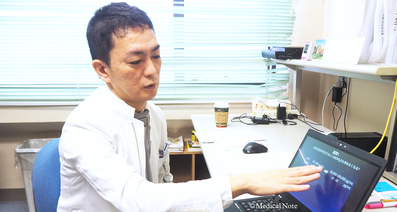
ビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症-治療

FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症——症状、検査、診断
関連の医療相談が1件あります
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「骨軟化症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。