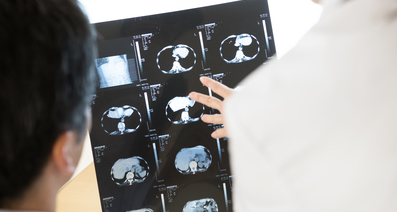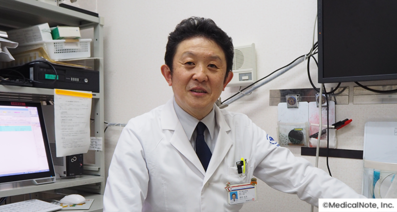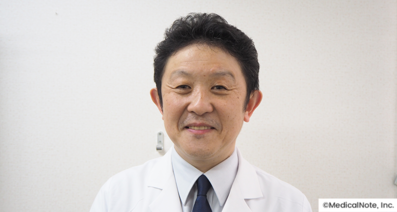2016年1月に横浜で行なわれた「第34回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会」において、粒子線治療と口腔がん領域における動注療法の第一人者として知られる伊勢赤十字病院放射線治療科部長(兵庫県立粒子線医療センター名誉院長)の不破信和先生がシンポジウム・学術セミナーなどに登壇されました。本記事ではその中から「頭頚部癌に対する動注併用放射線治療の役割―浅側頭動脈からのアプローチを中心に―」と題して行われた講演の内容をお伝えします。
動注方法の歴史、方法、適応例について
頭頚部がんに対する動注は1950年に始まる、古くて新しい治療です
1992年にアメリカのRobbinsらが、大腿動脈からのセルジンガー法によって、チオ硫酸ナトリウムで中和しながら高用量のシスプラチン(抗がん剤)を投与するという治療を報告しました。その良好な治療成績から動注療法が世界中に広がったとされています。一方、私達の方法は耳の前にある浅側頭動脈からカテーテルを挿入する方法ですが、この方法は脳血管障害の少ない点、長時間の薬剤投与が可能な点は大きな利点であるといえます。
治療方法の変遷について
従来の私達の方法は舌動脈の入り口にカテーテル先端部分を僅かに挿入する方法であったため、容易に脱落してしまうことがありましたが、その後、カテーテルを改良し、舌動脈の奥まで挿入することが可能になりました。その結果、脱落率は24%から1%に大幅に減少し、安定した治療が可能になりました。
頭頚部がんに対する動注併用放射線療法が市民権を得るには
以下に示すことが確認されて初めて、動注療法が安定した治療結果が得られることになると思います。
- 治療方法が再現性に優れ、安定した結果が得られること
- 動注の還流域が確認できること
- 動注療法に適した薬剤の種類、量が確立していること
- 薬剤の静脈内投与に較べて、明らかな優位性をもつこと。また手術に較べても何らかの優位性があること
まだ上記の条件を完全に満たしているとは言えませんが、カテーテル、手技の改善により、安定した治療効果が得られる様になりました。動注薬剤の流れる範囲の確認は、新たにMRIを用いる方法を開発し、より客観的な評価方法を確立しました。動注薬剤はカルボプラチン(CBDCA)から、シスプラチン(CDDP)を使用し、その中和剤であるチオ硫酸ナトリウムを同時に静脈からら投与することにより、より高い効果が得られることを示しました。Robbinsらが確立した方法の改良版ではありますが、彼らの方法より少ないCDDPを使用していますので高齢者にも治療の適応が広がりました。動注の適応例は舌癌に代表される口腔癌、上顎洞がんが対象と考えていますが、その治療成績は少しずつ改善されており、現在では手術と遜色のないレベルにあり、治療の選択肢の一つとなったと考えています。
頭頚部がん動注療法の今後について、粒子線治療との併用の意義
粒子線はX線に比べてがん細胞だけに集中的に照射することが可能で、周囲の正常な組織に影響を及ぼしにくい特徴があります。そのため、下顎に照射する場合、X線に比べて歯を守れるというメリットがあります。また、転移したリンパ節に集中的に照射する場合にも有効です。

粒子線の照射方法は、現在ブロードビームという方式ですが、将来的にはスポットスキャニングが可能になります。このことによって、IMRT(intensity-modulated radio therapy)よりも、より効果的なIMPT(intensity-modulated proton therapy)が実現するでしょう。これにより、さらにより高い治療効果と、より少ない有害事象が得られるものと考えています。
シースの有用性について
シースとは親カテーテルのことで、このシースから目的動脈にマイクロカテーテルを挿入する方法です。腹部での血管造影では大腿動脈からシースを挿入する方法は一般的な方法です。私達は浅側頭動脈から、世界初となるシース (External Carotid Artery Sheath:ECAS)を開発しました。この方法により、今まで1本の動脈にしか薬剤の投与が出来ませんでしたが、複数の動脈への安定した薬剤の投与が可能となり、より高い治療効果と適応の拡大に繋がるものと考えています。また手技の簡便さから動注療法の普及に繋がるものと期待されます。

また、ステアリングマイクロカテーテルという、最近我が国で開発された腹部用のカテーテルも利用可能です。これは手元のハンドル部分にあるダイヤルの操作でカテーテル先端の方向付けを遠隔に操作できるもので、ガイドワイヤーを必要としないため、透視時間が短くて済むという利点があります。その感触は良く、年内には頭頚部専用のステアリングマイクロカテーテルが完成する予定です。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
睾丸にシコリ
息子が3日前に男性の睾丸の中にシコリがあり今日、泌尿器科に行きました。レントゲン、エコーはなく尿検査はありました。後は先生が手で触っての診察でした。潜血反応±、白血球が+(尿一般)と書いてありました。息子が先生から説明されたのが精子を作る横に2つシコリがある(1個は良く男性にあるが2個は珍しい)炎症をおこしている。と言われたそうです。1週間後に病院受診。エコーがあるそうです。尿の菌は何か原因を調べましょう。と言われたそうです。薬を1週間毎朝食後に飲むようにもらいました。治らないと不妊症になりやすいとも言われたそうです。ガンが親の私は心配になりました。ガンの事は何も言われなかったそうですが可能性はありますでしょうか?
声のカスレが治らない。
本年4月5月の2か月間、風邪だと思いますが、咳が四六時中止まりませんでした。(これまでに経験したことがない状況)六月に入り止まりましたが、現在でも痰が絡むのと、声のカスレがあり元の声に戻りません。気になりますので対処方法を教えてください。
喉と頭の強い痛みと発熱
先週の月曜日から喉の痛みがあり受診。 PCR検査は陰性。 薬を処方され帰宅(薬の詳細不明)。 次の日から発熱、頭痛、喉の痛みが酷くなる。翌日、再度通院。2回目のPCRも陰性。 血液検査をした所、細菌性の風邪?でしょうとの事で、抗生物質を処方される。 食事が摂れない為、点滴して帰宅。 抗生物質を飲み始めて3日ですが、症状改善せず、喉の痛み、頭痛がかなり強い様子。 熱も7度台と8度台の繰り返し。 再度、受診した方が良いのか? 内科で良いでしょうか? ご意見お願いいたします。
再発リスクの評価
表在性膀胱癌の手術を6月に行い、単発抗がん剤注入を受けました。 その後、先9月の膀胱鏡検査では、再発をしていませんでした。 比較的簡易な処置で済む癌ですが、1年以内の再発率60%程度と高く、一度再発すると2度目は70%、3度目80%、とさらに上がるそうです。 よって近場の泌尿器科のクリニックでがん細胞診の尿検査を毎月受け、3ヶ月毎に膀胱鏡検査をすることにしています。 しかし、その確率の高さを考えると憂鬱です。先手を打ち再発リスクを下げる方法はないのでしょうか? また、よしんば再発が免れたとしても、いったいあと何年再発への注意をしなければいけないのか?見通しが欲しいです。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「口腔がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします