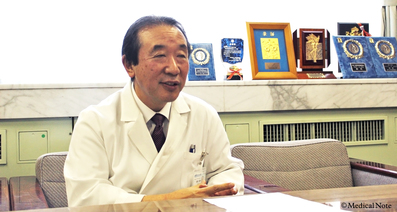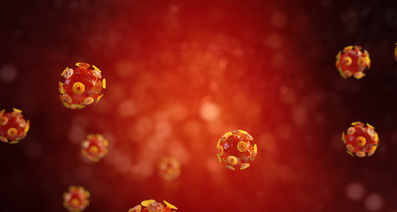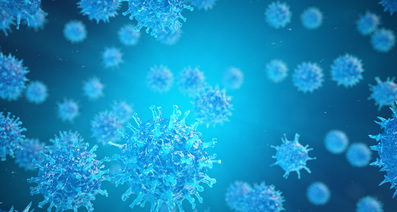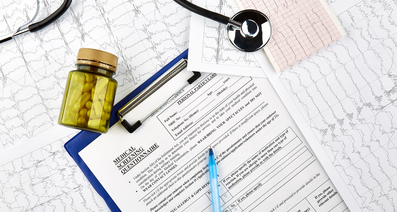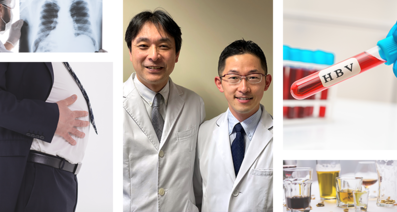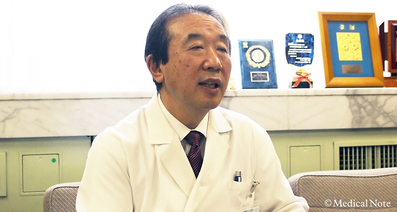
B型肝炎ウイルスも、「C型肝炎の治療―大きな進歩を遂げた治療」で説明したC型肝炎ウイルスと同様に肝炎の原因として有名です。B型肝炎においては、C型肝炎ほど画期的な治療の進歩があったわけではありませんが、近年ではきちんと薬を継続することによりコントロール可能な病気になっています。この記事ではB型肝炎の治療について、大阪市立大学肝胆膵病態内科学教授の河田則文先生にお話をお伺いしました。
B型肝炎の治療
B型肝炎は完治はしないが薬でウイルスを抑えられる
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気です。これもC型肝炎と同様に肝硬変や肝臓がんの原因になります。肝炎ウイルスの検査は各都道府県では健診に組み込まれていることがあり、そうでない場合も検査は都道府県などが指定した医療機関であれば無料で受けることができます。
B型肝炎の治療におけるC型肝炎との違いは、C型肝炎ウイルスは完全に排除することが出来る一方で、B型肝炎ウイルスは完全に排除することはできないということです。つまり、「完治」の状態に持っていくのは困難なのです。これは、B型肝炎ウイルスが肝細胞の核に入りこんでしまうためです。
しかし、B型肝炎ウイルスの増殖を防ぐための薬(逆転写酵素阻害剤といいます)はいくつか登場してきました。「エンテカビル」「テノホビル」という薬が有名で、これは飲み続けていれば血中ではウイルスの増殖を抑えこみ、血液検査上は検出限界以下(血液検査をしてもB型肝炎ウイルスが現れない)まで抑えることができます。飲み薬を飲めば病気を抑えこみ、ウイルスの増殖を抑えることができるようになったのです。つまり、「薬を飲まない状況にはできない」ものの「薬を飲んでさえいればコントロールは可能」ということです。
ただし、血液検査の見かけ上B型肝炎ウイルスが検出されない方でも危険なケースに「再活性化」があります。再活性化とは、免疫抑制剤や抗癌剤治療をした際に免疫力が落ちてしまうとB型肝炎ウイルスが暴れ出し、急性肝炎様に、時には劇症肝炎化してしまうことです。劇症肝炎は死に至る可能性もあり、非常に危険なので再活性化には注意しなければなりません。
B型肝炎は感染しやすい(うつりやすい)
性交渉、ピアスやタトゥーの針で感染する例も
B型肝炎が感染する機会は日常に存在します。特に若者において、性交渉、ピアス、ファッションタトゥーなどによる感染が見られます。現在200万人の方がB型肝炎と診断されていますが、肝炎を発症していなくてもB型肝炎ウイルスが肝臓の中に潜んでいる方は1000万人程度いるとされています。また、最近では海外から日本にはいなかったタイプのウイルスが入ってくるようにもなっています。
そのような経緯もあり、B型肝炎においてはさまざまな感染対策が行われています。「母子感染予防法」ができてからは新規のB型肝炎患者は減少してきています。また、予防接種においても定期接種となることが決まりました。
肝炎ウイルスを駆除しても治らない肝硬変を克服するための研究
「C型肝炎の治療―大きな進歩を遂げた治療」ではC型肝炎、本記事ではB型肝炎の治療を主にお話ししてきました。肝炎ウイルスにより引き起こされた肝炎は治療することが可能です。では、肝炎ウイルスにより引き起こされた肝硬変(肝炎が進行し、肝臓の機能が落ちて見た目もゴツゴツと固くなったもの)を治療することができるのでしょうか。
肝炎ウイルスにより引き起こされた肝硬変は軽症のもの(Child分類のAと言われます)であれば治療することができます。その場合、形態学的には元通りにはならないけれども機能的には改善します(つまり、見た目は肝硬変のようにゴツゴツしたままですが、肝臓の機能は元通りになります)。しかし、悪化した肝硬変に関してはまだ治療することができません。
1980年代のはじめには、なぜ肝硬変が生じるのかというメカニズムも分かっていませんでした。肝細胞が壊れて線維(コラーゲン)を作ると思われていました。しかし1985年に画期的な発見がなされ、星細胞という細胞が線維化を生じさせていることが分かりました。
肝硬変を克服するため、大阪市立大学ではこの「線維化」の研究が続けられてきました。そのなかで、星細胞による線維化と発がんが密接に関係しているということを突き止めました。現在、星細胞の活性化を食い止めるための物質の研究を行っています。星細胞の活性化を抑えることができれば、肝臓の線維化、つまり肝硬変を抑えることができます。今後は肝硬変の治療薬にもこの研究をつなげていくことを目指しています。
大阪市立大学医学部附属病院 病院長補佐、大阪市立大学医学部附属病院 肝胆膵内科部長、大阪市立大学医学部附属病院 輸血部部長、先端予防医療部MedCity21 副部長、大阪市立大学院医学研究科 肝胆膵病態内科学 教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
おたふくワクチンとB型肝炎ワクチンの間隔は?
おたふくワクチンと、B型肝炎ワクチンはどの程度間隔を空けた方がいいですか??今から10年くらい前に同時期に接種してたようです。今更ながら書類で確認し、 気になりまして質問しました。異なる病院でしたが、その当時も間隔空けず平気だったのかなと思いまして。。
短期間で数種類の予防接種とコロナ感染について。
10前にB型肝炎ワクチンし、去年またB型肝炎接種しました。(抗体調べず接種してしまった。)その後コロナワクチン.インフルワクチンと2ヶ月間隔で受け、4回目のコロナワクチンも済んでますが、今コロナに感染…。 そこで、B型肝炎の再接種した後であること、また短期間で複数のワクチン接種したあとに、 コロナに感染したことが気になりました。 特に持病とかはないですが 上記の状況で身体に悪影響はありますか?拙い文ですみません。 ご教示ください。
C型肝炎ウィルス陽性といわれました
目の治療で入院するときに血液検査でC型肝炎ウィルス陽性と言われました。 感染経路がわかりませんが、感染してから症状がでるまでどのくらいなのでしょうか。 また症状、治療法を教えてください。
予防接種前の抗体検査
海外渡航に際して、麻疹、風疹、破傷風、A型肝炎などの予防接種を求められています。 過去の接種歴はありますが、一般的に言われている持続期間は過ぎてしまっています。 麻疹/風疹に関しては接種歴あるものの1回しか摂取していませでした。 このような場合、通常、抗体検査をして抗体の有無を確認してから接種の検討をするのでしょうか。それとも切れている前提で抗体検査はせず接種をするのでしょうか。ご助言いただけますと幸いです。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「B型肝炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。