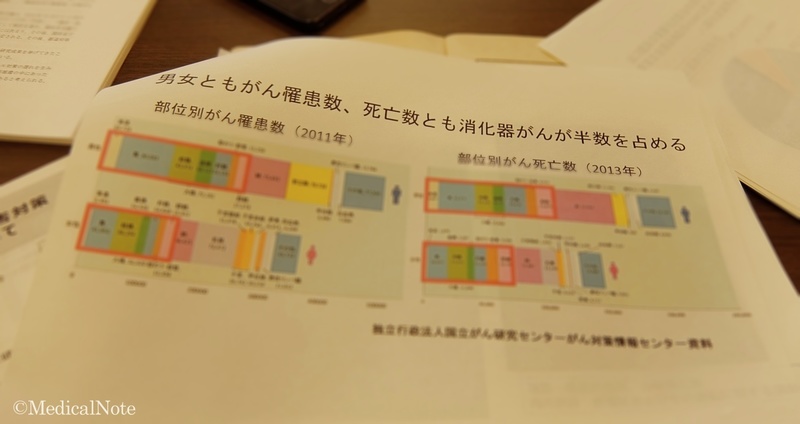飲酒の習慣には地域性が現れます。また、その地域性によってそれぞれに異なるアルコール問題があります。具体的にどのような問題が挙げられるのでしょうか。国際医療福祉大学病院の高後裕先生にお話をうかがいます。
飲酒の習慣に表れる地域性
たとえば、度数の強いお酒を飲む習慣のある九州や東北などでは肝障害が多いといわれます
全国的な消費量は減少傾向にあるものの、都会から離れた地域では、仕事が終わって早くからお酒を飲む習慣も根強く残っています。飲酒の習慣は古くからあるため、アルコールの教育は非常に難しいといわれています。
若い世代への飲酒問題の啓蒙
大人になってからのアルコール教育は非常に困難であるため、お酒に対する知識を子どもの頃から持ってもらおうとする取り組みも始まっています
たとえば、妊娠時に飲酒すると先天性奇形などアルコール性の胎児症候群の恐れがあります。ですから、若い女性にはできるだけ早くから飲酒の妊娠への影響を理解してもらうことが大切です。また、20歳になって飲酒ができるようになるまでにアルコール依存症などのリスクを知っておき、実際に飲酒できる年齢になった時に適正な量でとどめられる意識をお子さんたちに持っていただけるような指導が必要です。
お酒に寛容な日本
世界には、宗教上の理由から飲酒が禁じられている国などもあります。また、欧米ではアルコール依存症になるようなことがあれば社会的弱者とみなされ、差別の対象にすらなる可能性があります。それに比べると、日本は非常にお酒に寛容な社会といえます。ですから、社会的にお酒に対する価値観が育ち、多くの方がお酒はどういう嗜好品であるかを理解することができれば、1回の飲酒量はそれほどたくさんである必要がなくなるのではないかと思っています。
アルコールの良い影響
一方でアルコールは、非常に少ない量であれば、食欲を上げたりする効果があります
適正量であれば、胃酸も分泌されやすく、腸の動きもよくなります。食前酒などがふるまわれるのはそのためです。
記事2『飲酒の習慣に現れる地域性とアルコールの影響』でご紹介したように、「適正量=日本酒1合」という基準が意味するのは、このような良い影響が出るのがせいぜい1合程度だろうということです。1合といえば飲んだかどうかわからない、飲み足りないという程度に感じる方も多いと思われます。しかし、世間で騒がれている「お酒は体によい」という場合の好影響は、その程度の適正量でなければゆうに悪影響に変わりうるということです。
アルコールの悪い影響、消化器疾患
アルコールは、肝臓のみならず口内から食道、胃、腸、肛門に至るまで、その通り道すべてに影響を及ぼします
お酒によるもっとも多い症状として下記のようなものが挙げられます。
|
<それぞれの消化器官への影響> 肝臓・・・マロリーワイス症候群(お酒を飲んだ時に静脈瘤が破裂して吐血すること) 大腸・・・大腸がん |
発がんのリスクはいつの年代からでも高まる可能性がある
アルコールには発がんリスクがあることが知られていますが、発がんまでにはおよそ20~30年程度かかるといわれています
もし20歳から適正飲酒量を超えてお酒を飲み始めた場合、早ければ40歳の時点でがんが発生することになります。またこの時考慮するのも飲んだ日数や度数ではなくアルコールの絶対量です。つまり、「生涯でどれだけアルコール分を摂取したか」ということです。
生涯全体を考えると、お酒などのさまざまな嗜好品が生活に入ってきてそれを摂取し続け、発がんのリスクが高まる年齢はちょうど40歳頃ということになります。しかし、お酒を多量に摂取した悪影響が発症することは、高齢者になってから大量の飲酒を始めても、言い換えればどの年代からでも起こり得ます。現代人は100歳まで生きることも可能ですから、たとえば、60歳で定年を迎えるまであまり嗜好品を生活に取り入れなかった方が、その時点から毎日大量飲酒、大量喫煙を始めれば、80歳でこの影響によりがんを発症することもありうるということです。
お酒が「ダメ」ということではなく、そのようなリスクがあると理解して上手につきあうということが大切です。
国際医療福祉大学病院 消化器センター長/予防医学センター長、国際医療福祉大学 医学部教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。