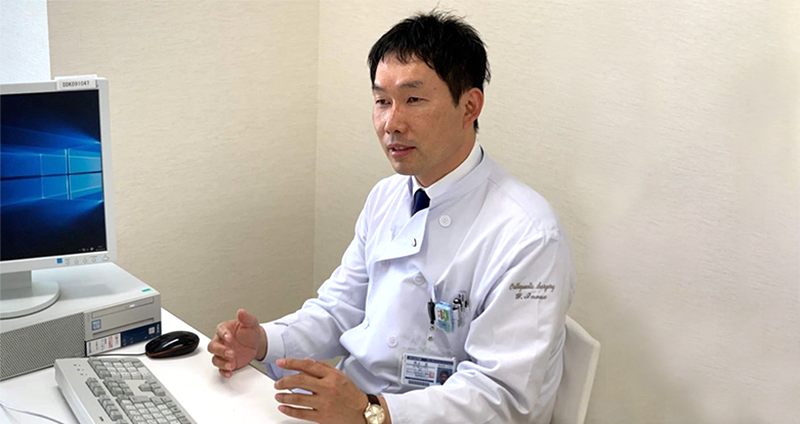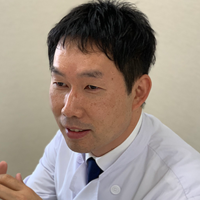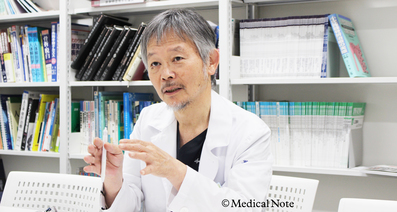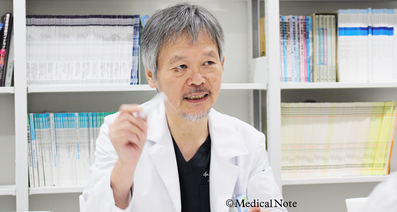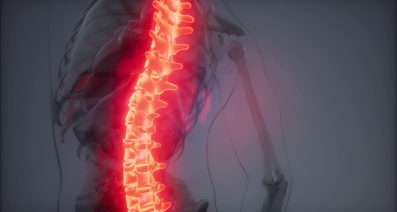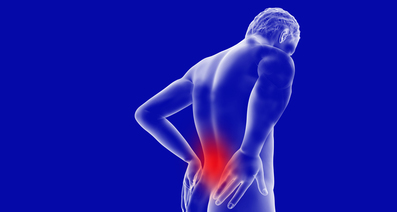人の背骨は常に体重を支えており、負担がかかりやすい場所の1つです。腰部脊柱管狭窄症とは、加齢に伴い腰の背骨に変化が生じてくることで末梢神経である馬尾神経の通り道である脊柱管やそこから枝分かれする神経根が圧迫され、下肢を中心にさまざまな症状が現れる病気です。腰部脊柱管狭窄症の治療には保存療法と手術療法がありますが、治療選択にあたっては、患者さんの困っている症状、重症度などから総合的に考える必要があります。腰部脊柱管狭窄症の原因・症状・治療について、北里大学医学部 整形外科学 診療教授の井上 玄先生にお話しいただきました。
概要
腰部脊柱管狭窄症とは
人の背骨は加齢に伴って少しずつダメージが蓄積し、変性(年齢的な変化)が生じてきます。背骨の変性によって脊柱管という神経が通る管が圧迫され、狭くなることで神経の機能が障害されると、四肢や体幹の痛み、しびれ、力が入りにくい、といった症状が起こります。このように、脊柱管の圧迫によりさまざまな症状が現れる病気が“脊柱管狭窄症”であり、中でも腰椎と呼ばれる腰の部分の神経が圧迫されているものを“腰部脊柱管狭窄症”といいます。腰部脊柱管狭窄症は手術に至る腰椎疾患のうちもっとも患者数が多いことが知られています。

原因
加齢
加齢に伴い脊柱管の後方を支えている黄色靱帯という脊柱管後方を支える靱帯がたわんだり肥厚したりして脊柱管を圧迫することが主な原因となります。また、椎間板(骨と骨をつなぐ軟骨状のクッション)が変性して膨隆したり、椎間板の高さが縮んで、骨棘という骨の出っ張りが形成されて発症するケースもあります。また、椎間板ヘルニアや椎体のずれを伴う場合もあります。
糖尿病、高血圧、心疾患を併発しやすい
糖尿病や高血圧、心疾患のある患者さんは、それらがない患者さんと比較して腰部脊柱管狭窄症の発症率が高いということが知られていますが、直接の因果関係があるかはまだ証明されていません。
生まれつき脊柱管の幅が狭い
先天的に軟骨の成長が不足して、腰椎が形成不全となりやすい体質の方がいます。そのような方の場合、脊柱管の幅が通常の方よりも狭く、加齢による変性が本格的に生じる前の若い時期に腰部脊柱管狭窄症の症状が現れることがあります。ただし、このようなケースは多くはありません。
症状——初期と進行期の違いは?

初期
初期には多くの場合、臀部(お尻)や下肢の痛み・しびれが現れます。
また、脊柱管狭窄症の特徴的な症状に間欠性跛行があります。間欠性跛行とは、足のしびれや痛みが現れるために歩きづらさを感じるものの、しばらく休むと楽になり再び歩けるようになるという特徴的な症状を指します。発症初期には明らかな間欠性跛行はない場合が多く、足の痛みやしびれといった症状は感じていても、歩行自体には制限がないという方が多いです。
進行期
症状が進行すると下肢の痛みやしびれが酷くなり、歩くことに影響が生じます。間欠性跛行が生じ、一度に歩ける距離もだんだんと短くなってきます。さらに進行すると、会陰部の灼熱感や排尿困難、残尿感などの膀胱直腸障害が生じる場合があります。
膀胱直腸障害が現れた場合、かなり病気が進行した状態と考えられます。
どのような症状が現れたらどの診療科を受診すべき?
腰部脊柱管狭窄症では神経が障害されるので、重度な症状が現れるまで進行してしまうと、たとえ手術などの治療を行っても神経の機能が思ったほど回復しない可能性が高くなります。そのため、早期診断・治療が大切です。大腿や下腿、足部がしびれる・痛む、歩行でそれらが悪化し長い距離を歩くことができないなどの症状がある場合は、整形外科(または脊椎疾患を扱っている脳神経外科)への受診を検討してください。
検査と診断
主な検査の内容
問診
問診では、どのような症状で困っているのか、症状はどういったときにどの場所に起こるのか、姿勢によって症状の強さは変わるのかなどを患者さんに伺います。膀胱直腸障害があっても背骨の病気と思わない患者さんもいるので、残尿感などの症状が生じていないかもお聞きします。これらに関する情報を得ることで、疑われる病気が腰にあるのか、別の場所なのかということをスクリーニングします。
神経学的所見のチェック
打鍵器(診察用のハンマー)を使い腱反射の状態を調べたり、手で抵抗を加えて力くらべをする徒手筋力テストで運動神経に麻痺がないかを調べたりして、患者さんの状態や重症度を詳しく観察します。他疾患との鑑別のために特定の姿勢を取っていただくこともあります。
画像診断
問診や神経学的検査からある程度の状態が確認できたら、X線検査(レントゲン検査)、MRI検査などの画像診断を行い、総合的に判断して診断を確定します。
似た症状が見られるほかの病気には何がある?
末梢動脈疾患(Peripheral Arterial Disease:PAD)という下肢の動脈が詰まる病気でも、足の先のしびれや痛み、間欠性跛行など腰部脊柱管狭窄症によく似た症状が生じることがあります。では、腰部脊柱管狭窄症との症状の違いは何かというと、腰部脊柱管狭窄症の場合は“前かがみになると楽になる”という特徴があることです。前かがみになると脊柱管を圧迫する主因である黄色靱帯がピンと伸びて脊柱管の面積が広がるため、前かがみの姿勢で休んでいるとまた歩けるようになります。一般的に腰部脊柱管狭窄症の患者さんは、通常の歩き方ではすぐに下肢のしびれ、痛み、あるいは脱力で歩けなくなるけれども、やや前屈状態でショッピングカートを押している状態ならばいくらでも歩ける、自転車はいつまでも漕いでいられる、という方が多いです。これに対して、末梢動脈疾患に伴う間欠跛行が生じている場合、その症状は姿勢に関係なく生じるため、前かがみの姿勢をとっても症状は和らぎません。
腰部脊柱管狭窄症の治療(保存療法・手術)について
保存療法の適応と特徴
麻痺などの重い症状が出ていない場合は、基本的に保存療法が適応されます。腰部脊柱管狭窄症に対する保存療法には主に“薬物療法”“運動療法”“神経ブロック療法”の3種類があります。
薬物療法
薬物療法は軽症例で最初に選択されることの多い治療法です。痛み止めや神経組織への血流を増やす薬(プロスタグランジンE1誘導体製剤)などを組み合わせたり量を増減したりして、その方に適した種類・量の薬を処方することで、歩行距離や日常生活動作(ADL)の改善を目指します。
運動療法
腰部脊柱管狭窄症に対する運動療法は最近さまざまなエビデンスが積み上がってきており、症状改善に有用であることが分かってきました。特に有用とされているのは運動療法の専門家である理学療法士の指導を受けながら、一定の運動課題を一定頻度で数か月間継続することとされていますが、それが難しい場合は地域で行われている運動教室などに参加し、定期的な運動を心がけるようにするとよいでしょう。
神経ブロック療法
X線やMRIなどの画像診断の結果と実際の症状から明らかにどこの神経が障害されているのかが分かっている場合は、それぞれの症状に応じた神経ブロック療法を行います。ただし、どの程度痛みが軽くなるか、どの程度の期間効果が持続するかは個人差があります。
手術の適応と特徴
どのような患者さんに適応される?
腰部脊柱管狭窄症では、治療前の状態が悪い方ほど治療後の経過もよくない傾向にあります。そのため病気が進行して、膀胱直腸障害、著しい筋力低下や歩行困難、麻痺などの日常生活に著しい支障をきたす症状が出る前に手術を行うことが望ましいと考えます。保存療法を行っているにもかかわらず下肢の痛みや麻痺が強くなってきている場合など、重症化する傾向にある患者さんには、積極的に手術の適応を検討します。
手術の実施は慎重に考えることが大切
しかし、腰部脊柱管狭窄症に対する手術の適応は慎重に行わなければなりません。手術を行う前に、手術という手段で患者さんが治してほしいと思っている症状が本当に改善するのかを判断することが私たち医師の役目でもあります。
手術をする最大の目的は患者さんが困っている症状を取ることですが、手術により改善が期待できる症状と、手術を行っても改善しにくい症状があります。たとえば、安静時に感じるしびれや、重度の筋力麻痺、足がつるといった症状は手術後も改善せず、残ってしまうことが多いとされています。一方で、痛み、歩行距離、日常生活動作(ADL)については手術で改善される可能性が十分にあります。
また腰部脊柱管狭窄症の手術とは、あくまで神経の通り道を整えて神経がはたらきやすい環境に戻す手術です。背骨という、人間の体を支える“屋台骨”の構造を一部壊す必要があるわけですから、術後、腰椎の負担が増す場合もあります。さらに、環境を整えた状態でどの程度神経が回復するのかは個人差がありますし、たとえ100%完璧な手術をしても神経症状を完全に取り除くことが実際には難しい場合もあります。手術が全ての症状を取る万能の治療法ではないということを、事前に患者さんにも理解していただく必要があると考えています。
具体的な手術の方法
腰部脊柱管狭窄症の手術には、除圧術と固定術という2つの方法に大きく分けられます。

除圧術
除圧術は、神経圧迫の元となっている骨や黄色靱帯などを切除することで、神経の圧迫要素を取り除く手術です。術後も腰の動きが制限されないため、術前と比べて体が硬くなる、腰が曲げにくくなるといった動きの制限が起こりにくく、腰椎が持つ本来の動きを温存することが期待できます。また、固定術に比べて侵襲性が低い点も特徴です。
しかし、背骨を固定せず動かせる状態のままにしているゆえに、手術後に不安定性(背骨のぐらつき)が増悪し、腰部脊柱管狭窄症の症状が再発する可能性があります。このため除圧術を行った部分にまた変形が進んできたり、不安定性が強くなったりした場合は、次に述べる固定術をやり直すことも少なくありません。
固定術
背骨の不安定性が強い患者さんの場合、除圧術で圧迫を取り除くのみでは神経症状が遺残する可能性があるため、固定術が選択されることが一般的です。
固定術では、神経を圧迫している部分を取り除いた後で、不安定性を認める範囲の背骨を固定し、神経機能が回復しやすい環境を作ります。背骨の固定方法は、金属製のスクリューなどを使用し、砕いた骨を固定する範囲に移植し、癒合させる方法が一般的です。最近は直接の除圧を行わず、側腹部から背骨を削らずに椎間板をかさ上げし、間接的に除圧を行う新たな固定術も行われています。
固定術で移植する骨はほとんどの場合、患者さん自身の骨(自家骨)です。固定術を行う際は、除圧術のときに削った骨を集めて移植するのが一般的ですが、自家骨のみでは対応が困難な場合は、人工骨やドナーから提供された骨(同種骨)を移植するケースもまれにあります。
背骨の不安定性が高い患者さんの場合は、一般的に固定術を行うことでより神経症状が回復しやすくなります。しかし固定術は除圧術に比べて侵襲度が高く、手術時間や合併症のリスク、難易度、コストなどのさまざまな面で負担が大きい方法といえます。固定術の直後は骨が癒合していないため、しばらくの間コルセットを着用して生活する必要があります。体が硬くなる、前かがみになりにくいなどの症状が術後に生じる可能性もあります。また、固定した骨の上下の動く部分には、固定しない場合と比較して負担が増すことになるため、固定した上下の椎間で脊柱管狭窄症が比較的早くに再発する患者さんもいます。つまり除圧術も固定術も、神経症状の再発のリスクがまったくない手術ではなく、それぞれに長所と短所があります。どちらがより望ましいかは患者さん個々で異なるといえます。
固定術の侵襲度をなるべく下げるための工夫
当院は元来、側弯症やすべり症などの脊柱変形が強い患者さんに対する大きな手術を積極的に行ってきたという背景があります。そのため、脊柱変形と腰部脊柱管狭窄症の合併例や、長範囲の複数箇所に脊柱管狭窄が見られる患者さんを治療する機会が多く、固定術を選択するケースが比較的多いといえます。
固定術は侵襲度が高い手術であるため、侵襲性の低い術式であるMIS(Minimum Invasive Surgery)を導入し、侵襲度をなるべく下げるような工夫をしています。具体的にはスクリューを刺入する部分のみをピンポイントで小さく切開し、わずかな幅の間から経皮的にスクリューを設置したり、筋肉や骨の大きな展開を避けて脇腹から椎間板を摘出し、固定を行う側方進入椎体間固定術などの負担の少ない術式を取り入れています。
さらに、神経モニタリングやナビゲーションシステムを導入していることも当院の特徴です。神経モニタリングは、手術中の操作により、神経が麻痺を起こしていないかなどを確認することができる装置です。ナビゲーションシステムは、直接目では見えない体の内部の画像データをモニターに映し出すことで、スクリューを刺入する方向や深さなどをリアルタイムで確認しながら手術を進めるためのシステムです。
こうした機器を腰部脊柱管狭窄症の手術にも、必要に応じて取り入れることで、出血を少なく、神経や血管損傷などの重篤な合併症のリスクをなるべく少なくした、より安全で確実な手術を目指しています。
手術後の合併症
繰り返しになりますが、手術は体に負担をかける治療法です。圧迫された神経機能を回復させるために、ほかの機能を犠牲にしなければならないこともあります。もちろん医療機関は合併症のリスクも考えたうえで適切な術式を選択し、術後合併症が起こらないように最大限の注意を払っていますが、手術によって下記のような合併症が起こる可能性はゼロではありません。
術後創部感染
背骨の手術の後に生じうる重大な合併症の1つです。術後創部感染(傷口が膿むこと)が起こった場合、抗生剤の治療では治癒せず、創部を切開し直して洗浄などの再手術を必要とする場合もあります。特にスクリューなどの金属製のインプラントを用いた手術の場合、1回の処置では治らず、長期間かけて複数回の手術を必要としたり、やむを得ず使用したインプラントを抜去して術後創部感染の治療をしなければならない場合もあります。
血腫
手術後に閉じた創の中で出血が起こり、神経の周りに大きな血の塊(血腫)が形成されて麻痺をきたす可能性があります。麻痺が進行した場合は、血腫を除去する再手術を早急に行わなければなりません。特に抗凝固剤を常用している患者さんは術後血腫を生じるリスクが高いといえます。
神経損傷
手術で剥離や除圧などを行った際、神経を傷つけてしまう(神経損傷)と、術前には見られなかったしびれや痛み、筋力低下などの神経症状が新たに現れることがあります。
血栓塞栓症
手術は同一姿勢で数時間、全身麻酔下で行うものが多く、術中や術後に下肢静脈に血栓(血の塊)が詰まる場合があります。重症化すると下肢静脈から剥がれた血栓が心臓を通り抜けて肺の動脈に詰まる場合があります(肺梗塞)。肺梗塞が生じた場合、生命に関わる事態となる場合もあります。
(固定術の場合)骨癒合不全
固定術の後に起こり得る合併症で、骨同士がうまく癒合せずにスクリューがゆるんで抜けてしまったり、骨折したりする可能性があります。骨の位置がずれた場合、神経症状が再発する場合もあります。
予後・治療後の経過
予後は重症度によって異なります。下肢のしびれや痛みなどの症状は出ているが間欠性跛行による歩行制限もなく、日常生活に大きな支障が出ていない軽度~中等度の患者さんの場合、適切な治療を受けていれば必ずしも悪化の一途を辿るわけではありません。中には、自然経過で症状が改善する方もいらっしゃいます。
一方で、治療前から間歇性跛行の距離が短い方や、膀胱直腸障害のような神経症状が出ている重度の患者さんに関しては、治療を行った後も症状の改善が限定的なものになる傾向があります。術前の症状の重さは術後の神経症状の回復の程度に影響することが分かっており、症状が悪化してきたら適切なタイミングで手術を検討することが大切だと考えます。
再発時の治療
除圧術、固定術によらず、腰椎の術後の変性を止められるわけではありません。術者が適切と考える術式で手術を行っても、やがて症状が再発することがあります。再発までの期間には個人差がありますが、数年で一定の割合で症状が再発し、再手術に至る方がいるのが現状です。
一方で、仮に症状が再発した場合でも必ず手術が必要というわけではなく、患者さんの希望や状態によっては、薬物療法や運動療法、神経ブロック療法などの保存療法で症状が改善することもあります。
日常生活での注意点
基本的に自己判断で治療を中断せず、患者さんになるべく合った治療を見つけ、継続していただくことが大事です。どのような治療法であっても継続してこそ効果が出るものです。もし、今行っている治療で症状が改善しない場合は主治医に相談したうえで、今の治療を継続するのか、治療方針を変えるのか、より自分自身に合った治療法を相談してみましょう。
また、腰部脊柱管狭窄症という病気に対して“安静”という治療法は長い目で見て有効でない場合が多いといえます。基本的な体力・健康維持の意味でも、一定の負荷で運動を心がけましょう。その内容も患者さんの状態によって異なるため、主治医とよく相談して安全に行ってください。

井上先生からのメッセージ
腰部脊柱管狭窄症は特に60歳代以上で患者数が多い病気の1つであり、保存療法・手術治療も含めて日進月歩で治療が発展しています。ご自身や家族に該当する症状が見られると思った方は、なるべく早く近隣の整形外科など脊椎疾患を扱っている医療機関に相談してください。そして、ご自身の健康状態を医師に評価してもらいましょう。
北里大学医学部 整形外科学 診療教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が24件あります
両足に、しびれ。歩行障害があり。腰椎の5番が飛び出して寝ると違和感があります。
しびれと歩行障害が、酷い状態です。9年前に、脊椎間狭窄症になり、4番と5番の間から内視鏡手術しました。痛みはありませんが、明らかに5番が飛び出しているようです。両足に、しびれがあり、歩行障害です。レントゲンとMRIを撮りましたが、多少、骨が、狭いところはあるが、神経を圧迫していないので腰には、腰椎に関連性がないと診断されました。原因は、何でしょうか?どのような治療が、必要でしょうか?
お尻、太もも、などしびれ
2年半前に腰痛になり、腰部脊柱管狭窄症L5と診断されました。 その時は歩くのも、しびれも軽くお薬、湿布で治療してました。手術は痩せないとダメと言われました。(157cm71㎏体脂肪39%) 他の病気、卵巣嚢腫(摘出手術済)めまい、大腸ポリープ、萎縮性胃炎、不整脈、左腎嚢胞、変形性膝関節炎、肘痛、1回顔面ふるえ 2015年~2019年まで病気が増えました。 3か月前から水中ウォーキングを週2回位して筋力をつけてましたら、最近急にお尻全体、両太もも、両ふくらはぎが、しびれるようになりました。特に起床時、だんだん椅子に座っててもしびれてます。 もうたくさん病気があるので、手術出来るのか? 一生しびれがとれないのか?寝たきりになるのか? お薬だけでしびれは取れず、どんどん進行していくのか? 手術は出来るだけしたくないです。MRIをとって、詳しい説明や相談は出来にくい近所の脳神経外科は、専門医の紹介をしたがらないです。 どうしたらいいか?
27年前に自然気胸の手術をしましたがMRIの検査はできるでしょうか?
27年前にと25年前に自然気胸の手術をしました。 レントゲンを撮ると胸の肺の上をの方に棒状の影が写ります。 脊柱管狭窄症のため始めてMRI検査をしましょうかと言われました。 25〜27年前の金属でMRI検査は可能なのでしょうか?
2ヵ月前から腰の痛みが激しい。
整形外科で診察を受け1ケ月以上たちます。この間投薬治療を受けています。多少はよくなった気がしますが、今手術を勧められていまして迷っています。他の病院の診察を受けてみたいが何科を受診すればよいか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「腰部脊柱管狭窄症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。