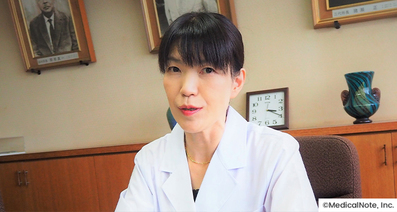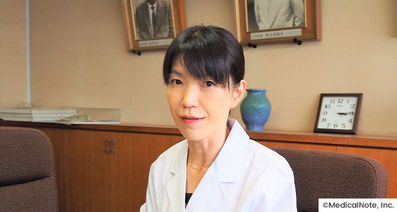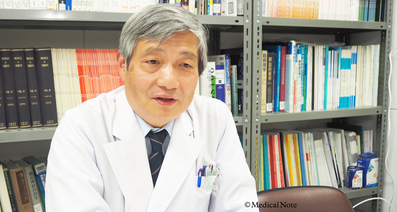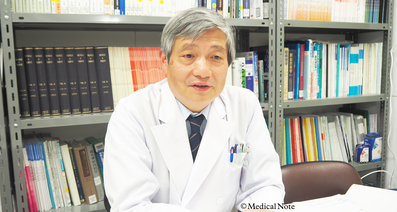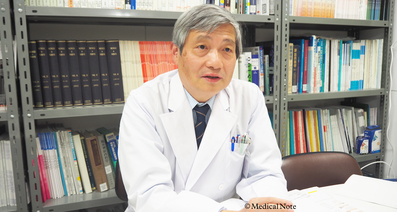視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発を防ぐために――生物学的製剤を選ぶときに大切にしてほしいこと


視神経脊髄炎を治療中の患者さんへ
スマホから症状の記録・管理ができる患者さん専用アプリ
「治療ノート」
視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)では、視力の低下や、手足のしびれ・麻痺などが現れることがあります。症状は急激に現れるのが特徴で、発症後なるべく早く急性期治療を行うことが大切です。
また、この病気の患者さんにとって再発を予防する治療は欠かせないものです。近年は新たな治療薬も登場し、治療の選択肢が広がっています。山口大学医学部 神経・筋難病治療学講座 教授の竹下 幸男先生は、「生物学的製剤の登場で、再発することなく過ごせる患者さんが増えたように感じる」とおっしゃいます。竹下先生に、発症の仕組みや生物学的製剤の特徴、治療選択のポイントについてお話をお伺いしました。
視神経脊髄炎スペクトラム障害とは?
視力の低下、手足のしびれなど多様な症状が現れる
視神経脊髄炎スペクトラム障害とは、免疫の異常によって作られたアクアポリン4抗体という自己抗体(自分自身の成分に対する抗体)が神経を攻撃することで、目の神経や脳、脊髄に強い炎症が起こる病気です。
炎症が生じた部位によって多様な症状が現れる可能性があり、眼痛を伴う視力低下や視野の欠損、手足の感覚がなくなる感覚障害や、しびれなどを生じる運動障害、止まらない嘔吐やしゃっくりなどが現れることがあります。
これらの症状は急激に進行するのが特徴で、発症後、数時間~数日でピークに達し最も強く現れるようになります。放置していると寝たきりや、失明など重篤な状態につながることもあるため、早期の治療が非常に大切です。急性期の治療後には、再発を予防するための治療を続けていく必要があります。
感染後や出産後の女性の発症が多い
男女比は1対9程で女性に多く、特に30歳代後半〜50歳代で発症しやすいことが分かっています。感染症にかかった後や出産後など、体内のホルモンバランスや免疫バランスの変化をきっかけに発症することが多いといわれています。

視神経脊髄炎スペクトラム障害はどのように発症する?
視神経脊髄炎スペクトラム障害は、“細胞性免疫”と、“液性免疫”という2つの病態が発症に関わっています。
細胞性免疫には、免疫細胞の1つであるT細胞が関わっています。T細胞は細胞自体が外敵を攻撃するタイプで、例えるならプロレスラーのような、直接相手を倒していく姿をイメージしていただくとよいでしょう。
一方、液性免疫には、免疫細胞の中でもB細胞が関わっています。B細胞は細胞自体ではなく、作り出した“抗体”によって外敵を攻撃するタイプです。こちらは警察官が銃を用いて犯人を制圧するような姿をイメージしていただくとよいでしょう。
視神経脊髄炎スペクトラム障害は、本来は悪い相手(細菌やウイルスなどの外敵)を倒すために奮闘するプロレスラーや警察官(免疫細胞)の一部が、誤って一般市民(自分自身の神経)を攻撃してしまうような状態が起こる病気だということです。攻撃を受けることで炎症が起こり、炎症が起こった場所によって多様な症状が現れるようになるのです。
発症後は、この2つの病態を抑えることを目的に直ちに治療を開始する必要があります。
視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療
視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療は、主に発症直後の急性期治療と、その後の再発予防治療に分けられます。
急性期治療
治療の流れと選択肢
急性期治療では、ステロイドパルス療法を行った後に、血漿浄化療法へ移行するのが一般的です。
ステロイドパルス療法とは、数日間かけて副腎皮質ステロイドを点滴で投与する治療法で、免疫機能や炎症を抑える効果が期待できます。血漿浄化療法は、炎症を引き起こすアクアポリン4抗体を血漿(血液中の液体部分)の中から取り除く治療法で、原因となる自己抗体を除去することで症状を改善する効果が期待できます。
ステロイドパルス療法は、基本的にどのような病院でも実施することは可能ですが、血漿浄化療法を導入している施設は限られているのが現状です。血漿浄化療法に対応していない医療機関にかかっている場合は、血漿浄化療法に対応している医療機関へ紹介を受けることが可能か、相談してみるとよいと思います。
ただし炎症が軽度であったり、治療を始めるのが早かったりした場合には、ステロイドパルス療法のみで軽快するケースもあります。患者さんの状態によっては、免疫グロブリン大量静注療法*などを追加で行うこともあります。
なお、血漿浄化療法と免疫グロブリン大量静注療法を選択できる場合は、先に血漿浄化療法を実施していただきたいと思っています。順番が逆だと、投与した免疫グロブリンが血漿浄化療法で除去されてしまい、効果が減弱する可能性があるためです。
*免疫グロブリン大量静注療法:免疫状態を改善させるために、点滴によって正常な免疫物質(抗体)を投与する治療法。
治療で大切なこと――しゃっくりや嘔吐が止まらない場合でも注意を
ステロイドパルス療法では感染症にかかりやすくなる可能性、血漿浄化療法では血圧が低下する可能性などがあるので、治療はこれらのリスクへの対策をしながら進めていきます。
また、この病気では、突然目が見えなくなったり動けなくなったりするなど急激な症状が現れるので、救急車を呼び受診されるケースが多くあります。しかし、症状が止まらないしゃっくりや嘔吐の場合、救急車を呼ぶことなく消化器内科を受診される方もいらっしゃいます。このような場合、原因が分からず適切な治療を受けられないまま1週間以上が経過し、さらに悪化することがあるため注意が必要です。止まらないしゃっくりや嘔吐が現れた場合は、この病気の可能性を思い出し医師に伝えてほしいと思います。
再発予防治療
治療の流れと選択肢
急性期治療の後には、再発予防治療を継続的に行います。治療の主な選択肢は、ステロイドや免疫抑制薬*、生物学的製剤です。生物学的製剤は自己抗体の産生や作用に関わる免疫物質などのはたらきを抑える薬で、再発を防ぐ効果が期待できます(現在使用できる薬の特徴と、選択のポイントについては後述します)。
このような生物学的製剤を用いながら、徐々にステロイドの量を減らしていくのが一般的です。特に発作が起こったあとの1年間程はクラスター期と呼ばれ、再発しやすいといわれています。私は、できるだけ早い段階で生物学的製剤を使用して、クラスター期を乗り越えていくことが大切だと考えています。
*現時点で、国内で視神経脊髄炎スペクトラム障害に対して保険適用がある免疫抑制薬はありません(2025年5月時点)。
治療で大切なこと――ステロイドを上手に減らすために
生物学的製剤が登場する前は、主にステロイドの飲み薬で再発予防治療が行われていました。しかし、長期的に継続することでさまざまな副作用のリスクもあることが明らかになってきています。
視神経脊髄炎スペクトラム障害は、30歳代や40歳代などの若い女性にも多い病気ですが、ステロイドを飲み続けることで、副作用である満月様顔貌(顔が丸くなること)などの整容的な問題が出てくる可能性があります。また、骨粗鬆症により骨折して寝たきりになれば社会的損失も大きいでしょう。このようなリスクを回避するためにも、若い患者さんであるほど、できる限りステロイドではなく生物学的製剤で治療することが大切だと考えています。
生物学的製剤が登場する前からステロイドを使用して再発を予防してきた高齢の患者さんには、長期的なステロイドの使用により、骨粗鬆症、糖尿病、肥満などさまざまな副作用が現れている例が少なくありません。副作用の治療のために、大量の薬を飲んでいる場合もあります。当院では、このような患者さんに生物学的製剤で治療を始めたところ、副作用による症状が改善し薬を減らせたケースがあります。
生物学的製剤の使い分けのポイント
それぞれの薬の特徴
生物学的製剤には5つの薬があり(2025年5月時点)*、それぞれ効果を発揮する仕組みが異なります。

エクリズマブは、自己抗体が攻撃するときに必要となる“補体”と呼ばれる物質をブロックすることで再発予防が期待できます。
ラブリズマブは、エクリズマブと同じ仕組みで効果を発揮します。
イネビリズマブとリツキシマブは、B細胞を枯渇させることで、原因である自己抗体が作られなくなる効果が期待できます。
サトラリズマブは、B細胞が分化してプラズマブラスト**になること、そしてプラズマブラストが自己抗体を作り出すことを抑制します。さらにIL-6(サイトカインと呼ばれる物質の一種)をブロックすることで、脳を守るバリアである“血液脳関門(Blood-brain barrier : BBB)”の機能低下を防ぎ、炎症細胞が脳の中に入るのを抑える作用があります。
投与の方法や間隔は薬によって異なります。サトラリズマブのようにご自宅での自己注射が可能な薬もあります。

生物学的製剤を使用している間は、感染症にかかっていないか定期的な確認が必要です。また、エクリズマブとラブリズマブは髄膜炎などの莢膜形成細菌に感染する可能性が高くなるので、使用する際には事前に髄膜炎菌ワクチンを接種しておく必要があります。ただし、ワクチン投与だけで感染予防ができるかは結論が出ていないのが注意点です。イネビリズマブやリツキシマブは、B細胞を枯渇させるため、IgGと呼ばれる細菌やウイルスから体を守るはたらきのある物質の値が低くなりすぎる低IgG血症に注意が必要になります。サトラリズマブは、感染時に値が上昇するとされるCRPという血液検査でのマーカーが上昇しなくなることが注意点となります。なお、どの生物学的製剤においても、脊髄炎による排尿障害を伴っている場合には尿路感染症の危険性が上昇しますので定期的な尿検査が必要です。尿路感染症において、特定の生物学的製剤で感染率が上昇するという根拠はありません。生物学的製剤の長期的な投与によるリスクについては、まだ十分に明らかになっていないのが現状です。特に感染症については、今後も経過を確認していく必要があるでしょう。
*国内承認取得日 エクリズマブ:2019年11月、サトラリズマブ:2020年6月、イネビリズマブ:2021年3月、リツキシマブ:2022年6月、ラブリズマブ:2023年5月
**プラズマブラスト:アクアポリン4抗体を産生するB細胞の一種。B細胞が活性化するとプラズマブラストへと分化する。
効果やリスク、生活面を考慮して選択する
5種類の生物学的製剤のうち、どれを選ぶのがよいのか悩まれる患者さんやご家族もいらっしゃるかと思います。私たち医療者側が最も重視するのは、きちんと再発を抑えられるか、長期的に使用した場合に感染の危険性があるのか、ステロイドの内服量を減少させられるかの3点になります。患者さんやご家族は、生活をしながら治療を続けるうえでの投与方法や間隔などが気になることが多いのではないでしょうか。このように医療面で期待できる効果やリスク、さらに生活面の両面を考慮して薬を選択します。
たとえばイネビリズマブやリツキシマブは、半年ごとの投与なので、仕事や家庭の事情などで通院の頻度を減らしたいという患者さんに対して使用することがあります。ただし、イネビリズマブやリツキシマブの投与間隔が半年ごとであることと通院頻度が半年ごとでいいということを一緒にしてはいけません。半年ごとの投与ということは、半年間は内服薬の影響を排除できないことになりますので、少なくとも3か月ごとの通院による感染症の確認や低IgG血症などの有害事象の確認が必要です。当院の場合は、脳を守るバリアの機能低下を防ぐなどさまざまな機序で作用し、皮下注射製剤で患者さんの投与負担が軽いと考えられるサトラリズマブから使用することが多いです。
“再発抑制率”の数字だけで判断しないで
再発を抑える効果は5剤全て、大差がないといってよいでしょう。どの薬も臨床試験の結果、再発抑制率が公表されていますが、それぞれの検証法や試験に参加した患者さんの背景は異なるため、数字のみで判断しないでほしいと思っています。
また、どの薬を使っても、合う患者さんと合わない患者さんはいらっしゃいます。効果が期待できない場合や、肝臓の障害、吐き気や下痢などの有害事象によって使用し続けることが難しいと判断した場合は、ほかの薬に変更する場合があります。

患者さんやご家族に知っておいてほしいこと
疑問に思うことはきちんと聞いてほしい
治療を選択する際には、医師としての意見を患者さんにきちんと伝えることを大切にしています。最終的には患者さんに決断してもらう必要がありますが、患者さんが自分だけで治療薬を選ぶのは難しいと思うからです。実際に、患者さんから「先生はどう思いますか」と意見を求められることも少なくありません。
納得して治療を受けるために、患者さんやご家族には、少しでも疑問に思うことは遠慮なく医師に質問してほしいと思います。
妊娠・出産を希望する場合は諦めないで
患者さんの中には、妊娠・出産を希望される方もいらっしゃるでしょう。再発予防治療を受けながらの妊娠・出産について、100%問題ないと言い切れるだけのデータは十分に揃っていないのが現状ですが、諦める必要はないと考えます。ただし、薬の選択などは自分で判断せず、主治医と相談しながら進めるようにしてください。安全な妊娠・出産のためには、産婦人科との連携も重要となります。
再発ではなく進行するケースがある可能性も
最近、注目されているトピックスを1つ挙げると、視神経脊髄炎スペクトラム障害の一部に慢性進行性の患者さんがいる可能性が示唆されており、発作の起こった日がはっきりとは分からないものの徐々に悪化していく例があるのではないかといわれています。症状が悪化していると感じている方がいらっしゃったら、慢性進行性の可能性を考え、我慢することなく医師に伝えてほしいと思います。
竹下先生からのメッセージ――医師や看護師と相談しながら前向きに治療を
生物学的製剤が登場したことで、再発することなく過ごせる患者さんが多くなったと感じています。視神経脊髄炎スペクトラム障害は、いずれ克服できる病気になっていくのではないかと期待しています。
治療を進めるうえで大切なことは、自分一人で全てを決めるのではなく、医師や看護師、ケースワーカーなどの専門家へ相談し、必要なサポートを受けることです。治療の選択肢も広がっているので、諦めずに前向きに治療に取り組んでいただきたいと思います。
山口大学医学部 神経・筋難病治療学講座 教授 / 血液脳神経関門先進病態創薬研究講座 研究代表 、株式会社ADDVEMO(アドビーモ) 代表取締役
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

視神経脊髄炎を治療中の患者さんへ
スマホから症状の記録・管理ができる患者さん専用アプリ
「治療ノート」
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


歌の力に支えられて――ソプラノ歌手・坂井田真実子さんの視神経脊髄炎ストーリー

視神経脊髄炎スペクトラム障害の治療の進歩――再発予防のための新たな選択肢とは?
関連の医療相談が10件あります
寝れないほどの腰痛
寝れないほどの腰痛は、何科を受診したらいいですか?
原因不明の右胸付近の痛み
昨日起床時から右胸付近に痛みが出ています。体をのけぞったり、息を強く吸い込んだりする際に痛みが出るので、肺の痛みなのか肋骨の痛みなのか分かりかねています。特に思い当たる原因はなく、起床時から息が吸いづらいと思ったところ痛みに気づいた状況です。昨日より少し痛みは良くなっていると思うのでおそらく時間が経てば治るかなと思っているのですが、念のため思い当たる症状がないかお伺いしたい次第です。
2日前から続く胸痛
2日前の起きた時から凄く胸の中心(若干左寄り)が痛いです。 何もしなくても痛くて息をしたり笑ったり少しでも動くと痛みが増して、くしゃみをすると激痛が走りました。 そして、今度は、左の肩甲骨付近も痛くなってきました。 胸だけなら肋軟骨炎とかなのかなぁと思って湿布を貼ってみたりしていたのですが(湿布の効果は無いように感じる)、肩甲骨らへんも痛くなってきたので別の何かなのでは?と不安です。 また、もし肋軟骨炎だとしたら肋軟骨炎は何が原因でなるのでしょうか? 因みに筋トレなどは一切行っておりません。 ただ、心臓の手術を幼少期にしたことがあります。それが多少は関係したりするのでしょうか?
全身の痺れ
一昨日から全身に時折、痺れ・チクチクピリピリ感が生じます。 ずっと同じ箇所ではなく全身を転々としています。頭、顔、舌、腕、足、本当に全身です。何かに触れた部分が痺れるわけでもありません。 脳神経外科で脳をMRIで検査してもらいましたが異常は見られませんでした。 何が原因でしょうか? または何科を受診すれば良いでしょうか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「視神経脊髄炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。