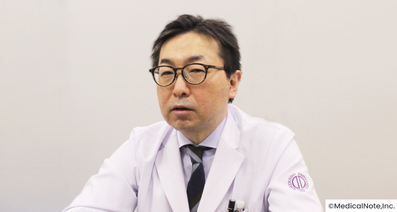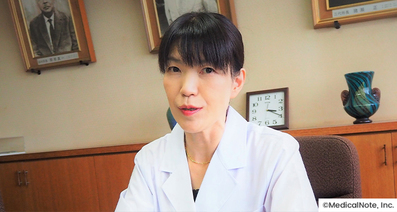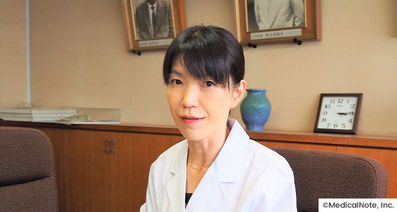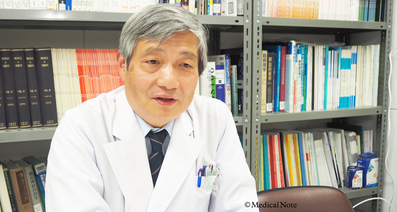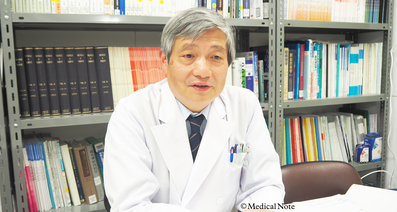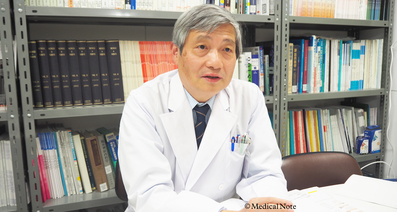視神経脊髄炎を治療中の患者さんへ
スマホから症状の記録・管理ができる患者さん専用アプリ
「治療ノート」
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(neuromyelitis optica spectrum disorders:NMOSD)は、脳・脊髄・視神経などの中枢神経系が障害される病気です。2000年代に入って研究が急速に進み、日本で多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)と診断されていた患者さんの中に視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)が20%前後含まれていたことが分かってきました。この記事では、順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経内科 横山 和正先生に、視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)についてご解説いただきました。
概要
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)とはどのような病気か
視神経脊髄炎(neuromyelitis optica:NMO)はその名前のとおり、主に視神経と脊髄が障害される病気です。1894年に初めて報告したフランスの医師、Eugene Davicの名前から、かつては“デビック病”と呼ばれていました。
その後長い間、多発性硬化症(MS)との関連やその違いについて診断マーカーや診断基準が明確になっていませんでした。特に日本を含むアジアでは多発性硬化症の症例が少ないこともあり、当時の多発性硬化症の診断基準を満たしていたため“視神経脊髄型MS(optic spinal multiple sclerosis:OSMS)”と呼ばれていた時代もありました。
2004年に視神経脊髄炎の患者さんの血液中にNMO-IgGという抗体があり組織染色で発見されてから、状況は大きく変化しました。さらにその後、体内の細胞膜に広く存在する水チャンネルであるアクアポリン4(以下、AQP4)を認識していることが分かり、NMO-IgGは“抗アクアポリン4抗体(以下、抗AQP4抗体)”と呼ばれるようになりました。
視神経脊髄炎は、2006年のWingerchuckらの診断基準では視神経炎と急性脊髄炎が主でしたが、視神経炎と脊髄炎が同時期にない症例や、抗AQP4抗体陽性症例で脳病変から発症するものもあることから、視神経脊髄炎スペクトラム疾患という、より広い疾患概念が設けられ、2015年の国際診断基準で確立しました。現在、視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)は中枢神経系の膜や血管周囲に豊富に存在するAQP4が自己抗体によって攻撃されることで起こる自己免疫疾患の一種と考えられており、この抗体が陽性であることが診断基準のひとつとなっています。
患者数、年齢、男女比
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の患者さんに占める女性の割合は約9割で、多発性硬化症よりもさらに高い比率となっています。小児から高齢の方までどの年齢でも初発、再発が起こる可能性があり、発症年齢のピークは20歳代です。患者さんの数は10万人あたり3~4人で、日本全体では3,000~4,000人と推定されています(2020年5月現在)。
女性に多い理由は?
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)を含めた自己免疫疾患が女性に多い理由のひとつとして、ホルモンバランスが影響しているのではないかと考えます。女性に特徴的なエストロゲン、プロラクチン、また男性ホルモンであるアンドロゲンなどは免疫システムに影響を与えるとされ、視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)は、妊娠でやや安定するものの出産後、再発リスクの悪化が見られます。

視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の症状
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)でよく見られる症状の例
- 目を動かしたときに眼球や目の奥が痛くなる
- 視力の急激な低下
- 視野の一部が欠ける
- 色彩感覚が低下する、濃淡が分からなくなる
- 手足が動かせなくなる
- 感覚の異常や麻痺
- 尿意を感じにくくなる、排便がうまくコントロールできなくなる
- しゃっくりが続き、24時間以上止まらないことがある
- 強い吐き気や嘔吐
- 異常に強い眠気やナルコレプシー様の睡眠発作
中枢神経は大脳のほか、間脳、脳幹部、小脳などの各部位からなり、脊髄も含んでいます。また、視神経は脳から出ている突起物であり、12対ある脳神経のなかで嗅神経とともに解剖組織学的には中枢神経に属しています。視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)ではこれら中枢神経のAQP4の豊富な部位が障害を受け、上記のようにさまざまな症状が現れます。
脳神経内科以外の受診をきっかけに見つかることも
視神経の炎症による視覚障害(視力低下や視野欠損)が起こると、最初に眼科を受診する患者さんが多いようです。脳に病変が生じていることもあるため、脳ドックなどで病変が見つかって病院を紹介される患者さんはおりますが、無症候性病巣が多い多発性硬化症と比較するとまれだと思います。
同じ脳の中でも延髄背側にある最後野と呼ばれる嘔吐反射や摂食、体重調節などに関わる部分がダメージを受けると、24時間以上続くしゃっくりや吐き気、嘔吐などの症状が見られます。その症状から最初に消化器内科を受診する患者さんもいらっしゃいますが、消化器内科で一般的に行われる検査では脳を調べないため、疑わない限り診断が困難です。
また、間脳や視床下部がダメージを受けると、日中でも発作的に強い眠気に襲われるナルコレプシーという病気に似た症状を起こすことがあるため、メンタルクリニックや精神科などの受診をきっかけに見つかることもあります。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の原因
AQP4を自己抗体が攻撃することで発症する
免疫システムは体を外部つまり“非自己”、ないし体内の有害細胞から守るため日夜稼働していますが、日、週、月、年によって大きく変動し、そのはたらきにはバランスが重要です。この免疫のバランスが何らかの理由で崩れて強くなり過ぎると、通常であれば免疫が反応しないはずの“自己”に反応してしまいます。視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)はこの自己免疫によって、中枢神経系に存在するAQP4を自己抗体である抗AQP4抗体が攻撃することが原因で起こると考えられています。
“アクアポリン(AQP)”とは細胞膜で水を透過させるはたらきをする水チャネルたんぱくで、AQP0からAQP12までその選択性により分類されています。AQP4は神経細胞を支持している“アストロサイト”という細胞に多く存在しています。
アストロサイトは神経細胞に必要な物質を供給し、血管から中枢神経系に不要な物質が入り込まないよう関門の役割を果たしている細胞でもあります。抗AQP4抗体がAQP4を攻撃すると、このアストロサイトが大きくダメージを受けます。その結果、脳の中に炎症が広がって脳に入り込んだ多くの免疫細胞は多発性硬化症の標的でもあるオリゴデンドロサイトの神経細胞死を引き起こし、さまざまな神経症状を引き起こすのです。
抗AQP4抗体が陰性でも視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)と診断されるケース
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の患者さんの多くは抗AQP4抗体が陽性です。一方で、抗AQP4抗体が陰性であるにもかかわらず、臨床症状などから視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の診断基準を満たすケースがあります。その一部は抗MOG抗体と呼ばれる抗体が陽性であり、これは新たな疾患概念としてクローズアップされてきています。
抗MOG抗体は、“ミエリンオリゴデンドロサイト糖(MOG)”という神経の繊維を覆っている“髄鞘(ミエリン)”という絶縁体の一番外側にある糖たんぱくを認識する抗体です。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の検査と診断について
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の診断のためには、問診、血液検査、MRI検査、髄液検査を行います。
問診
問診ではこれまでのワクチン接種歴や、膠原病の合併、いわゆる先行感染と呼ばれる風邪症状や下痢、発熱などの有無、過去にどのような初発神経症状の出現、およびその経過があり、どのような治療をしたかを確認します。
血液検査
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の診断には、血液検査で抗AQP4抗体の有無を確かめることが重要です。抗AQP4抗体の測定方法には、cell-based assay(CBA)法とEnzyme-Linked Immuno Sorbent Assay(ELISA)法があります。CBA法は感度や特異度に優れていますが、保険適用外のため検査費用が患者さんの自己負担になります。一方、ELISA法は精度がやや劣りますが保険適用のため、全例に対して診断のための初回のスクリーニングとして行う検査には適しています。
MRI検査
MRIでは脊髄に3椎体以上の長い病変が見られることが特徴です。また、脊髄の中心にある灰白質という神経細胞が存在しているところや、脳幹の背側延髄/最後野、脳室上衣の周囲などに病変が見られるかどうかは診断上で重要な手がかりになります。
髄液検査(腰椎穿刺)
髄液検査は、皮膚の局所麻酔後に背中に針を刺して脳と脊髄の周囲にある髄液を採取する検査です。視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)でよく見られる髄液細胞数増多や髄液たんぱく質の増加、その免疫活動性のパターンなどを解析することで診断に役立ちます。
診断的治療について
抗AQP4抗体が陽性の場合には、視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の診断のハードルは低いと考えます。しかし抗AQP4抗体が陰性の場合は診断が難しく、二つ以上の主要臨床症候やその他の所見を加味してもほかの病気と明確に鑑別できないケースがあることが現状です。
その場合は“みなし治療”(診断的治療)として、より重症で出現した神経症状が戻らなくなる可能性のあることが懸念される視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)を前提としてステロイド治療を始めることがあります。このような治療的診断は、急性期に行う治療で、MS含めてほかの神経免疫性疾患でもよく行われます。同時にMRIによる画像診断、髄液検査などのあらゆるデータを治療開始前に議論したのち、後々の治療法を含めたその後の免疫治療の方向性を注意深く決定し、実行していきます。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の治療について
急性増悪期の治療
急性期や再発による増悪期の治療には、ステロイドパルス療法、血漿交換などの血液浄化療法があります。このほか2019年12月から、ステロイドの効果が不十分な視神経炎に対する急性期治療として、免疫グロブリンの大量静注療法(IVIg療法)が承認されています。
ステロイドパルス療法は、病変部の炎症、免疫、浮腫を抑えるために、ステロイドを1日1g、3~5日間大量に静脈投与する方法です。
血液浄化療法は血液をいったん体の外に出してろ過してから体内に戻す治療で、血漿を全て捨ててアルブミン溶液、新鮮凍結血漿と入れ替える“単純血漿交換療法”と、二重膜濾過、抗体など悪いものを取り除いてから残りの血漿を再び戻す“免疫吸着療法”があります。
再発予防の治療

急性期の治療によってある程度症状を抑え込むことができたら、速やかに再発予防の治療に移ります。その際、国内ではステロイド薬をベースに使います。一定量以上のステロイドを使用すると糖尿病、高血圧、感染症、骨粗しょう症などのリスクが高まるため、長期使用による副作用に注意しながら徐々にステロイドの量を減らしていきます。最初は0.5mg~1mg/月程度から開始し、1か月はそのままで、それから1か月ほどかけて5mg/日程度薬の量を減らしていき、15mg/日からは月に1mg程度減量し、最終的には約1年かけて1日あたり0.1mg/kg/日程度で維持することを目指していきます。
その間に再び悪化、もしくは一時的にステロイドを増量しても症状コントロールがうまくいかない場合には、免疫抑制剤を組み合わせた治療を行うことがあります。免疫抑制剤を併用する理由は、炎症の原因となっている抗体の産生を抑えるだけではなく、上述した副作用のためにステロイドが使いづらいケースがあるためです。特に閉経後の痩せ型女性では骨粗しょう症による圧迫骨折がしばしば起こり得るため、こうした合併症にも配慮しながら治療を進めていく必要があります。
2020年5月現在、国内で唯一視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の再発予防の効果が承認されている薬剤はエクリズマブです。そのほか、一人ひとりのリスクとベネフィットを考慮したうえで、アザチオプリン、タクロリムス、シクロスポリンAなども使うことがあります。ただし、これらはいずれも視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の治療薬として承認されているわけではなく、あくまでも適応外処方となります。
アザチオプリンでは顆粒球減少症、肝機能障害や感染症に注意が必要なほか、白血病、悪性リンパ腫などの発がんリスクがあります。タクロリムスは副作用が比較的少ない薬ですが、白血球減少、糖尿病、腎機能障害に注意が必要です。また、シクロスポリンAで頻度の高い副作用には腎機能障害、肝機能障害、血圧上昇、多毛などがあります。
新型コロナウイルス感染症と免疫抑制剤の関係
2020年5月現在、世界各国で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。
現時点でまだ確固たるエビデンスはないものの、新型コロナウイルスに感染した一部の方では、免疫が暴走する“サイトカインストーム”という現象が起こっている可能性があるという報告が見られるようになりました。サイトカインストームとは、免疫の暴走によって免疫細胞からサイトカインが過剰に放出され、嵐(ストーム)のように細胞を壊してしまうという状態です。そのため、理論的には免疫抑制剤を使っていれば、サイトカインストームという免疫の暴走を抑制する可能性があるという考え方もできるのです。
ただしステロイドや免疫抑制剤を使っているとウイルスに感染しやすくなるリスクがあります。そのため、私は患者さんに“Stay Home”と“Social Distancing”、“手洗い”を第一にお伝えしています。しかしその反面、上述した理論が正しければ体に入り込んだウイルスによって免疫が異常に活発化して致死的な状況になることを抑えてくれる可能性があるのかもしれないということも同時にお話しして、患者さんが過度な不安を抱かないよう努めています。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の治療の発展
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の急性期治療は、今日ではほぼ確立されてきています。ステロイドをはじめ、既存の免疫抑制剤の長所・短所など、治療に関するノウハウが蓄積されているためです。しっかりと再発予防に努めれば、治療後は健康な人に近い生活を送っている患者さんも多くいらっしゃいます。一方で、なかには治療の効果が十分に得られず、失明したり車椅子の生活になったりしてしまう方がいらっしゃることも事実です。そうならないためには、病気を早く診断して早期に急性期治療を行い、その後の再発予防治療を継続することが大切です。
再発予防においては、ステロイドや免疫抑制剤、副作用を抑えるための薬といった従来の薬剤の使い方がガイドラインの策定に伴い確立されてきたことに加えて、新規薬剤の開発によって治療の選択肢が広がっています。また、日本ではかつて、妊娠が明らかになった女性に対するアザチオプリン、タクロリムス、シクロスポリンAなどの免疫抑制剤の使用は中止していましたが、現在ではリスクとベネフィットを考えたうえで、必要ならば妊娠中も含めて主治医と相談しながら使用を検討できるという方針に変わってきました。これまでは免疫抑制剤の使用をやめて症状が再発してしまい、出産がかなわなかったという患者さんもいらっしゃいました。しかし今は、治療をしながら子どもを産める可能性がより広がってきたといえるでしょう。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)との付き合い方について

視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)の再発予防の治療は長期間にわたって行う必要があります。そのため、急性期の治療がいったん終わっても、間を開けることなく定期的に通院することが大切です。当院では、遠くから通っている患者さんには近隣の脳神経内科の先生に紹介状を書いて、お住まいの近くにかかりつけの病院となっていただけるところを設けるような取り組みも行っています。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)では、過度でなければ運動に制限はありません。再発に注意して治療を受けるとともに、規則正しい生活を心がけ、適度な運動や食事・体重管理などに注意していれば、病気と上手に付き合いながら日常生活を送ることができます。しかし、ときには過度なストレスや過労などをきっかけに症状の再発や、薬の副作用による弊害が生じることもあります。またステロイドの副作用で肥満、糖尿病、高血圧、高脂血症、骨粗しょう症による病的骨折、大腿骨頭壊死、抑うつ状態となったり、精神症状が出たりすることもあるかもしれません。食事制限が必要かどうかはその方の背景疾患、内服薬によって異なります。ご本人はそういった自身の身体状況、なぜ治療の継続をしなければいけないかということも理解し、家族とともに病気を受け入れながら安定した日々を過ごしていただければと思います。
横山 和正先生からのメッセージ
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)は正しい診断を行えば適切な治療につながります。だからこそ、まず大切なのは、脳神経内科など、この病気を専門的に診ることができる診療科を受診して、診断を確定するということです。そして、患者さんは確定された診断のもとに病気の性質および免疫の治療について自分なりに勉強していただき、治療に対する理解、継続することの重要さを深めることが大事です。
視神経脊髄炎スペクトラム疾患(NMOSD)は多発性硬化症と病状の進み方が異なり、徐々に悪くなっていくことはまずありませんが、再発すれば激烈に症状が現れることがあるため注意を怠ることはできません。ですから、定期的に病院を受診して採血、骨塩定量などの検査および治療を継続し、そのなかでご自分の日常生活レベルが過去と比べてどのような状況にあるのかということを把握しながら、前向きな気持ちで生活を送っていただくことがとても大切です。

視神経脊髄炎を治療中の患者さんへ
スマホから症状の記録・管理ができる患者さん専用アプリ
「治療ノート」
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


変わる自己免疫疾患の治療――グルココルチコイド長期使用のリスクについて

歌の力に支えられて――ソプラノ歌手・坂井田真実子さんの視神経脊髄炎ストーリー
関連の医療相談が10件あります
寝れないほどの腰痛
寝れないほどの腰痛は、何科を受診したらいいですか?
原因不明の右胸付近の痛み
昨日起床時から右胸付近に痛みが出ています。体をのけぞったり、息を強く吸い込んだりする際に痛みが出るので、肺の痛みなのか肋骨の痛みなのか分かりかねています。特に思い当たる原因はなく、起床時から息が吸いづらいと思ったところ痛みに気づいた状況です。昨日より少し痛みは良くなっていると思うのでおそらく時間が経てば治るかなと思っているのですが、念のため思い当たる症状がないかお伺いしたい次第です。
2日前から続く胸痛
2日前の起きた時から凄く胸の中心(若干左寄り)が痛いです。 何もしなくても痛くて息をしたり笑ったり少しでも動くと痛みが増して、くしゃみをすると激痛が走りました。 そして、今度は、左の肩甲骨付近も痛くなってきました。 胸だけなら肋軟骨炎とかなのかなぁと思って湿布を貼ってみたりしていたのですが(湿布の効果は無いように感じる)、肩甲骨らへんも痛くなってきたので別の何かなのでは?と不安です。 また、もし肋軟骨炎だとしたら肋軟骨炎は何が原因でなるのでしょうか? 因みに筋トレなどは一切行っておりません。 ただ、心臓の手術を幼少期にしたことがあります。それが多少は関係したりするのでしょうか?
全身の痺れ
一昨日から全身に時折、痺れ・チクチクピリピリ感が生じます。 ずっと同じ箇所ではなく全身を転々としています。頭、顔、舌、腕、足、本当に全身です。何かに触れた部分が痺れるわけでもありません。 脳神経外科で脳をMRIで検査してもらいましたが異常は見られませんでした。 何が原因でしょうか? または何科を受診すれば良いでしょうか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「視神経脊髄炎」を登録すると、新着の情報をお知らせします