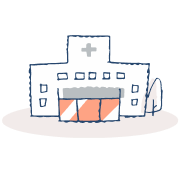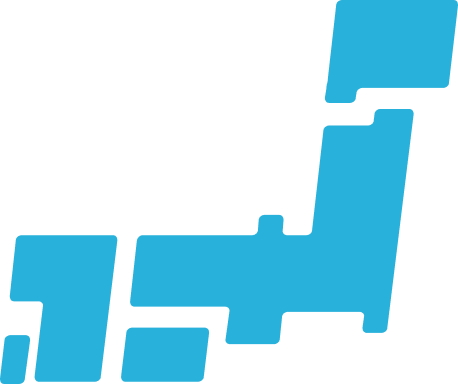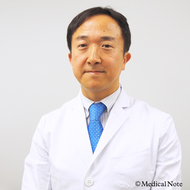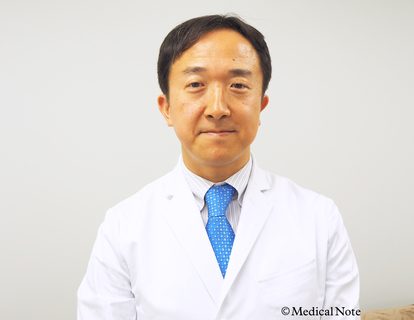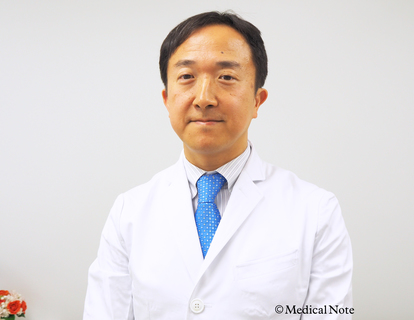概要
更年期とは、生殖期(性成熟期)と非生殖期(老年期)の間の移行期を指します。卵巣機能が減退し始めてから消失するまでの時期をいい、一般的に閉経の前後それぞれ5年間、合計で10年間が該当するといわれています。閉経の年齢は個人差が大きく、40歳代前半に迎える女性もいれば、50歳代後半になっても迎えない女性もいます。
この時期は女性ホルモンの分泌量が大きく変化するため、のぼせやほてり、発汗などの症状がみられる、いわゆるホットフラッシュをはじめ、めまいや頭痛、疲労感、不眠などといった身体的な症状、また、意欲の低下や不安、憂鬱などといった精神的な症状がみられます。これらの症状がひどくなり、日常生活に支障をきたす状態を更年期障害といいます。
閉経とは
閉経とは、子宮摘出や薬剤による治療を行っていないにもかかわらず、月経が永久に停止することです。40歳以降で最後の月経から1年間月経が来ない状態を確認できれば、閉経を迎えたということになります。閉経年齢は最後の月経があったときの年齢をいいます。
 これから更年期を迎える女性に知ってほしい、更年期障害の基本知識と対策香川大学医学部医学科健康科学 教授、香川...塩田 敦子 先生
これから更年期を迎える女性に知ってほしい、更年期障害の基本知識と対策香川大学医学部医学科健康科学 教授、香川...塩田 敦子 先生更年期は誰もが経験することですが、ご本人にとっては初めてのことです。更年期を迎える前から「どういった症状が出るのか」と、更年期に対して漠然とし...続きを読む
 閉経を迎える年齢は何歳?ーー閉経前後5年間の更年期に起こる様々な症状とは[医師監修]
閉経を迎える年齢は何歳?ーー閉経前後5年間の更年期に起こる様々な症状とは[医師監修]閉経について気にはなっていても、デリケートな話題なので普段なかなか話題にしにくいものです。40歳を過ぎて顔のほてりなど今までにない体の不調を感...続きを読む
 更年期障害とは?―ホルモンと自律神経のバランス藤田医科大学病院 国際医療センター 客員...太田 博明 先生
更年期障害とは?―ホルモンと自律神経のバランス藤田医科大学病院 国際医療センター 客員...太田 博明 先生更年期障害は、おおよそ45歳から55歳の女性に起こる症候群です。女性ホルモンや自律神経が関係しており、多くの女性にとってかかる可能性があります...続きを読む
原因
更年期障害の主な原因は、エストロゲンという女性ホルモンの血中濃度が大きく変動しながら低下していくことです。エストロゲンは卵巣から分泌されており、更年期になると卵巣機能の低下に伴い分泌量も減少します。これを脳が感知すると自律神経のバランスに乱れが生じ、さらに身体的要因(加齢など)、心理的要因(性格など)、社会的要因(職場や家庭の人間関係など)などが関与することで、更年期障害を引き起こすと考えられています。
症状
更年期障害の症状には、精神的症状、身体的症状の大きく2種類があります。
精神的症状
意欲の低下、不安、憂鬱など
身体的症状
のぼせやほてり、発汗などが起きるホットフラッシュのほか、動悸、息苦しさ、疲労感、頭痛、肩こり、めまい、腰痛、関節・筋肉痛、冷え、しびれ、疲れやすさ、湿疹、かゆみ、排尿障害、頻尿など
検査・診断
患者が感じている症状について、質問表などを用いながら詳しく問診を行います。その際、甲状腺疾患のように更年期障害とよく似た症状がみられる病気の可能性がないかも考慮して診断にあたります。
また、採血検査でエストロゲンなどの血中濃度を測定することもありますが、この値は閉経から約2年後までは大きく変動します。
治療
更年期障害の治療では、生活習慣を整えることが重要です。運動を習慣化し、食事療法を行って過度の飲酒や喫煙は避け、規則正しい生活を心がけましょう。
そのうえで、更年期障害に有効とされている治療法として、いくつかの薬物療法があります。代表的な方法として、ホルモン補充療法(HRT)や漢方薬、抗うつ薬などの治療法が挙げられます。
ホルモン補充療法(HRT:Hormone Replacement Therapy)
ホルモン補充療法(HRT)は、女性ホルモンを補うことで更年期障害の症状を改善させる方法です。さらに、長期的には骨粗鬆症や認知症の予防にも効果があることが分かっています。患者の状態に応じて、女性ホルモンの代表であるエストロゲンとプロゲステロンを組み合わせて投与するか、エストロゲン単独で投与されます。
薬剤には、飲み薬や貼り薬、塗り薬がありますが、薬剤によって副作用が生じるリスクもあるため、症状や状況を医師と相談しながら選択することが大切です。
HRTの方法には、さまざまなものがあります。開始年齢や実際の症状、子宮の有無、持病などによって使用する薬剤や量が選択されます。また、子宮体がんや乳がんを治療中の人、過去に乳がんの加療を受けた人、心筋梗塞、脳卒中、肝臓に重症な病気を患った人など、一部の人はHRTを実施できない場合があります。HRTの開始時期や継続期間、終了時期なども症状に合わせて医師と相談のうえ決めるのがよいでしょう。
治療を開始する場合や長期間継続する場合は、定期的に子宮がん検査や超音波検査などを受ける必要があります。
漢方薬
全体的な心と体のバランスを整えることを目的とした治療法です。処方される漢方薬は、体力の有無や症状などによって異なりますが、当帰芍薬散や加味逍遥散、桂枝茯苓丸が代表的です。
「更年期障害」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「更年期障害」に関連する記事