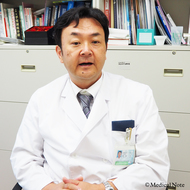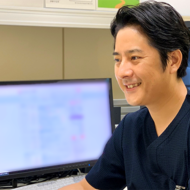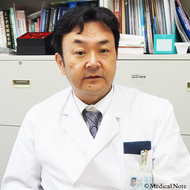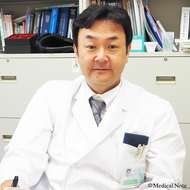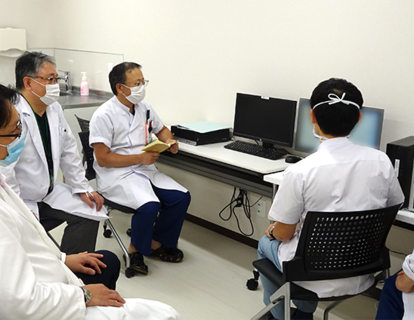概要
子宮体がんとは、子宮の内側を覆う“子宮内膜”と呼ばれる組織から発生するがんのことです。同じ子宮に生じるがんに“子宮頸がん”がありますが、がんの生じる部分が異なり、原因や症状、治療方法などがまったく異なる病気なので注意が必要です。
子宮は女性特有の臓器で、妊娠時に胎児を育てる重要な役割を果たします。子宮自体は筋肉(平滑筋)でできていて、内側は受精卵が着床する場でもある子宮内膜と呼ばれる粘膜で覆われており、女性ホルモンの分泌バランスによって増殖・成熟したり、剥がれ落ちたりすることを繰り返しています。なお、“月経”は妊娠に向けて増殖・成熟した子宮内膜が剥がれ落ちたものが血液などと共に排出されたものです。
子宮体がんの好発年齢は50~60歳代で閉経後に発症するケースが多く、早期の段階から不正出血が生じることが多いため、比較的早く発見できるがんの1つでもあります。しかし進行すると、がん細胞がリンパ節や腹腔内をはじめ、さまざまな箇所に転移することもあります。
 子宮がん(子宮体がん、子宮頸がん)の概要——種類や原因、症状について地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県...坂本 育子 先生
子宮がん(子宮体がん、子宮頸がん)の概要——種類や原因、症状について地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県...坂本 育子 先生子宮がんは女性に特有のがんで、がんができる部位によって子宮体がんと子宮頸がんの2つに分類されます。特に子宮頸がんにおいては20~30歳代の若い...続きを読む
 子宮体がん治療の最新トピックス~赤坂山王メディカルセンター 院長 青木 大輔先生インタビュー赤坂山王メディカルセンター 院長、国際医...青木 大輔 先生
子宮体がん治療の最新トピックス~赤坂山王メディカルセンター 院長 青木 大輔先生インタビュー赤坂山王メディカルセンター 院長、国際医...青木 大輔 先生子宮体がんの治療では、可能な限り手術療法によって子宮や卵巣・卵管を取り除くことが一般的です。近年ではより患者さんの体に負担がかかりにくい手術方...続きを読む
原因
子宮体がんの発症には、“エストロゲン”と“プロゲステロン”という2つの女性ホルモンが関わっています。
エストロゲンは子宮内膜の増殖を促す作用があります。一方で、プロゲステロンは子宮内膜の増殖を抑制する作用を持ち、エストロゲンの作用を調整しています。このプロゲステロンが不足して相対的にエストロゲンが過剰となる状態が続くと、刺激によって子宮内膜が異常に増殖し、子宮体がんを発症すると考えられています。
そのため、妊娠回数の少ない人や肥満の人など、エストロゲンに過剰にさらされている期間が長い女性は子宮体がんの発症リスクが高くなると考えられています。
また、以前は更年期障害などの治療で卵胞ホルモン(エストロゲン)製剤だけのホルモン療法を行うことがあり、子宮のある女性にエストロゲンだけのホルモン治療をすることによって子宮体がんのリスクが上がることが懸念されました。しかし現在は、子宮のある女性に対してホルモン治療を行う場合はエストロゲンとプロゲステロンを併用することが一般的であるため、ホルモン治療によって子宮体がんにかかるリスクは小さくなっています。
なお、手術により子宮を摘出した女性に対して行うホルモン治療では、エストロゲンのみのホルモン治療が行われます。
そのほかに月経不順のある人や肥満、糖尿病や高血圧といった病気を持つ人は子宮体がんにかかりやすくなるといわれています。また、子宮体がんや尿路上皮がんは遺伝子の異常によって引き起こされるケースもあり、同じ家系に大腸がんや乳がんを患ったことがある人がいると通常より発症リスクが高いことが知られています。
症状
子宮体がんの中でもっともよくみられる症状が不正性器出血です。出血の現れ方は人によって異なりますが、初期症状として現れることもあり、早期発見に役立つ場合があります。
月経のような赤い出血がみられるケースもあれば、茶色っぽいおりもののみがみられるケースも少なくありません。子宮体がんは閉経後に発症しやすいため、閉経したにもかかわらず性器出血があるときは婦人科を受診する必要があります。
子宮体がんは進行すると腟や卵巣、卵管などを巻き込んで破壊しながら増殖していき、リンパ節を含む遠隔転移を引き起こすこともあります。進行すると出血を伴う下腹部痛などの症状がみられるようになります。
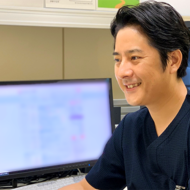 子宮体がんの初期症状では90%以上が不正出血を伴う〜気になる症状がある場合はどうしたらよい?〜名古屋市立大学 医学研究科産科婦人科学分...西川 隆太郎 先生
子宮体がんの初期症状では90%以上が不正出血を伴う〜気になる症状がある場合はどうしたらよい?〜名古屋市立大学 医学研究科産科婦人科学分...西川 隆太郎 先生子宮体がんとは子宮内膜がんとも呼ばれ、子宮体部(胎児が育つ部分)にできるがんのことを指します。一般的に40歳代から増加し、50歳代から60歳代...続きを読む
 子宮体がんの可能性がある症状とは?〜子宮体がんは放置すると進行する〜NTT東日本関東病院 産婦人科 部長塚﨑 雄大 先生
子宮体がんの可能性がある症状とは?〜子宮体がんは放置すると進行する〜NTT東日本関東病院 産婦人科 部長塚﨑 雄大 先生子宮体がんは子宮体部にできるがんのことです。日本では年間約17,800人が子宮体がんと診断されています(2019年時点)。患者は40歳代以降か...続きを読む
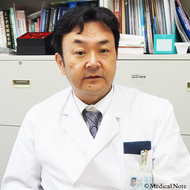 子宮体がんの初期症状—不正出血やおりものはサイン山形大学医学部附属病院 産科婦人科 教授永瀬 智 先生
子宮体がんの初期症状—不正出血やおりものはサイン山形大学医学部附属病院 産科婦人科 教授永瀬 智 先生子宮体がんは、子宮内膜から発生するがんです。不正出血やおりものの異常など、目に見える初期症状があります。今回は、子宮体がんの初期症状について山...続きを読む
検査・診断
子宮体がんが疑われたときには、次のような検査が行われます。
子宮内膜組織診(病理学的検査)
子宮内膜の一部を採取して顕微鏡で詳しく調べる検査です。子宮体がんの確定診断に必須の検査となっています。
子宮体がんの確定診断では子宮内膜組織診を中心に行い、補助的に子宮内膜細胞診を行うことがあります。細胞診だけでは確実な診断を行うことが困難なため、すでに子宮体がんを疑うような症状が現れている人には組織診を行うことが一般的です。
子宮内膜組織診とは、さじ状の器具もしくは吸引器具を使って子宮内部の組織を採取して行う検査のことです。一方、子宮内膜細胞診は、子宮の内部に細い棒状の器具を挿入し、細胞を採取して行う検査を指します。
超音波検査・子宮鏡検査
子宮の状態を調べるための検査です。
超音波検査は腟の中やお腹の上から子宮に向けて超音波を当て、子宮の大きさやしこりの有無などを外来受診時に調べることができます。
一方、子宮鏡検査は腟から子宮の内部に子宮鏡と呼ばれる特殊な器具を挿入し、内部の状態を詳しく調べる検査です。子宮体がんは子宮の内部から発生するので、診断するうえで有用な検査となります。
画像検査
病気の広がりや転移の有無などを詳しく評価するため、MRIなどの画像検査が行われます。また、遠隔転移の状況を把握するためにCT 、PET検査が行われることもあります。
治療
子宮体がんの治療は進行度や全身の状態によって大きく異なり、主に次のようなものが行われます。
手術
子宮体がんの治療の第一選択は手術によって子宮を摘出することです。
早期の子宮体がんであれば、腹腔鏡下手術やロボットを使用した手術などの低侵襲手術(患者の体にかかる負担が少ない手術)が行われます。また、転移を起こしたような進行がんであっても原則として手術が行われます。
子宮体がんでは子宮と卵巣、卵管を摘出します。摘出する範囲はがんの広がりによって異なり、範囲によって単純子宮全摘出術、準広汎子宮全摘出術、広汎子宮全摘出術の3種類があります。いずれの手術においても、子宮体がんの場合は卵巣と卵管は摘出されるのが一般的です。
単純子宮全摘出術は子宮を摘出する手術です。準広汎子宮全摘出術は子宮に加え、子宮を支える組織の一部も摘出する手術です。これらの手術では、がんの広がりに応じて骨盤内や腹部大動脈周辺のリンパ節をあわせて切除することがあります(リンパ節郭清)。
また、広汎子宮全摘出術は子宮に加え、子宮周辺の組織や腟の上部まで含めた広い範囲を摘出する手術です。この手術では通常骨盤内のリンパ節郭清が行われ、必要に応じて腹部大動脈周辺のリンパ節郭清も行うことが検討されます。子宮体がんに対して広汎子宮全摘術が行われることはまれです。
薬物療法
術後の再発を予防するために抗がん剤治療や放射線治療が行われることがあります。また、手術ができないケース、完全に摘出できないケース、再発したケースなどにもこれらの薬物療法が行われるのが一般的です。
近年では進行・再発した子宮体がんに免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ)という薬による治療が行われるようになりました。ペムブロリズマブによる治療は、マイクロサテライト不安定性と呼ばれる検査が陽性の場合にのみ適応となることから、使用できる例は子宮体がん全体の20%程度です。また、がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体がんに対してペムブロリズマブとレンバチニブの併用療法が行えるようになりました。現在さまざまな治験が行われている最中であり、今後のさらなる効果が期待されています。
手術で子宮を摘出してしまうと妊娠ができなくなってしまいます。そのため、患者が妊娠・出産を希望している場合には、早期の子宮体がんに限って子宮を残し、妊娠できる機能を残すことができる妊孕性温存療法を行うことがあります。
治療にはホルモン剤であるプロゲステロンを高用量で用いた薬物療法が行われます。ただし、妊孕性温存療法では出産後にがんが再発する確率が高く、遠隔転移などによって命を落とす危険を伴うこともあります。そのため、妊孕性温存療法を選択したケースでは、妊娠・出産後に子宮を摘出する手術が行われます。
放射線治療
がんに放射線を照射してがんの縮小を目指す治療です。日本では手術後の再発予防には抗がん剤が用いられるケースが多いのですが、放射線治療が行われることもあります。
また、術後に腟に再発した場合などにも放射線治療の効果が期待できます。手術に耐えうる体力がないなど手術が行えないケースにも、手術よりも治療成績は芳しくないものの放射線治療が行われることがあります。
予防
子宮体がんは肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣が発症リスクを高めることが分かっています。そのため、発症を予防するには食生活や運動習慣などをととのえていくことが必要です。
また、月経不順のある人も子宮体がんにかかりやすい可能性があるため、気になる症状がある場合は婦人科の受診を検討しましょう。
さらに、家系内に大腸がん・乳がん・尿路上皮がん・小腸がんなどを発症したことがある女性は遺伝によって発症リスクが高いことが知られています。何かしらの症状が現れたり、異常を感じた場合には、放置したりせずに婦人科を受診するようにしましょう。
 子宮体がんにワクチンが存在しない理由とは?〜早期発見のためにできることとは〜名古屋市立大学 医学研究科産科婦人科学分...西川 隆太郎 先生
子宮体がんにワクチンが存在しない理由とは?〜早期発見のためにできることとは〜名古屋市立大学 医学研究科産科婦人科学分...西川 隆太郎 先生子宮がんには、子宮体がんと子宮頸(しきゅうけい)がん()があり、それぞれが発症原因・症状・治療方法などの異なる別の病気として認識されています。...続きを読む
 子宮体がん治療の最新トピックス~赤坂山王メディカルセンター 院長 青木 大輔先生インタビュー赤坂山王メディカルセンター 院長、国際医...青木 大輔 先生
子宮体がん治療の最新トピックス~赤坂山王メディカルセンター 院長 青木 大輔先生インタビュー赤坂山王メディカルセンター 院長、国際医...青木 大輔 先生子宮体がんの治療では、可能な限り手術療法によって子宮や卵巣・卵管を取り除くことが一般的です。近年ではより患者さんの体に負担がかかりにくい手術方...続きを読む
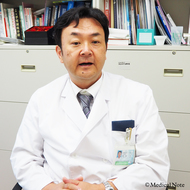 子宮体がんの原因と予防山形大学医学部附属病院 産科婦人科 教授永瀬 智 先生
子宮体がんの原因と予防山形大学医学部附属病院 産科婦人科 教授永瀬 智 先生子宮体がんとは、子宮内膜から発生するがんで、約80%以上はエストロゲンという女性ホルモンが過剰に分泌されることが原因です。子宮頸がんの原因はヒ...続きを読む
- 2023/11/16
- 更新しました
- 2022/11/28
- 更新しました
- 2021/06/02
- 更新しました
- 2021/04/26
- 更新しました
- 2020/07/28
- 更新しました
- 2020/07/01
- 更新しました
- 2017/04/25
- 掲載しました。
「子宮体がん」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「子宮体がん」に関連する記事
 子宮体がんはピルの服用で発症リスクを下げられる?~ピルの服用による様々ながんの発症リスクへの影響とは~国際医療福祉大学医学部 教授進 伸幸 先生
子宮体がんはピルの服用で発症リスクを下げられる?~ピルの服用による様々ながんの発症リスクへの影響とは~国際医療福祉大学医学部 教授進 伸幸 先生 子宮体がんの検査を受ける必要があるのはどのような場合? 組織診とは? 〜受診の目安や検査の流れとは〜国際医療福祉大学医学部 教授進 伸幸 先生
子宮体がんの検査を受ける必要があるのはどのような場合? 組織診とは? 〜受診の目安や検査の流れとは〜国際医療福祉大学医学部 教授進 伸幸 先生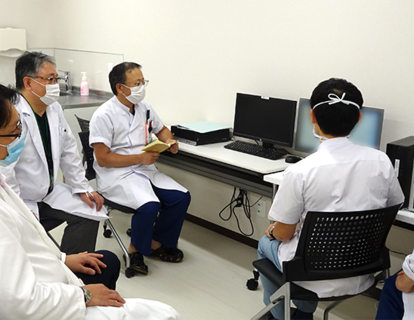 子宮体がんは遺伝することもあるの?〜子宮体がんのリスクがある“リンチ症候群”とは〜国際医療福祉大学医学部 教授進 伸幸 先生
子宮体がんは遺伝することもあるの?〜子宮体がんのリスクがある“リンチ症候群”とは〜国際医療福祉大学医学部 教授進 伸幸 先生 子宮体がんで生じる痛みのタイミングと対処法とは?〜痛みによって対処法も異なる〜NTT東日本関東病院 産婦人科 部長塚﨑 雄大 先生
子宮体がんで生じる痛みのタイミングと対処法とは?〜痛みによって対処法も異なる〜NTT東日本関東病院 産婦人科 部長塚﨑 雄大 先生 子宮体がん検査の疑陽性とは? ~疑陽性の場合のその後の検査や治療~NTT東日本関東病院 産婦人科 部長塚﨑 雄大 先生
子宮体がん検査の疑陽性とは? ~疑陽性の場合のその後の検査や治療~NTT東日本関東病院 産婦人科 部長塚﨑 雄大 先生