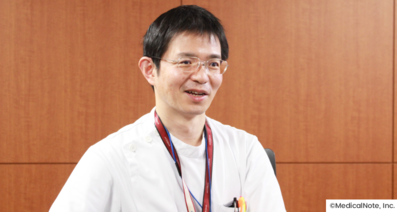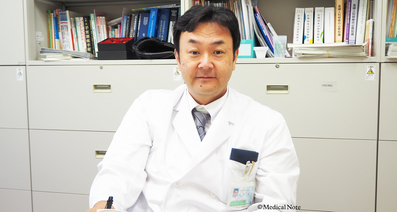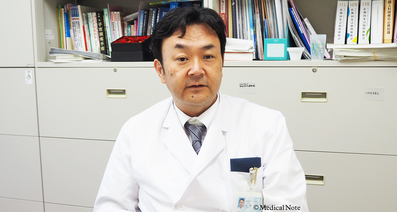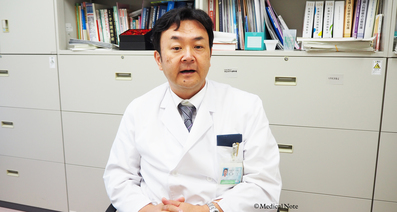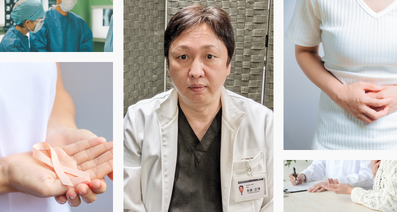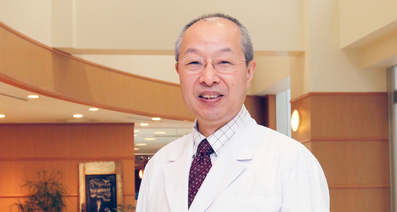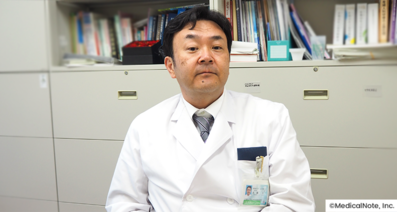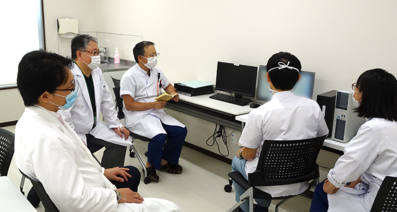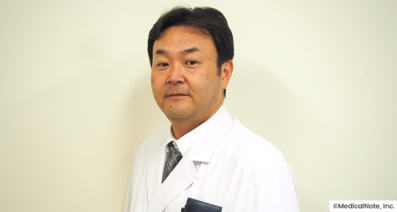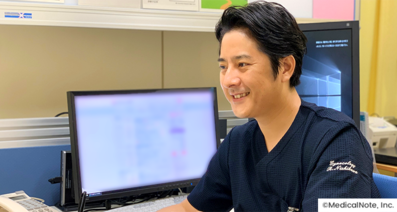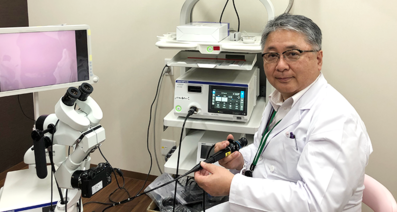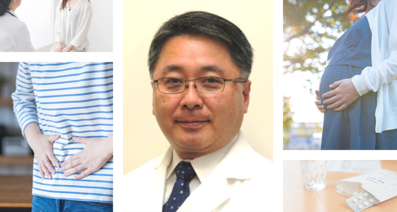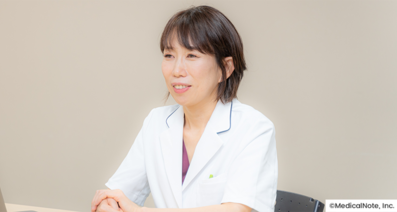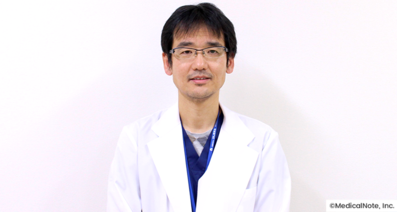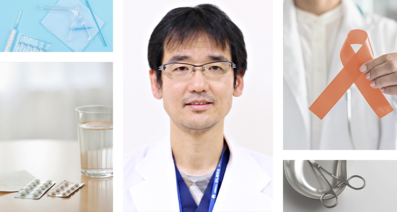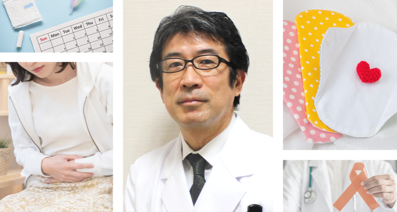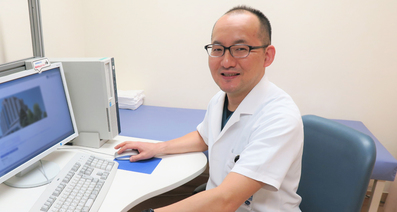
子宮体がんの症状としては、約80%の方で月経(生理)以外の時期に性器出血がある不正出血を認めます。進行すると下腹部痛も出現します。好発年齢は50歳代ですが、40歳より前の若年の方でも不正出血や不妊症(排卵障害)、過多月経の検査を行った際に偶然みつかる場合もあります。閉経後に不正出血がある場合、大部分の原因は萎縮性腟炎です。しかし、約10%の方で子宮頸がんや子宮体がんが潜んでいます。そのため、不正出血がみられた場合は婦人科を受診することが極めて重要です。
不正出血がみられた場合、子宮体がんの検査としては、まず“細胞診”と超音波検査が行われます。
出血が多い場合は、細胞診でがん細胞を捉えにくい場合もあります。その場合は、1回の検査では診断がつかないこともあるため、症状に応じて細胞診を何度か行う、組織診を併用するなどして検査の精度を上げる必要があります。
超音波検査では、腟の中に細長い器具を挿入して、子宮内膜の厚さを確認したり、エコー輝度(白さ)の異なる部分が混在しているかなどを確認したりします。これにより、子宮内膜ポリープや子宮筋腫、卵巣腫瘍の合併、腹水の有無なども確認することができます。痛みはほとんどありません。性交渉の経験のない方の場合は肛門から器具を挿入します。超音波の器具は便よりも細いため、痛みはほとんどなく違和感のみです。中学生や高校生の月経不順や不正出血の場合にもよく用いられる方法です。
子宮体がんの細胞診は子宮頸がんの細胞診と比べて精度が低いため、細胞診で異常があった場合には、“組織診”でさらに詳しくがんの有無や状態を調べる必要があります。組織診では子宮の組織の一部を採取するため、出血や痛みが伴うことがあります。このような症状があると不安に思う方もいらっしゃるでしょう。出産経験がない方や閉経後で子宮頸管が狭い方の場合は、細胞診に用いる器具を子宮内腔まで挿入するのに時間がかかる場合もあります。痛みを感じやすい、不安が強い場合は、検査前に医師に痛みを取る手段について相談してください。事前に痛み止めの坐薬を使用したり、施設によっては静脈麻酔をしたうえで行ったりすることが可能です。
また、組織診を受けた後はどのような合併症が起こり得るのでしょうか?特に、どのくらいの期間、出血や痛みがあるのでしょうか。また、出血が治まらない場合はどのように対処したらよいのでしょうか。
組織診とは
組織診の検査法
組織診とは、子宮体がんの確定診断で用いられる検査です。子宮体がんの検査で最初に行われる細胞診の結果が陽性や疑陽性の場合に、がんの有無や組織型、悪性度を調べるために行う精密検査のことを指します。
検査法は細胞診と同様に細長い形をした器具を使って、子宮内膜の疑わしい部分の組織を掻爬または吸引により採取し、顕微鏡を用いて診断を行います。組織診は細胞診よりも強い痛みを伴うことが多いので、痛みを感じやすい方には必要に応じて、事前に痛み止めの坐薬を使用したり、施設によっては静脈麻酔をしたうえで行ったりすることもあります。海外では外来または入院で麻酔下に行うことが多いのですが、日本では外来で麻酔をかけて検査することに対応できない施設が多く、多くの場合は入院して麻酔下で内膜全面掻爬を実施します。
出血や感染を防ぐための対処法
組織診では子宮内膜の組織の一部を採取するため、出血や月経痛のような痛みを伴うことが一般的です。検査後数日〜1週間程度は出血や茶色いおりものがみられます。しかし、このような症状は組織診のために生じる避けられないもので、通常は出血量が少なく、数日程度で治まります。ただし、数日〜1週間程度たっても出血が止まらない場合は、何らかの対処が必要なことがあるので注意しましょう。
病院では出血に対して止血薬が処方されます。また、非常にまれですが感染が起きて、腹痛や高熱が出現することもあるため、多くの施設では感染予防のために抗菌薬が処方されます。
自分でできる対処法――受診の目安
検査当日は、下腹部に鈍い痛みを感じる場合もあるため、運動や性交渉は避けて早めに休むようにしましょう。数日間少量の出血が続いても、過度に心配せずしばらく様子を見てもよいでしょう。ただし、数日〜1週間程度たっても生理の多いとき以上の出血量がある場合、あるいは腹痛や発熱が出現した場合には受診を検討しましょう。まず検査を受けた施設に連絡して相談してみてください。
また、組織診後に出血や痛みがある期間は以下のことに注意しましょう。
入浴や激しい運動は控える
入浴や激しい運動は血液の流れを活発にするため、さらに出血が止まらなくなったり、量が増えたりする可能性があります。そのため、お風呂では浴槽にはつからず、シャワーにとどめましょう。激しい運動は出血が少なくなってから行うようにしましょう。
タンポンの使用や性交渉は避ける
感染を防ぐため、検査時に挿入されたタンポンやガーゼは3時間程度で抜くように指導している施設が多く、それ以降はタンポンではなくナプキンを当てて対処しましょう。
子宮周辺を刺激することによって出血が止まらなくなる恐れがあるほか、再出血や痛みが増すこともあるため、検査後1週間程度は性交渉を控えましょう。
組織診後の流れ――精密検査の内容
組織診の検査結果は、約7~10日で出ます。検査結果は医師から直接聞くことになります。
子宮体がんと診断されなかった場合は、今後どのように経過を見ていくかなどを話します。不正出血があっても、子宮内膜細胞診や組織診で異常がない場合、小さな内膜ポリープや粘膜下筋腫がないか、3mmくらいの太さの内視鏡を子宮内腔に入れて子宮内腔を直接観察する子宮鏡検査を行うこともあります。また、定期的にエコー検査で子宮内膜の状態をフォローする必要がある場合もあります。
組織診で“異型のない子宮内膜増殖症”と診断された場合、約4%の方は将来子宮体がんに進行する可能性があるため、3~4か月ごとに検査を受ける必要があります。
“異型子宮内膜増殖症”または“子宮体がん”と診断された場合は、原則として子宮を全摘する手術を受ける必要がありますが、おおむね40歳以下の若年の方で妊娠を希望する場合は、いくつかの条件を満たせば、妊孕性温存目的の黄体ホルモン療法を受けられる場合もあります。
子宮体がんと診断された場合は、がんの位置や大きさなどを調べるために、必要に応じて複数の検査を行うことがあります。検査の内容は以下のとおりです。
子宮鏡検査
膣から子宮体部に内視鏡を入れ、がんの位置、形を直接確認する検査です。
この検査は通常、子宮内膜が剥がれる月経終了直後のタイミングで行われます。子宮内膜が厚くなる月経直後や排卵期などは、がんの状態を正しく確認できなくなるためです。
CT検査・MRI検査
CT検査・MRI検査は、体内の様子を画像にして調べるものです。CT検査はX線を、MRI検査は磁気を使うという違いがあります。
CTでは、リンパ節や子宮から遠い臓器への転移の有無、周囲の臓器へのがんの広がりなどを調べます。子宮体がんと同時に存在する重複癌がないかどうかも確認できます。また、MRI検査では、がんが筋層内に入り込んでいる深さや、頸部に進展しているかどうか、また卵巣の様子も調べることができます。子宮周囲の骨盤腔内にがんが広がっていないかも分かります。
腫瘍マーカー検査
腫瘍マーカーは血液検査などで測定できるものですが、卵巣がんと異なり子宮体がんでは診断に使用できる腫瘍マーカーは存在しません。しかし、組織診で子宮体がんと診断がついた後で、病変の広がりや進行を推定するのに参考になるものとしては、CA125という腫瘍マーカーがあります。子宮内に大きな腫瘍を形成している場合や子宮外に広がっている場合にはCA125が上昇してくることがあります。
不安や疑問は医師に相談を
組織診では、より詳しくがんの状態を調べるため、子宮内膜の組織の一部を切除することになり、組織診後は出血や痛みを伴うことがあります。また、数日〜1週間程度出血や茶色いおりものがみられることが一般的です。ただし、なかなか出血が止まらないなどの症状がある場合には、適切な対処が必要になることもあるので、放置せずに医師に相談するとよいでしょう。
また、組織診によって確定診断された後は、必要に応じてほかの検査も行うことがあります。これらは今後の治療方針を決めるうえでも重要な役割を果たすため、組織診をはじめ、その後の検査についても十分に理解し、不安や疑問がある場合は医師に質問するようにしましょう。
国際医療福祉大学医学部 教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
国際医療福祉大学医学部 教授
進 伸幸 先生日本産科婦人科学会 代議員・指導医・産婦人科専門医日本婦人科腫瘍学会 理事・指導医・婦人科腫瘍専門医日本臨床細胞学会 理事・教育研修指導医・細胞診専門医日本癌治療学会 G-CSF適正資料ガイドライン改訂ワーキンググループ委員・臨床試験登録医日本組織細胞化学会 評議員日本婦人科がん検診学会 理事日本先端治療薬研究会 会員日本外科系連合学会 評議員日本専門医機構 産婦人科専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医日本産科婦人科内視鏡学会 腹腔鏡技術認定医婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮体がん委員会 委員・GCIG委員会 委員Sentinel Node Navigation Surgery 研究会 世話人日本臨床分子形態学会 理事日本遺伝性腫瘍学会 評議員
進 伸幸 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が23件あります
体がん手術後の後遺症
お世話になります。 先月31日に開腹手術で子宮、卵巣、リンパ摘出の手術をしました。 結果はG2ステージ1bでした。 18日から抗がん剤治療が始まります。 先生にお聞きしたい事は2点あります。 1点目、術後2.3日してから右足前面に痺れがあり、側面が麻痺しており感覚が全くありません。歩行には支障はありませんが歩く度にジンジン響きます。退院前に先生に相談したところ、治りますよ。と言われました。 しかし2週間近く経っても何も変わりません。日にち薬で時間がかかるのでしょうか? 2点目、18日から抗がん剤治療始まりますが、治療中痺れが出ると聞きました。 今の痺れが酷くなるとゆう事はないですか? 歩けなくなるのではと不安です。 ご回答宜しくお願いします。
ペット集積あり、細胞診疑陽性
こんにちは、54歳女性です。12月6日、たまたまペットCTの検診を受けたところ子宮に集積あり、検査後の医師面談で子宮体がん濃厚と言われました。 婦人科で細胞診を行いましたら疑陽性、hyporplasia が考えられるとのコメントでした 子宮内膜増殖症と言われました。子宮内膜増殖症でもペット集積はするのでしょうか? 総合病院に紹介していただき12月20日受診予定です。全く症状がなかったのに昨夜微量の出血ありました。不安でたまりません。これまで全く症状が無くて今年の2月にも子宮体ガン検診を受け、陰性だったのに思いもよらない出来事に受診までの毎日が心配です。
黄体ホルモンとめまい
更年期障害と診断されホルモン療法を始めて2年が経ちました。子宮体がんの検査が思わしくなく、ホルモン剤を服用し始めて三日後に出血しました。5日程で出血はとまりましたが、その間ずっとめまいと嘔吐が続き苦しかったです。今から7年前には突発性難聴にかかり耳の閉塞感もあります。因みに、降圧剤と不整脈もあり薬も飲んでいます。黄体ホルモン剤とめまいと耳の閉塞感は何か関係あるのでしょうか?何科を受診したら良いのでしょうか?
子宮頸がんの遺伝について
子宮頸がんや子宮体がんは家族の遺伝とか関係ありますか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「子宮体がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。