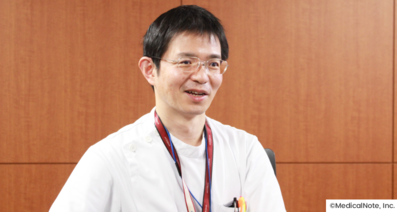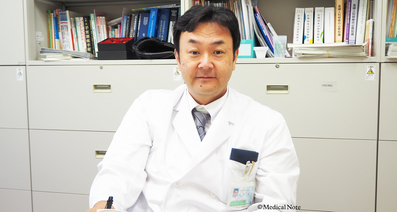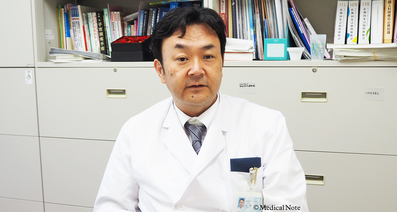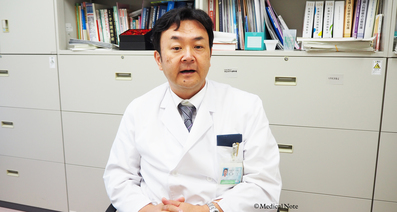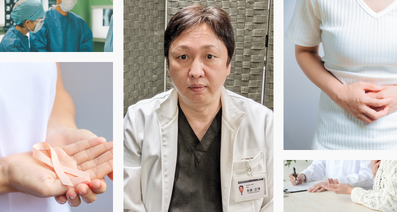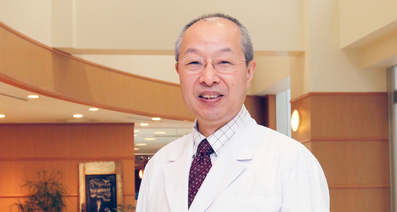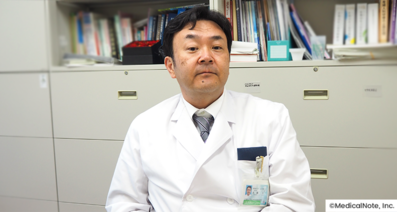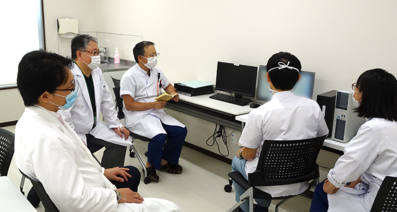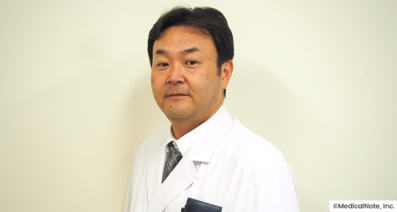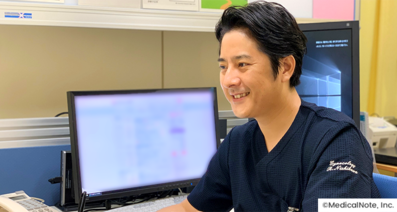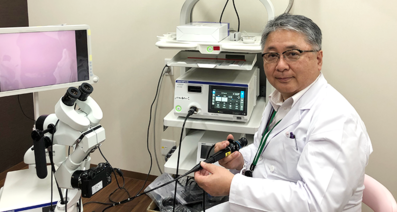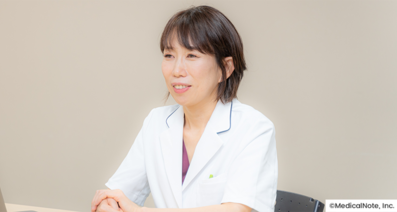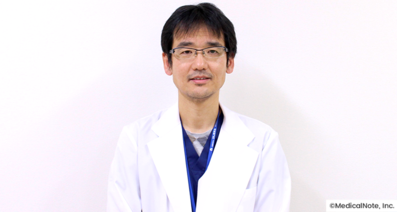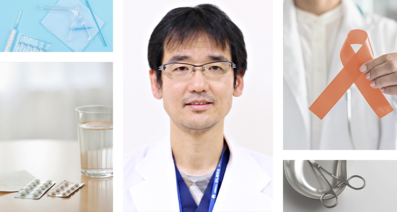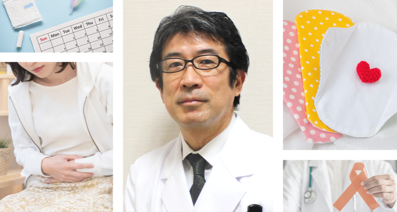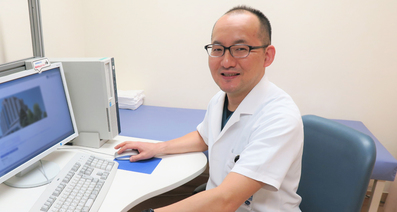

子宮体がんの標準治療は子宮と両側の卵巣・卵管の摘出であるため、妊娠する機能(妊孕性)に影響する可能性があります。しかし、なかには妊孕性を温存するために子宮を残した治療を強く希望する方もいます。がんの進行度合い(ステージ)や腫瘍の病態によって異なりますが、場合によっては子宮を温存することが可能です。では、どのような条件を満たせば妊孕性を温存できるのでしょうか。
本記事では子宮体がんと妊娠をテーマに、妊娠を希望する場合の治療法について詳しく解説します。
妊娠・出産希望の子宮体がん患者が増加傾向にある
近年、妊娠を希望する子宮体がん患者が増加傾向にあるといわれます。
子宮体がんは40歳頃から患者が増加し、50歳代でピークを迎えるとされており、閉経後に生じることが多いといわれています。しかし、子宮体がん患者全体の5~8%は、一般的に妊娠を希望する年代である40歳未満の若年者が占めています。さらに、近年は初回結婚年齢・妊娠年齢が徐々に高齢化していることから、妊娠を希望している年代で不妊治療中などに子宮体がんが発見されるケースが増えてきています。
妊娠・出産経験が子宮体がんのリスクに影響する
一方で、妊娠や出産経験がない人は子宮体がんのリスクが高いといわれていますが、これは子宮体がんの原因の1つである女性ホルモンのエストロゲンが関係しています。エストロゲンには子宮内膜を増殖させるはたらきがあり、その刺激に長くさらされることによって子宮体がんのリスクが上昇すると考えられているのです。つまり、出産経験がない、閉経が遅い、排卵障害*などによる不妊症である、肥満である、卵巣の莢膜細胞腫や線維腫、顆粒膜細胞腫などエストロゲンを産生する腫瘍があるといった場合、エストロゲンの刺激に長くさらされることになるため、子宮体がんのリスクが上がりやすいと考えられます。また、更年期障害に対する治療として黄体ホルモンを併用せずエストロゲン単独で長期に行う場合、また乳がんに対する治療としてタモキシフェン**を長期に内服する場合は、エストロゲンに長くにさらされるため子宮体がんのリスクが上昇します。
なお、妊娠中には子宮内膜の増殖を止めるはたらきがある黄体ホルモン(プロゲステロン)が大量に分泌されます。そのため、妊娠出産経験者は子宮体がんリスクが減少するとされています。
*排卵障害の原因としては、多嚢胞性卵巣、甲状腺機能低下症、耐糖能異常、向精神薬の内服などによる高プロラクチン血症などが挙げられます。
**タモキシフェンは、乳腺ではエストロゲンがエストロゲン受容体に結合することを妨げます(抗エストロゲン作用)が、子宮や卵巣に対しては弱いエストロゲン作用を示します。
妊娠を希望する場合の子宮体がんの治療法
妊娠を希望する場合は、子宮や卵巣・卵管を摘出しない治療方法を選択する必要があります。
高用量黄体ホルモン療法で子宮温存が可能
妊娠を強く希望する患者の場合、適応があれば子宮全摘出術を行わず、高用量黄体ホルモン療法という治療ができる可能性があります。
高用量黄体ホルモン療法とは、1日2〜3回ホルモン薬を服用することと内膜掻爬術によりがんの縮小・消滅を期待する治療方法です。具体的な適応については後述しますが、病変が子宮の筋層内に入り込んでおらず(筋層浸潤がない)、腫瘍のタイプが黄体ホルモンの効きやすい組織型・異型度(類内膜がんでグレードが1、低異型度)である場合、このような治療が検討されます。
高用量黄体ホルモン療法を行う場合、治療開始時に入院して子宮内膜の組織全体を採取する手術を行います。手術は前日に子宮頸管を拡張する処置を行った後、静脈麻酔か全身麻酔をかけて行います。この目的は腫瘍を摘出することと、病理検査で腫瘍が黄体ホルモンの効きやすいタイプであるかを確認することです。その後は、1か月ごとにエコー検査で子宮内膜が薄くなっているか、また子宮内膜の組織を採取する細胞診や組織診で病変の悪化がないか確認します。初回の手術の後、2か月後と4か月後にも子宮内膜の組織全体を採取する手術を行い、病変が消失していることが確認できれば高用量黄体ホルモン療法は終了になります。
治療後2年以内に子宮内に病変が再発する確率は40~50%です。そのため、引き続き外来でエコー検査、子宮内膜の細胞診や組織診、血液検査などを受ける必要があります。
子宮を温存できる条件
子宮体がん患者の全ての人が子宮全摘出を回避できるわけではありません。
なぜなら高用量黄体ホルモン療法には適応となる条件があるためです。高用量黄体ホルモン療法の適応となるかどうかは、事前に検査でよく精査することが必要です。
たとえば、病理組織型が黄体ホルモンの効きにくいタイプ(類内膜がんでグレードが2または3、漿液性がん、明細胞がん、がん肉腫など)であったり、MRIでがんが子宮の筋層に入り込んでいる(筋層浸潤がある)疑いがあったり、卵巣に悪性を疑う変化がみられたりするような場合は、適応外となります。
また、高用量黄体ホルモン療法は標準治療ではないので、さまざまな危険を伴うこともあります。黄体ホルモン療法後に再び子宮内にがんが現れる(再発)確率は治療後2年以内で40~50%、治療中や治療後に卵巣や腹腔内などの子宮外にがんが現れる(重複がんまたはリンパ節転移、遠隔転移、腹腔内播種)確率は数%以下です。これらを事前によく理解して、高用量黄体ホルモン療法を受けるかどうかよく考える必要があります。
子宮温存が治療の選択肢となるのは、基本的に以下のとおりです。
がんの広がりや悪性度が低いなど、さまざまな条件を満たした場合
子宮体がんのステージIA期であり、画像検査で子宮体部の粘膜内にしかがんがないことが確認でき、悪性度が低く予後が比較的良好な状態(類内膜がんでグレードが1)の場合、または前がん状態の子宮内膜異型増殖症である場合、つまり、がんがあまり進行しておらず、がんの広がりや悪性度が低い状態であることが必要です。また、CTなどの画像検査で卵巣や乳腺などに重複がんがないことも重要な条件です。
上記の条件に当てはまっていても子宮温存が可能かどうかは個人差があり、妊娠に適さないほどの高血圧、肥満、糖尿病などを合併している場合や、40歳以上で不妊治療を行っていても妊娠の可能性が低い場合などは適応にはなりません。40歳以上で高用量黄体ホルモン療法を開始した場合、病変が消失してその後妊娠に至る確率は子宮内膜異型増殖症で20%以下、子宮体がんで5%程度です。多くは体外受精などの生殖医療を行って妊娠に至っています。高用量黄体ホルモン療法を行う場合、事前検査として細胞診、組織診、CT・MRI、肝機能や血の固まりやすさなどを調べる血液検査などが必要となります。また、必要に応じて子宮鏡検査が実施されることもあります。
画像診断による適応の判断が難しい場合
画像診断で子宮筋にまでがんが入り込んでいる疑いがある場合、一般的には子宮を全摘出します。
しかし、MRIの画像では精度が不十分である場合が考えられるほか、腫瘍内に平滑筋を含んでいるAPAMという腫瘍の場合は、腫瘍の性格上、画像では筋に入り込んでいるように見えることがあります。このように高用量黄体ホルモン療法の適応を判断することが難しい場合は、子宮鏡下手術で腫瘍を取り除き、病理診断を行うことで高用量黄体ホルモン療法の適応を判断します。
病理検査の結果、子宮体がんの筋層浸潤が否定されれば、高用量黄体ホルモン療法ができる可能性があります。この手術は専門性が高いので、日本婦人科腫瘍学会認定の婦人科腫瘍専門医によく相談することが大切です。
高用量黄体ホルモン療法の効果が現れない場合
半年以上高用量黄体ホルモン療法を行ったにもかかわらずがんが消えない場合、子宮摘出をすすめられることがあります。現在は途中でMRIやCT検査で病変が進行、転移をきたしていないことを確認しながら、9〜12か月まで高用量黄体ホルモン療法と内膜全面掻爬術で病変消失まで治療を続行することができます。
しかし掻爬の病理検査で、高用量黄体ホルモン療法の治療効果ががん細胞にまったく現れてこないと判断された場合は、子宮全摘が望ましいと判断されることがあります。
高用量黄体ホルモン療法後に再発した場合
高用量黄体ホルモン療法を行った後に再発した場合、2018年以前は子宮全摘手術を行う以外の選択肢がありませんでした。しかし、『子宮体がん治療ガイドライン 2018年版』より、黄体ホルモン治療後に再発した場合でも、本人が妊孕性温存を強く希望する場合には厳重な管理を行ったうえで再び高用量黄体ホルモン療法を行い、子宮温存を目指すことができるようになってきました。
再発後の高用量黄体ホルモン療法はより高い専門性が必要となるため、婦人科腫瘍専門医によく相談して治療を受けましょう。専門性の高い医師によって、詳細に細かくフォローする手順が決められている前向きの臨床試験も2020年から日本で開始されています。このような臨床試験に参加を検討するのも1つの選択肢となります。詳しくは医師に相談してみるとよいでしょう。
治療後は早期妊娠を目指す
高用量黄体ホルモン療法は一度がんが消えても再発するリスクが高く、半分以上の人に子宮内再発が起こるという報告もあります。そのため、妊娠できる状況であれは早期の妊娠を目指すのがよいとされています。
場合によっては、治療後に不妊治療専門外来を紹介されることもあります。また、すぐに妊娠を希望しない場合は定期的に黄体ホルモン薬を内服することで、再発率を下げる方法もあります。
治療の選択肢を十分に理解する
子宮体がんは、早期であればあるほど子宮温存できる可能性が高まります。しかし、一方で進行度や腫瘍の病態によっては、子宮全摘出が望ましい場合もあります。そのため、妊娠を希望する場合は納得した治療が行えるよう、自身でも子宮体がんの妊孕性を温存できる治療について十分に理解することが非常に大切です。そのうえで、疑問や不安がある場合は医師や看護師に相談するようにしましょう。
国際医療福祉大学医学部 教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
国際医療福祉大学医学部 教授
進 伸幸 先生日本産科婦人科学会 代議員・指導医・産婦人科専門医日本婦人科腫瘍学会 理事・指導医・婦人科腫瘍専門医日本臨床細胞学会 理事・教育研修指導医・細胞診専門医日本癌治療学会 G-CSF適正資料ガイドライン改訂ワーキンググループ委員・臨床試験登録医日本組織細胞化学会 評議員日本婦人科がん検診学会 理事日本先端治療薬研究会 会員日本外科系連合学会 評議員日本専門医機構 産婦人科専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医日本産科婦人科内視鏡学会 腹腔鏡技術認定医婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮体がん委員会 委員・GCIG委員会 委員Sentinel Node Navigation Surgery 研究会 世話人日本臨床分子形態学会 理事日本遺伝性腫瘍学会 評議員
進 伸幸 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が23件あります
体がん手術後の後遺症
お世話になります。 先月31日に開腹手術で子宮、卵巣、リンパ摘出の手術をしました。 結果はG2ステージ1bでした。 18日から抗がん剤治療が始まります。 先生にお聞きしたい事は2点あります。 1点目、術後2.3日してから右足前面に痺れがあり、側面が麻痺しており感覚が全くありません。歩行には支障はありませんが歩く度にジンジン響きます。退院前に先生に相談したところ、治りますよ。と言われました。 しかし2週間近く経っても何も変わりません。日にち薬で時間がかかるのでしょうか? 2点目、18日から抗がん剤治療始まりますが、治療中痺れが出ると聞きました。 今の痺れが酷くなるとゆう事はないですか? 歩けなくなるのではと不安です。 ご回答宜しくお願いします。
ペット集積あり、細胞診疑陽性
こんにちは、54歳女性です。12月6日、たまたまペットCTの検診を受けたところ子宮に集積あり、検査後の医師面談で子宮体がん濃厚と言われました。 婦人科で細胞診を行いましたら疑陽性、hyporplasia が考えられるとのコメントでした 子宮内膜増殖症と言われました。子宮内膜増殖症でもペット集積はするのでしょうか? 総合病院に紹介していただき12月20日受診予定です。全く症状がなかったのに昨夜微量の出血ありました。不安でたまりません。これまで全く症状が無くて今年の2月にも子宮体ガン検診を受け、陰性だったのに思いもよらない出来事に受診までの毎日が心配です。
黄体ホルモンとめまい
更年期障害と診断されホルモン療法を始めて2年が経ちました。子宮体がんの検査が思わしくなく、ホルモン剤を服用し始めて三日後に出血しました。5日程で出血はとまりましたが、その間ずっとめまいと嘔吐が続き苦しかったです。今から7年前には突発性難聴にかかり耳の閉塞感もあります。因みに、降圧剤と不整脈もあり薬も飲んでいます。黄体ホルモン剤とめまいと耳の閉塞感は何か関係あるのでしょうか?何科を受診したら良いのでしょうか?
子宮頸がんの遺伝について
子宮頸がんや子宮体がんは家族の遺伝とか関係ありますか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「子宮体がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。