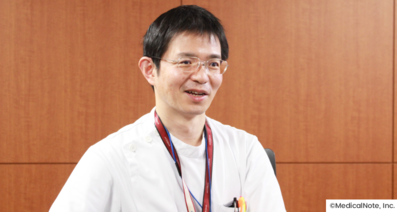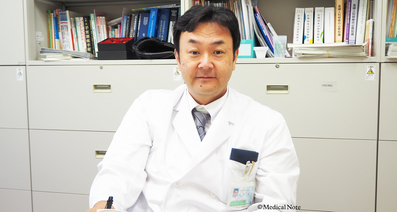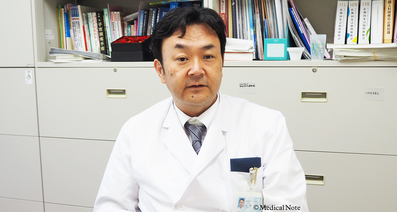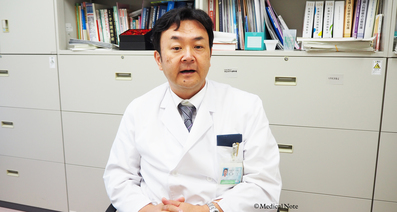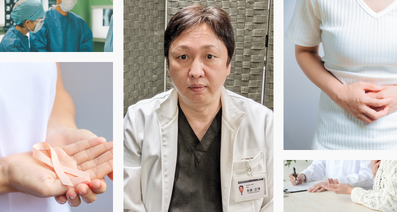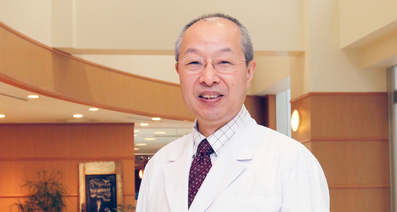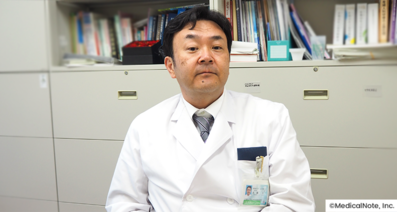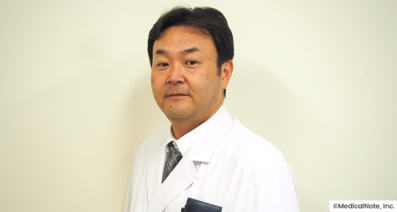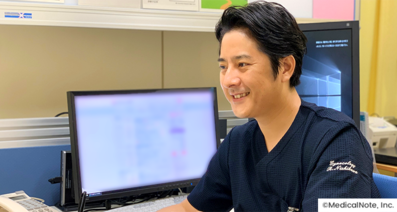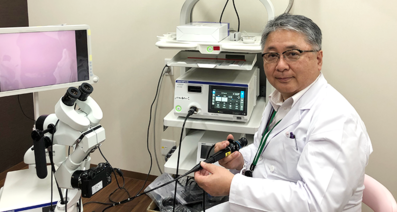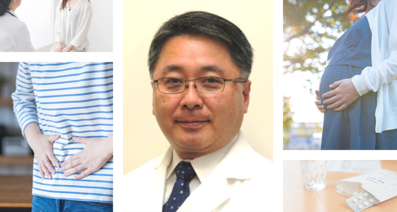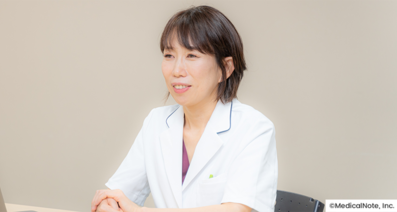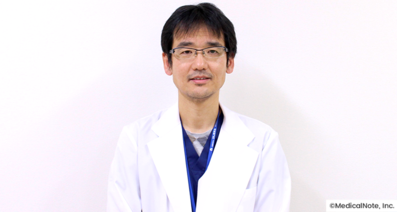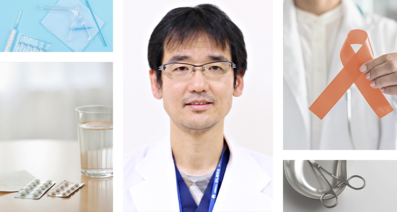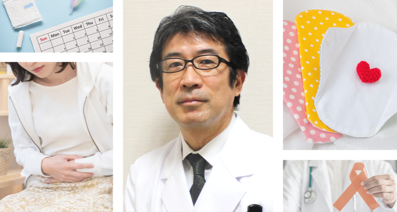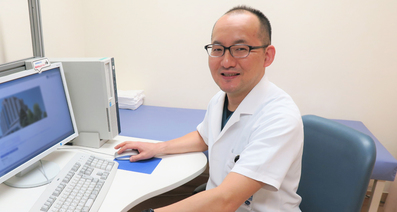
子宮体がんとは、子宮の内側を覆う子宮内膜から発生するがんのことで、主に女性ホルモンの一種であるエストロゲンが関与して発症するといわれています。一方で遺伝が関与して発症するケースもあり、約3~5%が遺伝によって発症するといわれています。一般的に、子宮体がんに限らず“がんは遺伝する”というイメージがあるため、家系内にがん患者がいる方は遺伝を不安に思う方もいるでしょう。では、子宮体がんの場合は遺伝して発生することも考えられるのでしょうか。
子宮体がんの原因と遺伝の関係性
子宮体がんの原因には、女性ホルモンの“エストロゲン”が関与している場合とそうでない場合の2つがあります。中でも遺伝が関与して子宮体がんを発症するのは、子宮体がんの約3~5%で、主に“エストロゲン”が関係していないケースで発症するとされています。
エストロゲンが関与していない場合
エストロゲンが発症に関与していない場合の原因は、主に糖尿病、血縁者にある種のがんになった人がいる、本人がリンチ症候群であることが挙げられます。中でも遺伝が関与して子宮体がんを発症するのは、血縁者に大腸がん、子宮体がん、卵巣がん、胃がん、腎盂尿管がん、膀胱がん、十二指腸がん、になった人がいる、または本人がリンチ症候群である場合です。
エストロゲンが関与している場合
ただし、子宮体がんの発症の多くはエストロゲンが関与しているといわれ、主に血中のエストロゲン濃度が高く、かつプロゲステロンの濃度が低い状態が長く続くことによって発症するとされています。この原因としては、出産の経験がない、閉経の時期が遅い、肥満などが挙げられます。そのほかに乳がん・更年期障害の治療薬に含まれる成分も、子宮体がんのリスクにつながるといいます。
また、甲状腺機能低下、向精神薬投与による高プロラクチン血症などによる排卵障害の場合も子宮体がんの原因となりえます。このほか、乳がんの術後ホルモン療法(タモキシフェンなど)や、更年期障害の治療薬に含まれる成分も、子宮体がんの発症リスクを上昇させます。
子宮体がんはどのように遺伝するの?
子宮体がんに限らず、がんが遺伝するのは“がん抑制遺伝子”と呼ばれる遺伝子が変異していることによって、さまざまながんを発症しやすくなるからだといわれています。がん抑制遺伝子とは、人が生まれつき2本持っている遺伝子のことで、がんのはたらきを抑える役割をしています。しかし、まれにその遺伝子が変異することがあり、2本とも変異するとその細胞はがんになります。
がん抑制遺伝子の変異の受け継ぎ方
もし親のがん抑制遺伝子が変異していた場合、子どもがこの遺伝子を受け継ぐと、最初からがん抑制遺伝子が1つ変異しているため、ほかの人よりも子宮体がんを含むさまざまながんになりやすいと考えられています。遺伝が原因のがんを“遺伝性腫瘍”といいます。
前項で解説したリンチ症候群も、広義のがん抑制遺伝子の変異によって起こります。リンチ症候群では、DNAミスマッチ修復遺伝子(MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、EPCAM)の遺伝子変化またはその発現異常によって、遺伝情報がコピーされて細胞が増えていくときにがん抑制遺伝子のコピー間違いを修復することができず、さまざまながんが発症しやすくなります。リンチ症候群は常染色体顕性(優性)遺伝で、親から子へは50%の確率で受け継がれます。日本では健常人の200~300人あたり1人の割合で認められるという報告があります。
ただし、変異した遺伝子を受け継いでいたとしても、必ずしもがんを発症するとは限りません。どちらかの親のがん抑制細胞遺伝子の1つが変異しているとすると、その子どもは変異した遺伝子を50%の確率で受け継ぐことになりますが、がんを発症しない場合もあります。この状態の人を“未発症保因者”といいます。
子宮体がんのリスクがある“リンチ症候群”とは
リンチ症候群とは遺伝子に変化があることで、主に大腸がんを発症しやすくなることがある病気です。ほかにも子宮体がんや卵巣がん、胃がん、腎盂尿管がん、膀胱がん、十二指腸がんなどさまざまながんのリスクが高く、50歳未満でがんを発症することが多いとされています。
リンチ症候群の可能性が考えられる条件は以下のとおりです。
- リンチ症候群に関連したがんを発症した人が家系内に最低3人いる
- その中の1人は、発症した2人と親、子、兄弟のいずれかである
- 最低二世代にわたってがんを発症している
- 最低1人は50歳未満でがんを発症している
リンチ症候群など遺伝に不安がある場合はどうしたらよい?
リンチ症候群やそのほかの遺伝性腫瘍の可能性があり不安な場合は、“遺伝カウンセリング”を検討するとよいでしょう。遺伝カウンセリングとは、遺伝子検査や予防についての知識、リスクや自身の状況について相談をすることができる場です。
遺伝カウンセリング自体は多くの病院で受けることができるため、近くの病院で実施しているかどうかの確認をしてみるとよいでしょう。なお、臨床遺伝専門医や遺伝カウンセラーの資格は、日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会が共同で認定するもので、前者は2022年1月段階で1,651名、後者は2021年12月段階で318名が認定されています。
子宮体がんの手術を受けた場合は、手術で摘出した組織を用いてリンチ症候群かを調べることが可能です。
まず、スクリーニング検査としてマイクロサテライト不安定性(MSI)検査を行います。この検査は保険適用のため、自己負担割合3割の方の場合、費用は1万円以下です。子宮体がんでは約3割の方がMSI陽性となります。MSI陽性の方で、希望する場合は確定診断のためにミスマッチ修復遺伝子の遺伝学的検査を行います。この検査は保険適用外のため、費用は施設によって異なります。もし、リンチ症候群であると診断された場合、関連して生じる腫瘍の早期に発見するため、さまざまな検査が推奨されます。
子宮体がんの予防法
エストロゲンが関与する子宮体がん(血中のエストロゲン濃度が高く、かつプロゲステロンの濃度が低い状態が長く続くこと)では、ピルの服用が子宮体がんの予防につながるといわれています。なぜなら、ピルにはエストロゲンとプロゲステロンの両方が含まれているため、そのバランスをコントロールして子宮体がんのリスクを約半分に低下させることができるといわれているためです。ただし、ピルの服用によって乳がんなどのリスクが上昇することがあるので、メリットとデメリットを事前に理解して、医師の指示の下で服用をするようにしましょう。
また子宮体がんにかかわらず、さまざまながんの予防法として、禁煙、節酒、減塩した食事、適度な運動、適正なBMIの維持が効果的とされています。これら5つを実践すると、がんになるリスクが約4割低下するともいわれています。
遺伝が気になる場合は遺伝カウンセリングや予防・検診を
家系の中にがんを発症した人がいる場合でも、必ずしも遺伝によって子宮体がんやそのほかのがんを発症するとは限りません。しかし、不安がある場合は遺伝カウンセリングを受けることを検討するとよいでしょう。受診前に、父母、兄弟姉妹、子ども、孫、祖父母、おじ、おば、いとこ、甥、姪などの範囲に、何歳でどのようながんになったか、あらかじめ確認しておくことも大事です。
80歳までに子宮体がんや卵巣がんになる頻度は、一般の方でそれぞれ3.1%、1.3%ですが、リンチ症候群の場合は5~10倍程度高くなるといわれていました。最近では変異のある遺伝子の種類によって、発症リスク(頻度)と発症年齢が異なることが分かってきました。MLH1遺伝子の変異がある場合は子宮体がん34~54%(発症平均年齢49歳)、卵巣がん4~20%(同46歳)、MSH2遺伝子の変異がある場合は子宮体がん21~57%(同47~48歳)、卵巣がん8~38%(同43歳)、MSH6遺伝子の変異がある場合は子宮体がん16~49%(同53~55歳)、卵巣がん1~13%(同46歳)などです。早期発見のための検査として、経腟超音波検査、子宮内膜組織診を30~35歳から年1回受けることが推奨されています。予防的に子宮全摘や卵巣摘出の有効性についてはまだ分かっていません。
国際医療福祉大学医学部 教授
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
国際医療福祉大学医学部 教授
進 伸幸 先生日本産科婦人科学会 代議員・指導医・産婦人科専門医日本婦人科腫瘍学会 理事・指導医・婦人科腫瘍専門医日本臨床細胞学会 理事・教育研修指導医・細胞診専門医日本癌治療学会 G-CSF適正資料ガイドライン改訂ワーキンググループ委員・臨床試験登録医日本組織細胞化学会 評議員日本婦人科がん検診学会 理事日本先端治療薬研究会 会員日本外科系連合学会 評議員日本専門医機構 産婦人科専門医日本がん治療認定医機構 がん治療認定医日本産科婦人科内視鏡学会 腹腔鏡技術認定医婦人科悪性腫瘍研究機構 子宮体がん委員会 委員・GCIG委員会 委員Sentinel Node Navigation Surgery 研究会 世話人日本臨床分子形態学会 理事日本遺伝性腫瘍学会 評議員
進 伸幸 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が23件あります
体がん手術後の後遺症
お世話になります。 先月31日に開腹手術で子宮、卵巣、リンパ摘出の手術をしました。 結果はG2ステージ1bでした。 18日から抗がん剤治療が始まります。 先生にお聞きしたい事は2点あります。 1点目、術後2.3日してから右足前面に痺れがあり、側面が麻痺しており感覚が全くありません。歩行には支障はありませんが歩く度にジンジン響きます。退院前に先生に相談したところ、治りますよ。と言われました。 しかし2週間近く経っても何も変わりません。日にち薬で時間がかかるのでしょうか? 2点目、18日から抗がん剤治療始まりますが、治療中痺れが出ると聞きました。 今の痺れが酷くなるとゆう事はないですか? 歩けなくなるのではと不安です。 ご回答宜しくお願いします。
ペット集積あり、細胞診疑陽性
こんにちは、54歳女性です。12月6日、たまたまペットCTの検診を受けたところ子宮に集積あり、検査後の医師面談で子宮体がん濃厚と言われました。 婦人科で細胞診を行いましたら疑陽性、hyporplasia が考えられるとのコメントでした 子宮内膜増殖症と言われました。子宮内膜増殖症でもペット集積はするのでしょうか? 総合病院に紹介していただき12月20日受診予定です。全く症状がなかったのに昨夜微量の出血ありました。不安でたまりません。これまで全く症状が無くて今年の2月にも子宮体ガン検診を受け、陰性だったのに思いもよらない出来事に受診までの毎日が心配です。
黄体ホルモンとめまい
更年期障害と診断されホルモン療法を始めて2年が経ちました。子宮体がんの検査が思わしくなく、ホルモン剤を服用し始めて三日後に出血しました。5日程で出血はとまりましたが、その間ずっとめまいと嘔吐が続き苦しかったです。今から7年前には突発性難聴にかかり耳の閉塞感もあります。因みに、降圧剤と不整脈もあり薬も飲んでいます。黄体ホルモン剤とめまいと耳の閉塞感は何か関係あるのでしょうか?何科を受診したら良いのでしょうか?
子宮頸がんの遺伝について
子宮頸がんや子宮体がんは家族の遺伝とか関係ありますか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「子宮体がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。