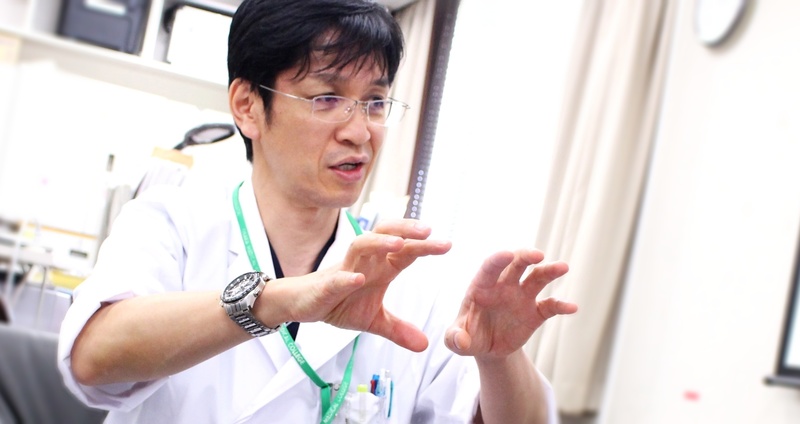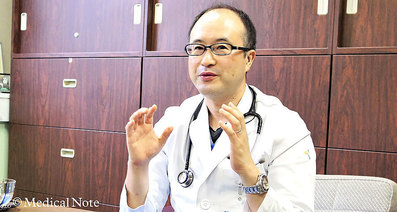
肺高血圧症と聞いて、いわゆる高血圧を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、肺高血圧症は一般的な高血圧症とは全くの別物です。今回は、肺高血圧症とはどのような病気なのか、先天性心疾患に伴う肺高血圧症を中心に大阪医科大学附属病院小児心臓血管外科診療科長の根本慎太郎先生に解説していただきました。
肺高血圧症とは?
肺高血圧症は、肺への血流が著しく増加していたり、肺静脈の心臓への流れがつまっていたりする場合に、肺動脈の壁が硬く厚くなって、内腔が狭くなってくる状態を指します。結果として、肺動脈の圧力が上昇します。
肺高血圧症には様々な原因がある
具体的には原因不明の原発性のもの、遺伝子的な問題によるもの、先天性心疾患に伴うもの、慢性肺疾患に伴うもの、慢性肺動脈血栓によるもの、そして膠原病(関節リウマチや全身性エリテマトーデスなど、自己免疫の異常によって発症する病気の総称)によるものなど、原因は多岐に渡ります。
先天性心疾患にともなう肺高血圧症
たとえば心室中隔欠損症という病気は、右心室と左心室のあいだに穴があいている状態です。この状態では、左心室から右心室に血液が流れ、肺動脈に血流が増えていきます。この大量の血流は肺の血管にストレスをかけます。
常にストレスがかかった肺の血管は、これ以上血管に負担をかけないよう、血管を厚く細くして、血液を流さないようにしてしまいます。いわゆる防衛システムの作用ですが、長い間ストレスに曝されると、徐々に元に戻らない状態となります。
一般的な高血圧症は中高年の方に多く発生する病気ですが、肺高血圧症は血行動態からくるものであり、むしろ先天性心疾患を持つ子どもから若い人がなりやすい病気です。
アイゼンメンジャー症候群とは?ー肺高血圧症のなれの果て
アイゼンメンジャー症候群は、先天性心疾患に伴う肺高血圧症を未治療のまま放っておくと起こる可能性がある合併症のひとつで、最終的に静脈血が動脈血に流れ込んでいる状態を指します。
肺動脈の圧力が上昇し、それに伴って右心室の圧力が上がります。そして、左心室よりも高くなると、酸素の少ない静脈血が左心系に流れ込み、チアノーゼ(皮膚や粘膜が紫色になる状態)を引き起こします。ここまでくるとかなり重篤であり、予後(患者さんの容態の経過)は不良で、命が危ぶまれます。先天性心疾患の患者さんに対しては、肺高血圧症はもちろん、特に絶対にアイゼンメンジャー症候群にならないよう、医師が細心の注意を払う必要があります。
手術後に起きる肺高血圧症の注意点ー肺高血圧クライシス
仮に心室中隔欠損症の患者さんに手術を施して穴を閉じたとき、手術後にアイゼンメンジャー症候群のように肺に血液が流れなくなった場合には命の危険があります(肺高血圧クライシス)。ですから、手術が無事に終わっても安心はできないのです。
肺高血圧クライシスは、手術のストレスなどの影響で血管をリラックスさせる物質の生産が減ったり、その逆の現象が起こったりして、肺の細い動脈(末梢血管)がけいれんを起こしてしまう状態で、重症発作ともいいます。こうなると全く肺に血液が流れなくなり命の危険を伴うため、絶対に回避しなければなりません。
※『フォンタン手術とは。ひとつの心室に対する手術』で述べたフォンタン手術も、肺高血圧症になってしまったらできない手術です。肺血流が多すぎる場合は、肺動脈バンディングという手法を用います。肺動脈バンディングとは、肺動脈をバンドのようなものでくくっておいて血流を減らすように調整する手術です。この姑息手術を事前に行っておいてから、フォンタン手術に入ります。
肺高血圧症治療の進歩
肺高血圧の治療は、基本的には、肺高血圧症を起こさせないということが大前提です。
それでも万が一、肺高血圧症を起こしてしまったら、それに対応した肺高血圧症の治療薬を上手に使いながら、組み合わせて集中的に治療していかなければいけません。
かつては肺高血圧症ともなるともはや致死的と言える状態でした。それが今ではそれに対する治療法が少しずつ出てきており、手術にもいい影響が出ています。
肺高血圧症が治療できるようになったおかげで、今までだったら手術は無理とされていた先天性疾患が手術の対象になってきました。それにより、治療の対象が増えつつあります。
医療の格差―肺高血圧症手術を受けられる子どもと受けられない子ども
医療に恵まれた日本だと、生まれて早い時期に先天性心疾患であるかどうかの診断がつきます。ですので、心室中隔欠損症などの先天性心疾患を持っているとわかれば医師が放っておくことはありません。しかし、かつてはすぐ治療まで持っていくことができなかったので、肺高血圧になってしまった子どももたくさんいました。
かつての日本がこのような状態であったように、現在の途上国も肺高血圧症の患者さんが多くいらっしゃいます。現在の日本の技術と知識があれば、救える命が他国にはたくさん存在しています。
肺高血圧症が知られるように―小児科だけでなく、内科や循環器科、呼吸器科へも広がりを
膠原病の患者さんのなかにも肺高血圧症を合併する患者さんがいて、内科の先生方も現在肺高血圧症に対して注目を高めています。このように、肺高血圧症は内科・内分泌科の領域までトピックスとして広がってきています。
もともと肺高血圧症の患者さんの総数としては先天性心疾患の方が多かったのですが、だんだん様々な診療科でも見つかってきています。肺高血の領域では、すごいスピードで経験と知識が増えてきているのです。
大阪医科大学附属病院 小児心臓血管外科診療科長
根本 慎太郎 先生日本外科学会 外科専門医日本循環器学会 循環器専門医日本胸部外科学会 認定医・指導医日本移植学会 会員日本集中治療医学会 会員
新潟大学医学部を卒業後、東京女子医科大学、米国サウスカロライナ医科大学、米国テキサス州ベイラー医科大学、豪州国メルボルン王立小児病院、マレーシア心臓病センターなど海外各地での経験を経て、大阪医科大学附属病院小児心臓血管外科診療科長。フォンタン手術などの難手術をこれまでに数多くこなし、先天性心疾患をもつ多くの幼い命を救ってきた。自らが数多くの臨床を受けるかたわらで、医師や大学、企業などの垣根を超えた地域全体での医療体制に向けた取り組みや、新しい手術製品の新開発など、未来を担う子どもたちのために幅広い活躍を見せている。
根本 慎太郎 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
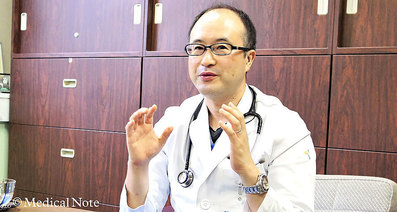
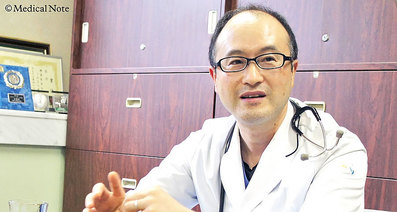
肺高血圧症の原因・症状・治療
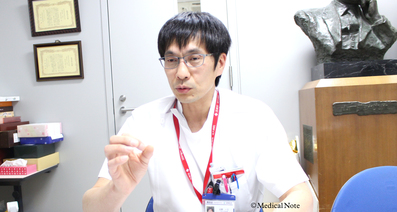
肺高血圧症の治療とは? 大きく変わりつつある肺高血圧症治療の進歩を解説
関連の医療相談が12件あります
肺高血圧症 最大肺動脈圧
入院して5日目 BNP300近くありCTで肺血栓あり入院しました。 今だカテーテルできずBNP下がって安心していますが、自分としては肺血管拡張薬早くはじめてほしいといいました。末梢型 中枢にもあったように思います 手術は適応なくバルーン考えているようです とにかく肺血管拡張薬始めたいと言っているのに、右心カテーテルやってからだと言われて凝固障害あるし心配です。右心カテーテルやらずに肺血管拡張薬不可能なんですか?薬適応ないわけではないと言われています。
子宮筋腫から来る症状について
お世話になります。五年ほど子宮筋腫の経過観察中でしたが、現在一番大きいものが10センチほか6センチが二つ、小さいものもあるようです。 MRIは2月に撮っています。その時はまだ症状が経血もそこまで多くなく貧血もないので、そのまま経過観察をしていましたが、このところ寝起き尿が出にくい、お腹が張る、頻尿、右腰骨右脚がだるい、があり本日病院に行って来ました。内診では卵巣は炎症なし膀胱炎でもない、貧血は大丈夫で、膀胱は圧迫されて変形している。 症状が強くあるなら手術した方が良い。と言われ手術することを決断したのですが、心配なのは右脚の違和感です。腫れてるとか色が違うとかはないのですが、巨大な子宮筋腫が血栓を作る、とから肺に飛んだなどの記事を見つけて 怖くてたまりません。どう気をつければよいのでしょうか、どうなったら深部栓症なのでしょうか。なんとなく最近息苦しくなったりして怖いです。また、どの科に行けばよいのでしょうか。本日婦人科の主治医に話したのですが脚についてはスルーされてしまいました。 話がうまくまとまらずすみません、よろしくお願いします。
味覚障害について
昨年2月に扁桃腺摘出手術を受けて以来、味覚障害が続いています。具体的には塩味がほとんど感じられません。手術を受けた病院でも原因がわかりませんでした。本格的に治療したいと思っていますが何かいい治療方法や治療方針、おすすめの病院などはありますでしょうか?ちなみに亜鉛は2ヶ月程毎日サプリを飲んでます。また糖尿病・高血圧とIgA腎症の治療で服薬しております。
高血圧の治療法について教えてください
先月と今月に別件で病院を受診した際に、どちらも血圧が高った(先月168、今月191)ため、以下の検査を受けました。 ・24時間血圧計・心電図・血液検査・心臓エコー 24時間血圧計の結果は平均値:日中が150/96 就寝時:136/85 心電図では左心室肥大 血液検査では善玉、悪玉、総合コレステロール値の全てがが基準値より僅かに超える結果となり、高血圧という診断で、降圧剤COZAARを処方されました。 私は会社の健診を毎年受診しており、昨年までは血圧は上が110台、下は60代台かつ血液検査の総コレステロール値は基準値を下回っていました。 直近数ヶ月でひどく頭痛がしたり、めまい、息切れなどの自覚があり、更年期障害の可能性もあると考えております。 ここで質問なのですが、更年期障害による高血圧なのであれば、降圧剤を飲むより先に婦人科を受診してホルモン療法を試した方が良いのでしょうか?それとも、かなり血圧が上昇しているので、まずは降圧剤を飲んで血圧を下げた方が良いのでしょうか? ネットで調べたところ、降圧剤は一度飲み始めたら一生やめることができないと書かれていたので、気軽に飲み始めて良いものかどうか躊躇しております。ご意見をお聞かせいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「肺高血圧症」を登録すると、新着の情報をお知らせします