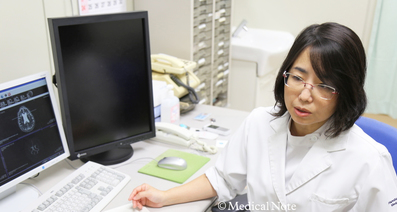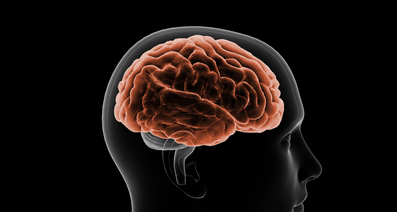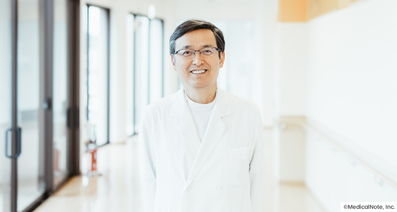
パーキンソン病やレビー小体型認知症の診断に重要な役割を果たす「MIBG心筋シンチグラフィ」という検査法があります。関東中央病院神経内科部長の織茂智之先生はこの研究において世界的に評価されている第一人者であると同時に、日々の診療を通して多くのパーキンソン病患者さんと関わっておられます。地域のクリニックと連携し、病気が進行して外来に来られなくなった患者さんの在宅医療にも力を入れておられる織茂智之先生にお話をうかがいました。
この記事で書かれていること
- ステージにもよるが、薬の使い方で、パーキンソン病の症状進行を遅らせることが可能
- パーキンソン病の治療には「在宅」の位置づけが重要
織茂先生がパーキンソン病の診療に力を入れるようになったきっかけ
自律神経の機能障害をより早く見つけてあげたいという思い
私がパーキンソン病の患者さんにより深く向き合うようになったのは、1994年(平成6年)の1月にこの関東中央病院に来てからのことです。ある寒い日のこと、来院されたパーキンソン病の患者さんをみると、手がソーセージのように真っ赤に腫れていました。血流が非常に悪くなって二次的に浮腫状のむくみが生じていたのです。その患者さんは薬がよく効いていたので、体の動きそのものは比較的よかったのですが、手がパンパンに腫れ上がっていることで非常に困っておられました。
私は直感的に、これはおそらくパーキンソン病の自律神経の症状だろうと考え、そのことをきっかけにパーキンソン病による自律神経の機能障害を早く見つけて治療することはできないだろうかと考えるようになりました。
パーキンソン病での自律神経障害をどのように検査で発見するか
ちょうどその頃、私はSSR(Sympathetic Skin Response:交感神経皮膚反応)という検査を始めていました。皮膚の表面に電極を置いて刺激をすると、交感神経の働きによって手のひらから汗が出てきます。このことを利用してウソ発見器と同じ原理で交感神経の機能をみる検査がSSRです。
当時、東京医科歯科大学の横田隆徳教授に相談をしながら1年ほどその検査に取り組んでいたのですが、なかなかうまくいきませんでした。自律神経障害の強い方はこの検査でもわかるのですが、私はむしろ軽い人を早く見つけてあげたいと考えていたので、その点が難しかったのです。
MIBG心筋シンチグラフィを知るきっかけとなった研修医のひと言

パーキンソン病の運動症状は、特に早期の方であれば薬でコントロールすることができます。しかし、自律神経の症状は、その症状によってはコントロールすることがなかなか難しいのです。ですから、私はなんとかして自律神経の異常を早く見つけ、できることなら治療をしてあげたいと考えていました。
1995年3月のある日、私が若い医師たちを相手にパーキンソン病の自律神経症状やSSRという検査のこと、それがなかなかうまくいかないという話をしたところ、たまたま循環器内科を回っていた研修医が、循環器の領域では最近、MIBG心筋シンチグラフィという検査があることを教えてくれました。
それはパーキンソン病などの神経疾患のためではなく、心臓疾患で心臓の局所の交感神経に起こる異常をみるための検査なのですが、私はそれを聞いて、自律神経に関係するのであればもしかしたらパーキンソン病の自律神経障害の診断にも使えるのではないかと考えました。そこで、パーキンソン病で入院していた患者さんの了承を得てMIBG心筋シンチグラフィを行ったのが最初のきっかけだったのです。
パーキンソン病の検査のひとつMIBG心筋シンチグラフィでわかること
MIBG心筋シンチグラフィを行うと、パーキンソン病の患者さんの心臓にはMIBGが集積しませんが、他のパーキンソン症候群、いわゆるパーキンソニズムと呼ばれる病態ではそれが集積するため、病気の鑑別ができるようになります。
しかし、なぜそうなるのかということが最初のうちはわかりませんでした。そこで、パーキンソン病で亡くなった方の心臓を実際に調べてみようと考え、1998年頃に私が診ていた患者さんが亡くなったときに剖検(ぼうけん・解剖して調べること)をさせていただくことができました。
調べてみたところ、パーキンソン病では、心臓を支配している交感神経に変性が起こり脱神経(脱神経)の状態でした。ところが、他のパーキンソン症候群の場合はそれがないため、MIBGの集積に差があるのだということがわかったのです。これがその後、私の一連の研究につながっていきました。
パーキンソン病の患者さんと向き合う中で気づいた在宅医療の重要性
通院が難しくなった患者さんがたどり着く「在宅」という選択
パーキンソン病の鑑別診断につながる研究をしていると、私のところへパーキンソン病の患者さんがたくさん集まってくるようになり、私自身も興味を持って臨床に取り組んでいましたから、ますます患者さんが多く集まるようになっていきました。
最初のうちは薬でかなり運動症状をコントロールできます。薬にはたくさんの種類がありますが、私たちはさまざまな薬を組み合わせて使い方を工夫し、患者さんのQOL(Quality of life:生活の質)を大事にしながら診療を行っていきます。
しかし患者さんが歳をとり、治療を始めてから10年、20年と経過していくと、歩くことが難しくなって車いすの生活になったり、あるいは何とか歩けてもひとりでは病院に来られないのでタクシーを使わなければならなくなったりします。その結果、どうしても通院ができない方は「在宅」になってしまいます。
在宅での問題となるパーキンソン病の薬の使い方
当時、私自身はまだ在宅診療は行っていませんでしたから、在宅診療を行っている開業医の先生に診療情報提供書を書いてお願いをするという形をとっていました。ところが、在宅診療の先生たちは一生懸命診てくださるものの、やはり神経内科の疾患には詳しくありません。特にパーキンソン病の薬の使い方はわからないことが多く、私たちが紹介状を書いたときから1年経っても2年経っても薬の処方がまったく変わらず、その結果、実は患者さんの症状がどんどん悪くなってしまっていたのです。
パーキンソン病の薬が十分に効果を発揮するには、薬の量を調整する必要がある
脳の中のドパミンを作る細胞は健康な方でも年齢とともに少しずつゆっくりと減少していきます。パーキンソン病の方はそれが非常に早いスピードで減っていき、脳の中のドパミンやそれ以外の神経伝達物質もだんだん減っていきます。
いったん減った細胞を元に戻すことは今の医学ではまだできませんから、足りなくなった分を外から補う必要があります。つまり半年、1年経ったら減った分は新たに薬を増やして調整しなければならないのです。
また、パーキンソン病は運動症状だけではなく、非運動症状といって自律神経症状、嗅覚障害、睡眠障害などがみられますが、進行期になるとさらに認知機能障害や幻覚が現れるようになります。その結果、薬を増やすと非運動症状が悪化することがあり、なおさら薬の使い方が難しくなります。そのため、在宅診療の医師は薬を一切変えず、その結果、病状が悪くなってしまうという例が少なくなかったのです。
地域のクリニックとの連携による訪問診療

そのような状況を目の当たりにして、私は神経内科の医師が在宅診療をすることによって、パーキンソン病の薬を調整できないものだろうかということを以前から考えていました。そこへたまたま関東中央病院にいた神経内科の先生が、訪問診療専門で開業されました。そこでいろいろなやりとりをしている中で、やはり我々が診ている患者さん、特にパーキンソン病の患者さんを彼ひとりで診ていくことは難しいと考え、我々が往診をして訪問診療で一緒に診ようということになったのです。
普段勤務している関東中央病院にも、我々がその訪問診療のクリニックに出向するという形で了承を得て、2011年(平成23年)の6月から在宅の患者さんのところへの訪問診療を始めました。最初は訪問する件数も少なかったのですが、最近はかなり多くなってきて、私も月に何回か実際に訪問して、以前自分が診ていた患者さんを在宅で診ています。そうすると、患者さんもとても安心されています。
先ほど申しましたように、たとえばなんとか歩けるという方でも、ひとり暮らしだとタクシーなどで病院へ行かなければなりません。しかしこちらから往診すればタクシー代などの負担がありません。また、パーキンソン病は難病指定の特定疾患ですから、認定を受けていると医療費の助成を受けることができ、金銭的な面でも患者さんの負担が減ります。
薬を調整することでパーキンソン病の症状の進行を遅らせることができる

パーキンソン病の薬の中では、レボドパ(L-ドパ)という薬が代表的なものです。これはドパミンの材料となるもので、もっともよく効く薬です。しかし、パーキンソン病の薬にはそれ以外にもいろいろなものがあるので、それらをL-ドパに換算して評価します。これをLED( L-dopa equivalent dose:L-ドパ換算用量)といいます。
そうすることによって、たとえばこの薬はL-ドパに換算して何mg相当という形で比較ができます。これを使って我々は、パーキンソン病の患者さんに投与する薬を調節することで症状の進行がどのようになるのかということについて、2年間実際に統計を取ってみました。すると、このLED換算で薬の量は20~30%増えていましたが、症状の進行は非常に少なく抑えられていました。
私たちは症状の進行度を、「ホーエン&ヤールの重症度分類」という尺度を使ってI度からV度までの5段階で評価しますが、その進みが非常に少なかったのです。このことは訪問診療を行っている先生方から学会にも報告してもらったのですが、やはり薬を調整することによってよい状態が長く続くということが実証できたのです。
しかし、私がこれまで診てきた患者さんを引き続き訪問診療でフォローしていくことはできても、すべての在宅患者さんを診ることはできません。全国に在宅のパーキンソン病の患者さんはたくさんいらっしゃるのです。我々はこのことを今後、訪問診療を行っている先生方に知っていただかなくてはなりません。
神経内科医として、訪問診療を行っている医師に知ってほしいこと
まず知っていただきたいのは、薬はある程度増やさなくてはならないということです。その増やし方を実際にどうするかということはたしかに難しいのですが、しかし最低限これとこれとこれなら大丈夫だというように、ある程度の目安となるようなものを今後作っていきたいと考えています。
まだ具体的なことを言える段階ではありませんが、少なくとも症状が進行してきたならば薬を増やすなどの調整が必要であること、進行期の患者さんではレボドパが一番使いやすいのでこれを上手に使っていくということです。
薬の調整でよくしてあげられるのは、どの程度の症状の方なのか?

我々が想定しているのは臥床状態の患者さんではなくて、なんとか伝い歩きができる患者さんです。それぐらいまでの状態であれば、薬の調整によってある程度症状の進行を抑制できると考えています。
したがって、訪問診療医がどのような患者さんを診ておられるのかということによっても話が変わってきます。私が実際に往診している患者さんは、臥床状態や車いす生活(ホーン&ヤールⅤ度)の患者さんより、姿勢の反射が障害され転倒しやすくなっている(ホーン&ヤールⅢ度)患者さんや何とか一人で歩行が可能(ホーン&ヤールⅣ度)な患者さんの方が多いです。なんとか歩けている患者さんをなるべく寝たきりにさせないということも、往診医の重要な使命です。
私も当初在宅の患者さんというと、臥床状態の患者さんが多いのではないかと思っておりました。ところが必ずしもそうではなく、さまざまな理由で通院が困難になった患者さんがいらっしゃるのです。なんとか歩けるけれども通院が本当に大変な方、病院に連れて来てくれる家族がいない患者さんなどは往診の適応があるということになります。そういう患者さんに対する診療を行っていくことが重要であり、今後いろいろな活動を通じてそのことを理解していただきたいと考えています。
第6回 MDSJ 教育研修会「パーキンソン病 200年分を一日で学ぶ」
MDSJ教育研修会は日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(Movement Disorder Society of Japan: MDSJ)が主催し、2012年から始まった教育研修会で、医師・コメディカル・その他の医療関係者を対象に、パーキンソン病についての知識を深めていただくための研修会です。
2017年はパーキンソン病が報告されてからちょうど200年にあたる記念の年です。その2017年3月11日に、日本におけるパーキンソン病のトップランナーの先生方にご登壇いただき、パーキンソン病について1から10までを一日で学ぶ研修会を開催することとなりました。多くの皆さんのご参加をお持ちしています。
日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)公式サイト・教育研修会のページより
http://mdsj.umin.jp/training/index.html

関東中央病院神経内科 部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
織茂 智之 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
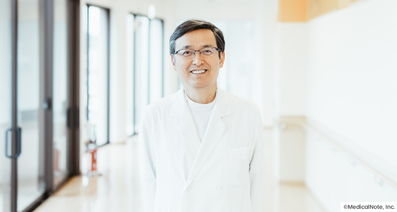
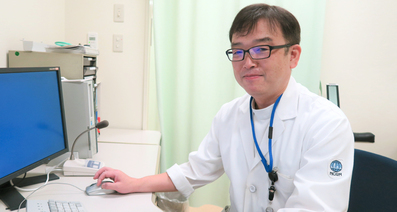
パーキンソン病はどのように診断する? 必要な検査について
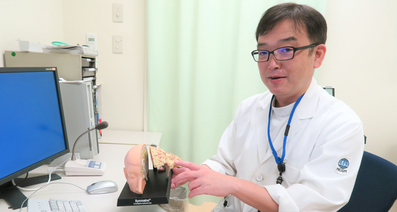
パーキンソン病の治療――使用する薬や服薬の注意点を解説
関連の医療相談が31件あります
パーキンソン病の振戦
パーキンソン病の振戦は安静時にはずっと震えているものなのですか?? それとも震えのない日や時間帯によっては震えが止まっている時もあるのでしょうか?? よろしくお願いします。
脇の下のリンパの痛み
おとといから右脇の下のリンパあたりが痛みます。腫れもしこりもありません 6年前にパーキンソン病と診断され通院中ですが、その辺りから良く首や両脇のリンパは時折痛みを感じていました。 担当の神経内科医は 『パーキンソン病特有の症状によりリンパの流れを悪くし痛みが出る』 気にしだすとますます痛みを感じるので気にしない…とのことでした。 考えてみればその通り…のような気もしますがこの2日間の痛みは今まで以上でした。 (痛くてずっとさすっていたので尚更だったのか?) 今朝は痛みがありません また気にして触ったりすると痛むかも?と思いやめています パーキンソン病の症状(現在 薬服用のおかげで日常生活は自立していますが 筋固縮、身体の可動率の悪さ、便秘、自律神経系からくる立ちくらみなどのいろいろな症状の1つとして考え、やはり 『気にしないこと』が最良なのでしょうか? 怖いのは『そう思っていたら別の病が隠れ ていた』ということで 腫れやしこりがない状態でも、何か他の病気の可能性もあるのでしょうか? よろしくお願い致します
パーキンソン病
祖父と父が60代でパーキンソン病になりました。優性遺伝でのパーキンソン病になると思うのですが原因遺伝子の浸透率は高いのでしょうか?
かかりつけの病院で
かかりつけの病院で、 薬を処方されてますが、 毎回、何を飲んでも薬は効かない、 よくはならないけどねと、 毎回、言われますが、 全く知識もなく、わからない私は、 父親になんと言えばいいですか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「パーキンソン病」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。