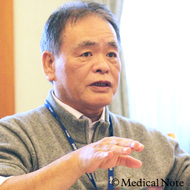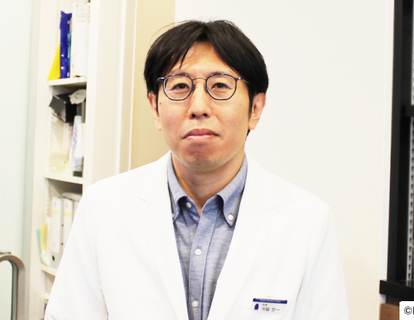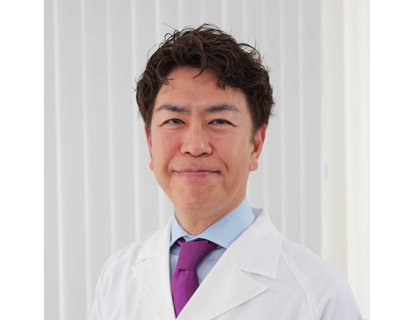概要
2型糖尿病とは、インスリンの作用不足により、血糖値が慢性的に高くなる糖尿病のひとつです。糖尿病は1型・2型・妊娠糖尿病・その他に分けられています(2018年3月時点)。このうち、2型糖尿病は糖尿病の90%以上を占める最も発症が多い病態です。2型糖尿病の多くは食生活や運動不足、あるいはそれらに基づく肥満など、環境因子により起こっています。
糖尿病は、初期の頃は無自覚・無症状で経過することが多い病気です。しかし、病状が進行すると糖尿病(性)網膜症、糖尿病(性)腎症、糖尿病(性)末梢神経障害(糖尿病性ニューロパチー)の3大合併症を起こすことがあります。また、大血管障害である心筋梗塞や脳梗塞などにつながる危険性があります。
このほか、糖尿病により歯周病や認知症、がん、骨粗しょう症などにかかりやすくなることも知られつつあります。歯周病は糖尿病の悪化と関連するともいわれています。
原因
2型糖尿病には、インスリン分泌が低下している場合とインスリンのはたらきが悪くなっている場合(インスリン抵抗性)があります。その原因としては、遺伝因子と環境因子が挙げられます。
遺伝因子
インスリンの分泌、または機能に関わる遺伝子は複数報告されており、これらの遺伝子異常が重なるほど発症しやすくなるといわれています。
環境因子
環境因子としては、肥満、運動不足、食生活の欧米化による脂質摂取量の増加が考えられています。また、栄養バランスの取れていない食事や不規則な食生活も関係しています。
食生活の変化と糖尿病
近年では、戦後の食生活の変化として大麦・雑穀などの摂取が激減したことによる、食物繊維とマグネシウムの摂取不足が2型糖尿病の発症にも大きく関わっていることが指摘されています。
症状
2型糖尿病はほとんどの場合無自覚・無症状です。悪化して高血糖やケトーシスやケトアシドーシスに陥った場合は、口の渇き、多飲、多尿、倦怠感が生じ、体重減少を来します。
多尿
尿糖がある程度出ても症状は現れないことがほとんどです。しかし、大幅に尿糖が出て、さらに高血糖による浸透圧利尿が加わると多尿となります。
口の渇き、多飲
多尿になることで口が渇く症状が現れ、多飲となります。多飲により、さらに多尿が進みます。
検査・診断
2型糖尿病の診断には血液検査の結果が用いられます。
血糖値
はじめに血糖値を確認します。血糖値は食事のタイミングにより、空腹時血糖と随時血糖に分けられます。空腹時血糖126mg/dl以上または随時血糖200mg/dl以上が、糖尿病を診断するうえでの条件のひとつとなります。
HbA1c
HbA1c(ヘモグロビンA1c(NGSP))の値も重視されており、6.5%(NGSP値)以上であれば糖尿病と診断されます。HbA1c値は、過去1~2か月の血糖の平均を反映しているといわれています。これは、血液中のブドウ糖がモグロビンと結合するため、また、赤血球の寿命が平均120日(約4か月)であるためです。
75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)
このほか、血糖値の変化を調べるため、75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)が実施されることもあります。この検査では、75gのブドウ糖を摂取した後、時間の経過を追って採血し、血糖値を測定します。
健康な方の場合、血糖値は摂取後30分ごろに最大値を迎え、その後2時間ほどで基準値以下に戻ります。しかし、糖尿病(糖尿病型)の場合には血糖値が十分に下がらず高値のままとなります。2時間値が200mg/dl以上が、糖尿病の診断条件のひとつとなっています。
2型糖尿病は、これらの検査の結果を組み合わせて総合的に診断されます。
治療
治療の基本は、食事療法と運動療法です。食事を改善し、適度な運動を生活に取り入れたうえで、薬も上手に組み合わせるといった治療が重要です。
食事療法
日常生活における身体活動量と体重などから摂取すべき適正なエネルギー摂取量を知り、指導に従いバランスよい食事を摂るよう努めます。穀物は全粒穀物をしっかり摂ることが大切です。
運動療法
指導に従い、定期的に汗をかく程度の運動を行うこと、毎日十分に歩くことが大切です。日頃から体をまめに動かすことも重要です。
薬物療法
食事療法や運動療法を実践しても血糖値をコントロールできない場合には、薬物療法が行われます。まず、病態に応じてインスリン以外の経口糖尿病薬を1種類もしくは複数使用します。経口糖尿病薬による薬物療法で効果がみられない場合はインスリン療法との併用や、インスイン療法のみの治療に切り替えることがあります。
「2型糖尿病」に関する
最新情報を受け取ることができます
処理が完了できませんでした。時間を空けて再度お試しください
「2型糖尿病」に関連する記事
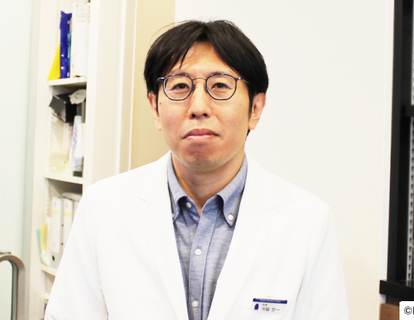 2型糖尿病は早期治療が鍵を握る――患者さんに知っておいてほしいこと二田哲博クリニック姪浜 副院長寺脇 悠一 先生
2型糖尿病は早期治療が鍵を握る――患者さんに知っておいてほしいこと二田哲博クリニック姪浜 副院長寺脇 悠一 先生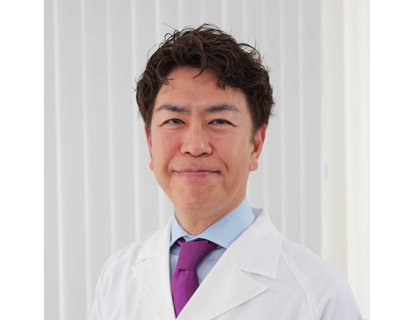 糖尿病治療の変遷――糖尿病のない方と変わらない生活の質(QOL)の実現に向けて医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニ...戸﨑 貴博 先生
糖尿病治療の変遷――糖尿病のない方と変わらない生活の質(QOL)の実現に向けて医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニ...戸﨑 貴博 先生 糖尿病が寿命に影響しない未来を目指して――現在の治療と今後の展望金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 教授...熊代 尚記 先生
糖尿病が寿命に影響しない未来を目指して――現在の治療と今後の展望金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 教授...熊代 尚記 先生 患者さんを1人で頑張らせない――合併症を考慮した2型糖尿病治療三浦中央医院 院長瀧端 正博 先生
患者さんを1人で頑張らせない――合併症を考慮した2型糖尿病治療三浦中央医院 院長瀧端 正博 先生 2型糖尿病の特徴と治療――良好な血糖管理を継続してより長く元気な生活を山梨県立中央病院 糖尿病内分泌内科 臨床...滝澤 壮一 先生
2型糖尿病の特徴と治療――良好な血糖管理を継続してより長く元気な生活を山梨県立中央病院 糖尿病内分泌内科 臨床...滝澤 壮一 先生