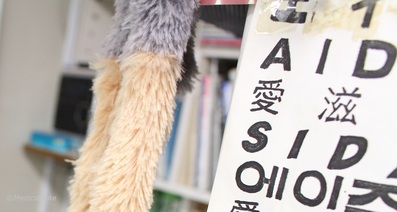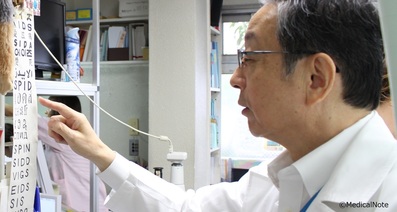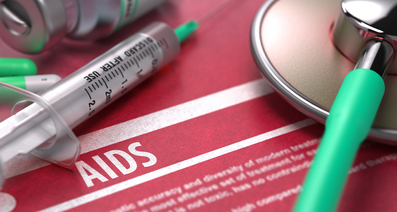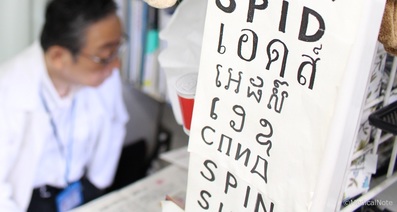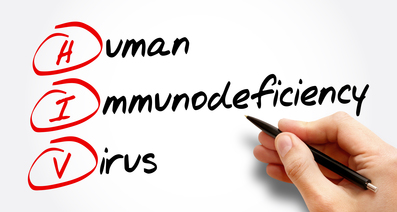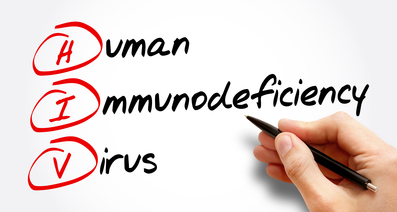感染すると免疫不全を引き起こすことのあるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、AIDS(エイズ:後天性免疫不全症候群)発症の原因となります。近年の治療では、ウイルスを抑え込みつつ、生活の質をより高く保ちながら治療を継続することが重視されています。
今回は、HIV感染症の治療選択時のポイントについて北里大学病院 リウマチ膠原病・感染内科 講師 和田 達彦先生にお話を伺いました。
HIV感染症とは?
免疫力の低下を引き起こす病気
HIVは“ヒト免疫不全ウイルス”という名のとおり、感染すると免疫不全に陥る可能性があります。免疫は外敵(ウイルスや細菌)から身を守るいわば防御システムで、人が健康を保つうえで非常に重要な役割を担っています。この免疫を司るリンパ球にHIVが感染すると、徐々にリンパ球を壊していきます。
初期段階では発熱や喉の痛みを感じますが、一定期間を過ぎると症状は治まり、無症候期に入ります。初期段階で見つからなかった場合には、数年かけて免疫不全が進行していき、健康な場合にはかからないような感染症などを引き起こすようになってしまいます。こうしてHIVに感染した方が、その免疫機能の低下によって特定の病気を発症したときに初めてAIDSであると診断されます。
早期発見・早期治療が鍵
HIV感染が分かった際、一番に気になるのは命を落としてしまうのかということだと思います。近年では医療の進歩により、AIDS発症前の早期段階で治療を行えば、今までどおりの生活を続けられるようになりました。また、AIDSにかかった患者さんでも治療を継続することで、免疫力を回復させることが可能になってきました。
ただ、未診断の方の場合、無症候期に入ってしまうとHIV感染に気付けないケースも多くあります。早期発見・早期治療のためにも、心配な方は検査を受けることを検討してみてください。
HIV感染症治療の目標と方針
近年のHIV感染症の治療目標
2000年ごろまでのHIV感染症治療は、体内からHIVを取り除くことが目標とされていましたが、現在の医療においてHIVを完全に取り除くのは難しいということが分かっています。一方で、近年では薬剤(抗HIV薬)の進歩により、体の中のウイルス量を抑え続け免疫機能を回復させることが目指せるようになってきました。そして現在はウイルスを制御するとともに、患者さんにとってできるだけ服薬が負担にならないようにすることで生活の質を上げていくという点も重視するような治療目標にシフトしてきています。
HIVを抑制しながら、いかに患者さんの生活に合う薬剤を選ぶか
治療薬は著しく進歩していますが、正しく服用できなくては十分にその効果を得ることはできません。患者さんにとって、どの治療方法が続けやすくて負担が少ないのかを考えていくことが重要です。たとえば、1回の服薬数や服薬のタイミング、錠剤か注射か、あるいは錠剤の大きさや副作用など、多くの点を考慮する必要があります。
どの治療薬を使用するかを検討するにあたっては、患者さんの生活スタイルや性格なども考慮して治療方針を提案したうえで、しっかりとご自身が納得いくように話し合うことを大切にしています。中にはほかの基礎疾患の薬を服用している方もいらっしゃるので、飲み合わせなどにも注意して治療方針を決定していきます。
新しい治療法に関する知識のアップデートも大切に
HIV感染症治療は、新たな薬剤の登場によってここ数十年で目まぐるしく変化しています。治療による効果が現れていて、服薬に負担を感じていない場合には、無理に新しく登場した薬剤に変更する必要はありません。しかし、治療を開始した当初はその薬剤がもっとも生活スタイルに合っていると思われた場合も、数年後には、よりその方の生活スタイルに合う薬剤が登場しているかもしれません。そのため、新たな治療薬が登場した場合には、患者さんが受診するタイミングでその治療薬について説明するようにしています。

治療の見直し――服薬の負担軽減と生活の質向上を目指して
服薬の負担を減らせる薬剤の例
前述のとおり、HIV感染症治療は継続的に、正しい方法で服薬を続ける必要があります。そのうえで大切なことは、治療をする患者さん自身の負担ができるだけ少なくなるよう薬剤を選択していくことです。
もちろん、どうすれば負担が少なくなるのかというポイントは患者さんごとに異なりますが、近年注目されているのがSTR(Single Tablet Regimen)です。HIV感染症の治療では複数の薬剤を組み合わせて使用することが一般的であり、以前の抗HIV薬は2剤併用、あるいは3剤併用が必要なものが主流でした。一方、STRは複数の薬剤をまとめて1日1回1錠の服薬で済むようにした治療方法です。ほかの病気も含めて1日に複数回にわたって多数の薬剤を服用していた患者さんにとっては、負担が軽減されたのではないかと感じています。
また、抗HIV薬はボトルに入ったものだけでなく、PTPシート(錠剤をプラスチックとアルミで挟んだもの)に入ったものも登場しています。ボトルに入ったものだと飲み忘れが起こりやすいという面がありましたが、7錠が1シートにまとまっているタイプのPTPシートを使用すると、患者さんも服薬管理がしやすくなるというメリットがあります。

患者さん自身が治療方針について考え、納得することが重要
大切なことは、患者さん自身が能動的に治療方針について考え、納得したうえで服薬をすることです。服薬方法などこれまでのルーティンを崩したくないという方もいらっしゃるかと思いますが、もしもSTRにしたい、PTPシートにしたいなどの希望がある場合、まずはその旨を医師や看護師、薬剤師に伝えてみてください。
また、診療の際にこちらから服薬状況、困り事などについて伺うこともあります。服薬が上手くできていない場合に後ろめたさを感じて濁してしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そうした場合にはその根本的な理由を把握し、一緒に改善する方法を探したいので、ぜひ素直に気持ちや状況をお話しいただけたらと思います。
HIV感染症の患者さんの生活
適切な治療でさらなる感染を防ぐ
HIV感染者に対して早期に抗HIV薬を投与し、ウイルスの活性を抑制することで、未感染者へのHIV感染リスクの低下が期待できることが分かっています。最近では、治療を行いHIVが検出できない状態を6か月以上維持できている場合には、性交渉によってHIVが感染することはないといわれています。こうした研究結果を踏まえて、一人ひとりの患者さんが適切な治療を続ける重要性をぜひ知っておいていただけたらと思います。
HIV感染を理由に仕事を辞める必要はない
実際に生活を送るうえで患者さんからの懸念として挙がるのは“仕事が継続できるのか”という点です。確かに診断直後は治療開始に向けた手続きや診察、治療開始後の経過の確認などで通院頻度が高くなり、仕事を休まざるを得ない日も出てきます。しかし、体調や治療効果が安定した後は、日々の服薬を継続しながら健康維持に努めることがメインになります。
そのため、最初は有給休暇や休職制度などを利用するとよいかと思いますが、一時的なものなので、HIVに感染していることが分かったからといって仕事を辞める必要はありません。

患者さんの高齢化とそれに対するサポート
HIVに感染していても、適切な治療によって以前とほとんど変わりない生活を送れるようになったことで、患者さんの高齢化が起こっています。それ自体は喜ばしいことですが、施設入所などが難しいという新たな課題も生じてきています。そこで当院では、患者さんの入所を受け入れてくださっている施設に対して、HIV感染症治療を行っているチームでお話をしに行き、理解を深めていただくといった取り組みを行っています。
また、高齢化に伴いほかの病気にかかるリスクも高まります。そこで、ほかにも病気がある場合には、他科の先生に対して「こちらのチームではこうした治療を行うので、この部分の治療をお任せしたい」などと説明・コミュニケーションをしてスムーズに治療を行えるよう動いています。
診療で大切にしていること
これまでの知見を次に生かすことで患者さんの力に
私は感染症領域には医学生の頃から関心があり、授業も熱心に受けていました。基本的に感染症はよくなる病気であり、少しでも多くの方を診療し、治したいという思いがありました。その中でも、研修医の頃から診療に携わっていたHIV感染症に専門的に関わるようになったのは自然な流れだったのかもしれません。
特にHIV感染症の診療においては、ほかの医療機関で治療をすることができずに当院に訪れる方もいらっしゃいます。そうした方々に対しても、この数十年でのHIV感染症治療の進歩によって得られた知見を、チーム医療という形にして患者さんに提供したいと思っています。それによって少しでも安心してもらいたい、当院に来てよかったと思ってもらいたいという気持ちが根底にあります。
患者さんへ寄り添いながらプロフェッショナルとして向き合う
どのような病気であっても、診療では言語コミュニケーションだけでなく非言語コミュニケーションも大切にしています。とりわけHIV感染症に関しては、自分の個性や考え方が理解されるかと気にされる患者さんも少なくありません。そうした患者さんの気持ちをまずは受け入れること。そのうえでどのような治療方針にすればその方の生活がよりよいものになるのかを、プロフェッショナルとして提案すること。こうしたことを大切にしながら日々診療にあたっています。また、医療者が良かれと思って行ったことであっても、患者さん自身がどう感じるかは分かりません。そこで、看護師経由で客観的な治療満足度が測れるようなアンケートをとって診療における意見をいただき、それをさらなる診療の改善に生かすといった取り組みも実施しています。
HIV感染症の治療は日頃どれだけきちんと服薬できているかが重要なポイントです。そのため、患者さんとのコミュニケーションの中では、服薬に関して困っていること・つまずいていることがないかを丁寧に確認しています。スマートフォンのアプリなどを活用しながら上手に生活に組み込んでいる患者さんもおり、私自身もそうした方との会話の中で、ほかの患者さんにお伝えできそうなアドバイスを学ぶことが多々あります。私よりも患者さんと接する時間が長く患者さんのことをより理解している看護師や薬剤師と共に、個人個人に対してどのような指導をするのがよいか話し合うこともあります。また、近年の高齢化の影響もあり、どうしても服薬を忘れてしまう患者さんもいらっしゃいます。その場合には、通院する手間や時間は増えるものの、こちら側で服薬状況を管理できる注射に変えるなどといったことも検討するようにしています。

和田先生から読者へのメッセージ
まだ治療を受けていない方へ――怖がらずに受診・治療を
現在では必ず各都道府県にHIV感染症の治療が受けられる医療機関が整備されています。早期発見・治療が重要な病気ですから、怖がらずにまずは近くの医療機関を受診して相談していただきたいと思います。今後の就労や生活など不安なことも多いと思いますが、ソーシャルワーカーに相談できる環境などもあるのでぜひ活用してみてください。
すでに治療を行っている方へ――自分自身の生活をよりよくするために
HIV感染症の診療にあたるなかで、医師をはじめとした医療チームは患者さん自身が日常生活をよりよいものにすることを支援する立場であると考えています。日々の生活に気を付けたり、服薬をしたりするのはあくまでも患者さん自身だからです。だからこそ、治療しているご自身が気になること、困っていることがあるならばぜひ主治医などに相談をしてほしいと思います。近年のHIV感染症治療は、さまざまな薬剤が登場したことによって服薬の回数や方法など、患者さんの生活に少しでも合う薬剤が選択できるように変化してきています。ぜひ負担を減らしながらよりよい生活ができるよう、医療者と共に頑張っていきましょう。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
脇の下がたまに痛い、違和感を感じる
3月にコロナウイルスに感染しました。 その後くらいから、右の脇の下にたまに痛くなります。自分で触ってとくにしこりのようなものはないとは思います。 コロナとは関係ないのかと思い、乳腺エコーをしました。特に異常なしでした。 乳腺など婦人科なのか、もしくはリンパなのか?どのような病院に行けば良いのでしょうか? たまに違和感を感じる程度なので、このまま様子見で問題ないでしょうか?肩こりや筋を違えたようなことはないように思います。 考えられる病気はリンパか乳腺系以外にありますか?よろしくおねがいします。
オミクロン株について
本日17時頃から37.6〜36.5の熱を繰り返しており、倦怠感、鼻詰まり、下痢をしています。 同居人も37.4の熱があり、PCR検討中です。 コロナの可能性はありますか?
コロナウイルス オミクロンについて
オミクロンウイルスにもし感染したら最初に どの様な 症状が出るのでしょうか?参考にお聞きしたいのですが
妊娠中のコロナワクチン接種
妊娠中もコロナワクチンを推奨されていますが、副作用や胎児への影響、長期的な影響を考えると躊躇しています。 現在、安定期に入ったので受けるタイミングは今かなとも思っています。 やはり受けた方が良いでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「HIV感染症」を登録すると、新着の情報をお知らせします