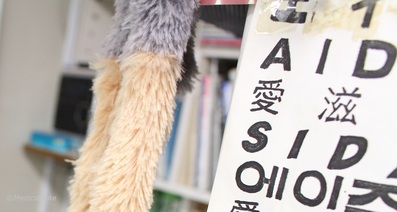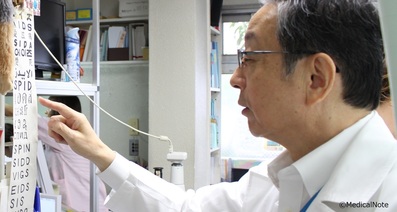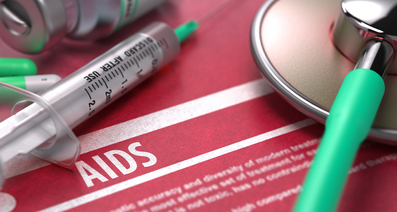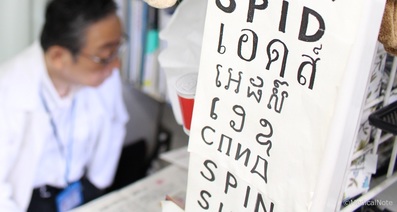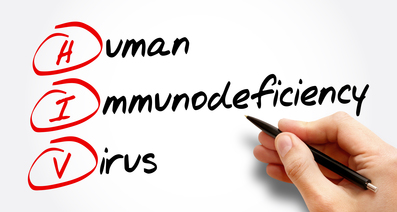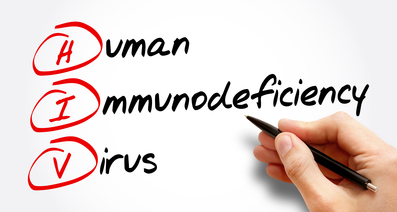かつてはHIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染しAIDS(エイズ:後天性免疫不全症候群)を発症すると、そのまま命を落としてしまうというイメージがありました。しかし近年ではさまざまな治療薬が開発され、自身の生活に合わせて薬を選択し、きちんと服薬を継続することで症状をコントロールしながら日常生活を送れるようになっています。
今回は、新橋南桜パーククリニック 院長 吉田 正樹先生に、HIV感染症の治療選択や見直しの際のポイント、治療時に大切にしていることについてお話を伺いました。
無症状の場合もあるHIV感染症――感染に気付くためには?
“HIV感染症=エイズ”ではない
HIV感染症は、私たちの体を細菌やウイルスなどの病原体から守るのに重要な役割を果たす“CD4陽性リンパ球”という細胞にHIVが感染し、免疫機能が低下する病気です。HIVは感染したCD4陽性リンパ球の中で増殖し、この細胞を破壊します。その結果、体内から徐々にCD4陽性リンパ球が減り、免疫機能が低下します。さらに、HIVに感染した人が、指定された23疾患のうちいずれかを発症するとエイズと診断されます。
無症状期間が長いため心配な方は検査を
HIV感染の初期段階(急性期)では発熱やリンパ節の腫れ、喉の痛みといったインフルエンザのような症状のほか、頭痛や嘔吐を伴う無菌性髄膜炎などを引き起こすこともありますが、いずれも数日~数週間程度で治まります。一方、急性期であっても無症状というケースもあります。急性期を過ぎると無症候期(症状のない期間)に入りますが、この間も体内ではHIVが増殖し体の免疫に重要な細胞を壊し続け、数年~10数年程度でエイズ発症期へ移行します。
こうした経過から分かるように、一度急性期を過ぎてしまうと自発的に検査をしないとエイズ発症前の早期診断に至ることは難しくなります。HIV感染が心配な方は、無症状でも定期的に検査を受けるのがよいでしょう。現在ではエイズ発症前にHIV感染を発見できれば、治療によりエイズ発症はほぼ確実に予防できることが分かっています。
HIVの主な感染経路は、性行為による感染、母子感染、血液による感染の3つです。国内では、男性同性間の感染が多いので、これらの方々は保健所などで定期的な検査が推奨されます。

進歩するHIV感染症治療と治療選択のポイント
1日1回1錠の服薬で患者さんの負担が軽減
HIV感染症治療の目的は、抗HIV薬によって体内のHIV量を抑え続けることで進行を抑制して、免疫機能を回復・維持することです。現在の抗HIV薬は体内からHIVを完全に排除することはできないため、治療は開始したら基本的にはずっと継続していく必要があります。
近年は基本的には、抗HIV薬を複数種類組み合わせる“多剤併用療法”が行われます。以前は1回分で何錠もの薬を内服する必要があるなど、患者さんへの負担が大きい部分もありました。しかし現在は、1錠の中に2~3種類の成分が含まれた薬が多数発売しており、1日1回1錠での治療も可能となったため、治療が続けやすくなってきているといえるでしょう。内服薬以外にも、1~2か月に1回の筋肉注射の薬も使用できるようになりました。
自分の希望に合った治療を選択し継続することが重要
このように治療薬が多数発売されている近年、HIV感染症は患者さん一人ひとりが続けやすい治療を選択することが大切になっています。抗HIV薬は定期的な内服を忘れると、治療効果が損なわれるだけではありません。ウイルスが薬に対する耐性を手に入れ、使用できる薬が減ってしまう恐れがあるため、正しい方法での服薬治療を継続することが重要です。
治療方法を決める際には、錠剤数やサイズ、服薬回数、食事との兼ね合いなどに注目してみましょう。たとえば食中あるいは食後に服薬が必要な薬は、食事時間や頻度が不規則な方には向きません。服薬が苦痛にならないようにするため、できるだけ小さい錠剤にしたいという方もいらっしゃいます。
ウイルス量が十分に抑えられている場合、通院頻度は上がるものの1~2か月に1回の筋肉注射の治療という選択肢もあります。この場合普段の服薬は不要となるため、服薬が負担、あるいは忘れがちという方に適しています。
そのほかの病気やそれに伴い使用している薬、妊娠の有無などによっても治療の選択肢は変わるため、主治医とよく相談のうえ、より続けやすい治療を選択できるようにしましょう。
長期的に病気と付き合うために
検査の数値だけにとらわれず相談を
通院頻度は患者さんの状態によって異なりますが、大体1~3か月に1回程度通院し検査を行います。検査では、患者さんの免疫状態を示すCD4陽性リンパ球数や、HIV感染症の進行速度を示す血中ウイルス量(HIV RNA量)を確認するほか、副作用の観点からも状態を確認します。こうした検査結果や状態を総合的に見て、現在の治療を継続するか別の薬に切り替えるかを判断するのです。
毎回こうした検査を行っていると、なかなかCD4陽性リンパ球の数が増えずに不安を感じられているような方も見受けられます。しかし、検査結果は1年あるいは数年単位の長期的な目線で追っていく必要があります。また、仮にCD4陽性リンパ球数があまり増加していない場合でも、リンパ球一つひとつの機能が改善していれば感染を防ぐ力が戻ってきているということです。ぜひ検査の際にはその数値だけにとらわれず、普段の治療で困っていることはないかなど積極的に主治医とコミュニケーションを取るようにしましょう。ただし、HIV RNA量が上がっている場合には薬剤耐性が生じている可能性もあります。その場合は、別途、薬剤耐性検査を行い治療方法の見直しを検討していきます。
このようにHIV感染症の治療では、その経過を見ながら治療方法を検討していくことになります。薬剤耐性がついているか、リンパ球数がどのように変化しているかなどは検査をして数値を確認することで分かるため、自己判断で服薬や通院をやめることがないよう気を付けていただきたいと思います。
医療機関で自身の内服薬を伝えることが大切
基本的にHIV感染症やエイズの診療は、全国に設置されたエイズ治療拠点病院、地方ブロック拠点病院、中核拠点病院などで実施されており、遠方から通う患者さんも多くいらっしゃいます。そういった方は、体調不良などで来院するのが難しい場合には自宅近くの医療機関を受診しても問題はありません。ただし、抗HIV薬の中にはほかの薬やサプリメントと一緒に服用すると、十分に効果が得られなくなってしまうもの、あるいは副作用を引き起こしてしまうものもあるため、できれば受診先の医療機関でHIVに感染していること、服用している薬の種類をきちんと伝えるのが望ましいといえます。

自分の生活スタイルに治療は合っている? 治療の見直しや再検討
薬剤耐性や副作用は治療見直しのきっかけの1つ
長期間にわたって特に大きな問題・不便がなければ、薬の変更を希望しない患者さんも多くいらっしゃるかと思いますが、薬剤耐性が生じて抗HIV薬の効果が低下した場合や、副作用が生じた場合には、治療薬の見直しを行います。また、より治療を続けやすくするために見直しを行うこともできます。
薬剤耐性が生じた可能性が考えられる場合には、ウイルスの遺伝子変異検査を行うことで、特定の薬への耐性があるかを調べます。もしも使用している薬に耐性が出てきているようであれば、別の薬に変更します。近年では治療薬が進歩して薬剤耐性が出にくくなっているため、きちんと服薬していれば心配しすぎる必要はありません。薬の飲み忘れや自己判断による減薬、薬を飲んだり飲まなかったりという不規則な服薬をすることがないように気を付けていただきたいと思います。
薬自体はよく効いていても、副作用の面で患者さんが服薬をつらいと感じている場合にも変更を検討します。抗HIV薬は多くの場合、複数種類の合剤になっているため、どの薬が副作用を引き起こしたのかは判断が難しいこともありますが、疑いのある薬を他剤に変えて治療を行い、経過を見ていきます。
より治療を続けやすくするための治療見直しも重要
正しい服薬をしないと薬剤耐性が生じる可能性が高まってしまうことからも、“いかに自分にとって服薬を続けやすいか”が治療選択をするうえでとても重要なポイントです。現在1回で複数錠、あるいは1日に複数回の服用をしているのが負担だと感じる場合には1日1回1錠のみの薬に変更する、あるいは1~2か月に1回の筋肉注射に変更を検討するという方法もあります。また、1週間分の薬が1シートに入ったPTP包装*のものを服用すれば、飲み忘れ防止につながります。そのほか、食事の時間や頻度が不規則な場合には服薬タイミングが食事と関係しない薬が適しています。HIV感染症は治療がずっと続くものであるため、年齢を重ねると大きな錠剤を飲みにくいと感じることもあると思います。そのような場合には錠剤のサイズに着目するとよいでしょう。
長年同じ薬で治療を続けている方であっても、もしも現在の治療で困っていること、負担に感じていることがあれば主治医や薬剤師に相談してみるとよいでしょう。
*PTP包装:薄い金属とプラスチックで薬が1錠ずつ包装されたもの

吉田 正樹先生の診療にかける思い
完治しない病気に患者さんと向き合う
私自身は元々HIVに限らず感染症全般を専門にしていました。HIV感染症は免疫機能の低下によりさまざまな感染症を合併するため、感染症を総合的に診ることができるという意味では当時の経験が非常に役立っています。感染症は基本的には治療すれば完治するものが多いですが、HIV感染症の場合は体内にあるHIVを完全に取り除く方法がまだないため、ずっと治療を続けていくことになります。だからこそ、一人ひとりの患者さんを長期にわたって担当することになるという点は、自分自身のやりがいにもつながっている部分です。
患者さんも年齢を重ねると、生活習慣病をはじめ加齢による体の不調が出てくることがあります。患者さんの訴えや思いを伺って一緒に対応を考えるためにも、診療時間には少し余裕を持ちコミュニケーションを大切にするようにしています。一方で、患者さんには医師をはじめとする医療従事者以外にも、悩みを相談できてサポートしてくれる方が周囲にいたほうがよいと感じることもあります。HIV感染症であることをなかなか周囲に伝えられずに悩む方も多くいらっしゃいますが、周囲のサポートはとても心強いものです。もしも周囲への伝え方で悩んでいる場合には、医師や看護師、ソーシャルワーカーなどに相談してみるとよいのではないでしょうか。
HIV感染症だけでなく“患者さん自身”を診る
当院ではチームで患者さんによりよい医療を提供すること、患者さんと正しい知識を共有し、共に治療に向き合うことを目指しています。少しでも患者さんが無理なく安心して治療が受けられるよう、医師だけでなく看護師や薬剤師、ソーシャルワーカー、カウンセラーなど、さまざまな職種が一丸となって患者さんの診療にあたっています。多職種でのミーティングや勉強会もその一環です。
また、患者さんも年を重ねると、脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病になることがあります。そうした病気もある程度は感染症科で対応しますが、コントロールが難しい場合などには他科と連携してきちんとその病気の専門家に診てもらうようにしています。一口にHIV感染症といっても患者さんごとに病気の状態や置かれている環境は異なるため、患者さん一人ひとりに寄り添った医療を提供することが大切です。HIV感染症であることによって患者さんが不利益を被らない医療体制にすることがとても重要だと考えていますし、それを実現できているという自負があります。

吉田先生から患者さんへのメッセージ
さまざまな治療薬の開発により、HIV感染症はきちんと継続して治療を受けていれば予後は非常によくなっており、HIV感染のない方とほぼ同等の生活を送ることが期待できるようになっています。一方で、現在も完治が見込める治療法は確立できておらず、感染した場合には治療の継続が必要です。たとえ現時点では症状が出ていなくとも、無治療では徐々に病気が進行してしまうため、もしも現在服薬や通院を中断している方がいらっしゃる場合には、どうか早急に再受診と治療の再開をしていただきたいと思います。
もちろん、患者さん一人ひとりにそれぞれの生活があります。現在の治療、あるいは過去に受けていた治療で大きく負担になる部分があれば、ぜひ主治医や薬剤師にそのことを伝えてみてください。できるだけ自分の生活スタイルに合った治療を受けられるよう、相談していただければと思います。
新橋南桜パーククリニック 院長、東京慈恵会医科大学附属病院 感染症科 非常勤診療医長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
脇の下がたまに痛い、違和感を感じる
3月にコロナウイルスに感染しました。 その後くらいから、右の脇の下にたまに痛くなります。自分で触ってとくにしこりのようなものはないとは思います。 コロナとは関係ないのかと思い、乳腺エコーをしました。特に異常なしでした。 乳腺など婦人科なのか、もしくはリンパなのか?どのような病院に行けば良いのでしょうか? たまに違和感を感じる程度なので、このまま様子見で問題ないでしょうか?肩こりや筋を違えたようなことはないように思います。 考えられる病気はリンパか乳腺系以外にありますか?よろしくおねがいします。
オミクロン株について
本日17時頃から37.6〜36.5の熱を繰り返しており、倦怠感、鼻詰まり、下痢をしています。 同居人も37.4の熱があり、PCR検討中です。 コロナの可能性はありますか?
コロナウイルス オミクロンについて
オミクロンウイルスにもし感染したら最初に どの様な 症状が出るのでしょうか?参考にお聞きしたいのですが
妊娠中のコロナワクチン接種
妊娠中もコロナワクチンを推奨されていますが、副作用や胎児への影響、長期的な影響を考えると躊躇しています。 現在、安定期に入ったので受けるタイミングは今かなとも思っています。 やはり受けた方が良いでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「HIV感染症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。