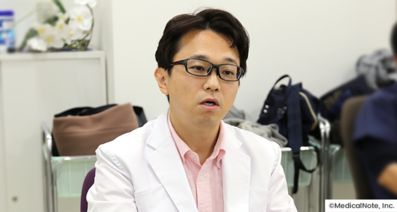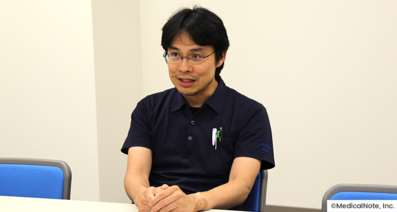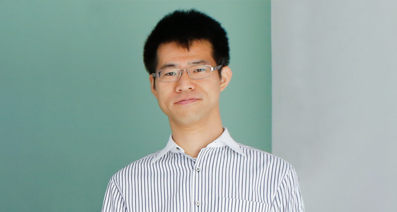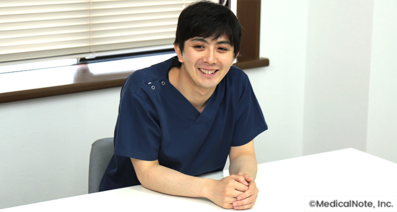腸に便が停滞する状態である便秘は、排便回数の少なさ以外にも腹痛や肛門痛といった症状によって見つかることもあります。子どもの便秘症の発症を防ぐためには幼児期からの排便習慣の獲得や正しくトイレトレーニングを行うなどの生活習慣の改善、重症化を防ぐための適切な便秘治療が重要です。本記事では子どもの便秘症の原因や家庭でできる改善法、医療機関の受診のタイミングについて、東京都立小児総合医療センターの細井 賢二先生に伺いました。
便秘とは? ――便が長時間停滞した状態
便秘とは、腸に便が長時間停滞してしまう状態のことをいいます。年齢によっても排便回数は異なり、新生児・乳児では平均4回/日、幼児期以降は1回/日程度といわれています。ただしこれらはあくまでも目安であり、正常な回数の排便があっても、排便量が少なかったり硬い便(硬便)であったりする場合などは便秘を疑います。また便が詰まった状態(便塞栓)では、硬便の脇を下痢便が通過して排泄される漏便という状態をきたします。従いまして、もともと便秘がある子どもでは、下痢であっても重症便秘症による漏便が原因である可能性があるため、下痢であっても注意が必要です。
子どもの便秘の割合は、10人に1~2人ほどといわれています。便秘により腹痛や肛門痛などの症状が現れる場合を便秘症といい、治療が必要となることがあります。腹痛を繰り返すなどの症状がある場合には、排便回数や便の形などを観察するようにしてください。
便の構成と性状(便性)・量との関係
便は大きく分けて食物繊維、腸内細菌、水分(電解質)、腸の粘膜、分泌液などで構成されています。
まず食物繊維については、大豆や根菜類、穀類に含まれるセルロースやヘミセルロースなどの不溶性食物繊維が便性と便の量に影響します。そのため不溶性食物繊維の摂取量が減ると、便の量は減ります。
腸内細菌は、人間の腸管内に約100兆個生息していて、さまざまな種によって腸内細菌叢を作っています。腸内細菌の中でも善玉菌は腸内環境を整え、便秘を防ぐといわれています。
水分は便の硬さに影響します。通常、便の約80%は水分ですが、水分量が多ければ下痢になり、少ないとコロコロした兎糞状になります。便の水分は腸管で吸収されるため、便が腸管内に長く停滞すればするほど水分は吸収され、便は硬くなります。しかし、水分を必要以上に摂取する必要はないとされていますので通常の水分摂取を心がけてください。また電解質は体内に水分をとどめるはたらきがあり、電解質を調整する下剤もあり、内服することで便に水分を含ませて柔らかくする作用が期待できます。
腸粘膜に関しては、腸の古い粘膜が新陳代謝されて新しい粘膜に代わり、古い粘膜は便として排泄されます。また腸の粘膜は分泌物を排出しており、食事を取っていなくても腸の分泌物が便として排泄されます。
便秘の原因――子どもが便秘になりやすい時期とは?

子どもの便秘の原因となる病気として二分脊椎、巨大結腸症(ヒルシュスプルング病)、鎖肛、甲状腺ホルモンの異常などがありますが、多くは生活習慣が関係し、排便習慣や偏食などが影響しています。
また、子どもには便秘になりやすい時期があり、以下の3つのタイミングが挙げられます。
離乳食の開始時期
第1に離乳食の開始時期です。ミルクや母乳には不溶性食物繊維は含まれていないため便が柔らかくなりやすいですが、離乳食は不溶性食物繊維が含まれているため便が固まり始めます。また、まだ腹筋が弱いため腹圧をかけられず、いきみや肛門を緩めるといった協調運動がうまくできないことも原因となります。
幼児期のトイレトレーニング
次に、幼児期のトイレトレーニングを行うタイミングです。成長とともに腹筋が発達し、肛門の協調運動も可能となりますが、排便を我慢できるようにもなるため便秘となることがあります。無理にトイレトレーニングを行い排便に対して苦手意識ができてしまうと悪化してしまうため、叱責などをしないように気を付けましょう。
通園・通学
最後は、通園・通学の時期です。通園・通学の準備で忙しくなり排便時間が限られてしまう場合や、園や学校などで排便することを拒むことで便秘を発症することがあります。
便を我慢しているうちに便意が落ち着くと排便せずに過ごしてしまい、便が大腸に貯留してしまいます。長く腸管内に貯留した便は水分が吸収され、さらに硬くなります。これにより排便時に肛門痛を訴えたり、裂肛となったりします。また、肛門痛を避けるために排便を我慢してしまうといった悪循環となります。この状態になったお子さんの中には治療に難渋してしまう場合もあります。このような悪循環を改善することが治療の第一歩となりますので、早めに医療機関を受診してください。
家庭でできる子どもの便秘の改善法
子どもの便秘の治療は、排便習慣を獲得することが重要です。規則正しい生活や栄養バランスのよい食事の摂取、トイレトレーニング、排便を我慢しない環境づくりがベースとなります。
乳児期早期の便秘については、前述した便秘をきたす病気がない場合は腹筋や肛門の協調運動の未熟性が原因であるため、肛門刺激や浣腸により排便ができるようになることがあります。また、腹部のマッサージは腹圧をかける補助になるといわれています。
幼児期になると腹筋が強くなって腹圧をかけることができるようになり、また肛門括約筋をうまく使うことができるようになります。これによりトイレトレーニングを開始することができます。
幼児期のトイレトレーニングはどのように行えばよい?

トイレトレーニングは、子どものトイレへの興味や発達に合わせてトレーニングを始めることをおすすめします。便秘があり、過去に排便時の肛門痛などで排便に恐怖感を抱いている場合にはトイレに座ること自体を怖がることがあるため、トイレの空間を子どもの好きなもので飾るなど、楽しい空間にすることもよいかもしれません。
また、朝の起床後は腸管の動きが活発であり、朝食の摂取によってさらに消化管が活発に動くため、朝食を摂取し、トイレに座る時間を確保できるよう心がけてください。これにより、毎朝排便する“習慣性排便”を獲得することもできます。
トイレトレーニングは、始めに自宅のトイレで排尿や排便ができるようにし、つづいて外出先でも排便できるように順序立ててトレーニングしていくことが多いですが、安心できる空間で進めることを優先する必要があります。多忙などの理由でご家庭でのトイレトレーニングの開始が難しい場合でも、保育園などでトレーニングしてくれることがあるため確認するとよいでしょう。
注意点として、子どもの意思に反して無理にトレーニングを行うと、子どもの排便に対する不安が強くなります。また排便に対して嫌なイメージがついてしまうと、排便を我慢するようになり便秘を引き起こす危険性があるため、声かけをしながら無理に行うことなく実施するよう心がけてください。
子どもが排便を失敗することは当然のことです。漏らしてしまっても叱らないで優しく声かけしてあげられるよう、保護者に余裕があるときを選んで行いましょう。
病院の受診が必要となるタイミングは?
毎日排便があっても量が少ない場合やお腹が張っている場合は便秘になっていることがあります。便秘が強いと食思不振(食欲の低下)、腹部膨満(お腹が張る)などを認めることがありますので、このような状態に気が付いた場合には小児科へご相談ください。
規則正しい排便習慣を身につけ、快適なトイレ時間を過ごすことがとても大切です。われわれ医療者と一緒に子どもの排便に関して考え、子どもにとってよりよい排便習慣を身につけていきましょう。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
胃腸炎の後の腹鳴・ガス
11/28(金)の夕方から胃の不快感(ムカムカ)があり、市販の胃腸薬を飲んで様子をみるとおさまったのですが、食欲はまったく無し。 11/29(土)はお粥を少量食べる程度(食欲がない) 11/30(日)のam2時ぐらいから急な水便が朝まで続く(10回以上)。 腹痛はなし。便意があるので急いで行くと水便。 日中は排便なし。 胃の不快感も無し 12/1(月)am4時頃からまたもや水便4~5回 消化器内科クリニックを受診。 迅速血液検査で、炎症反応も白血球も異常なし(正常範囲内)といういうことで、消化不良による胃腸炎と診断 リーダイ配合錠とミヤBM錠が4日分でました。 下痢はおさまったのですが、やたら腹鳴とガスがでます。 まだ、腸の状態がよくないのでしょうか?もう一度受診して別のお薬をいただくのがいいでしょうか? また、別の事も考えられるでしょうか? 消化不良でそんな激しい水便症状はでますか? 現在は胃の症状も下痢もおさまりましたが、やたら腹鳴(特に左腹部)とガスが多くて困っています。 消化不良による胃腸炎に関係しますか?
おへその中や周りのチクチクした痛みやつっぱり感
1週間くらい前からおへその中やおへそのすぐ外側にチクチクした痛みや突っ張り感が出るようになりました。 寝返りをした時や朝起きた時に伸びをした時、動き始める時に感じることが多いです。 同じ頃から下痢や軟便になり今は便秘3日目です。おへそのすぐ上あたりに何かが詰まってるような苦しさがあり食後にひどくなります。食後苦しくて吐きたいという気持ちになります。 元々、機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群があるため、胃腸が張ったり苦しくなったり、下痢や腹痛はよくあるのでその影響かと思っていたのですが、いつもは胃のあたり全体、下腹部全体に症状が出ておへそ周りピンポイントでというのはあまりなかったので気になっています。便秘もたまにはあるけどいつもは快便な方だと思います。 3ヶ月前に虫垂炎になり腹腔鏡手術を受けています。その時退院してから1ヶ月以上、おへそ周りだけ筋肉痛のような痛みやつっぱり感があり、今の症状と似ていて場所も同じです。私の体感は手術後いつの間にか消えていた症状が、何かのきっかけでまた出始めたという感覚です。 手術後3ヶ月以上経つので今頃傷がどうこうというのはないかと思うのですが、他の2箇所の傷はしっかり残っているのでたぶんおへその傷も残ってると思います。見た感じおへその窪みが深くなって縦に細くなったような気がします。 腹腔鏡手術でも癒着はするし腸閉塞になることもあると聞いているので、その不安もあります。 虫垂炎発症前2ヶ月くらい、ひどい便秘が続き手術後に快便に戻ったという経緯もあり、便秘とお腹周りの変化に敏感になっています。 おへそ周りのチクチクやつっぱり感で考えられることって何かあるでしょうか? 仮に癒着してたとして何か症状を自覚できるものなのでしょうか? 機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群の影響というのもあるでしょうか? また、どのくらい症状が続いたりどんな症状が出たら受診した方がいいとか、受診するなら何科に行けばいいのかも教えて頂きたいです。
生理6日目
生理が始まり今日で6日目ですが左右の腹痛(左の方がキツイ)があります。 夕方から急に腹痛が出てきました。 ふとした時に少し痛くなる感じです。 生理中は便秘だったのでその影響もあるのですか? 痛いところは腸骨の横からおへそにかけてです。 生理6日目に痛くなったのは初めてです。 生理痛と思っても良いのでしょうか? 筋腫持ちなので何か関係あるのでしょうか? 生理自体の出血はほぼありません
消化器系の異変について
ここ数ヶ月、 ・ゲップの回数が激増した ・すぐに満腹感(食事量減少) ・便秘ぎみ、以前よりおならもしたくなる と、消化器系の変化を感じています。 特に日常生活に大きな支障はないのですが、大病に繋がる可能性はあるのか、知りたいです。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「便秘症」を登録すると、新着の情報をお知らせします