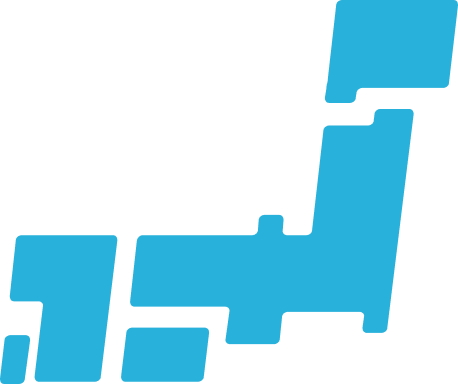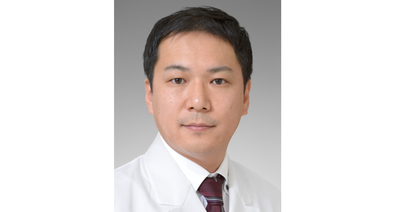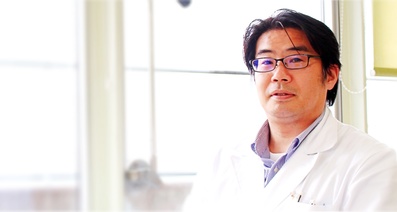糖尿病の合併症の1つである糖尿病網膜症は、重症化すると視力低下や失明につながる病気です。しかし、糖尿病網膜症は黄斑部と呼ばれる部分に症状が及ばなければ、重症化するまで自覚症状がほとんど現れません。また、糖尿病網膜症の患者さんの7.5%ほどに合併する糖尿病黄斑浮腫という病気を発症すると、ものが歪んで見えたり、視力が低下したりします。このような糖尿病の合併症に伴う視力低下を防ぐためには、病気を早期に発見し、治療を継続することが重要です。
今回は、京都大学医学部附属病院 眼科の講師を務める村上 智昭先生に、糖尿病網膜症ならびに糖尿病黄斑浮腫の症状や治療選択肢などについてお話を伺いました。
糖尿病網膜症、糖尿病黄斑浮腫とはどのような病気?

糖尿病網膜症
糖尿病網膜症とは、糖尿病もしくは高血糖(血糖値が高い状態)によって網膜血管が障害された結果、視力低下をきたす病気です。糖尿病に伴う細小血管障害(細い血管に起こる障害)の1つであるといわれていますが、近年では高血糖によって神経や血管を含む網膜全体に負荷がかかり、神経障害を起こすことが悪循環につながっていると考えられています。
糖尿病になって直ちに起こるものではなく、高血糖の状態を一定期間経てから糖尿病網膜症を発症することが分かっています。その期間は個人差があるものの、糖尿病の早期診断・早期治療が進んだことで、日本の糖尿病患者さんにおける糖尿病網膜症の有病率は減少傾向にあります。
糖尿病黄斑浮腫
高血糖によって網膜血管のバリア機能が破綻して血管から血液成分が漏れ出ると、網膜にむくみ(浮腫)が生じます。このむくみが網膜の中でも黄斑部と呼ばれる視力を決める大切な部分にまで及ぶと、中等度の視力低下や変視症(ものが歪んで見える状態)といった症状が現れます。これを糖尿病黄斑浮腫といい、糖尿病網膜症の患者さんの7.5%ほどに糖尿病黄斑浮腫の合併がみられると報告されています。
以前は糖尿病網膜症の病態の1つと考えられていましたが、糖尿病黄斑浮腫の治療法が確立されたことから、近年では糖尿病網膜症とは別の病名として診断されるようになりました。
糖尿病による視力や見え方の変化
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症を発症しても、黄斑部に症状が及ばなければ自覚症状はありません。しかし、進行すると失明する恐れがあるため、自覚症状がなくとも早期の段階から内科的治療とともに定期的に眼科を受診し、悪化を予防していくことが大切です。
糖尿病網膜症の進行度には国際重症度分類を含めいくつかの分類方法がありますが、本記事では患者さんが理解しやすいDavis分類に基づき3つの病期に分けて説明します。
単純糖尿病網膜症
高血糖が長期間続くと、網膜にある毛細血管という細い血管が傷みます。すると、毛細血管にこぶ(毛細血管瘤)ができたり、出血をきたしたりします。ただし、黄斑部にこれらの病状が進行しなければ、自覚症状はありません。
増殖前糖尿病網膜症
病期が進むと毛細血管の血流が悪化し、網膜に酸素や栄養がきちんと供給されない部分が出るようになります。増殖前糖尿病網膜症の段階まで進行しても、黄斑部に病状が及ばなければ自覚症状はほとんどありません。
増殖糖尿病網膜症
さらに進行すると、足りない酸素や栄養を補うために新生血管という異常な血管が作られます。しかし、新生血管は脆いために出血(硝子体出血)をきたしたり、そこから増殖膜が形成されて網膜が引っ張られると剥離(牽引性網膜剥離)したり、隅角に新生血管が形成されて眼圧が高くなったり(血管新生緑内障)します。
糖尿病網膜症によって硝子体出血や牽引性網膜剝離、血管新生緑内障を併発すると、急激に視力が低下し、失明に至るケースもあります。硝子体出血と牽引性網膜剥離は、適切な治療を行うことで失明を避けられるようになってきていますが、血管新生緑内障の治療法は完全には確立されておらず失明率がいまだ高いため、特に注意が必要です。
糖尿病黄斑浮腫

糖尿病黄斑浮腫は糖尿病網膜症の病期とは関係なく発症しますので、単純糖尿病網膜症の段階であっても糖尿病黄斑浮腫になれば視力低下や変視症を生じます。自然寛解することもありますが、放置してしまうとゆるやかに視力が下がっていくことが多いでしょう。
糖尿病黄斑浮腫のみを発症している場合には、治療すれば視力はある程度の改善が見込めます。視力の低下や見え方の変化に気付いた場合には、なるべく早く眼科で検査を受けることをおすすめします。
それ以外の合併症による視力低下のリスク
近年では、糖尿病に伴う黄斑虚血や黄斑変性といった病態が視力低下の原因になり得ると考えられています。しかし、黄斑虚血や黄斑変性を合併している糖尿病網膜症および糖尿病黄斑浮腫に対する治療法はまだ確立されていません。したがって、これら2つの病態を合併している症例については、視力を改善させるのは難しいとされています(2023年9月時点)。今後は糖尿病に伴う黄斑虚血や黄斑変性の病態の解明、治療法の開発が進むことが期待されます。
糖尿病網膜症、糖尿病黄斑浮腫の検査
問診に加えて、視力検査や眼底検査*、OCT(光干渉断層計)検査**などを行うのが一般的な検査の流れです。検査機器のある医療機関では網膜の血流の状態を調べることができるOCTA(光干渉断層血管撮影)検査を行い、網膜に血流障害がないか確認することが多いでしょう。
血管から血液が漏れ出ているか否かという異常はOCTA検査では評価できないので、血管の機能異常を確認する必要がある場合は蛍光眼底造影検査を行います。ただし、蛍光眼底造影検査は造影剤によるアレルギー反応が起こるリスクがあるため、実施する機会は減少していると思われます。
*眼底検査:網膜や血管などの状態を確認する検査
**OCT検査:網膜の断層を撮影する検査
糖尿病網膜症の治療――失明を防ぐための治療法について
糖尿病網膜症はどの病期においても、血糖値と血圧のコントロールが必要不可欠です。眼科では、単純糖尿病網膜症の段階では定期的に経過観察を行います。一般的には増殖糖尿病網膜症になる前、いわゆる増殖前糖尿病網膜症(重症非増殖糖尿病網膜症)の段階から眼科での治療を開始します。
以下では、糖尿病網膜症に対する治療について解説します。
汎網膜光凝固――失明につながる病気の発症予防
増殖前糖尿病網膜症または増殖糖尿病網膜症に進行している場合には、血管新生緑内障の発症予防、あるいは硝子体出血や牽引性網膜剥離の悪化を防ぐために汎網膜光凝固というレーザー治療を実施します。なお、黄斑部とその周囲を焼灼すると視力が低下してしまうため、それらを除いた網膜にレーザーを照射していきます。
失明につながる合併症に対する治療
硝子体手術――硝子体出血、牽引性網膜剥離に対する治療
硝子体出血や牽引性網膜剥離が起こった場合には、局所麻酔による硝子体手術が行われます。硝子体手術では、視力低下の原因となっている部分を治すために、硝子体出血に対しては出血の除去、牽引性網膜剥離に対しては剥がれた網膜の回復を図ります。
糖尿病網膜症の患者さんには若い方も多いため、術後早期の復帰が必要である場合も多々あります。硝子体手術にはいくつかの方法がありますので、重症度や年齢、社会的背景なども考慮したうえで患者さんに応じた手術方法を選択しています。
血管新生緑内障に対する治療

血管新生緑内障をはじめとする緑内障の治療目標は、眼圧を下げて視機能を維持することです。一般的な緑内障と同様に、血管新生緑内障も点眼薬による薬物療法や手術を行います。近年では、隅角が閉塞していない血管新生緑内障に対しては、抗VEGF薬を用いることで眼圧が下降する症例も増えています。
糖尿病黄斑浮腫の治療――視力をおびやかす黄斑浮腫の治療法を中心に解説
黄斑部の中心にあるくぼみは中心窩と呼ばれ、視力に大きな影響を及ぼす部分に当たります。中心窩近傍を含む黄斑浮腫を“視力をおびやかす黄斑浮腫”といいます。それはさらに“中心窩を含む黄斑浮腫”と“中心窩を含まない黄斑浮腫”に分けられ、それぞれ治療選択肢が異なります。
糖尿病黄斑浮腫の治療の流れ
糖尿病黄斑浮腫の治療法には、抗VEGF療法、レーザー治療、ステロイド薬の眼内注射(ステロイド療法)、硝子体手術といった4種類の治療選択肢があります。中心窩を含む黄斑浮腫に対しては、抗VEGFという薬を眼内に注入する抗VEGF療法という治療がまず行われます。そのほか、レーザー治療やステロイド療法、硝子体手術を含む4種類の治療法のいずれも選択肢として考慮しながら、むくみと視力の改善に努めます。
なお、中心窩を含まない糖尿病黄斑浮腫に対してはそこまで強い治療を必要としないため、黄斑光凝固治療というレーザー治療で対応することが多いでしょう。
薬物療法を行ううえでの注意点
抗VEGF薬
抗VEGF療法の導入期には月に一度の注射を3~5回連続して行います。抗VEGF薬は導入期にしっかりと治療を行って症状が落ち着けば、投与する頻度を減らすことも可能です。症状が安定すれば抗VEGF薬の投与が不要になるケースもありますので、医師の指示の下できちんと治療を継続しましょう。

糖尿病黄斑浮腫の治療薬として承認されている抗VEGF薬は5種類あります(2023年9月時点)。抗VEGF薬の中には価格を抑えることができるバイオシミラー(バイオ後発品)*や投与回数を少なく抑えられる薬もあります。頻度は低いものの、眼内炎や網膜剥離といった合併症を起こす可能性はありますので、それぞれの薬剤の特徴やリスク、経済的な負担、通院頻度などについて説明を受けたうえで、医師と相談しながら使用する治療薬を決めていきましょう。
*バイオシミラー:先行の医薬品と同じ基準で製造された医薬品で、同等程度の効果や安全性が承認された薬。先行の医薬品より安価という特徴がある。
ステロイド薬
ステロイド薬は薬剤が安価で作用期間も長く、治療のコストが抑えられるというメリットがあります。一方で、眼圧上昇、白内障、眼内炎といった副作用のリスクが報告されていますので、使用する際は医師による総合的な判断が必要であると考えます。
治療継続と発症予防の重要性
治療継続が視力改善・維持の鍵
以前は、“失明を防ぐこと”が糖尿病網膜症の治療目標でした。しかし、近年では糖尿病の早期発見・早期治療が行われるとともに、硝子体出血や牽引性網膜剝離に対する治療法が確立されたことにより、糖尿病網膜症によって失明する方は減少傾向にあります。そのため、今では失明させないことと同時にできるだけよい視力を保つ、あるいは視力を可能な限り改善していくことが糖尿病網膜症の治療のゴール設定になってきていると思います。
糖尿病黄斑浮腫に関しても、治療を行うことで半数程度は視力改善が期待できます。視力が改善しない場合にも治療を続けることで、視力の維持や視力低下のスローダウンが見込めます。患者さんにとって視力を維持するための治療というのはストレスを感じることも多いでしょう。そこで当院では、“視機能が改善された暁には仕事に復帰して社会貢献する”というような具体的な出口を示したうえで、治療に取り組んでいただくようにしています。患者さんに積極的に治療に関与していただくことが、忍耐強く治療を続けるモチベーションにつながるのではないかと考えています。
発症予防のための対策――定期的な眼科受診が重要
糖尿病網膜症や糖尿病黄斑浮腫の発症を予防するためには、内科において血糖・血圧のコントロールを行うことが必要不可欠です。また、糖尿病と診断を受けた方は定期的に眼科を受診し、糖尿病に伴う合併症がないか確認する必要があります。
糖尿病網膜症の重症度や患者さんの生活背景などによっても異なりますが、高血糖の方や糖尿病網膜症が軽症の方は6か月~1年に1回の頻度で眼科受診をすることが望ましいと考えます。糖尿病網膜症が重症化している方、あるいは糖尿病黄斑浮腫がある方は1~2か月に1回は眼科で検査を受けましょう。
村上 智昭先生からのメッセージ――糖尿病網膜症に対する正しい理解とサポートを
糖尿病の発症には、遺伝的素因が大きく関与していることが明らかになっているにもかかわらず、悪い生活習慣だけが原因であるという誤った認識が社会に広まっています。それゆえに、差別や偏見を持たれて苦しんでいる糖尿病患者さんが多くいます。特に失明につながるような状況になってくると、ご家族の負担が大きいために患者さんを咎めたくなるかもしれません。しかし、責めるのではなくサポートをしていただき、患者さんが家族や社会に貢献できるように医師とともに努めていただければ幸いです。
糖尿病網膜症ならびに糖尿病黄斑浮腫は視力低下につながる病気ですので、脱落することなく治療を続けることが大切です。複数の治療法がありますので、主治医と相談のうえで納得して治療を受けていただきたいと思います。
糖尿病黄斑浮腫の相談ができる病院を調べる
エリアから探す
京都大学大学院医学研究科眼科学 講師
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が8件あります
糖尿病網膜症
今年の2月に糖尿病網膜症と診断を受け、 光凝固術を受けました。昨日から急に右目に黒い長い線が見えるようになりました。 目を閉じても入れても見えるのですが、 これは飛蚊症でしょうか。それとも網膜症が 進行している症状でしょうか。
糖尿病予備軍
今までHbA1cは5.4を超えたことはありません。空腹時の血糖値も100を越えたことはありませんでしたが、先月の健康診断で初めて108という数字が出ており、また、今月受けたOGTTでは、2時間後の数値が140超え(詳しい数値は後日分かります)となってしまいました。 以前より気になっていたかすみ目のため、3日前に眼科に行った際は糖尿病網膜症ではないと言われました。 恐らく糖尿病予備軍か、初期である可能性が高いと思っています。 今月に入った辺りから軽い手の震え、しびれがあります(足のしびれ等は自覚症状なし)。もう神経障害が出始めているのではと思い、動揺しているのですがその可能性はあるのでしょうか? 起床時はほとんど症状がなく、しばらくすると出始め、ほぼ1日続きます。空腹時や食後に症状が強くなるという感覚は特にありません。 他の病気の疑いや、精神的なものであることもあるのでしょうか?
視力低下と目の中の出血
目に出血があるが、白内障が強くて評価が難しいので、白内障をまず手術してからと言われた。 目の中の出血にはどんな理由が考えられるか。それぞれの予後は?
出血のみか網膜剥離まで起きているか分からない
父のことで相談です。 糖尿病性腎不全で人工透析を2年半ほど継続しています。 先日視界に煙のようなものが見え、飛蚊症を疑って眼科医に相談しました。 糖尿病網膜症による視界の悪化について調べるため、造影剤検査とエコーを行いました。これらの検査では出血だけなのか、網膜剥離まで起こしているのか分からず、手術してみないと分からないと言われました。執刀医の先生は手術の予定がいっぱいのため、手術予定日が1ヶ月先になるとのことです。 そこまでの期間をそのままで置いておいても悪化・失明する確率は低いのでしょうか。それとも すぐにでも手術をできるところを探した方が方が良いのでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「糖尿病網膜症」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。