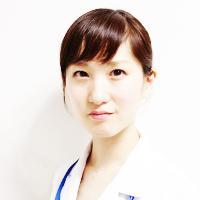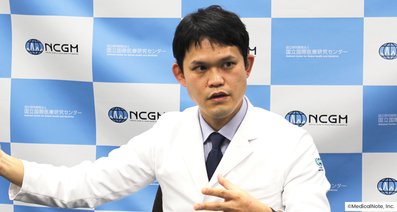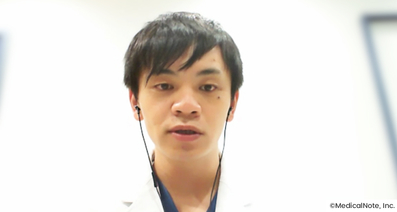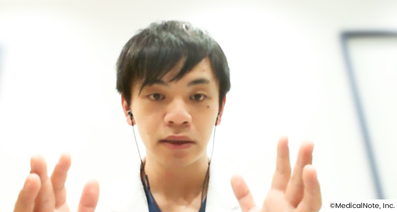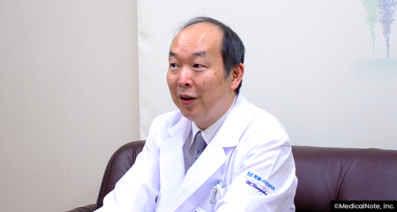慢性腎臓病の患者さんが腎臓を守るにあたって、減塩はとても大切です。慢性腎臓病における減塩の重要性について、2回にわたってご説明します。
前編では、腎臓の働きと構造、過剰な食塩摂取が腎臓・心臓・脳に及ぼすダメージについてご説明しました。後編では、減塩目標、減塩の方法などについて見ていきましょう。
食塩制限の重要性について―前編のまとめ
前編で、食塩制限がなぜ大切なのかについてご説明しました。その理由を以下にまとめます。
なお、この食塩制限は、腎不全(腎臓の機能が落ちてしまった状態)の程度に関わらず重要です。
1つは腎臓を守るためです。透析前の方であれば、透析の状態になるまでの時間を長くするために食塩制限はとても大切です。また、これは透析治療を始めた方でも同じです。ご自分の残った腎臓の機能を保つことが、その後のお体の状態を良くしていくのに非常に重要だと言われています。
そして、もう1つは心臓や脳、血管への負担を減らし命に関わる合併症を減らすためです。血液透析患者さんの場合は、減塩により透析と透析の間の体重増加を減らすことで心臓への負担を減らします。腹膜透析患者さんでも同様です。
参考記事:透析治療を受けている人はどのような食事をとればいい?
ちなみに、しっかり食塩管理を行えば、降圧剤(血圧を下げるためのお薬)も減らすことができます。降圧剤に頼らずに血圧管理ができるようになると、心臓への負担もさることながら血管へのダメージも少なく済みます。
逆に降圧剤だけで血圧を下げて、食塩や水分管理をしなければ、心臓への負担が強くなります。これは透析治療をされている方には、特に重要なポイントですので覚えておきましょう。
ここで1日の減塩目標について見てみましょう
1日に摂取してよい食塩の量は、日本では6gに設定されていますが、ヨーロッパの高血圧学会では3.8gから5gと設定されています。
では、なぜそのような数値になるのでしょうか?
実は、7g/日以上食塩を摂取すると血圧を下げる効果はなく、6g/日未満に制限したケースでは血圧を下げる効果があると確認されているのです。
また腎臓が弱っている方の場合は6g/日でも多く、3~6g/日にしたほうがよいとされていますが、まずは一般の高血圧患者さんと同様に6g/日以下を目指しましょう。
どのようにその6g/日や3.8g/日を実現すればよいのでしょうか?
まずは現在の食塩摂取量を調べてみましょう。
食塩はほぼ全て尿に排泄されますので、24時間の畜尿検査(24時間尿をため、その尿を調べる検査)を行えば、食塩摂取量を知ることができます。お家で尿をためて、その一部を外来の際に持参していただく方法です。
普段自分がどのくらい食塩を摂取しているのか、一度確認してみましょう。また、たびたびチェックすることでご自分の食事がうまくいっているかどうかの目安にもなります。ご希望の方は担当の先生に相談してみましょう。
食品の成分表示に関する注意点―ナトリウム量と食塩量は違う
最近では食品の成分表に食塩やナトリウムの量が記載されていることがありますが、1つ注意していただきたいことがあります。
それは、「ナトリウム量と食塩量は違うもので、ナトリウムに2.5をかけたものが食塩量となる」ということです。例えば、ナトリウム量2.0gと表記されているカップラーメンは、実際の食塩量としてはこれに2.5を掛けて5.0gとなるのです。
表記されている量が「ナトリウム表記」なのか「食塩表記」なのかを良く確認するようにしましょう。
食塩をおさえるためのポイント
実際に食塩をおさえていくためのいくつかのポイントをまとめてみました。試したことがないものがありましたら、ぜひ試してみてください。
- 食品の表示内容を確認しましょう。
- お醤油は「減塩醤油」に変更し、“かける”のではなく、“つける”ようにしましょう。また醤油や塩ではなく、ポン酢・お酢・レモン・香辛料などを味付けに使用してみるのもポイントです。
- 麺類は食塩が多いので、スープは残すなどの工夫をしましょう。
- レシピ本を活用しましょう。
- 1食だけ配達食を頼んだり、なるべく外食を控えたりするのも良いでしょう。
ただし、これらの食塩制限を実際の生活になじませていくのは簡単にはできることではないと思います。これまで味の濃い食事をされてきた方は特に難しく感じるかもしれませんが、実は塩分を感じる味覚は日々の食事によって変化することが分かっています。
『素材の味を感じるようになった』、『前食べていた食事を食べたら、とてもしょっぱく感じるようになった』これらは時間をかけて食塩制限ができるようになった患者さんから度々耳にする言葉です。
逆に、今の食事を変えていかなければ、味覚は変化せず塩分への感度が落ちたままになってしまいます。ご自身でなかなか食塩制限ができないときは、実際の食事内容を可能な範囲でメモして、担当の先生と工夫のしかたを一緒に考えましょう。
減塩がいかに大切かお分かりいただけましたでしょうか。減塩の取り組みは、誰でもすぐにできるようなものではありません。お一人で抱え込まず、医療スタッフと相談しながら一歩ずつ進んでいきましょう。
記事1:血液透析患者さんは海外旅行できる?―その準備、注意点について
記事2:腎臓移植とは(前編)—ドナーとレシピエントの条件、移植の手順について
記事3:血液透析とは?―そのしくみ、合併症、生活上の注意について
記事4:透析治療を受けている人はどのような食事をとればいい?
記事5:腹膜透析とは?―自宅でできる透析治療
記事6:腹膜透析の合併症にはどんなものがある?-塩分と感染に注意
記事7:腎臓移植とは(後編)ー移植後の生活、移植のメリット・デメリット、費用について
記事8:腎臓を守るためには減塩が大切!(前編)—慢性腎臓病における減塩の重要性について
記事9:腎臓を守るためには減塩が大切!(後編)—慢性腎臓病における減塩の重要性について
記事10:慢性腎臓病(CKD)とは—腎臓が悪くなると、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まる?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が10件あります
肺炎について今後の治療方針や転院について相談
現在89歳である父が肺炎と診断され、現在、近くの病院に3週間入院しています。現在の症状は 1. 熱が38度近くになったり、平熱になったりを繰り返している 2.本人は息苦しさを今も感じており、酸素吸入器をつけている。血中酸素飽和度は70代くらいの数値 3.医師からは、色々な薬を試しているが、なかなか適したのが見つからないとの事で、三日前にステロイド剤を使用したところ、副作用から本人は起き上がる事もできなくなり、ぐったりしてし始めた。トイレも自力で行けなくなり、体力も相当消耗している様子で 腎臓が悪くなり、病院からはステロイド剤を変えてみるとの事。 尚、何の種類の肺炎かについては、医師からの明確な説明は無く、少し前は誤嚥性肺炎の可能性もあると話しをしていたが、明確な肺炎の種類が分からないように見える。 4.食欲は今のところ有り、意識もしっかりしている。既存症は無い。 この病院がまだ色々な薬を試している一方で父の体力がどこまで持つのか心配しています。 今の病院の治療方針は正しいのか、他の病院に転院した方が良いのかアドバイスを頂けないでしょうか。 病院からは、今は安静にして動かさず、体力の温存に努めるべきとの説明を受けています。 よろしくお願いします。
腎臓結石の治療について
他病気の疑いがあり、CTを受けたのですが、その際に腎臓に結石があるのが偶然見つかった、と言われました。 先生からは現状では治療の必要がなく、尿管に落ちてくるかどうかもわからない、と言われました。 そこで疑問なのですが、 ①CTは内科で受けたのですが、泌尿器科の診断を受けた方がよいでしょうか? ②経過観察は、健康診断を受ける1年に1回エコーを受ける程度でいいのでしょうか?(そもそもエコーでは結石があるのがわかっていない) ③尿管に落ちると激痛を伴うようですが、回避する方策はないのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。
NASHの治療について
人間ドックでNASHの可能性が高いと診断され、精密検査で肝臓内科を受診したところやはりNASHの可能性が高いと診断されました。 病院ではNASHは運動して食事をコントロールして体重を減らせば治りますから深刻な考える必要はないですよと言われました。 しかし自分でNASHについて調べると2割の人が肝硬変になるというデータもあり、恐ろしい病気なのではと思ってます。 NASHは肝臓内科の先生が言う通り体重を減らすことによって完治することは可能な病気なのでしょうか? 肝硬変にならないために体重管理以外にしなければいけないことはないのでしょうか?
健康診断で血圧が
昨日健康診断を受けて、血圧をはかったら上が150で下が88でした。昨年は上が110で下が85ぐらいだったのにいきなり上がり出して怖いです。何か病気のサインでしょうか?自分では疲れやすいぐらいで前とあまり変わらないと思うのですが?病院に行った方が良いですか?ちなみに143cm体重79キロです。体重落とさないと駄目ですよね?塩辛いおつまみやお酒、スナック菓子大好きです。これはやめないとまずいですね。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「慢性腎臓病」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。