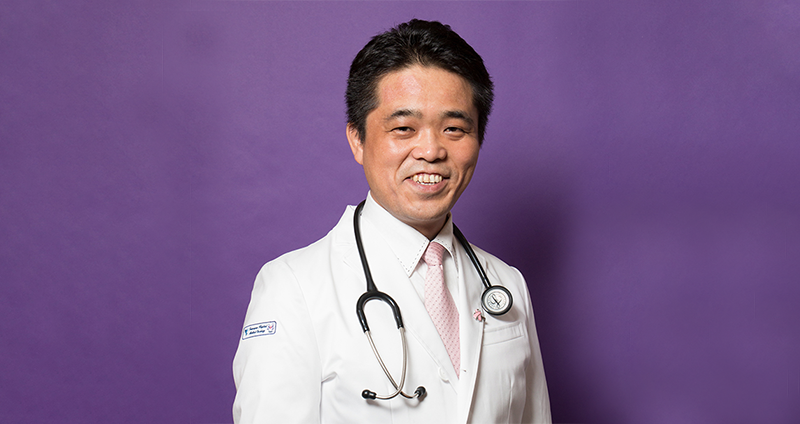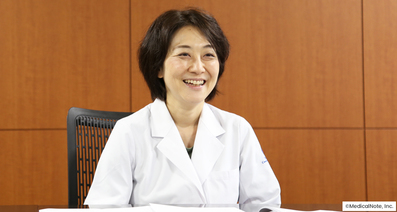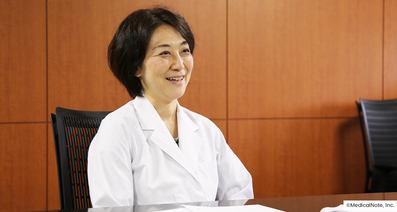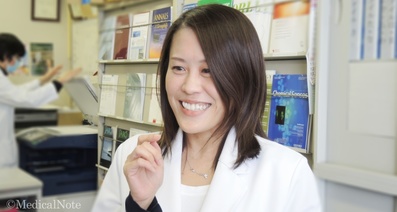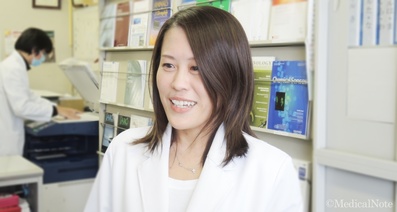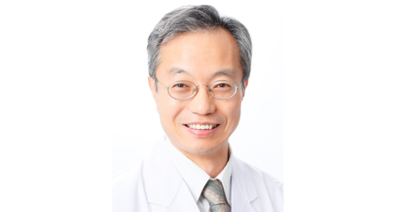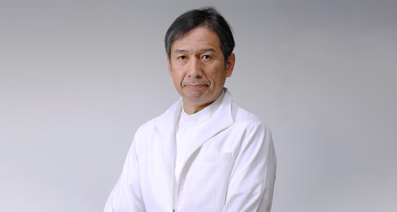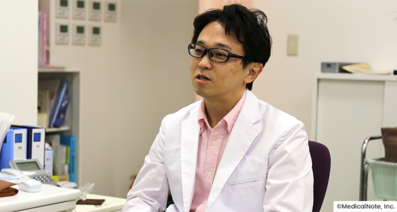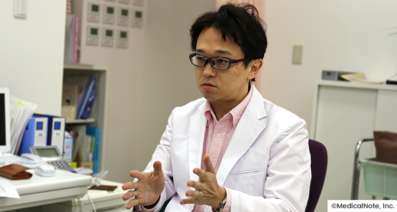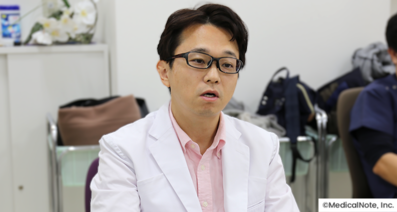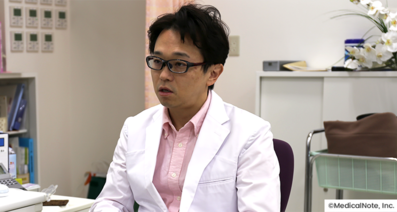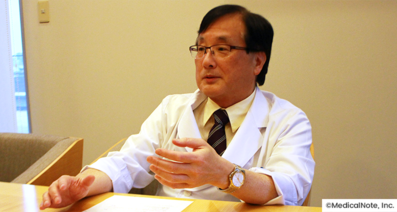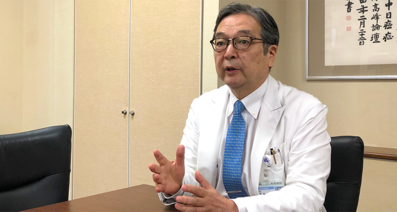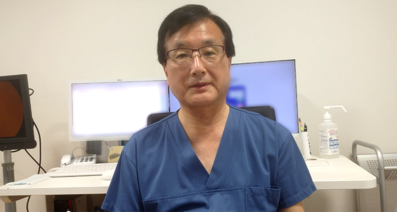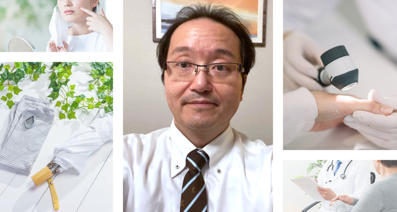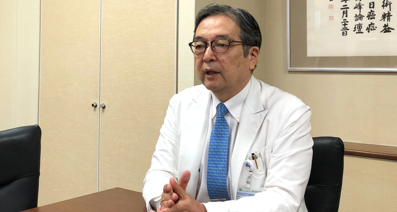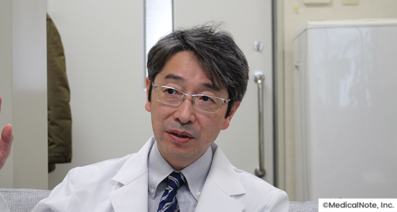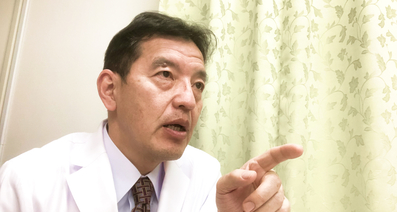味覚障害とは、甘味、辛味などの味覚に異常が現れることを指します。このような味覚障害はがん患者も生じることがあり、主に食べ物に対する味が感じられなくなる、逆に味が濃く感じる、何も食べていないのに口の中で塩味や苦味を感じるなどの症状があるといいます。そこで本記事では、がん患者が生じる味覚障害の原因や、その対処方法について詳しく解説します。
がん患者が味覚障害を生じる原因
がん患者における味覚障害は、主にがんの発症、またはがん治療に伴った味覚、口内環境、嗅覚の変化を原因としています。特に抗がん剤治療や放射線治療の後に起こることが一般的です。詳細は以下のとおりです。
味細胞の変化
舌には味蕾と呼ばれる味細胞が多く分布しており、これに食べ物が触れることで味を感知することができます。しかし、薬物療法や口周辺への放射線照射によって味細胞が傷ついたり、味細胞をつくるのに必要な亜鉛や鉄の吸収が阻害されたりすると味覚障害につながります。
口内環境の変化
舌や歯、歯茎が汚れたままだったり、口内の乾燥や唾液分泌の減少が起こったりすると、味覚に変化が起きることがあります。口周辺に放射線治療を行った場合は唾液腺が萎縮することがあり、これによって唾液の分泌が少なくなることに伴って味覚障害が起きることもあります。また、がん患者は免疫力が低下していることも多く、それが原因で口の中に感染症が発生すると口内環境が変化して味覚が変わることもあります。
嗅覚の変化
嗅覚の低下は味覚の低下と大きく関係しているため、薬物療法や放射線治療によって嗅細胞が傷つくことで味覚障害が起きることがあります。
そもそも人が味を感じるのは脳が味覚と嗅覚の両方の情報を統合して風味として認識しているため、嗅覚が低下することで味覚にも異常が生じてしまうのです。このことからも、鼻腔がんなどの場合はがんの発症や手術によって嗅覚が変化して味覚障害を生じることがあります。
がん患者の味覚障害に対する治療と対処法
がん患者が味覚障害を生じている場合、医療機関では薬の処方や口腔内ケアの指導を行います。
味覚障害の原因が体内の亜鉛や鉄の量に関係している場合は、それらを補う薬が処方されます。また、唾液分泌の低下が原因である場合は、唾液の分泌を促す薬や人口唾液が処方されます。さらに、歯磨きや保湿など口腔内のケアで味覚障害が改善することもあるため、口腔内ケアの指導が行われることもあります。薬物療法に伴う味覚障害は薬を使わなくなれば数か月程度で改善するといわれていますが、長く持続する場合もあり、患者によって異なります。
治療や対処法はがん患者によって異なるため、担当医とよく相談しながら治療を進めるようにしましょう。
がんによる味覚障害のセルフケア
セルフケアとしては、がん患者は以下の対策を試してみるとよいでしょう。ただし、治療や対処法は患者一人ひとりで異なるため、担当医とよく相談しながら実施するとよいでしょう。
歯磨きやうがい
舌や歯、歯茎が汚れていると味覚障害につながることがあるため、食後や就寝前など1日に2~4回程度口腔ケアを行います。歯ブラシは毛の柔らかいものを使い、舌や歯、歯茎を優しくブラッシングします。また、うがいも小まめに行うとよいとされています。入れ歯の方は食後に必ず口をゆすぎ、1日2回は柔らかいスポンジブラシなどで歯茎や舌をブラッシングしましょう。
口内の保湿
唾液の分泌が少なくなって口の中が乾燥している場合は口腔内の保湿も行いましょう。水で濡らしたガーゼで口元を拭いたり、市販の口腔保湿剤を使ったりするとよいでしょう。また、ガムをかむ、食事はよくかんで食べることなどを心がけると唾液の分泌を促すことができます。
味付けや調理法の工夫
味覚の変化を感じる場合は味付けや調理法を工夫することで味覚障害を補い、食事を楽しめる可能性もあります。たとえば塩味や醤油を苦いと感じる場合は甘味や酸味が中心の味付けに変えてみたり、ドレッシングや香辛料で味の調整がしやすい料理を選んだりするとよいでしょう。また、肉や魚がサビ臭く感じる場合は、アク抜き、臭み抜きをすることで改善されることがあります。
口の中が乾燥する場合は、シチューやスープなどの水分の多い料理や、ゼリー寄せなどのなめらかなものを選ぶとよいでしょう。また、金属製のスプーンなどで苦味を感じる方は素材をプラスチックや木製に変えてみることで和らげることができるといいます。
味覚に気になる変化を感じたら担当医や栄養士に相談を
がん患者に生じる味覚の変化は、一定期間を過ぎると改善することが一般的です。しかし、味覚障害によって食欲が低下したり、栄養不足に陥ったりすることもあるため、必要に応じて適切な治療やケアを行うことが非常に重要です。いずれにせよ、味覚に気になる異変を感じたら担当医や看護師、栄養士に相談するとよいでしょう。
がん研有明病院 乳腺内科 部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
がん研有明病院 乳腺内科 部長
高野 利実 先生日本臨床腫瘍学会 がん薬物療法専門医・指導医日本乳癌学会 乳腺専門医
東京共済病院、帝京大学医学部附属病院、虎の門病院の3ヶ所で腫瘍内科を立ち上げたのち、2020年にがん研有明病院に乳腺内科部長として赴任。2021年に院長補佐となり、患者・家族支援部長、および、臨床教育研修センター長を兼任。日本臨床腫瘍学会専門医部会長、西日本がん研究機構乳腺委員長も務め、日常臨床のみならず、患者支援、腫瘍内科医育成、臨床研究、情報発信にも力を入れている。
Human-Based Medicine(HBM: 人間の人間に拠る人間のための医療)がモットー。読売新聞社「ヨミドクター」でコラム連載中(2024年7月時点)。著書は「気持ちがラクになる がんとの向き合い方」(ビジネス社)など。高野 利実 先生の所属医療機関
関連記事
関連の医療相談が10件あります
痩せているのに下腹がとても膨らんでいる
1か月位前から腰が痛く、立っていても、座っていても、横にになっていても痛く、たまらなく病院に行ったら圧迫骨折している事が分かった。随分前から咳と鼻水が出て治らない。自分では肺癌だと思っていたので民間療法をやっていた。近藤誠の本をたくさん読んでいたので病院に行ってない 腰の痛みに耐えられず行った。自分では肺癌からの転移性脊髄圧迫とか悪性骨髄腫瘍だと思うので医者に話し、胸のレントゲン、MRI ,CT, 血液検査 尿検査をしたが癌の心配はない、と言われた。 腹水はない、と言われたが、下腹がとても膨らんでいる。総合診療科の医者は体は見てない。 現在、整形外科から腰の痛み止めの薬と骨粗鬆症の薬、カルシウムの薬を飲んでます。 今は体は怠く、腰は痛く、痩せていくし、下腹は膨らんでいるので、異常ない、と言われても喜べないのです。セカンドオピニオンで大学病院に行っも癌の心配はない、と同じなのです。 どうすれば良いのでしょうか?
ガンかどうか確認したい時はどうすればいいですか。
弟が2ヶ月前から斜め掛けの紐を仕事でかけていましたが左胸に擦れる度に痛みがあることから、2件程病院に行きましたが原因不明でホルモンによる乳腺肥大ではないかとの事です。成分検査はしていません。私は男性の乳がんなのではないかと疑っていますが何処であれば男性の乳がんの検査をしてもらえるでしょうか?
前立腺肥大症について治療(投薬・手術・慣れる等)を考えのアドバイスを下さい。
半年前に肺がん(9年前手術)の経過観察でPSA値が高いと指摘され、本日造影MRIを撮影しました。がんに関しては問題ありませんでしたが、画像で前立腺肥大(約5cm)を指摘されました。がん専門の大病院のため、詳細は泌尿器科へ紹介状を出すとの説明を受けました。 「前立腺肥大症」という言葉は聞いたことはありましたが、深く考えたことはなく、少し調べると「前立腺が卵ほどに大きくなり、尿の勢いが弱くなる・頻尿になる」とありました。今日の医師の話では、「尿の出が悪くなれば治療を検討」「頻尿はあまり関係ない」「投薬は一時的な対処で、根治には腹腔鏡手術」「大きくなるかは人それぞれ」とのことでした。 私は還暦を過ぎ、実際に尿の勢いが弱く、夜間も1〜2時間おきにトイレに行きます。ただし、加齢により排尿機能や体力が衰えるのは自然なことと考え、ある程度は受け入れてきました。老眼なら眼鏡を新調すれば済みますが、前立腺の腹腔鏡手術は身体的にも経済的にも負担が大きく、できれば避けたいと感じています。次回は来年2月に再診予定(画像検査なし)です。 AIに相談したところ、以下の回答が得られました。 ・軽症なら経過観察+薬物療法 ・生活に強い支障があれば手術 ・手術後は改善が見込めるが、加齢に伴い再肥大の可能性もある ・治療方針は「生活の質をどの程度改善したいか」で決めるのが現実的 私としては、命に直結しない限り、治療負担や予後の不確実さを考えると手術は避けたい気持ちです。今後の生活において、どのような考え方や対応が望ましいか、アドバイスをいただければ幸いです。
首筋にできたしこり
6月の中盤あたりに喉の違和感と顎あたりの リンパが腫れてるのかな?と違和感があり 耳鼻科咽頭に行きました。 その時は炎症を抑える薬などをもらいました! その後沖縄に行き途中で薬は飲み切ってしまい、腫れが治まったかな?と様って見たらまだあるなと思い沖縄でも見てもらい触りすぎてリンパが腫れてると薬をもらいました。 それからは触らないようにして東京に戻ってきた時に念のためいつもの耳鼻科咽頭で診てもらおうと行きました。 そしたら気になるような腫れではないので薬は大丈夫、様子見しましょかと言われました! そらから役1週間経つのですが、ピラティスをしてる時に首を思いっきり左に向けて首の筋?顎の付け根の下らへんにしこりがありました。 普段前向いてる分には何もなく気付きませんが横向いて触るとなんかいるなと。 押すとリンパの腫れてる時のような痛みがあります。 とても不安になり、もしかしたら何かしらのガンや重い病気とかなのでしょうか? いつ頃からあったのかと言われたらわからないのですが沖縄に行く前からもしあればもう少しで1ヶ月経つくらいなのですが。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。