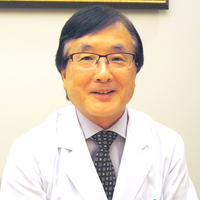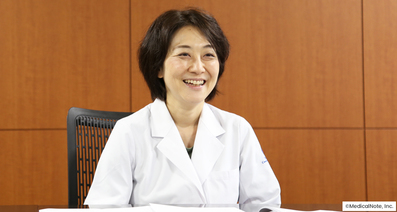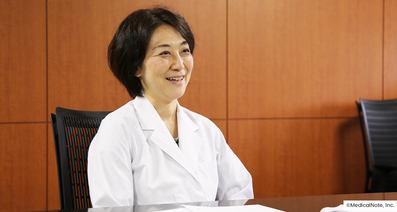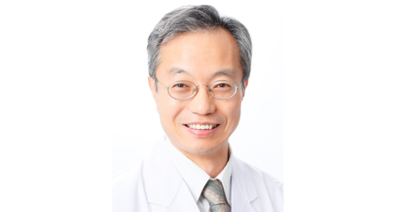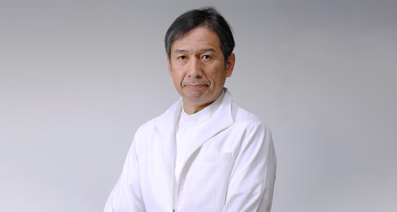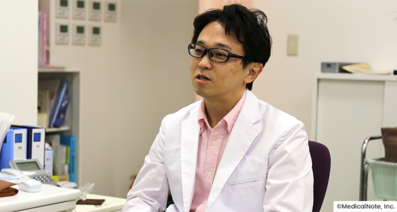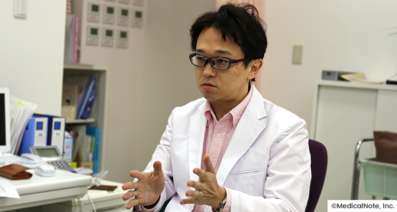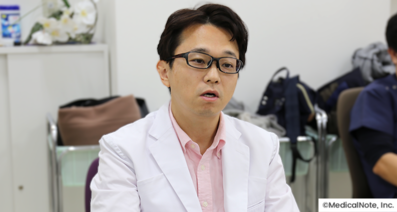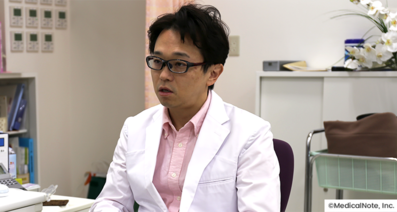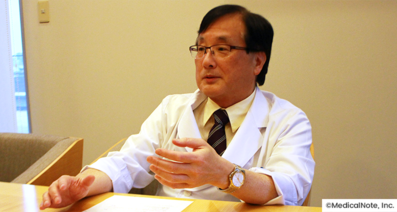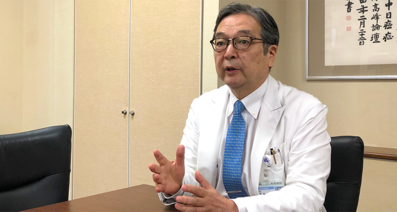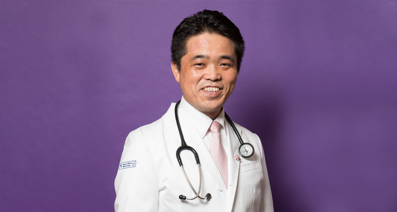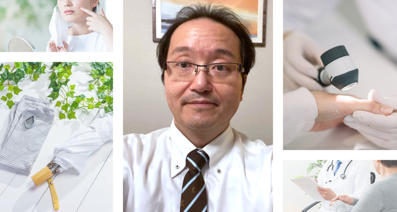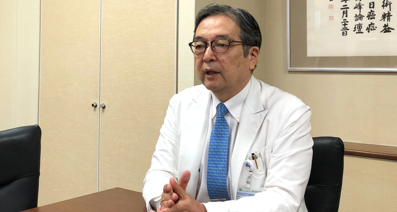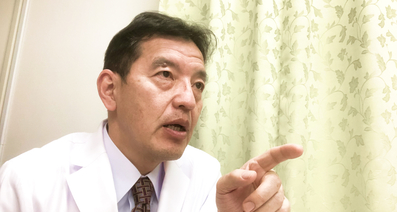がんは早期のうちは自覚症状がないことが一般的です。また、初期症状があってもほかの病気と勘違いしたりして知らぬ間に進行していることがあります。しかし、進行すればするほど治療が複雑になり生存率も減少していくため、がん治療においては早期発見が非常に重要となります。では、がんの早期発見のためには何ができるのでしょうか。
がんの早期発見の重要性
がん治療においては早期発見が非常に重要となります。
がんの進行具合(ステージ)はI期~IV期で表し、数字が大きくなるほどがんが進行しています。国立がん研究センターが集計した3年生存率(がんと診断された患者が3年後に生存している確率)では、全てのがんでI期の生存率に比べてIV期の生存率がほぼ半分になっており、がんが進行するにつれて生存率が減少していることが分かっています。
また、がんが進行するにつれ体への負担は大きくなり、治療内容も複雑になることに比例して医療費も高額になることがあります。これらのことからも、がんはできる限り早期発見・早期治療が行えるとよいと考えられます。
がんの早期発見のためにできること
通常、がんには自覚症状がないためがんを早期発見するにはがん検診を受けることが必要です。
なお、健診は自身の健康状態を把握するために行われ、がんなどの特定の病気を検査するためのものではないため検診とは異なります。ただし、健診の種類や受ける内容によっては、がんの危険因子を早期に発見でき予防や対策を講じることができるので、がんの早期発見につながると考えられるでしょう。
がん検診の種類と目的
検診とは、がんなどの特定の病気を早期発見するための検査のことを指します。
がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行って死亡率を減少させることです。がん検診には大きく分けて、国で推奨されている“対策型検診”と個人で受ける“任意型検診”の2種類があります。
国で推奨されているがん検診
国で推奨されているがん検診(対策型検診)は、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5種類で、対象集団全体の死亡リスクを下げることを目的に行われます。
これらのがん検診は公的な予防対策であるため、検診にかかる費用は無料か自己負担額が少額で済むようになっています。検診例には、各市区町村で行われている“住民検診”や職場で行われる“職域検診”などが挙げられます。
それぞれの対象者と回数、検診の内容は以下のとおりです。
- 胃がん検診:50歳以上で2年に1回。問診とX線検査や内視鏡検査の実施。
- 子宮頸がん検診:20歳以上で2年に1回。問診、視診、子宮頸部の細胞診と内診の実施。
- 肺がん検診:40歳以上で年に1回。問診や胸部X線検査を実施(喫煙者の場合は検査内容が異なる場合あり)。
- 乳がん検診:40歳以上で2年に1回。問診とマンモグラフィの実施。
- 大腸がん検診:40歳以上で年に1回。問診と便潜血検査の実施。
個人で受けるがん検診
個人で受けるがん検診(任意型検診)は、住まいや職業・年齢に関係なく受けることができます。これはがんによる個人の死亡リスクを下げる目的で行われます。このような検診はあくまで任意で受ける検診であるため、かかる費用は全て自己負担となります。
検診例としては、医療機関で提供される“人間ドック”などが挙げられます。
健康診断
健診は健康診断もしくは健康検査の略語で、現在の体の健康状態や病気の危険因子の有無を把握するための検査です。健診には法律で義務付けられた“法定健診”と任意で受ける“任意健診”の2種類があります。
職場で行われる健康診断
職場で行われる健康診断(法定健診)は、労働安全衛生法により事業者は労働者に対して健康診断を実施しなければいけないと定められています。これは労働者の健康状態を把握し、脳や心臓疾患の発症を防いで生活習慣病などを予防する目的があります。検査内容は胸部X線検査や尿検査、肝機能検査など計11項目です。ただし、定期健康診断の場合は一部の項目を省略することができるほか、自身でオプションとして検査を追加することも可能な場合があります。
人間ドック
人間ドックは個人が任意で受けることができる健康診断で、通常の健康診断よりも検査項目が多いことが特徴です。一般の健康診断が約10項目であるのに対し、人間ドックは40~100項目とより細やかな検査を行うことができ、自身で検査の内容を選択することができます。また、個人で受けるがん検診として豊富な内容が準備されています。医療費が自己負担となり、項目を増やすごとに金額が大きくなることがデメリットですが、健康保険などの補助を利用すると減額できることがあります。
がん死亡数から見る対策型検診の対象
対策型検診の目的は、早期発見によりがんの死亡率を下げることです。そのため、対策型検診は、発症者数が多いがん、またそれによる死亡者数が多いがんに対して行われます。“胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん”は、定期的な検診によって、死亡率を低下させることができると科学的に証明されていることから、対策型検診に採用されています。
実際、2018年に日本におけるがんの死亡者数のうち、以下のがんの死亡が多かったことがデータに示されています*。
<男性>
1位:肺がん、2位:胃がん、3位:大腸がん
<女性>
1位:大腸がん、2位:肺がん、3位:膵臓がん
また、がんにかかる年齢は、男女ともに50~80歳代に多い傾向にあります。決して他人事とは考えずに、対策型検診の対象年齢に達したら、積極的に検診を受けるようにしましょう。
*2018年人口動態統計(厚生労働省大臣官房統計情報部編)より
定期的ながん検診で早期発見を
これまで解説したとおり、がんは進行するにつれて生存率が低下するとされています。国で推奨されている検診は子宮頸がんを除き40歳以上からですが、年齢にかかわらず気になる点がある場合は定期的な検診を検討し、がんの早期発見を心がけるとよいでしょう。また、がんの発症リスクは種類によって異なるため、近年はリスクの程度を見る検査も行われています。特定のがんのリスクが分かれば、より効率よくがんの早期発見・治療につながると考えられています。気になる方は近くの医療機関に問い合わせてみるとよいでしょう。
一般財団法人 淳風会 理事、淳風会健康管理センター センター長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
痩せているのに下腹がとても膨らんでいる
1か月位前から腰が痛く、立っていても、座っていても、横にになっていても痛く、たまらなく病院に行ったら圧迫骨折している事が分かった。随分前から咳と鼻水が出て治らない。自分では肺癌だと思っていたので民間療法をやっていた。近藤誠の本をたくさん読んでいたので病院に行ってない 腰の痛みに耐えられず行った。自分では肺癌からの転移性脊髄圧迫とか悪性骨髄腫瘍だと思うので医者に話し、胸のレントゲン、MRI ,CT, 血液検査 尿検査をしたが癌の心配はない、と言われた。 腹水はない、と言われたが、下腹がとても膨らんでいる。総合診療科の医者は体は見てない。 現在、整形外科から腰の痛み止めの薬と骨粗鬆症の薬、カルシウムの薬を飲んでます。 今は体は怠く、腰は痛く、痩せていくし、下腹は膨らんでいるので、異常ない、と言われても喜べないのです。セカンドオピニオンで大学病院に行っも癌の心配はない、と同じなのです。 どうすれば良いのでしょうか?
ガンかどうか確認したい時はどうすればいいですか。
弟が2ヶ月前から斜め掛けの紐を仕事でかけていましたが左胸に擦れる度に痛みがあることから、2件程病院に行きましたが原因不明でホルモンによる乳腺肥大ではないかとの事です。成分検査はしていません。私は男性の乳がんなのではないかと疑っていますが何処であれば男性の乳がんの検査をしてもらえるでしょうか?
前立腺肥大症について治療(投薬・手術・慣れる等)を考えのアドバイスを下さい。
半年前に肺がん(9年前手術)の経過観察でPSA値が高いと指摘され、本日造影MRIを撮影しました。がんに関しては問題ありませんでしたが、画像で前立腺肥大(約5cm)を指摘されました。がん専門の大病院のため、詳細は泌尿器科へ紹介状を出すとの説明を受けました。 「前立腺肥大症」という言葉は聞いたことはありましたが、深く考えたことはなく、少し調べると「前立腺が卵ほどに大きくなり、尿の勢いが弱くなる・頻尿になる」とありました。今日の医師の話では、「尿の出が悪くなれば治療を検討」「頻尿はあまり関係ない」「投薬は一時的な対処で、根治には腹腔鏡手術」「大きくなるかは人それぞれ」とのことでした。 私は還暦を過ぎ、実際に尿の勢いが弱く、夜間も1〜2時間おきにトイレに行きます。ただし、加齢により排尿機能や体力が衰えるのは自然なことと考え、ある程度は受け入れてきました。老眼なら眼鏡を新調すれば済みますが、前立腺の腹腔鏡手術は身体的にも経済的にも負担が大きく、できれば避けたいと感じています。次回は来年2月に再診予定(画像検査なし)です。 AIに相談したところ、以下の回答が得られました。 ・軽症なら経過観察+薬物療法 ・生活に強い支障があれば手術 ・手術後は改善が見込めるが、加齢に伴い再肥大の可能性もある ・治療方針は「生活の質をどの程度改善したいか」で決めるのが現実的 私としては、命に直結しない限り、治療負担や予後の不確実さを考えると手術は避けたい気持ちです。今後の生活において、どのような考え方や対応が望ましいか、アドバイスをいただければ幸いです。
首筋にできたしこり
6月の中盤あたりに喉の違和感と顎あたりの リンパが腫れてるのかな?と違和感があり 耳鼻科咽頭に行きました。 その時は炎症を抑える薬などをもらいました! その後沖縄に行き途中で薬は飲み切ってしまい、腫れが治まったかな?と様って見たらまだあるなと思い沖縄でも見てもらい触りすぎてリンパが腫れてると薬をもらいました。 それからは触らないようにして東京に戻ってきた時に念のためいつもの耳鼻科咽頭で診てもらおうと行きました。 そしたら気になるような腫れではないので薬は大丈夫、様子見しましょかと言われました! そらから役1週間経つのですが、ピラティスをしてる時に首を思いっきり左に向けて首の筋?顎の付け根の下らへんにしこりがありました。 普段前向いてる分には何もなく気付きませんが横向いて触るとなんかいるなと。 押すとリンパの腫れてる時のような痛みがあります。 とても不安になり、もしかしたら何かしらのガンや重い病気とかなのでしょうか? いつ頃からあったのかと言われたらわからないのですが沖縄に行く前からもしあればもう少しで1ヶ月経つくらいなのですが。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。