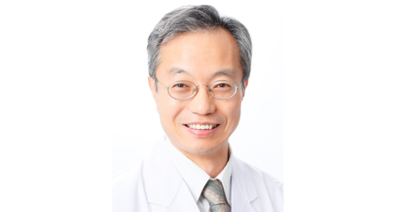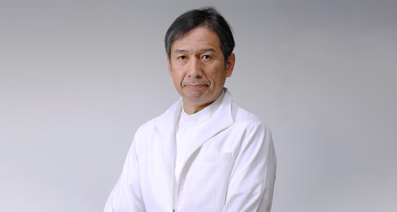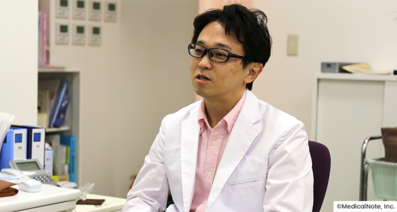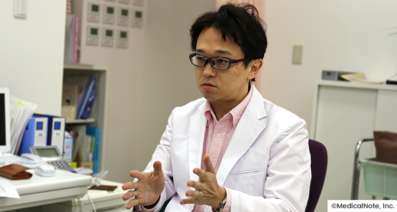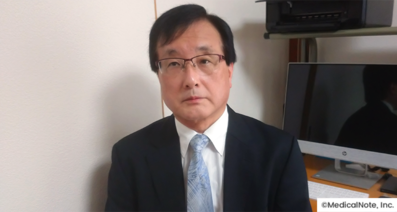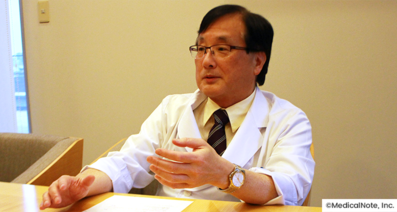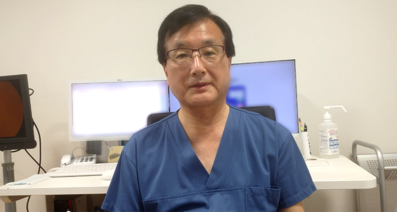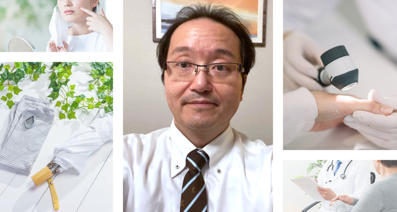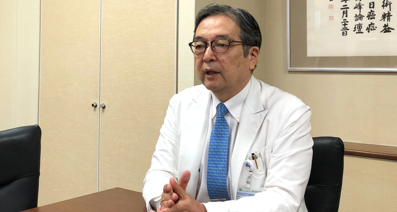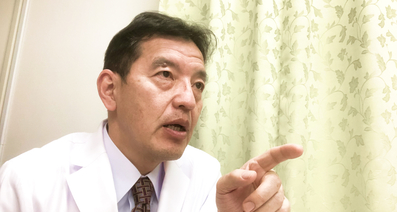がんとは、細胞の遺伝子に傷がつくことによって生じる悪性の腫瘍です。日本では、2人に1人が一生のうち1度はがんにかかり、3人に1人はがんによって命を落とすといわれています。がんはおよそ20年という長い期間をかけて発生することが多く、高齢の方ほどかかりやすい病気です。高齢化が進む日本ではがんの罹患数が増加傾向にありますが、早期発見技術や医療技術の進歩によって治療成績が向上し、がんを治せる確率も向上してきています。
今回は2021年7月時点のがんの治療や検査に関する最新トピックスや今後の展望について、国立がん研究センター 理事長 中釜 斉先生にお話を伺いました。
そもそもがんとはどんな病気?
Q1.がんという病気について、あらためて教えてください。
がんとは遺伝子に傷がつくことによって発生する悪性の腫瘍です。日本では1981年に死因の第1位となり、その後も患者数は毎年のように増加しています。現在は毎年およそ100万人の方が新しくがんと診断され、およそ38万人の方ががんのために命を落としています。
がんには治療効果などを測る1つの目安として、5年生存率という基準があります。これは多くのがんで診断後5年生存することができれば、その後の再発のリスクなどが低くなるためです。2009~2011年にがんと診断された方の5年生存率は、がん全体で見ると64.1%で、このデータから6割強の方はがんにかかってもその後治療によって治っていることが分かります。
また、がんの患者数は高齢化などによって徐々に増加している一方、5年生存率はこの15年程度の間に10%ほど向上しており、少しずつですががんで命を落とす確率が減ってきています。これは早期発見技術や医療技術が進歩しているためです。がんは進行する前に早期の段階で治療したほうが治りやすく再発しにくいため、早期発見が非常に重要です。また、がんの治療の基本は「手術治療」「放射線治療」「薬物治療」の3つを単独、あるいは組み合わせることによる集学的治療であり、それぞれの治療方法が発展したことによって今まで根治の難しかったがんも治るようになってきました。
がん治療の進歩
Q2.がん治療において、近年どのような変化があるのでしょうか?
先にお話ししたとおり、がん治療は手術治療・放射線治療・薬物治療というそれぞれの治療方法において技術の進歩が見られます。
中でも、近年注目されているのはゲノム医療を活用して患者さん1人ひとりに合わせた薬物治療です。このような考え方を “プレシジョン・メディシン(精密医療)”といい、がん治療においては非常に重視されています。
薬物治療の進歩とこれまでの課題
1990年代は薬物治療といえば細胞障害性の化学療法剤のイメージが主流でしたが、2000年以降に分子標的薬が登場するなど、現代のがんに対する薬物治療にはさまざまな選択肢があります。
化学療法剤治療とは活発に活動する細胞にダメージを与え、がん細胞の増殖を抑える治療です。がん細胞にダメージを与えるとともに正常な細胞にも障害が及んでしまうため、さまざまな副作用が見受けられることがデメリットとなっていましたが、近年は薬の種類が増えたことや投与方法の改善などによって副作用が軽減されつつあります。
また、分子標的薬とはがん細胞の増殖に関与する分子のはたらきを抑える治療薬で、化学療法剤と比較すると副作用が少ないといわれています。このほかにも、免疫チェックポイント阻害薬などの治療薬が使用できるがんもあります。
従来のがんの薬物治療では、化学療法剤や分子標的薬など使用できる治療薬(抗がん剤)を一律で患者さんに投与することが一般的でした。しかし、多くの患者さんでは薬物治療をしても十分な効果が得られないというのが現状でした。
同じがんでも薬物治療の効果が出ない理由
同じがんでも薬物治療に効果があったり、なかったりするのはなぜなのかというと、これは同じがんでも患者さんの体質やがんのタイプなどに違いがあるためです。
肺腺がんの分子標的薬を例に挙げて説明すると、肺腺がんの主な分子標的薬には、EGFR阻害剤やALK阻害薬などがあります。日本では2002年にEGFR阻害剤のゲフィチニブが承認され、使用されるようになりました。肺腺がんの患者さんの20~30%に効果を示すといわれていましたが、当時はどのような患者さんに効果が生じるのか明らかになっていませんでした。
しかし、研究を進めていくと、ゲフィチニブが標的にしているEGFRというタンパク質を作る遺伝子に異常がある人に投与すると、効果が現れやすいということが分かってきました。そのため、以降はEGFRに遺伝子異常がある人のみにゲフィチニブを投与するようにしたところ、投与した患者さんの75%に効果が現れるようになり、治療成績が3倍ほど改善されました。
一方、ALKと呼ばれるタンパク質を作る遺伝子に異常が生じる肺腺がんも全体の2%程度あります。このような患者さんにはEGFR阻害剤を投与しても効果はありませんが、ALK阻害薬を投与すると効果を示すようになりました。
このように、患者さんやがんの特徴に合わせた薬物を選択することで、より少ない副作用でこれまで以上に高い治療効果が現れるようになってきました。
プレシジョン・メディシンという考え方
がんは一見同じ病気のように見えても、患者さんによって体質やがんの原因となる遺伝子異常に違いがあり、効く薬、効かない薬があります。そこで近年がん治療では“プレシジョン・メディシン”という、患者さん一人ひとりに合わせた適切な治療を行うという考え方が重要だとされています。患者さんをそれぞれのタイプに層別化し、それに合わせた治療を行うことで治療効果を高めようとするのがプレシジョン・メディシンの目的です。がん治療におけるプレシジョン・メディシンの第一歩として今注目されているのが、がんのゲノム医療です。
Q3.ゲノム医療は実際に医療現場においてどのように運用されているのでしょうか?
近年、がんの薬物治療では患者さんに一律で同じ治療薬を投与するのではなく、がんの遺伝子異常を調べる遺伝子検査を行い、その結果から治療薬を選択する“がんゲノム医療”が行われています。2019年6月にはがんの遺伝子パネル検査が保険収載されるようになり、保険医療で遺伝子検査を実施し、治療に役立てることができるようになりました。
がんの遺伝子パネル検査とは
がんの遺伝子パネル検査とは、がん細胞で遺伝子異常が起きている可能性が高い数十~数百個の遺伝子について異常の有無を確認する検査です。がんのある部位を採取して検査を行います。この検査によって特定の遺伝子に異常が生じていることが分かった場合、それに合わせた治療薬を投与します。
ただし、遺伝子の異常が明らかになったとしても、それに合った治療薬がまだ開発されていない可能性もあります。実際、遺伝子異常に合った治療薬に巡り会える確率は国立がん研究センターの場合で約15%、全体的には約10%といわれ、がんの遺伝子パネル検査を受けても10人に1人しか自分に合った治療薬に出会えないのが現状です。しかし、多くの患者さんががんの遺伝子パネル検査を受けることにより、さまざまな遺伝子異常のデータが蓄積され、新しい治療薬の開発に役立っています。そのため、がんの遺伝子パネル検査の結果によっては、現在行われている臨床試験や治験に参加できる可能性もあります。
Q4.がんゲノム医療の可能性をより向上させるために、どのような取り組みが行われているのでしょうか?
先にお話したように、今のところ遺伝子異常が見つかってもそれに合った治療薬に出会える確率は10~15%といわれています。そこで、より多くの患者さんに自分に合った治療薬を使用してもらえるよう、新しい薬の開発に向けたさまざまな取り組みが行われています。日本でも保険収載でがんの遺伝子パネル検査を受けることができ、そのデータを国で集約できるという強みを生かして治療薬の開発が行われています。
アジアを主導とした薬の開発
近年はアジア諸国が協力し、アジアが主導となってがんの治療薬を開発する動きが盛り上がりつつあります。これまでは薬の開発というと大きな製薬会社のある欧米が中心となることが一般的でした。もちろんアジアの企業や医療機関が加わって研究を行うこともありますが、主導権は欧米にあることが多いのが現状です。
しかし、アジアは中国や東南アジア諸国、インドなど人口の多い国も含むため、世界人口を見ると大きな割合を占めているといえます。また、がんの場合には人種によって遺伝的な背景も異なり、地域によって罹患数の多いがんの種類も異なります。たとえば、日本では胃がんや肝臓がんの患者数が多いという特徴がありますが、アメリカでは胃がんにかかる人はそう多くはありません。
また肝臓がんもアジアでは肝炎ウイルスに起因するものが多いといわれていますが、欧米ではアルコールを飲みすぎることによるものが多く、地域によって肝臓がんの成因やその背景となる肝疾患に相違があるために、薬の効果や副作用にも差が生じやすいといわれています。このため、アジア人に多いがんの治療薬はアジア主導で開発しようという動きが強まっています。
マスターキープロジェクトの取り組み
国立がん研究センターでは、肉腫や小児がんなど希少がんの患者さんのための治療薬を開発する「マスターキープロジェクト」を行っています。希少がんは患者数が少ないことからデータを集めにくく、薬剤としての市場性も小さいため、企業がこのような希少ながん種の治療薬開発に積極的に着手することはあまりありません。そこでマスターキープロジェクトでは、がんの遺伝子パネル検査のデータを活用し、医師主導で希少がんの治療薬の開発に取り組んでいます。
マスターキープロジェクトでは、現在10数本の医師主導治験や企業治験が行われています。また、国立がん研究センターから京都大学、北海道大学、東北大学、九州大学などに声をかけ、まずは日本国内でプロジェクトを拡大させました。今後はアジアの諸外国にも協力を仰ぎ、アジア主導の一大プロジェクトとして広げていきたいと考えています。このように協力体制を広げていくことによって、希少がんであっても多くの患者さんのデータを集められるようになり、薬の研究に役立てられると考えられます。
Q5.今後のゲノム医療の展望についてはどのようにお考えでしょうか?
がんのゲノム医療はこの先、さらに発展していくことが期待されます。
臓器別の治療から遺伝子異常別の治療へ
がんの遺伝子パネル検査などのゲノム医療がさらに進歩すると、がんを臓器別に診て治療薬を選択するだけでなく、遺伝子異常別に診て治療薬を選択するということもできるようになると考えます。実際、がんの遺伝子パネル検査を行うと、別の臓器のがんで同じ遺伝子異常が発見されることもあります。
国立がん研究センターでは新薬臨床開発に特化した“先端医療科”という診療科があり、臓器別の概念では括れない遺伝子異常別の治療開発が可能である臓器横断的な診療部門として機能しています。そのため、さまざまな臓器のがんに発生する同一の遺伝子異常について臨床試験を行うことも可能です。
リキッド・バイオプシーの導入
現在は、がんの遺伝子検査を血液のDNAを使用して行えるようにするための研究が精力的に進められています。このように、患者さんの血液などの体液を用いて行う検査を“リキッド・バイオプシー”といいます。
今行われているがんの遺伝子パネル検査は、患者さんからがんの病変(組織)を採取して行います。これは病変を採取する際に患者さんの体に負担がかかり、繰り返し行うことは困難です。一方、もし血液などの体液からがんの遺伝子検査が行えるようになれば、血液検査同様に血液を採取するだけで検査ができるため、患者さんへの負担も小さく、繰り返し検査を行うことができます。
血液によるがんの遺伝子検査が主流になれば、検査時の患者さんへの負担が軽減されることはもちろん、検査を繰り返し行えるようになるため、手術治療後の患者さんや抗がん剤治療中・治療後の患者さんにこの検査を行い、検査結果によってその後の追加治療が必要かどうかを判断できるようになるかもしれません。
全ゲノム検査の導入
また、今後はがん細胞の全ての遺伝子を検査する全ゲノム検査を行うようになる日も来るかもしれません。現在行われているがんの遺伝子パネル検査では、数十~数百個程度の遺伝子中の異常が分かるに過ぎず、これは遺伝子全体のごく一部に過ぎません。そのため、検査に含まれない遺伝子の中にこれまで知らなかったがん特有の異常を持つ遺伝子が存在する可能性もあります。
現在はがん細胞に対して全ゲノム検査を行おうとすると、数十万円という費用がかかるといわれています。しかし、今後技術が発展すれば費用も下がり、診療としての検査が行われやすくなるのではないでしょうか。
がん予防のためにできる取り組み
Q6.医療の進歩によってがんの予後はよくなってきていることは分かりましたが、そもそもがんを予防する、または発症した場合に早期発見・受診につなげるために、私たち個人ではどのような取り組みが必要でしょうか?
医療の技術が向上することによって、がんで命を落とす確率は徐々に減少している一方で、実際にがんにかかる人の数は増加傾向にあります。これは社会全体の高齢化の影響が大きいのですが、罹患数を減らすためには国民の行動変容が大切です。
特にがんの場合には大規模な疫学研究の成果から、日本人では男性の約50%、女性の約30%が明確な原因によって発症しているといわれています。具体的には、喫煙習慣や感染症への罹患、アルコール摂取です。感染症というのは、胃がんの発症リスクを高めるピロリ菌への感染や肝臓がんの原因となる肝炎ウイルス、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染などです。このように原因が明らかなものに対しては、生活習慣の改善やワクチン接種などによる感染症の治療、感染後の治療を行うことによって予防がかなうと考えられます。
がん検診の受診も大切
がんは早期発見・治療をすることによって根治しやすくなります。早期発見のためには、がん検診の受診が欠かせません。
現在日本では、胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんの検診を受けることが推奨されています。しかし、欧米のがん検診の受診率が約70~80%といわれる一方、日本のがん検診の受診率は50%に満たず、受診率の低さが問題となっています。
がん検診を受けない理由を探ってみると、「病気が見つかることが怖い」「自分は大丈夫だろうと思っている」というような方もいます。しかし、がんは今や日本人の2人に1人がかかる病気です。早期発見できれば根治する可能性も高まりますので、がん検診を受診できる年齢になったら必ず受けることを心がけましょう。
Q7.国民全体ががん予防に取り組む必要があるなか、医療機関ではどのような取り組みをしているのでしょうか?
医療機関においても、いかに国民に正しい情報を伝え、実践につなげていただくかという部分に力を入れているところです。具体的には、普及と実装科学研究(D&I:Dissemination and Implementation Science)と題し、医学的根拠のある情報をいかに国民に伝え、がん予防に必要なアクション(行動)を取り入れてもらうかということを研究しています。この分野は医療従事者の力だけでは実現が難しい部分もあると思います。さまざまな分野の研究者や企業と連携して国をあげて取り組んでいます。
がんの治療後も安心して暮らせる社会の実現
Q8.最後に、がん領域の現時点での課題や、今後必要な取り組みには何があるとお考えでしょうか。
治療できるがんが増えてきた今、今後は治療後の患者さんの生活をサポートできる支援がさらに必要と考えます。患者さんには、治療のために仕事を辞めることになった方や子育てをしながら治療を受けている方など、さまざまな社会的背景を抱えている方がいます。多様な背景を持つ個々のがん患者さんに対して、必要に応じた支援ができる仕組みづくりを模索していきたいと考えています。一昔前は医療機関の役割は「がんを見つけて治す」というところにとどまっていました。しかし、これからは治療するだけでなく、治療後も安心して暮らせる社会の実現を目指していくべきだと考えます。これには医師などの医療従事者の力だけでなく、さまざまな専門家の力が必要です。国立がん研究センターは国の機関として日本中が協力し取り組んでいけるような環境づくりに力を入れたいと考えています。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
痩せているのに下腹がとても膨らんでいる
1か月位前から腰が痛く、立っていても、座っていても、横にになっていても痛く、たまらなく病院に行ったら圧迫骨折している事が分かった。随分前から咳と鼻水が出て治らない。自分では肺癌だと思っていたので民間療法をやっていた。近藤誠の本をたくさん読んでいたので病院に行ってない 腰の痛みに耐えられず行った。自分では肺癌からの転移性脊髄圧迫とか悪性骨髄腫瘍だと思うので医者に話し、胸のレントゲン、MRI ,CT, 血液検査 尿検査をしたが癌の心配はない、と言われた。 腹水はない、と言われたが、下腹がとても膨らんでいる。総合診療科の医者は体は見てない。 現在、整形外科から腰の痛み止めの薬と骨粗鬆症の薬、カルシウムの薬を飲んでます。 今は体は怠く、腰は痛く、痩せていくし、下腹は膨らんでいるので、異常ない、と言われても喜べないのです。セカンドオピニオンで大学病院に行っも癌の心配はない、と同じなのです。 どうすれば良いのでしょうか?
ガンかどうか確認したい時はどうすればいいですか。
弟が2ヶ月前から斜め掛けの紐を仕事でかけていましたが左胸に擦れる度に痛みがあることから、2件程病院に行きましたが原因不明でホルモンによる乳腺肥大ではないかとの事です。成分検査はしていません。私は男性の乳がんなのではないかと疑っていますが何処であれば男性の乳がんの検査をしてもらえるでしょうか?
前立腺肥大症について治療(投薬・手術・慣れる等)を考えのアドバイスを下さい。
半年前に肺がん(9年前手術)の経過観察でPSA値が高いと指摘され、本日造影MRIを撮影しました。がんに関しては問題ありませんでしたが、画像で前立腺肥大(約5cm)を指摘されました。がん専門の大病院のため、詳細は泌尿器科へ紹介状を出すとの説明を受けました。 「前立腺肥大症」という言葉は聞いたことはありましたが、深く考えたことはなく、少し調べると「前立腺が卵ほどに大きくなり、尿の勢いが弱くなる・頻尿になる」とありました。今日の医師の話では、「尿の出が悪くなれば治療を検討」「頻尿はあまり関係ない」「投薬は一時的な対処で、根治には腹腔鏡手術」「大きくなるかは人それぞれ」とのことでした。 私は還暦を過ぎ、実際に尿の勢いが弱く、夜間も1〜2時間おきにトイレに行きます。ただし、加齢により排尿機能や体力が衰えるのは自然なことと考え、ある程度は受け入れてきました。老眼なら眼鏡を新調すれば済みますが、前立腺の腹腔鏡手術は身体的にも経済的にも負担が大きく、できれば避けたいと感じています。次回は来年2月に再診予定(画像検査なし)です。 AIに相談したところ、以下の回答が得られました。 ・軽症なら経過観察+薬物療法 ・生活に強い支障があれば手術 ・手術後は改善が見込めるが、加齢に伴い再肥大の可能性もある ・治療方針は「生活の質をどの程度改善したいか」で決めるのが現実的 私としては、命に直結しない限り、治療負担や予後の不確実さを考えると手術は避けたい気持ちです。今後の生活において、どのような考え方や対応が望ましいか、アドバイスをいただければ幸いです。
首筋にできたしこり
6月の中盤あたりに喉の違和感と顎あたりの リンパが腫れてるのかな?と違和感があり 耳鼻科咽頭に行きました。 その時は炎症を抑える薬などをもらいました! その後沖縄に行き途中で薬は飲み切ってしまい、腫れが治まったかな?と様って見たらまだあるなと思い沖縄でも見てもらい触りすぎてリンパが腫れてると薬をもらいました。 それからは触らないようにして東京に戻ってきた時に念のためいつもの耳鼻科咽頭で診てもらおうと行きました。 そしたら気になるような腫れではないので薬は大丈夫、様子見しましょかと言われました! そらから役1週間経つのですが、ピラティスをしてる時に首を思いっきり左に向けて首の筋?顎の付け根の下らへんにしこりがありました。 普段前向いてる分には何もなく気付きませんが横向いて触るとなんかいるなと。 押すとリンパの腫れてる時のような痛みがあります。 とても不安になり、もしかしたら何かしらのガンや重い病気とかなのでしょうか? いつ頃からあったのかと言われたらわからないのですが沖縄に行く前からもしあればもう少しで1ヶ月経つくらいなのですが。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします