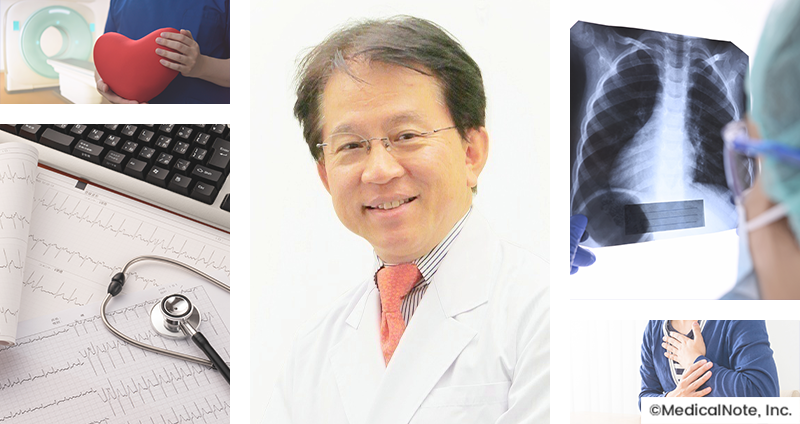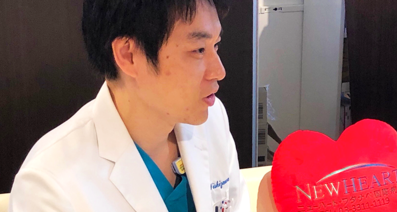心臓は4つの部屋に分かれた構造をしており、右心房、右心室、左心房、左心室という決まった順番で血液が流れています。各部屋の出口には心臓弁があり、タイミングよく開閉することで血液の流れをスムーズにしています。しかし、この弁が正常に機能しなくなる状態を“弁膜症”と呼びます。
僧帽弁は、左心房と左心室の間にある弁です。弁膜症の1つである僧帽弁閉鎖不全症は、僧帽弁逆流症とも呼ばれ、僧帽弁がうまく閉じなくなることで心臓が収縮するたびに左心室から左心房へと血液が逆流し、心臓に余計な圧がかかったり、肺に血液がたまったりする病気です。
本記事では、僧帽弁閉鎖不全症の症状や合併症、治療について詳しく解説します。
僧帽弁閉鎖不全症の症状
僧帽弁閉鎖不全症の症状
自覚症状は僧帽弁閉鎖不全症の原因や重症度、発症の仕方によってさまざまですが、肺や心臓に関連した症状が多く現れます。異常な血液の流れによって肺に負担がかかると、強い息切れや呼吸困難が生じます。また、心臓に負担がかかり続けると心機能が低下し、息切れや疲れやすさ、不整脈、動悸などが現れます。肺や心臓への負担によって、横になると息苦しくて眠れない“起坐呼吸”やむくみが生じることもあります。
一方で、僧帽弁閉鎖不全症では自覚症状が乏しい場合も少なくありません。特に、血液の逆流が軽度である場合や症状がゆっくりと慢性的に進行する場合などは、自覚症状が現れないまま重症化することがあります。
合併症による症状
もっとも重要な合併症は心不全です。血液の逆流によって心臓に余計な負担がかかり続けると、やがて心臓が負担に耐え切れなくなり徐々に心機能が低下し心不全となります。心不全の悪化によって、息切れやむくみ、疲れやすさなどの症状が顕著になることがあります。
また、心臓への負担は心房細動を引き起こすこともあり、不整脈や動悸などの症状が現れるとともに、心房細動が血流の異常をより悪化させることがあるので注意が必要です。血液の逆流によって僧帽弁が傷付くと、感染性心内膜炎にかかるリスクが高まります。
さらに、僧帽弁閉鎖不全によって血液が逆流すると、肺に血液がたまり負担がかかります。このため、肺高血圧症や肺水腫(肺の中に水がたまる状態)を合併し、息苦しさ、呼吸困難を生じることがあります。
僧帽弁閉鎖不全症の治療
僧帽弁閉鎖不全症は、症状が必ずしも病気の進行具合と一致しないのが特徴です。症状の有無によらず、弁の状態や、心臓や肺への負担のかかり方などを総合的に判断して適切な時期に治療を開始することが大切です。
治療方法
僧帽弁閉鎖不全症の治療は、僧帽弁の外科手術が基本となります。手術は大きく分けて、“僧帽弁形成術”と“僧帽弁置換術”の2つがあります。元の弁を一部切ったり縫い合わせたりして形を整え、逆流が起こらないようにするのが僧帽弁形成術です。
僧帽弁置換術では、元の弁を取り除いて、生体弁や機械弁に置き換えます。これら開胸手術は現在、ロボット手術や小切開手術など低侵襲手術が主流になりつつあります。体に小さな穴をあけるだけで開胸手術と同じ手術が可能となるので回復も早く、傷あとも残らないとされています。
治療のタイミング
治療のタイミングは重症度によって異なります。
僧帽弁閉鎖不全症の重症度は、逆流の強さや、肺や心臓への負担の大きさによって分類されます。軽症や中等症の場合は経過観察が基本となるため、定期的に受診し悪化を見逃さないことが重要です。
有症状や逆流が重症の場合は手術適応となることが多いですが、原因や症状によって治療の時期を見極める必要があります。特に、心臓の状態や手術による効果がどの程度見込めるかが重要なポイントとなるため、どのような治療をいつ行うべきかについては、専門の医療機関で検査を受け、慎重に判断することが必要です。
僧帽弁閉鎖不全症に気付くためのポイント
僧帽弁閉鎖不全症の自覚症状として多いものは、息切れや疲れやすさ、息苦しさなどです。これらの症状は単に日常的な疲れや加齢によるものと見過ごしてしまいがちですが、違和感があれば医師に相談することが大切です。
僧帽弁閉鎖不全症は無症状のまま進行して重症化することも多く、心臓や肺などの病気を合併する可能性もあります。健康診断などで異常を指摘された場合は、専門の病因で詳しい検査、正しい診断を受けて適切な治療を開始することが大切です。
ニューハート・ワタナベ国際病院 総長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
ニューハート・ワタナベ国際病院 総長
渡邊 剛 先生日本外科学会 指導医・外科専門医日本胸部外科学会 指導医日本循環器学会 循環器専門医
ドイツ・ハノーファー医科大学心臓血管外科留学、金沢大学第一外科教授、東京医科大学心臓外科兼任教授、国際医療福祉大学教授などを経て、2014年にニューハート・ワタナベ国際病院総長。
心臓疾患におけるロボット手術のスペシャリスト。これまでにロボット心臓手術は850例以上、合計5000以上の手術経験を持ち、その成功率は99.5%以上と圧倒的な成功率を誇る。
渡邊剛先生のHP(http://doctorblackjack.net)
ニューハート・ワタナベ国際病院のHP(https://newheart.jp)渡邊 剛 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事

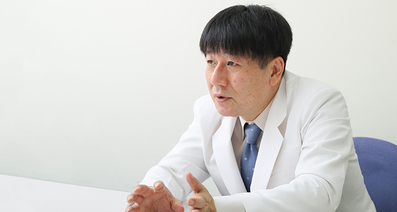
僧帽弁閉鎖不全症の治療――手術と小さい創で行う“MICS”について
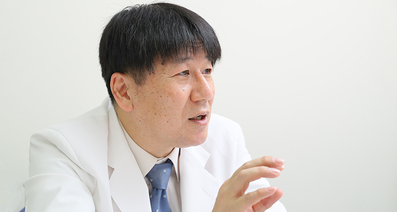
僧帽弁閉鎖不全症とは?――その原因と症状

僧帽弁閉鎖不全症の手術適応
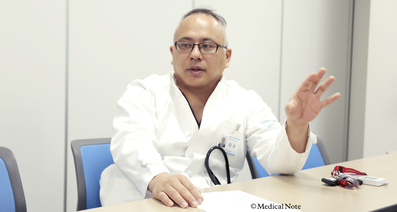
僧帽弁閉鎖不全症の治療法「僧帽弁手術」とは?

小切開低侵襲心臓手術(MICS)とは?
もっと見る
関連の医療相談が9件あります
拡張型心筋症について
生後2ヶ月間近の娘が僧帽弁逆流と診断され現在薬で治療中です。 重症度は中度で、体重が問題なく増えているので今は薬で経過観察となっております。 そこで問題なのが、心臓の動きが通常と比べて動きが悪いと言われています。 拡張型心筋症の可能性も0ではないので頭の片隅に入れておいて欲しいと言われました。 本人がしんどそうではないので心臓が元気になる薬は使わずに利尿剤と血管拡張剤を処方されています。 拡張型心筋症だった場合、どういう症状がでてくるのでしょうか。 いろいろ調べましたが、とても怖い病気だと言うことは分かりました。 ミルクも健常者の子以上に飲みます。 よく笑うし、すごく大きな声で泣きます。 とても心臓が悪い子には見えません。 もし拡張型心筋症だった場合、急に症状がでるものでしょうか? それとも徐々に悪くなるのでしょうか。
脈が飛んでます
今日のお昼頃から 脈がおかしいです。 脈拍は1分間に90回でした。 ドク、ドク、ドクと脈は正常なはずなのですが、 脈が何回も何回も飛びます、、 吐き気などはありませんが 不快感があります、横になって休んでも脈が大きいせいか落ち着きません。。 深呼吸してもあまり意味がないです ホルター心電図をしたときに限って 脈が正常で、異常なしと言われます。 昨晩お酒を飲んでしまいました。350mlを4.5本ほど。 お酒は関係してますかね?、、、 怖くてなかなか安心して休めません、、 何か家でできる改善方法ないでしょうか?
昨日の昼頃から続く胸の違和感
昨日のお昼頃から胸の真ん中あたりが軽く締め付けられる?ような感じや痛み、息の苦しさがあります。 明日病院に行くべきか、もう少し様子見しても良いかどうしたら良いのでしょうか
手術に関して
双子の兄が僧帽弁閉鎖不全症で、先月胸痛発作、呼吸困難を起こし入院しています。 4月に引っ越してきて病院が変わってしまい、兄自身まだ不安はあるみたいです。 それで、主治医にできるだけ早めの手術を進められました。前の病院でも言われてはいたんですが、兄が嫌だ、と言っていた為手術しませんでした。しかし、今回に関しては心不全になっていて、上の兄も双子の兄を手術するように説得してるんですが、怖いからやだとの一点張り。 私は医療の知識はないので何も言えないですが、兄には生きて欲しいです。 早くしないと心臓が手術に耐えられなくなってしまうとか言ってたんですが、その場合ってどうなるんですか? 私が兄にできることって何かあるのでしょうか? 長文すみません。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
-
-
大動脈瘤
-
急性大動脈解離
-
心臓弁膜症
-
狭心症
- 冠動脈バイパス術
-
心筋梗塞
- 人工心膜非使用冠動脈バイパス術
- MICS-CABG(左小開胸 心拍動下多枝冠動脈バイパス術)
-
僧帽弁閉鎖不全症
- 胸骨正中切開
- MICS-MVP(小開胸アプローチによる僧帽弁形成術)
-
大動脈弁狭窄症
- 弁置換術
- MICS-AVR(小開胸アプローチによる大動脈弁置換術)
-
大動脈弁閉鎖不全症
-
-
-
僧帽弁閉鎖不全症
- 僧帽弁形成術
- 僧帽弁置換術
- 渡邊式超精密鍵穴(キーホール)手術(手術支援ロボット「ダビンチ」を用いた完全内視鏡下外科手術)
- MICS
-
狭心症
-
大動脈弁狭窄症
- 自己心膜大動脈弁形成術
- 大動脈弁置換術
-
大動脈弁閉鎖不全症
- 自己心膜大動脈弁形成術
- 大動脈弁置換術
-
大動脈瘤
- ステントグラフト内挿術
- 人工血管置換術(軽度低体温手術)
-
-
-
心臓弁膜症
- カテーテル治療
-
僧帽弁閉鎖不全症
-
大動脈弁狭窄症
-
-
-
心臓弁膜症
- 低侵襲心臓手術(MICS)
- 三尖弁手術
- 大動脈弁手術
- 僧帽弁手術
-
僧帽弁閉鎖不全症
- Mitra Clip
- 低侵襲心臓手術 (MICS)
-
大動脈弁狭窄症
- TAVI
- 低侵襲心臓手術 (MICS)
-
狭心症
- 冠動脈バイパス術
-
心筋梗塞
- 冠動脈バイパス術
高い技術力とチームで難手術に挑む
-
-
-
僧帽弁閉鎖不全症
- ロボット支援下僧帽弁形成術
-
虚血性心疾患
- 低侵襲冠動脈バイパス術
- ハイブリッド冠動脈治療
-
狭心症
- 低侵襲冠動脈バイパス術
- ハイブリッド冠動脈治療
-
心筋梗塞
- 低侵襲冠動脈バイパス術
- ハイブリッド冠動脈治療
-
大動脈弁狭窄症
- 低侵襲大動脈弁置換(MICS大動脈弁置換)
-
心臓弁膜症
- 僧帽弁形成術
- 僧帽弁置換術
-
-
-
僧帽弁閉鎖不全症
- 僧帽弁形成術
-
大動脈弁閉鎖不全症
- 大動脈弁形成術
- 自己弁温存大動脈弁置換術
-
大動脈弁狭窄症
- 大動脈弁置換術
-
狭心症
- 低侵襲冠動脈バイパス手術
-
心筋梗塞
- 低侵襲冠動脈バイパス手術
治療を終えた患者さんのQOL(生活の質)向上を追求することが使命
-
-
-
心臓弁膜症
- 弁膜症手術全般
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
- 自己弁温存基部置換術(Davidデービット手術)
-
低侵襲心臓手術
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
大動脈弁狭窄症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
大動脈弁閉鎖不全症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
- 自己弁温存基部置換術(Davidデービッド手術)
-
大動脈弁輪拡張症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
- 自己弁温存基部置換術(Davidデービッド手術)
-
大動脈二尖弁
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
- 自己弁温存基部置換術(Davidデービッド手術)
-
僧帽弁閉鎖不全症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
僧帽弁逸脱症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
僧帽弁狭窄症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
三尖弁閉鎖不全症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
大動脈瘤
- 胸部および腹部ステントグラフト内挿術
- 開腹および開胸による人工血管置換術
-
腹部大動脈瘤
- 腹部ステントグラフト内挿術
- 腹部大動脈人工血管置換術
-
胸部大動脈瘤
- 胸部ステントグラフト内挿術
- 腹部大動脈人工血管置換術
-
急性大動脈解離
-
大動脈解離
-
マルファン症候群
- 自己弁温存基部置換術(Davidデービッド手術)
-
心房中隔欠損症
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
心室中隔欠損症
-
心臓腫瘍
- 3D内視鏡下MICS(低侵襲心臓手術)
-
大動脈炎症候群
-
感染性心内膜炎
-
心疾患
-
労作性狭心症
-
収縮性心膜炎
-
心タンポナーデ
-
心内膜炎
-
-
-
心臓弁膜症
-
大動脈弁狭窄症
- TAVI(経カテーテル的大動脈弁留置術)
-
狭心症
- PCI(冠動脈カテーテル手術)
- 薬物治療
-
心筋梗塞
- PCI(冠動脈カテーテル手術)
- 薬物治療
-
虚血性心疾患
-
末梢動脈疾患
-
肥大型心筋症
-
拡張型心筋症
-
心内膜炎
-
無症候性心筋虚血
-
労作性狭心症
-
心疾患
-
急性心不全
-
心原性ショック
-
慢性心不全
-
うっ血性心不全
-
心不全
-
心肥大
-
僧帽弁閉鎖不全症
-
僧帽弁逸脱症
-
僧帽弁狭窄症
-
大動脈弁閉鎖不全症
-
大動脈二尖弁
-
三尖弁閉鎖不全症
-
感染性心内膜炎
-
高血圧症
-
深部静脈血栓症
-
肺塞栓症
-
-
-
狭心症
- 冠動脈バイパス手術
- MICS-冠動脈バイパス手術
- 左室形成術
-
心筋梗塞
- 冠動脈バイパス手術
- MICS-冠動脈バイパス手術
- 左室形成術
-
心臓弁膜症
- 大動脈弁置換術
- 僧帽弁形成術
- MICS-僧帽弁形成術
- MICS-大動脈弁置換術
-
大動脈弁狭窄症
- 大動脈瘤弁置換術
- MICS-大動脈瘤弁置換術
-
虚血性心疾患
-
大動脈瘤
-
胸部大動脈瘤
-
腹部大動脈瘤
-
急性大動脈解離
-
マルファン症候群
-
無症候性心筋虚血
-
労作性狭心症
-
僧帽弁閉鎖不全症
-
僧帽弁逸脱症
-
僧帽弁狭窄症
-
大動脈弁閉鎖不全症
-
大動脈弁輪拡張症
-
大動脈二尖弁
-
三尖弁閉鎖不全症
-
感染性心内膜炎
-
低侵襲心臓手術
-
大動脈解離
-
大動脈炎症候群
-
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。
僧帽弁閉鎖不全症