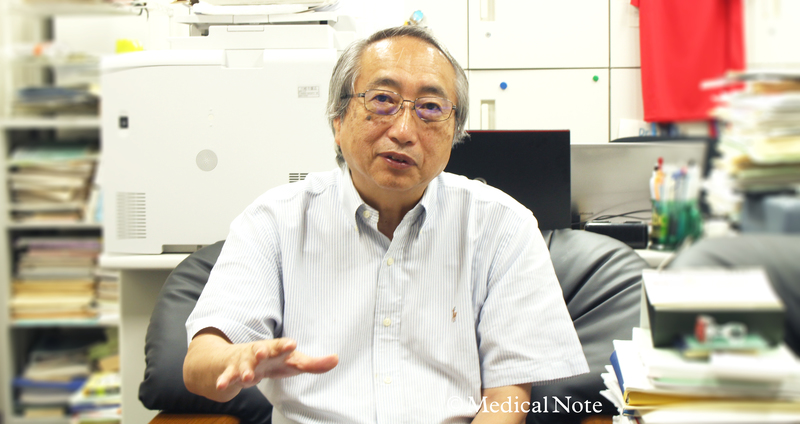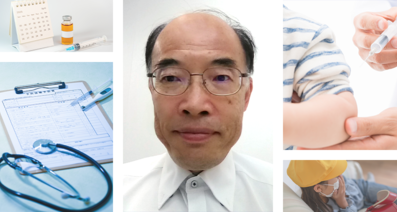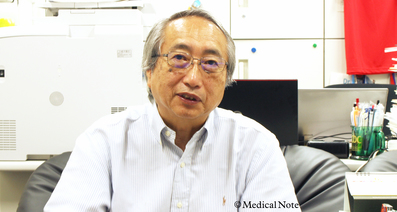
子どもに高熱が出たとき、解熱用の座薬(肛門から注入する薬)や飲み薬を使用したことはありますか。インフルエンザの高熱に対して解熱剤を使用する際、薬の種類によっては急性脳症などのきっかけとなったり、発症した脳症を悪化させたりする因子となることがあるため、厳重な注意が必要です。
本記事では、川崎市健康安全研究所所長である岡部信彦先生に、インフルエンザのときに使用できる・できない解熱薬の種類や、使用上の注意点などについてお話を伺いました。
小児のインフルエンザに使用できる・使用できない解熱用の座薬や飲み薬は?
インフルエンザによる高熱を下げるために、解熱用の飲み薬や座薬が頓用(一時的な使用)として処方されることがあります。
解熱薬には、さまざまな種類がありますが、小児のインフルエンザのときに使用できる薬は限られています。
では、どのような薬が使用できて、どのような薬が使用できないのか解説していきます。
使用できる解熱薬
インフルエンザのときに使用できる解熱薬は、アセトアミノフェンという薬剤です。アセトアミノフェンには、熱を下げたり、全身の痛みを和らげたりする効果があります。ただし、その効果は強くありません。
使用できない解熱薬
インフルエンザのとき、基本的に使用してはいけない解熱薬は、アスピリン・メフェナム酸・ジクロフェナクナトリウムです。アセトアミノフェンより高い解熱効果があります。
アスピリン−子どもの場合、ライ症候群を引き起こす危険性がある
インフルエンザにかかっている小児がアスピリンを服用すると、急性脳症のひとつであるライ症候群を引き起こす危険性があります。そのため、インフルエンザにかかっている子どもにアスピリンを使用することはしません。
メフェナム酸・ジクロフェナクナトリウム等−インフルエンザ脳症を悪化させる危険性がある
メフェナム酸やジクロフェナクナトリウムは、インフルエンザ脳症を悪化させる危険性があります。これらの薬剤は、インフルエンザ脳症を引き起こすわけではありませんが、インフルエンザ脳症にかかっている場合に、その進行を後押ししてしまいます。そのため、メフェナム酸やジクロフェナクナトリウムも、小児のインフルエンザの解熱剤として使用することは基本的にはありません。
インフルエンザのときの解熱用の座薬や飲み薬の使い方と注意点
使用するタイミング
解熱薬を使用するかどうか、またそのタイミングは、主治医や患者さん(またはご家族)の考えによって異なりますが、一般的に小児の場合には、38.5〜39度が使用の目安になると考えます(大人の場合は38〜38.5度)。
しかし、解熱はあくまでも症状の緩和であり根本治療ではないため、高熱による辛い症状がないにもかかわらずむやみに解熱薬を使用することはよいことではありません。高熱によって食べたり飲んだりすることができない、眠ることができない、などの症状がみられる場合に、解熱薬を適宜、上手に使用するとよいと思います。
使用上の注意点
解熱薬を使用する場合、自己判断で使用方法を変えることはしないでください。たとえば、早く熱を下げたいからといって1回の使用量を増やしたり、解熱効果がないからといって使用間隔を短くしたりしないようにしましょう。使用間隔は、最低5〜6時間はあけるようにしてください。1日の回数も多くて3〜4回までにとどめていただきたいと思います。
処方時に、医師や薬剤師から受けた指示をよく守って使用することが大切です。
インフルエンザに対する解熱薬の効果は?座薬と飲み薬で効果は違う?
飲み薬と比べると、座薬は直腸から薬剤が吸収されるため効果が早く現れます。
ただし、先ほどもお話ししたように、熱を下げることはインフルエンザの根本治療ではありません。熱は下がっても病気が治っているわけではないので、再び熱が上昇することは十分あり得ます。あくまで一時的効果と考えてください。
解熱薬を使用して熱が下がることで、少し食べたり飲んだり、しっかり眠ることができるようになることが、回復につながります。
解熱薬に潜む危険を十分に理解して、正しい使用を心がけてほしい
通常の風邪よりも高い熱が出るインフルエンザでは、熱による辛い症状を緩和させるために解熱薬は有用です。ただし、先ほどもお話ししたように、薬の種類によってはインフルエンザのとき使用することで、ライ症候群のきっかけとなったり、インフルエンザ脳症を悪化させたりする危険性があることを知っておく必要があります。
そのため、解熱薬は必ずその人に処方されたものを、処方されたときに使うようにしてください。
「大人の分を半分にして使う」「インフルエンザのときによく効いた座薬が余っているから友達にわけてあげる」などの行為は避けるようにしましょう。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。