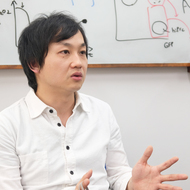概要
再生医療とは、病気やけがなどで機能を失った組織や臓器を修復、再生する治療のことです。患者自身、または他者の幹細胞(全ての細胞のもとになる細胞)などを用いて特定の組織や細胞を人為的に作り出し、それを移植することで失われた組織や臓器を再生することが可能という考え方に基づきます。
再生医療で用いられる幹細胞には、“体性幹細胞”“ES細胞”“iPS細胞”の3つの種類があります。このうち、体性幹細胞は私たちの体内に広く存在し、血液や脂肪、骨、軟骨、筋肉、血管などの細胞のもとになっています。ある種の細胞は、特定の組織や細胞しか作り出すことができないのが特徴です。現在もっとも再生医療への応用が進んでいるのは、この体性幹細胞を用いたもので、保険適用となって多くの患者に行われている治療もあります。
一方、ES細胞やiPS細胞はさまざまな組織や細胞を作り出す能力を持ち、“多能性幹細胞”とも呼ばれる細胞です。ES細胞は受精卵を培養することによって生み出すことができ、iPS細胞は体の細胞から人工的に生み出す幹細胞ですが、2012年にはその功績が称えられ、開発者である山中 伸弥氏がノーベル賞を受賞しています。また、2014年には世界で初めてiPS細胞から作られた網膜の移植手術が実験的に行われ、今後も広い分野の治療への応用が期待されています。
再生医療は、従来の治療法では十分な効果が望めなかった病気や、けがを治癒に導く治療法として大きく期待される一方、その安全性はまだ確立されていません。このため、再生医療を行うときだけでなく、再生医療に使用する細胞や組織の培養を行う際にも厚生労働省への申請が必要となります。
 再生医療に用いられる間葉系幹細胞とは?新潟大学 大学院医歯学総合研究科 消化...寺井 崇二 先生
再生医療に用いられる間葉系幹細胞とは?新潟大学 大学院医歯学総合研究科 消化...寺井 崇二 先生再生医療という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。再生医療が登場したことで、これまで治療の施しようがなかった病気を治すことがで...続きを読む
 “持続可能”な再生医療の仕組み――神戸アイセンターがつくる未来株式会社ビジョンケアグループ 代表取締役...高橋 政代 先生
“持続可能”な再生医療の仕組み――神戸アイセンターがつくる未来株式会社ビジョンケアグループ 代表取締役...高橋 政代 先生日本は再生医療領域で世界を先導する立場にある一方、治験や特許を理由とした最先端治療の高額化という大きな問題を抱えています。よい治療を早く、そし...続きを読む
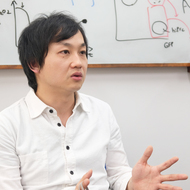 小さな臓器“オルガノイド”研究が拓く未来――新たなアイデアを生み出す思考とは大阪大学 大学院医学系研究科 器官システ...武部 貴則 先生
小さな臓器“オルガノイド”研究が拓く未来――新たなアイデアを生み出す思考とは大阪大学 大学院医学系研究科 器官システ...武部 貴則 先生2013年、当時26歳だった武部 貴則(たけべ たかのり)先生(東京医科歯科大学 統合研究機構 先端医歯工学創成研究部門 教授)は、世界で初め...続きを読む
 iPS細胞を用いた神経の再生医療——その進歩とこれからの展望慶應義塾大学医学部生理学教室 教授岡野 栄之 先生
iPS細胞を用いた神経の再生医療——その進歩とこれからの展望慶應義塾大学医学部生理学教室 教授岡野 栄之 先生視覚や聴覚などの感覚を通じてあらゆる情報を集約し、司令塔の役割を果たす中枢神経。これまで、中枢神経である脳と脊髄(せきずい)は、一度損傷すると...続きを読む
 心不全に対する再生医療の進歩——iPS細胞を用いた治療の実用化に向けて大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 ...澤 芳樹 先生
心不全に対する再生医療の進歩——iPS細胞を用いた治療の実用化に向けて大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 ...澤 芳樹 先生現在、世界中で増加が報告されている心不全。高齢化が進展する日本においても、心不全の発症数は増加の一途を辿っています。心不全は、重症化すると補助...続きを読む
 持続可能な再生医療の実現に向けて——日本再生医療学会の取り組み神奈川県立保健福祉大学 イノベーション政...八代 嘉美 先生
持続可能な再生医療の実現に向けて——日本再生医療学会の取り組み神奈川県立保健福祉大学 イノベーション政...八代 嘉美 先生病気やけがで失われてしまった臓器や機能を回復(再生)するための医療を再生医療と言います。これまでに、世界中で再生医療の研究が行われてきました。...続きを読む
目的
再生医療は病気やけがなどによって失われた組織や臓器を再生することを目的として生まれた新たな医療です。
現在、再生医療を適応できると考えられている人体の部位は多岐にわたり、脳神経、目、耳、歯、歯肉、心臓、肝臓、食道、大腸、腎臓、尿道、卵巣、子宮、血管、皮膚、関節、骨などが挙げられます。これらの部位に生じる病気の中には、望み得る最高レベルの医療を行っても十分に改善しないものも多いため、手の施しようがなく命を落とすケースや重大な後遺症を残すケースも多々あるのが現状です。
再生医療は、患者自身や他者の細胞から治療に必要な組織や細胞を作り出して移植するため、他者の臓器移植などに頼ることなく治療を行うことが可能となります。また、現在の医学では治療法が確立していない病気の中にも、再生医療によって治癒する可能性が示唆されているものもあり、これまでの医療では治すことができなかった病気やけがのある部位を“新たに作り出した健康的な組織や臓器に入れ替える”ために生み出された治療法なのです。
現在、再生医療の対象となっている病気やけがは多岐にわたりますが、体性幹細胞を用いた一部の再生医療を除いて多くは研究段階にあります。このため、再生医療が行われるのは極めて限定的なケースといってよいでしょう。
万が一、臨床研究や治験の適応対象となっている病気やけがになり、本人の体力や合併症の有無、研究参加への意欲などの条件がそろえば、研究を行っている医療機関で再生医療を受けることができる場合があります。
検査・診断
再生治療を行う前にはそれぞれの病気の診断や重症度の評価を厳密に行うため、血液検査や画像検査などが必要に応じて行われることが一般的です。
検査の内容は病気の種類によって異なり、医療機関によって取り入れられている検査に差があるため、担当医の指示に従って検査を受けましょう。
治療
現在、健康保険を適用して使うことができる再生医療等製品は16種類あります(2022年6月時点)。なお、多くの場合は体性幹細胞を用いますが、近年は遺伝子発現を用いる製品も現れています。
健康保険が適用される再生医療の例
- 重症熱傷、先天性巨大色素性母斑、表皮水疱症
- 膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く)の臨床症状の緩和
- 造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病
- 虚血性心疾患による重症心不全
- 脊髄損傷に伴う神経症候及び機能障害の改善
- 再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫
- 再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫及び濾胞性リンパ腫
- 慢性動脈閉塞症における潰瘍の改善
- 脊髄性筋萎縮症(遺伝子検査により脊髄性筋萎縮症の発症が予測されるものも含む)
- 角膜上皮幹細胞疲弊症
- 角膜上皮幹細胞疲弊症における眼表面の癒着軽減
- 悪性神経膠腫
- 再発又は難治性の多発性骨髄腫
- 非活動期又は軽症の活動期クローン病患者における複雑痔瘻の治療
など
一方、多能性幹細胞であるES細胞とiPS細胞のうち、iPS細胞から作られた網膜組織が加齢黄斑変性の患者に移植されるなど、治療への実用化が始まっているものの、保険適用となっているものはありません。研究の段階であるため“治療”というよりはむしろ“研究”といってよいでしょう。現在は、パーキンソン病、脳梗塞、水疱性角膜症、鼓膜損傷、重症心筋症、口唇口蓋裂、歯周病、糖尿病、先天性食道閉鎖症、クローン病、潰瘍性大腸炎、肝硬変、卵巣がん、子宮頸がん、変形性関節症、難治性骨折、閉塞性動脈硬化症、再生不良性貧血、表皮水泡症などに対する治療への応用が研究されています。
しかし、これら多能性幹細胞はがん化するリスクが現状では否定できません。また、ES細胞は本来胎児として成長するはずの受精卵を用いるため、倫理面で議論を呼ぶこともあります。
 変形性膝関節症に対する再生医療とは? 治療のあゆみと可能性について東海大学医学部外科学系整形外科学教授 、...佐藤 正人 先生
変形性膝関節症に対する再生医療とは? 治療のあゆみと可能性について東海大学医学部外科学系整形外科学教授 、...佐藤 正人 先生変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)とは、加齢などが原因で膝関節の軟骨がすり減り、関節が変形して、歩くときに膝に痛みが生じる病気で...続きを読む
 間葉系幹細胞を用いた再生医療の可能性——肝硬変のみならず新型コロナウイルス感染症の治療にも新潟大学 大学院医歯学総合研究科 消化...寺井 崇二 先生
間葉系幹細胞を用いた再生医療の可能性——肝硬変のみならず新型コロナウイルス感染症の治療にも新潟大学 大学院医歯学総合研究科 消化...寺井 崇二 先生再生医療に用いられる間葉系幹細胞(かんようけいかんさいぼう)には、炎症や免疫を抑制する効果があります。最初に肝硬変に対する臨床治験(第1相試験...続きを読む
 口腔粘膜やヒトiPS細胞を利用した角膜の再生医療の可能性と展望大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外...西田 幸二 先生
口腔粘膜やヒトiPS細胞を利用した角膜の再生医療の可能性と展望大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外...西田 幸二 先生角膜は、目の中に外から光を取り入れ、その光を屈折させてピント調節をするはたらきを持つ組織です。私たちにとって、カメラのレンズのような役割を果た...続きを読む
 筋芽細胞シートによる心不全治療の方法と手術を受けるタイミング、iPS細胞の活用大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 ...澤 芳樹 先生
筋芽細胞シートによる心不全治療の方法と手術を受けるタイミング、iPS細胞の活用大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻 ...澤 芳樹 先生肉離れなどを起こしたとき、脚にある筋芽細胞の働きにより筋肉は素早く修復します。この筋芽細胞をシート状に培養し、心筋に移植することで、進行した心...続きを読む
医師の方へ
Medical Note Expertでしか読めない、学会や医局の最新医療知見を得ることができます。
糖尿病治療への再生医療応用――β細胞新生・再生研究の現状と展望
糖尿病患者の根治CUREを目指して大学院、研修医のころから臨床と研究の二足のわらじを履きながらやってきた。1990年代から糖尿病の再生医療に期待がかけられてきたが、なかなか進まなかった。たとえば、血液の病気であればエリスロポエチンやG-CSFが90年代から臨床で使われてきたように、薬による再生医療は
【インタビュー】4年ぶり現地開催の再生医療学会 「双方向的議論」の場も―髙橋淳・総会会長が見どころなど紹介
「みんなでつくる、未来」をテーマに第22回日本再生医療学会総会が3月23~25日、国立京都国際会館(京都市左京区)で開かれる。山中伸弥・京都大学iPS細胞研究所名誉所長・教授によるiPS細胞(人工多能性幹細胞)の作成で世界にインパクトを与えた日本の再生医療。その研究者が、新型コロナウイルス感染症拡大
「再生医療」を登録すると、新着の情報をお知らせします