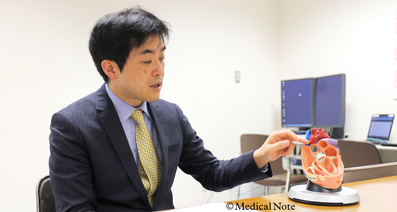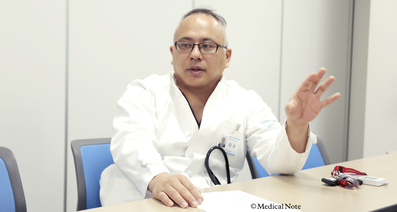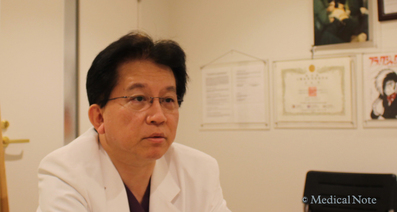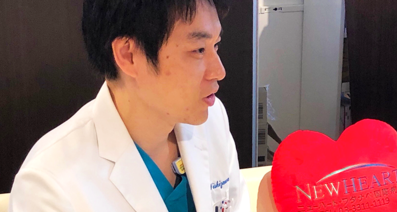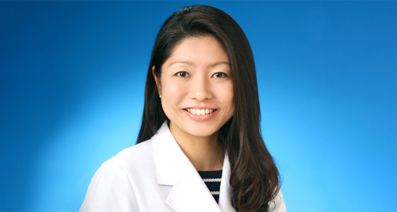心臓弁膜症に対して行う外科的治療には、大きく分けて“機械弁を用いる弁置換術”、“生体弁を用いる弁置換術”、“弁形成術”の3つの方法があります。本記事では、それぞれの治療の内容と、治療法を選択する際のポイントについて解説します。
心臓弁膜症の治療のポイント
心臓弁膜症を根本的に治すためには、原因となった弁に対して手術を行います。具体的には、元の弁を人工弁に置き換える“弁置換術”や、異常な部分を切る・縫うなどして弁を修理する“弁形成術”が挙げられます。
また、弁置換術に使われる人工弁には、工学的に作られた機械弁と、動物から作られた生体弁という2つの種類があります。
それぞれの治療に、手術後に薬を飲み続ける必要があったり、置き換えた弁に寿命があったりと、考慮しておかなくてはならない点があるため、治療方法を選ぶときには慎重に検討する必要があります。
機械弁を用いる弁置換術とは

弁置換術では、病気の原因となった元の弁を切り取り、代わりとなる人工弁をその場所に縫い付けます。
人工弁の1つである機械弁は、パイロライトカーボンやチタンなどの材質で作られています。
耐久性に優れている点が長所
機械弁の材質は非常に硬く、耐久性に優れています。そのため、手術後に機械弁自体が壊れることはほとんどなく、再手術の可能性が低いことが特徴です。
ワルファリンを飲み続けなくてはならない点が短所
しかし、機械弁は人間にとって異物にほかなりません。人間の血液は異物に触れると固まろうとする性質があり、機械弁のヒンジ(蝶つがい)の部分で血液が固まってしまうと、弁として正常に開け閉めができなくなってしまいます。
この事態を防ぐため、弁置換術で機械弁を使った患者さんは、ワルファリンと呼ばれる血液の抗凝固薬を、生涯にわたって飲み続けなくてはなりません。
ワルファリンを服用する際の注意事項
このワルファリンという薬は、誤って多く飲んでしまうと、脳・胃・皮膚など、全身で出血が起こりやすくなり、また飲むのを止めてしまうと、血液が固まって機械弁が動かなくなる危険性があるため、毎日の内服管理をしっかりと行わなくてはなりません。
特に高齢の患者さんの場合、ご本人は飲んだと思っているが実際は飲み忘れていた、それが何日も続いてしまった、ということもあり得るため、周りに理解していただく必要があります。
また、血液が固まりにくい状態になるので、けがをしたり、ほかの病気などで治療や手術を受けたりするときにも、細心の注意が必要となります。たとえば、手術を受けることになった場合、手術の数日前からワルファリンの内服を止め、止めている間は代わりの抗凝固薬を注射し、手術中は全ての抗凝固薬を中和させ、手術が終わったら再びワルファリンの内服を始める、というように、厳密な処置が行われます。
なお、歯の治療で抜歯をする場合は、事前に病院で薬の調整や、抜歯後の出血に対する処置が必要になることもあります。あらかじめ担当の歯科医にもワルファリンを飲んでいることを伝えるようにしましょう。
生体弁を用いる弁置換術とは

人工弁のもう1つの種類に、生体弁があります。
生体弁は、ブタの心臓の弁や、ウシの心膜(心臓を包んでいる膜)から作られ、なめした革のような材質をしています。これを細いフレームに縫い付けて、元の弁の代わりに埋め込みます。
人体に馴染みやすいことが長所
機械弁に比べると、生体弁のほうが人体によく馴染み、また、ヒンジ(蝶つがい)を使わないので、ワルファリンを飲む必要がありません。
弁を取り換える可能性があることが短所
ただし、機械弁ほどの耐久性はなく、生体弁の寿命は一般的に10~20年とされています。
また生体弁は、作られるときに抗石灰化処理が施されていますが、動脈硬化の影響を受けると石灰化が起こり、およそ15年前後で弁が硬くなって動きが悪くなります。この場合、元の弁と同じように狭窄症につながる可能性があるのです。
つまり、生体弁を使う場合は、人生の中で再度、弁を取り換える必要が出てくることを考えておかなくてはならないのです。
弁形成術とは
弁形成術は、開け閉めが上手くできなくなっている弁を、再びきちんとはたらくように修復する方法です。特に、僧帽弁閉鎖不全症に対しては、この弁形成術が選択されます。
弁を形成する方法はさまざま
具体的な方法としては、弁と弁の距離を詰めて閉じるように縫う“弁輪縫縮術”や、壊れた腱索の代わりに糸を使って弁を支える“人工腱索”などがあります。そのほかにも、弁が大きくなっている場合は、余っている部分を切って形を整えたり、広がってしまった心臓の筋肉を切って寄せたりと、起こった異常に応じた方法を取ります。
修復しても、別のところに異常が起こる可能性も
弁形成術は元の弁を利用したまま原因を直接治すため、機械弁のようにワルファリンを飲む必要もなく、生体弁のように弁の寿命に限りがあるものでもありません。
ただし、修復しても別のところに異常が起こってしまう可能性もあり、その場合はあらためて手術が必要になります。そのため、一定の基準をクリアした製品としての機械弁や生体弁と比較すると、将来的な見通しが予測しづらいという側面を考慮する必要があります。
心臓弁膜症の手術に伴うリスクについて
弁置換術・弁形成術のどちらであっても、心臓の手術をするときは、一度心臓の動きを止める必要があります。その間、人工心肺を用いて患者さんの心肺機能を維持することになるのですが、心臓を停止させておける時間は限られていますから、手術時間をできるだけ短くすることが重要だと考えられています。
また、手術時間が長くなる場合、合併症として感染症を引き起こすリスクも高まります。
こうした危険をできるだけ回避するために、心臓弁膜症の手術には、限られた時間の中でよどみなく流れるような手術を行えるよう、的確な技術とチームワークが欠かせません。
心臓弁膜症の最適な治療法を選択するために――患者さんによって最適な治療法は異なる
ご説明してきたように、心臓弁膜症の治療には3つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
たとえば、比較的若い患者さんに対して、20年ほどで壊れるかもしれない生体弁を選ぶかどうか、また、職業によってけがが多い患者さんに対して機械弁を用いるか、子どもを産みたいと考えている患者さんにはどの治療法を選ぶかなど、患者さんによって答えは異なります。
適切な時期に手術を受けることの重要性
手術のタイミングが遅れることは命に関わる
心臓弁膜症に対する外科的治療を行う際は、治療の内容を適切に選択することはもちろん、どのタイミングで手術を受けるかということも重要です。
記事1『心臓弁膜症とは? 発症のしくみを詳しく解説』でもお伝えしたとおり、心臓弁膜症は自然に回復することはありません。特に、心臓弁膜症の1つである大動脈弁狭窄症は、症状が現れてから2~5年の間に亡くなってしまうことが多いといわれています。心臓弁膜症の治療では、手術のタイミングが遅くなることは、できるだけ避けなくてはなりません。
手術時期の検討が大切
それでは、手術は早ければ早いほどよいといえるのでしょうか。
たとえば弁置換術で、異常のある弁を生体弁に入れ換えた場合、その耐久性が問題となります。生体弁は10~20年が寿命といわれており、生体弁が機能不全に陥った場合、再手術することが必要です。つまり、必要以上に早い段階で生体弁に入れ換えた場合、2回目の手術の時期はその分前倒しとなってしまうのです。
手術のタイミングが早まることによって、患者さんのその後の人生における大事なイベントに影響が及ぶ可能性もあります。患者さんの人生設計やご希望も踏まえて手術の時期を検討することが大切です。
適切な時期を見逃さないための定期検診
手術を受ける正しい時期を見逃さないために、心臓弁膜症の診断をされた後は、定期的に検診を受けていただく必要があります。医師が経過を観察することにより、「そろそろ手術を行いましょう」と提案できるのです。
心臓弁膜症は自然に治る病気ではありませんので、きちんと定期検診を受けるようにしましょう。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が10件あります
喘息発作について
喘息、弁膜症を持ってる弟が、9時半過ぎ頃喘息の発作を起こしてしまい、吸入をさせ落ち着いたので眠っているのですが、呼吸が少し苦しそうで、喘鳴がかすかに聞こえます。 この際、どう対処したら良いのでしょうか?
心臓弁取り替え手術をしないといけないのか?
急いで手術をしないといつ死ぬかわからないので、早くと結論を急がれている。
ミックス手術で振動細動の手術(左心耳切除)他
はじめまして、私の病名は心臓弁膜症三芯弁逆流です、一般の手術は開胸手術だそうですが、年齢が86歳の高齢なので悩んでいます、九州医療センターでは、ミックス手術ができるそうなので、相談いたします、 体重は60k,今のところ、心臓疾患でこれとゆう、症状は、全くありません.
右耳からザッザッという拍動性の耳鳴りが半年以上続いています
今年の4月頃に右耳からザッザッという音が聞こえるようになりました。主に静かなところで聞こえます。4月に脳神経外科に行きMRIで血管に異常がないことを確認してもらい様子を見てみましょうと言われました。 それでも毎日のように耳鳴りが続くので先月耳鼻科に行き鼓膜の検査や聴力検査をしました。鼓膜は異状なし、聴力はやや悪くなっているがまだ正常範囲とのこと。ビタミンや血管の流れをよくする薬などをもらいましたが未だに良くなりません。 どうすれば改善するでしょうか。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心臓弁膜症」を登録すると、新着の情報をお知らせします

![メディカルノート編集部 [医師監修]](http://carbon-assets.medicalnote.jp/uploads/doctor/image/0/740/s200x200_5c2d6660-6479-496b-a4d5-a475eca85c88.png)