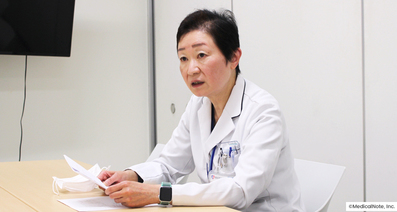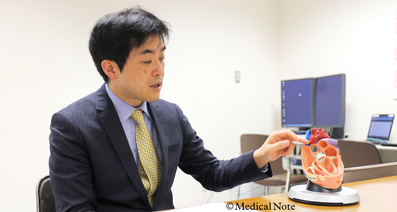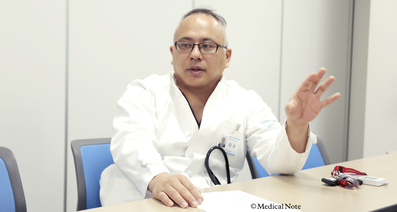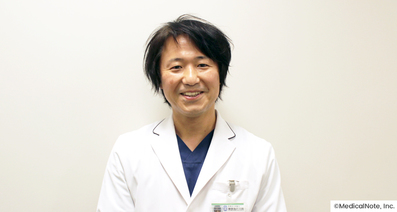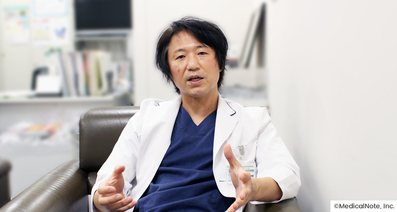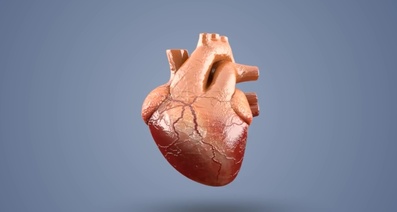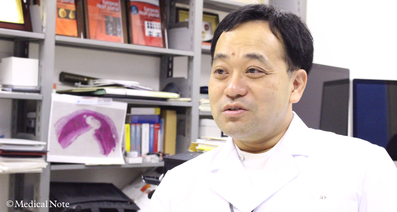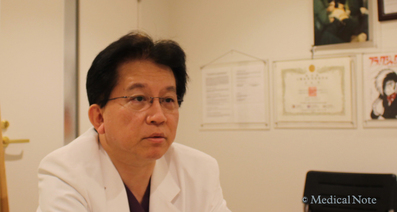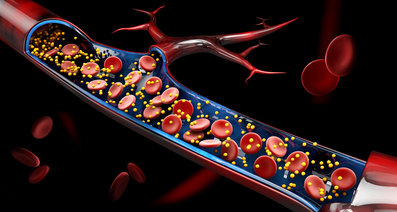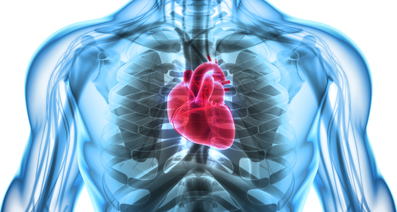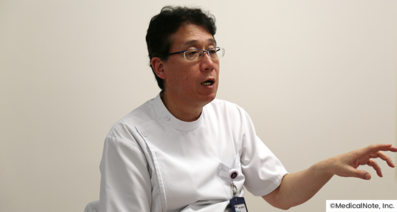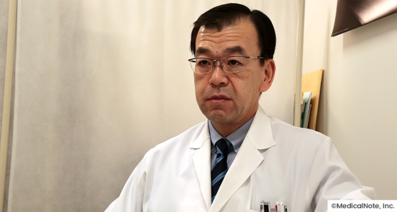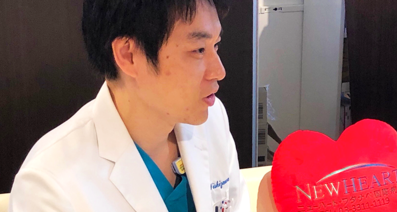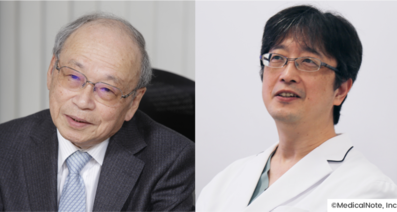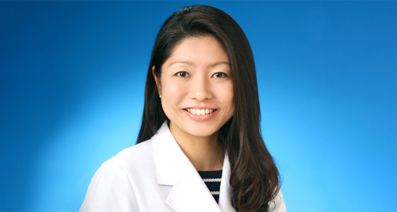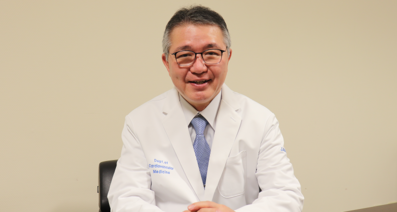
記事1『不整脈治療で使われるS-ICDとは? ICDとの違い、適応やメリット・デメリット』では、S-ICDとICDの違いや適応、手術の手順などについてお伝えしました。S-ICD植え込み後は、ほとんどは健康な方と同様の生活を送ることが可能ですが、一部、気をつけるべき点があります。S-ICD植え込み後に、日常生活で気をつけるべきポイントやS-ICDが作動した場合の対処法、痛みなどについて、引き続き日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野 大学院教授 清水 渉先生にお話をうかがいました。
S-ICD植え込み後の日常生活における注意点
S-ICD本体に強い衝撃を与えないように注意
S-ICDを植え込み後に最も注意していただきたい点は、S-ICDを植え込んである胸部に、衝撃を与えないようにする点です。故障の原因となります。
しかし、従来のICDやペースメーカーのようにリードの負担を考慮する必要がないため、S-ICDはICDやペースメーカーと比べて動作の制限は少ないです。
運動は行ってもOK
ウォーキングなどの適度な運動も自由に行えます。むしろ、適度な運動は心臓に負担のかかる高血圧などの生活習慣病予防の観点からも、行っていただくことが望ましいです。
S-ICDなどの植え込み後は、自動車の運転が原則禁止される
S-ICDを含むICDを植え込むと、原則、自動車の運転が禁止されます。運転を行うには医師の診断書を警察署に提出し、運転の可否が判断されます。運転が可能となった場合でも、6か月ごとに診断書を提出しての再審査が必要です。
また、トラックやタクシーの運転などの第二種免許による職業運転、中型免許(8t限定を除く)、大型免許を用いた運転は許可されていません。発作による失神やICD等での電気ショック治療が、重大な事故に結びつく可能性があるためです。そのため、現在、運転士などの仕事に就いている方は内勤に変えるなど、職場で対応していただく必要があります。
携帯電話・スマートフォンなどの電子機器は使用できない?

携帯・スマホは使用可。体内に電気が流れる機器、強い磁場が発生する機器は使用を控える
従来のICDと同様、体内に電気が流れる機器や強い磁場が発生する機器は使用を控えることが勧められています。
携帯電話やスマートフォンなどの電子機器は、機器の取り扱いの注意事項をしっかり守っていれば安全に使用できます。
<S-ICDの動作に影響を及ぼすものや場所>
- マッサージチェア
- 電気布団
- 体脂肪計
- 全自動麻雀卓
- アマチュア無線
- 電気自動車の急速充電器
- 業務無線
- 発電および変電施設内
- 高周波溶着器
- 誘電型溶鉱炉
- 各種溶接機
- 脱磁気装置
- 磁気バイス
- 電磁石
- MRI
- 放射線治療器
- 電気メス
- 体外式除細動器(AEDを含む)
- 電位治療器
- ジアテルミー装置
- 通電鍼治療器
- 高周波・低周波治療器 など
S-ICDが作動した際の対応
1日に複数回の作動があればすぐに受診を
S-ICDが1日に複数回正常に作動した場合は、疾患が悪化している可能性があります。そのため、1日に複数回の作動があればすぐに医療機関を受診してください。
不整脈の頻度が安定している患者さんや、S-ICDの作動が1度だけの患者さんであれば、S-ICDが作動しても緊急受診の必要はないでしょう。
症状が安定していても、定期検査は必ず受けてください。
S−ICD作動時の痛み
意識がある状態では強い痛みが出る
心室細動などでは意識がない状態でS-ICDによる電気ショック治療が行われることが多いため、この場合は痛みを感じることは少ないでしょう。しかしながら意識がある状態で電気ショック治療が行われると、体が硬直するような、胸を強く叩かれたような痛みが伴います。
睡眠時に不整脈が起き、本人が気づかないまま電気ショック治療が行われることもあります。
S-ICDの不適切作動(誤作動)
S-ICDを含むICDには、不適切作動のリスクがあります。たとえば、運動などで一時的に一定の心拍数を超えた場合に、機械が心室頻拍や心室細動と判断して電気ショック治療を開始する場合があります。
その際には意識がある状態での電気ショック治療となり、強い痛みが生じます。
不適切作動が生じる場合には再度設定を変えて、対処が可能です。
なかには、不適切作動を経験して精神的苦痛を覚える方もいます。その際には抗不安薬などの処方を行うときもあります。
S-ICDはICDよりも動作の制限が少なく生活ができる

S-ICDはリード断線のリスクが低いことから、ICDよりも動作の制限が少なく、日常生活を送りやすいと考えます。ICDと同様に激しい運動は控えるべきですが、ウォーキングなどの運動であれば楽しむことができます。
不適切作動のリスクもあるものの、多くは再設定により対処が可能です。
何よりも、本治療によって不整脈による突然死を防ぐことができる点は大きいでしょう。S-ICDを検討し、植え込み後の日常生活について気になる場合は医師に相談してみてください。
新東京病院 副院長・不整脈疾患診療特別顧問
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が25件あります
急性心筋梗塞
お尋ねします 先日 家人を,目前で亡くしました 急性心筋梗塞でした 私は倒れて3~4秒位で現場にいたんですが、唖然として顔を見つめるだけで、何もできませんでした その後1分後位に口を3~4回位プープーと 目を3~4回位開け 次にお腹を膨らまかし、そのうち左腕で起きようとする仕草しました その後日ネツトで調べましら「死線期呼吸」の行為だそうです もし、心臓マッサジーを施していてば助かったしょうか お尋ねします その日、本人は倒れる1時間半ぐらい前に、寝とれば動悸がしないが立ち上がると動悸がすると言って起床し、病院に行くと言っていたそうです 食事も,何ら普段と変わり無く済ましたそうです 尚倒れる,5分ほど前に一言、二言、言葉を交わしています 尚 私は 人工呼吸、心臓マッサージの講習も実習も受けた事がありませんが悔やまれます その後直ぐに救急隊が 人工呼吸をしてくれましたが駄目でした 急性心筋梗塞でAEDは使えなかった状態だったです 今でも その場面が脳に焼き付き、何も出来なかった事の悔しさが募ってたまりません 尚 こんな場面で無知識の者が出来る延命処置は なかっでしょうか 重ねて お尋ねいたします 救急車は4~5分位できてくれ救急隊の1人の方が 今脈が止まりましたと告げられていました 敏速な対応をしたつもりですので諦めらめ切れません 尚 家人は毎年、健康診断は受け、1 カ月程前は 職場を変るため指定の病院にて健康診断をうけ、何れも異常が無かったそうです 本人50歳 男性、酒もタバコもしません 最後に前兆が無くても急性心筋梗塞は起きますか ストレスとの関係はありますか お尋ねします 宜しくお願いします
健康診断結果における心電図判定について
健康診断の結果にて心電図判定にて「要経過観察」の結果がでました。 所見として「Q波」という記載があったのですが、何が問題なのか不明でした。 付属の健康診断説明にも説明がなく、何を注意すればいいのでしょうか? 過去(3年前)の検査は洞徐脈、右軸偏位という所見もありました。
心臓の詰まりと首の絞めつけ感
7、8年程前から2、3ヶ月に一度位、心臓の動きが一瞬詰まったような感じになり、その後首がグッと絞められたように苦しくなり血の気が引きます。今のところ5秒ほどの出来事なので我慢出来ますが、これが長くなると倒れそうで心配です。2年程前に別の症状で心電図をとった時には異常はありませんでした。たまにしか起きないので受診するほどではないと思っていましたが心筋梗塞や血栓の詰まりなど何か病気が潜れていることは考えられますか?
呼吸時の胸の痛みについて(受診は必要か?何科に行けば良いか?教えてください)
昨夜からですが、呼吸時に胸の奥に痛みがあり、続いていて少々気になるので、何科を受診すべきか(あるいは放置しておさまったら医療機関にかかるほどでもないのか…)教えてください。 【場所】 左胸の奥(中?)のほう 【痛みの症状】 骨がこんがらがった(?)ような痛み。(刺すような、と表現するのもちょっと違うような…。) 呼吸に合わせてきゅっと痛くなるのですが、主に息を吸うときに痛い。 【いつから】 昨晩から現在まで。 過去にもこのような何とも言えない痛みが胸の周辺で発生することは稀にあって、 しかしいつもしばらくするとおさまるので特に気にしてきませんでした。 今回は症状がちょっと長く続いているので気になっています。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心筋梗塞」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。