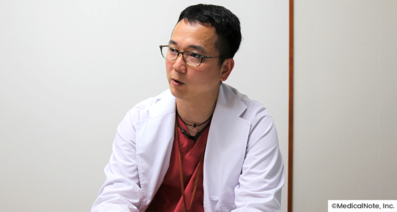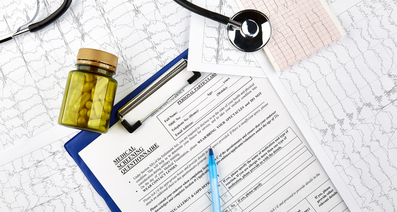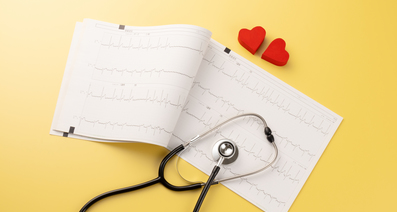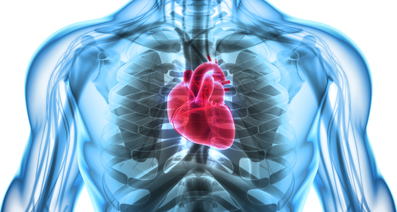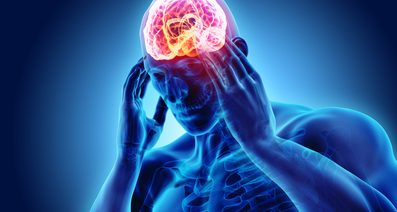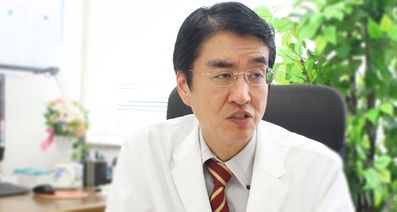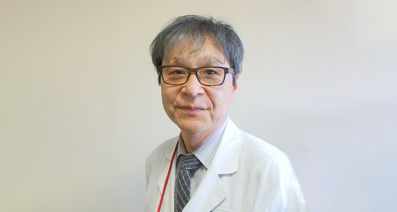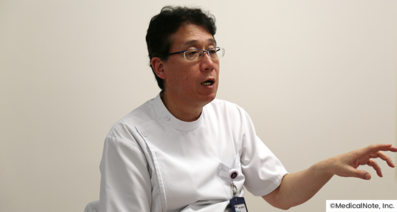高齢者に多い不整脈のひとつである心房細動は、脳梗塞の原因となることが問題視されています。心房細動があるとなぜ脳梗塞のリスクが高くなるのでしょうか。脳梗塞にならないために心房細動を管理していく必要性について、国際医療福祉大学三田病院 予防医学センター・心臓血管センターの加藤貴雄先生にお話をうかがいました。
心房細動とは
心房細動とは、心房内で秩序を失った興奮が不規則に起こっている状態で、電気的には非常に細かく不規則で速い興奮が起きているのですが、有効な収縮が得られなくなり、心房がほぼ止まってしまっているような状態です。
心室細動と心房細動は、同じ細動でもまったく異なる病態です。「細動」というと何かよくわからない、非常に怖いものだと思われる方もいらっしゃいますが、心房細動そのもので命に障ることはありません。一方、心室細動では心室が収縮しなくなり、血液を循環させることができなくなって死亡してしまうのです。
心房細動の原因・誘因
近年心房細動が増えている一番の原因は高齢化です。日本の統計でみると心房細動は年々増加しており、おそらく2015年時点では日本全国で100万人近くになっていると見込まれます。心房細動は高齢になればなるほど発生頻度が高くなり、80歳代ではほぼ1割近くの方が心房細動を起こしているといわれていますので、団塊の世代が高齢化する2025年にはこの数がどこまで増えるか想像がつきません。
高齢化以外にも、心房細動の発症にはさまざまな因子が関与しています。たとえば心筋梗塞などによって心臓の機能が低下し、心臓に負担がかかって心房細動が起きる、あるいは高血圧や弁膜症のために左心房に負担がかかり心房細動が起きるという症例がよくみられます。特に僧帽弁の弁膜症は心房細動を合併する率が非常に高いことが知られています。また若い人では、深酒の後など、夜間に発症する一過性の心房細動もあります。
心房細動はなぜ問題か
心房細動になると有効な心房の収縮ができなくなり、血液が心房の中でうっ滞します。その結果、特に左心房の中に血栓、つまり血のかたまりができやすくなります。この血栓が何かのきっかけで血流にのって左心房から左心室、左心室から大動脈、そして頸(くび)の動脈から頭に行き、頭の中の血管の狭いところに行って詰まってしまうのです。
これが典型的な心原性の脳梗塞というもので、脳梗塞の半数以上を占めていると考えられます。心房細動そのもののリスクよりも、それに伴って起こる脳梗塞のリスクが、何といっても一番の問題点なのです。心房細動が見つかったときは、まず血栓ができないように対処していくという積極的なアプローチが必要です。
心房細動管理の必要性
心房細動は次の3つのタイプに分けることができます
- 発作性心房細動:数秒間から数分間、あるいは数時間発作が起きて自然におさまることを繰り返す
- 持続性心房細動:いったん起きた心房細動が1週間以上続いてしまう
- 永続性心房細動:慢性的にずっと心房細動の状態が続く
心房細動の3つのタイプによってそれぞれ治療のアプローチの仕方が異なりますが、共通して行なわれるのは抗凝固療法です。血栓ができて脳梗塞を起こすリスクを減らすための治療として、3つのタイプに共通して行なわれます。
また、それぞれのタイプごとに、もうひとつのリスクについてのアプローチが必要です。それは心不全を起こすリスクです。
心房細動は1分間に600〜800回という極端に速いペースで心房が興奮するため、いくつかの興奮は心室まで伝わってしまいます。その結果、通常は1分間に60回ぐらいである心室の拍出(はくしゅつ・心臓の拍動によって血液を送り出すこと)回数(心拍数)が、100回、150回と増えてしまうことになります。すると、今度は心臓全体のポンプ機能が損なわれ、血液の循環が悪くなって心不全を起こすリスクが出てくるため、そのリスク管理も同時に考えていく必要が生じます。
発作性や持続性と呼ばれる心房細動は心不全のリスクが高いので、心拍数が増えないようにする治療(通常は薬物治療)を並行して行なっていきます。一方、永続性心房細動になるとだんだん脈が落ち着いてきて、心不全のリスクは比較的少なくなります。このように心房細動のタイプによって、それぞれに必要な治療を同時進行で行なっていくのです。
永続性の場合は自覚症状がほとんどなく、ご本人は気が付かない場合も少なくありません。しかし心電図をとってみて明らかに心房細動であれば、脳梗塞のリスクは同じようにあるわけですから、やはり治療はしなければなりません。
抗凝固療法、増える選択肢
心房細動の治療における一般的な考え方は次のとおりです。
【心房細動を止める】
- 直流通電で除細動する
- 抗不整脈薬を静注する
【再発を防ぐ】
- 抗不整脈薬を長期内服する
- カテーテルアブレーション
【心不全を防ぐ】
- 心拍数調節薬を長期内服する
- アブレーションCRT
【脳梗塞を防ぐ】
- 抗凝固薬・抗血栓薬を長期内服する
【基礎疾患を治療する】
【心臓病を予防する】
- 食事、メタボ対策、禁煙、睡眠など生活習慣の改善を図る
心房細動を管理し、脳梗塞を予防するためには、抗凝固薬・抗血栓薬と呼ばれる薬剤を継続的に服用する「抗凝固療法」を行う必要があります。従来はワルファリンという薬が主に使われてきましたが、近年、新しい経口抗凝固薬が相次いで登場し、治療の選択肢が増えています。抗凝固療法に使われる薬剤については、次の記事以降で詳しく説明していきます。
高橋淳先生監修、心房細動の最新記事はこちら↓
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連の医療相談が15件あります
心房細動の再発について
2年前から心房細動と診断されています めまいがきっかけで、3年前に2週間程度入院しましたが、病気がつかめず、ループレコーダーを体内に入れました 2年前に病気が見つかり心房細動と診断されました 2年前にカテーテルアブレーションをしましたが、1年前に再発しました 2回目のアブレーションの時に、1回目の治療をしたところの跡がないと言われました 最近になって体調が悪くなった時があって、病院で心電図をしたところ、心房細動が再発していることが分かりました 3回目のアブレーションは現実的なんでしょうか 通院している病院が、提携している大学病院の専門医が出張でアブレーション治療を行ってくれるのですが、その先生の判断待ちの状態です もし、3回目のアブレーション治療が無かったら、担当医からは薬になるかもしれないと言われました 薬になったら、日常の行動に支障は出ますか もしくは、ほかの治療法はあるのでしょうか 宜しくお願いします
手術について
脳動脈瘤が見つかり、開頭クリッピング術での手術を勧められました。心房細動の持病があり、2月にそれによる脳梗塞、4月に心臓のカテーテルアブレーションの治療をしましたが、再発するようならもう一度しないと・・との診断。最近になって寒さのせいか動悸を感じる事があります。脳外の担当医には伝えてあります。 心房細動を患いながらの開頭クリッピング手術ってのは、危険なのでしょうか?
今後の注意する事は?
2日前に、カテーテルアブレーションの手術しました。悪い所をすぐ、解り、1時間ぐらいで終わり、手術前の検査では、心臓が大きくなっていて、70パーセント完治と言われてましたが、80パーセント完治と言われ安心してます。軽度の、心不全にもなってますが、今後の生活では、注意する事ありますか?お酒は、一口も飲んだら、駄目なんですか?カフェインや、塩分はどうですか?又、この手術によって、心不全が良くなりますか?心不全は、生活習慣や、食事(塩分)の制限したり、薬で、完治しますか?今後、ずっと薬を飲み続ける生活ですか?まだ、54歳で、仕事は、パソコン等デスクワークですが、大丈夫ですか?車の運転はどうですか?今後の生活と、完治について教えてほしいです。
心房細動の手術を受けるかどうか?
2013年に鬱血性心不全で入院。薬をそれから服用し経過観察。今年3月6日に体調異変で翌日かかりつけの病院に行ったら心房細動の診断。薬を変更し経緯を観察中だが、医者からはカテーテル手術を勧められている。手術の失敗確率より、このままにしておいて死ぬ確率の方が高いと言われました。ただ最近は血圧や脈拍も安定して、症状は出ていない。 どうしたら良いか?
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心房細動」を登録すると、新着の情報をお知らせします