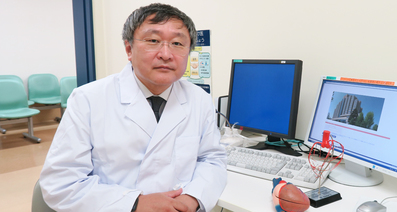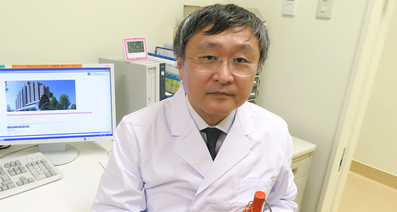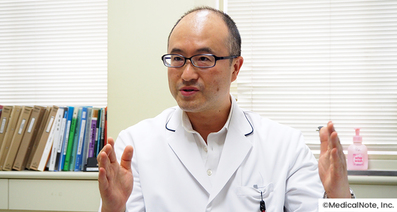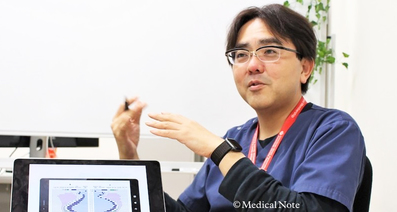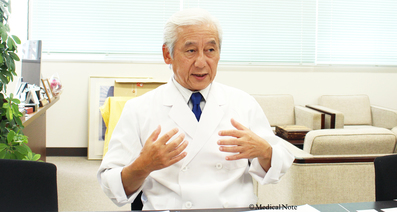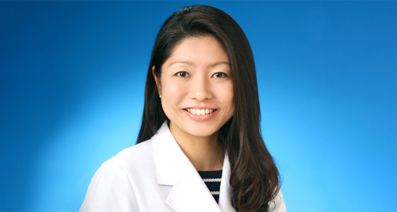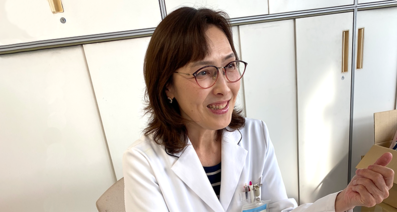心不全とは心臓の機能、つまり全身に血液を送り出すポンプの力が低下した状態の総称で、あらゆる臓器を含め全身に必要量の血液を送り出すことができなくなったり、肺や全身に血液が滞るうっ血状態になったりする病態です。心不全には大別すると、慢性心不全と急性心不全がありますが、心臓のポンプ機能が「急激に低下」することによって血液循環が維持できない状態と血液が滞るうっ血状態とが短期間のうちに起こることを急性心不全と呼んでいます。
心不全には収縮不全と拡張不全とがあります。収縮不全は血液を送り出す力の低下した状態ですが、拡張不全は血液が心臓にもどりにくくなった状態です。両者はしばしば伴ってみられます。
急性心不全とは?
心筋梗塞や、様々な心臓の基礎疾患が原因となる
急性心不全の原因として最も多いのは突発的に発症する急性心筋梗塞などの虚血性心疾患です。心臓を動かすための筋肉(心筋)に必要な酸素や栄養素を送る冠動脈が閉塞して、心筋の一部が酸素不足(虚血状態)に陥ってしまうことに起因します。一方で、慢性的な心不全を抱えている患者さんの容体が急激に悪化して起こる場合もあります。
たとえば、
その他にも先天性心疾患や甲状腺機能亢進症、不整脈、糖尿病などは慢性心不全を引き起こす原因となります。慢性心不全を患っている患者さんが、精神的・肉体的ストレスを受けたり、暴飲暴食をしたり、風邪や感染症にかかったり、あるいは貧血や妊娠などをきっかけに急性心不全を起こすことがあります。
急性心不全の症状
代表的なのは激しい呼吸困難
代表的な症状としては、激しい呼吸困難や咳き込み、血痰、胸部の痛み・圧迫感、脈拍数の増加、動悸、乏尿、腹部膨満、冷や汗、顔面の皮膚蒼白、冷感、浮腫、腹水、全身が酸素不足に陥いると唇や爪先、皮膚や粘膜などが青紫色に変色するチアノーゼ、さらに意識障害が現れることもあります。多くの場合、血圧は低下します。
急性心不全の検査方法
最初に急性心筋梗塞が原因でないかと考える
急性心不全の診断はまず、自覚症状と病歴の確認、および全身状態の診察からはじまります。また急性心不全を引き起こすようなきっかけ、持病の有無を確認します。病態を詳細に把握し、予測を行いながら、診断・治療につなげていきます。急性心筋梗塞が原因であれば、緊急のカテーテル治療が必要になります。以下のような検査を行いながら、これらの可能性を一つずつ検討していきます。
心電図検査
この検査では、両手足と胸に複数の電極を取り付けて、心臓から発生する微弱な電気信号を取り出し、その電気的活動を記録します。これにより、急性心筋梗塞や心筋症の所見が現れていないか、また不整脈がないかなどを確認します。急性心不全の原因追求には不可欠な検査です。
心エコー図検査
心臓に超音波を投入し、心臓の筋肉や弁の動きを画像にするのが心エコー検査です。心臓の収縮力や拡張力を評価したり、心臓の壁の厚さを調べることで心臓の動きや心肥大の有無を確認します。心筋の一部が収縮運動をしていなければ、心筋梗塞の可能性を考え、場所と範囲を特定します。また、血液の流れる速度や方向も確認でき、弁構造を可視化できるので、弁逆流や弁狭窄などの弁膜症の診断にも有効です。リアルタイムで心臓の動きを確認できるため、診断やその後の治療方針を決定する上で重要な検査です。
胸部X線検査
心臓と肺の状態を詳細に観察するために胸部X線検査が行われます。特に急性心不全においては、肺うっ血像の確認に不可欠です。
血液検査
急性心不全が疑われる患者さんから採取した血液中の血液ガス、電解質やたんぱく質など特定の成分値を調べます。急性心不全では動脈血の酸素含量が低下します。激しい呼吸困難があるときには二酸化炭素含量も減少する傾向があります。クレアチニンフォスフォキナーゼやトロポニンなどの心筋細胞成分が逸脱していれば、心筋梗塞と診断できます。BNPが上昇していれば、心臓壁の伸展、つまり心臓への負荷状態が推測され、その他の異常値についても、腎臓や肝臓のうっ血を推測できる場合があります。
呼吸困難に対しては酸素吸入を行ないますが、高度の肺うっ血のために動脈血の二酸化炭素含量が高いときに呼吸を抑制するとCO2ナルコーシスと呼ばれる意識障害を起こして状態が悪化する危険があります。動脈血のガス分析はこの意味でも大事なことです。
カテーテル検査
カテーテルと呼ばれる細い管を足の付け根や手首などの動脈、あるいは頚静脈から体内に挿入し、肺静脈に留置します。これによって、うっ血の指標である肺静脈楔入圧を測定し、心拍出量も測定できます。こうして心不全状態を定量的に計測しながら、管理することが可能です。
さらに心筋梗塞などが疑われる場合には、カテーテルを動脈に挿入し、冠動脈にまで進めて造影検査し、冠動脈血管の形や狭窄、あるいは閉塞箇所などを知ることができます。急性心筋梗塞が疑われるときには、冠動脈のカテーテル検査を緊急で行うことが必要ですが、いそがない場合には、心不全が落ち着いてからの精密検査の一環として行います。
急性心不全の治療方法
急性期の治療後、原因に応じた手術と継続的な内科治療を行なう
急性心不全が生じた場合、まずは呼吸困難の改善と臓器のうっ血改善を早急に行う必要があります。いわゆる救命救急措置が最優先となるわけです。そこで、万一の場合に備えて蘇生措置も取れる体制の中で治療を進めます。
一般的に行われる初期治療は酸素療法と投薬です。酸素療法は呼吸の安定化と共に動脈血の酸素含量を高め、臓器虚血を改善させる大事な措置です。また、投薬はうっ血を改善し、血液循環の改善をはかることを目的とします。
急性心不全を起こしたときに、心臓が収縮した際の血圧(収縮期血圧)が100mgHg以下と低いときには、血圧を上げる昇圧薬や強心薬を用います。収縮期血圧に異常が認められない場合や高値である場合には、硝酸薬やカルペリチドなどの血管拡張薬を投与し、血液の臓器循環の改善を図ります。うっ血の改善には体内水分貯留を防ぐ利尿薬を使用します。
これらの措置により急性期の発作的症状が治まった後は、入院安静の状態を保ちながら心不全の原因特定のための精密検査を行い、その後の治療・手術方針を決めていきます。すなわち、心不全に至った原因となる基礎疾患によっては、狭心症に対する心臓カテーテル手術や心臓弁膜症の手術、不整脈に対する治療、あるいは手術やペースメーカの植え込みなどが検討されます。場合によっては心臓移植が検討されることもあり得ます。
もちろん、内科的治療も非常に重要です。原因や基礎疾患によって、継続的な投薬治療・管理が続けられていきます。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


心不全は退院後も外来で“先手”の心臓リハビリテーションを

心不全に対する治療の新たな選択肢とは
「心不全」に関連する病院の紹介記事
特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。
関連の医療相談が17件あります
心不全と腎臓透析との関係について
私の母親84歳についての相談です。7月から現在も入院中です。当初薬物療法で様子を観察して改善が無ければペースメーカーを埋め込むという治療方針を主治医に言われ了承し服薬しながら入院生活をしていたのですが、そのうち尿の出が悪くなり足のむくみが酷くなり肺に水が溜まり呼吸が苦しくなって酸欠による意識障害になり一命は取り止めたもののHCUという処に入っています。透析によって血液から水をひいて肺に溜まった水を抜く治療で回復し、現在は意識もハッキリし呼吸も少しの酸素を鼻から吸っている位で、会話食事も出来ますがまだ起き上がるのは無理です。透析をすると血圧が下がり腎臓の機能が低下して尿の出が悪くなりやらないと水が溜まって呼吸が辛くなる状態です。医師はシャントして恒常的に透析をしていくと言っていますが、それは何か違和感を覚えます?最初に示されたペースメーカーによる治療との整合性が無いように思いますが。そもそも心臓の治療で恒常的な透析と云うのは有りなのでしょうか?
今後の注意する事は?
2日前に、カテーテルアブレーションの手術しました。悪い所をすぐ、解り、1時間ぐらいで終わり、手術前の検査では、心臓が大きくなっていて、70パーセント完治と言われてましたが、80パーセント完治と言われ安心してます。軽度の、心不全にもなってますが、今後の生活では、注意する事ありますか?お酒は、一口も飲んだら、駄目なんですか?カフェインや、塩分はどうですか?又、この手術によって、心不全が良くなりますか?心不全は、生活習慣や、食事(塩分)の制限したり、薬で、完治しますか?今後、ずっと薬を飲み続ける生活ですか?まだ、54歳で、仕事は、パソコン等デスクワークですが、大丈夫ですか?車の運転はどうですか?今後の生活と、完治について教えてほしいです。
心不全の症状とは?
喋ると息切れがします。(階段登っても) 隠れ心不全のような疑いはありますでしょうか?ちなみに今週、胸部CTを撮る予定です。 CTでそのような兆候はわかるのでしょうか? 異常であれば、血液検査の値は、どのようにあらわれるのでしょうか?
母乳育児による心不全の進行影響有無
幼児の頃にファロー四徴症の心内修復術を受け、現在循環器内科にて年1回程度経過をみています。心雑音はありますが、特に問題はないと言われています。今回出産で大量出血し、ヘモグロビン値が低くなったため輸血を行いました。その後の入院中は点滴で鉄剤を投与され、退院後は内服で処方をされています。 退院時のヘモグロビン値は8とのことですが、母乳育児を続けることで貧血が続き心臓に負担をかけ心不全に繋がらないかを懸念しています。もし母乳育児が心臓に負担をかけるようであればミルク育児に切り替えるべきか教えてください。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心不全」を登録すると、新着の情報をお知らせします