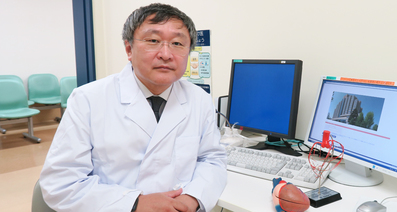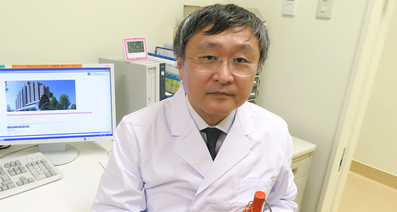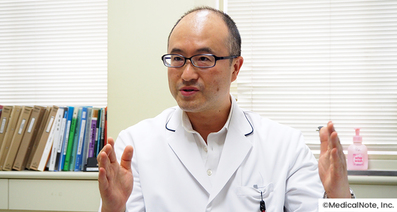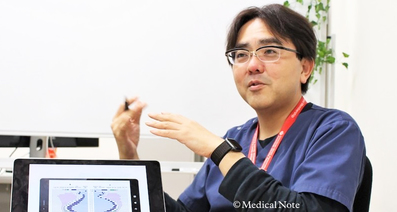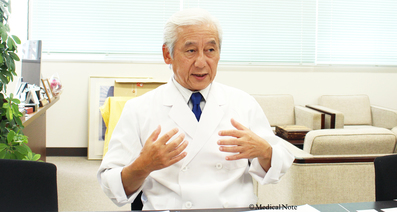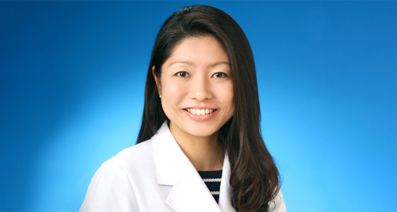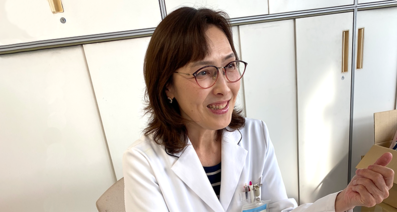心不全とは、全身に血液を送る心臓のポンプ機能が低下し、息切れやむくみなどの症状が起きた状態をいいます。その状態が長く続くと心臓の機能は徐々に悪化し、最終的に命を縮めてしまう可能性があります。
今回は、心不全の治療を急性期と慢性期に分け、日常生活での注意点も含めて詳しく解説します。
治療の概要
心不全の治療は、心不全症状の改善と心不全の原因となる病気の治療の二本柱で行われるのが基本です。心不全はガイドラインにおいて4つのステージに分類されており、ここではそれぞれについての説明とその治療目標を説明します。
ステージA:器質的心疾患のないリスクステージ
器質的心疾患のリスク因子を持つが、心不全症候のない場合をステージAと分類します。リスク因子には高血圧や肥満・糖尿病などの生活習慣病、アルコール多飲や喫煙などが含まれます。このステージではこれらのリスク因子を適切にコントロールすることと器質的心疾患の発症を予防することが治療目標となります。
ステージB:器質的心疾患のあるリスクステージ
器質的心疾患があるものの、心不全症候のない場合はステージBに分類されます。このステージは心不全を発症する一歩手前といえます。そのため、心不全の発症予防とともに、器質的心疾患がこれ以上進行しないように予防することが、とても重要な治療目標となります。
ステージC:心不全ステージ
器質的心疾患があり、心不全症候を有する場合はステージCに分類されます。肺炎や血圧上昇などをきっかけとして急性心不全を発症し、身体機能が低下します。未治療のまま放置するとさらに心機能が悪化するため、早期治療介入が非常に重要です。治療目標は症状をコントロールするとともにQOL(生活の質)を改善していくことが最優先となります。
ステージD:治療抵抗性心不全ステージ
ステージCよりもさらに悪化し、多くの治療介入を行ってもなお症状が改善されない場合はステージDに分類されます。このステージでは、植込み型除細動器や補助人工心臓、心臓移植などを含む特別な治療、および人生の最終段階における医療(終末期医療)*が治療の中核となります。
*平成27年3月に厚生労働省「終末期医療に関する意識調査等検討会」において終末期医療から人生の最終段階における医療に名称変更
急性期(急性心不全)の治療
急性心不全とは何らかの原因で心臓に構造的または機能的な異常が生じ、ポンプ機能が急速に悪化した状態をいいます。初期対応が非常に重要で、降圧薬点滴静注や利尿薬、酸素吸入などで全身状態を安定化しつつ、各種検査を行い原因検索のうえ、病態に応じた治療を行います。重度の場合はICUやCCUでの治療が望ましいとされます。急性期を脱し状態が安定した後に、外来にて状態に応じた治療を行います。
慢性期の治療
急性心不全から改善した状態である慢性心不全の治療は、大きく分けて薬物療法と非薬物療法の2つに分けられます。
薬物療法
心臓に負担がかかるとそれを元に戻すシステム(代償機構)が働きだします。しかしこの代償機構は自ら心臓に負担をかけるため、その状態が続くといずれ限界を迎え、代償できなくなり心不全へと進行してしまいます。
薬物療法は代償機構を薬物で補助することによって、心臓の負担を軽減し心不全症状を改善する効果があります。具体的にはアンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)やアンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)、β遮断薬などが使用されます。
非薬物療法
薬物療法で治療効果が見られない場合に、薬物療法と併用して行われます。
植込み型除細動器
心不全によって致死的不整脈が起こる可能性が高い患者に対しては、植込み型除細動器が用いられます。導入することで、突然死の予防効果があります。
心臓再同期療法
心臓の収縮するタイミングのずれによる左室収縮不全に対しては、心臓再同期療法が有効となる場合があります。導入する際は薬物療法の効果をしっかりと判断した後に行われます。
呼吸補助療法
薬物療法などの治療を行ってもなお、肺うっ血による呼吸困難などの症状が持続する重症例に用いられます。呼吸補助療法、特に陽圧呼吸療法を行うことで症状が改善されることがあります。この治療法は、在宅でも継続できます。
運動療法
近年、慢性心不全に対する運動療法の効果が明らかになっています。低強度レジスタンストレーニングや高強度インターバルトレーニングがあり、症状に合わせて医師と相談しながら、適切に行う必要があります。
日常生活での注意点
無理な運動など心臓の負担になることは避け、適度な運動を心がけるようにしましょう。また、肥満や塩分過多、喫煙やアルコール多飲は生活習慣病の原因となり、心不全発症のリスク因子となるので、気を付けるようにしましょう。過労や風邪、熱いお風呂や長風呂も心不全を悪化させる可能性があるので注意が必要です。
気になる症状がある場合は受診を
心不全は生活習慣の見直しをすることで発症を予防することができるだけでなく、早期治療で悪化を防ぐことができます。息切れ、動悸など気になる症状がある、また、現在の治療方法などを相談したい場合は、内科(特に循環器内科)を受診するとよいでしょう。
横浜南共済病院 循環器内科 総括部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
横浜南共済病院 循環器内科 総括部長
鈴木 誠 先生日本循環器学会 循環器専門医・FJCS日本心臓病学会 FJCC日本不整脈心電学会 不整脈専門医・植込み型除細動器(ICD)/ペーシングによる心不全治療(CRT)研修修了者日本心臓リハビリテーション学会 心臓リハビリテーション指導士日本救急医学会 会員日本高血圧学会 会員日本内科学会 認定内科医・内科指導医日本医師会 認定産業医
東邦大学医学部を卒業後、東京医科歯科大学第三内科(現:循環器内科)へ入局。その後、市中病院での研修や海外留学を経て、2001年に亀田総合病院の循環器内科医長、2004年には部長に就任。2018年4月より現職。循環器疾患の中でも、特に不整脈と心不全を専門としている。日々の診療に尽力する傍ら、講演や研究会なども積極的に行っている。
鈴木 誠 先生の所属医療機関
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事


心不全は退院後も外来で“先手”の心臓リハビリテーションを

心不全に対する治療の新たな選択肢とは
「心不全」に関連する病院の紹介記事
特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。
関連の医療相談が17件あります
心不全と腎臓透析との関係について
私の母親84歳についての相談です。7月から現在も入院中です。当初薬物療法で様子を観察して改善が無ければペースメーカーを埋め込むという治療方針を主治医に言われ了承し服薬しながら入院生活をしていたのですが、そのうち尿の出が悪くなり足のむくみが酷くなり肺に水が溜まり呼吸が苦しくなって酸欠による意識障害になり一命は取り止めたもののHCUという処に入っています。透析によって血液から水をひいて肺に溜まった水を抜く治療で回復し、現在は意識もハッキリし呼吸も少しの酸素を鼻から吸っている位で、会話食事も出来ますがまだ起き上がるのは無理です。透析をすると血圧が下がり腎臓の機能が低下して尿の出が悪くなりやらないと水が溜まって呼吸が辛くなる状態です。医師はシャントして恒常的に透析をしていくと言っていますが、それは何か違和感を覚えます?最初に示されたペースメーカーによる治療との整合性が無いように思いますが。そもそも心臓の治療で恒常的な透析と云うのは有りなのでしょうか?
今後の注意する事は?
2日前に、カテーテルアブレーションの手術しました。悪い所をすぐ、解り、1時間ぐらいで終わり、手術前の検査では、心臓が大きくなっていて、70パーセント完治と言われてましたが、80パーセント完治と言われ安心してます。軽度の、心不全にもなってますが、今後の生活では、注意する事ありますか?お酒は、一口も飲んだら、駄目なんですか?カフェインや、塩分はどうですか?又、この手術によって、心不全が良くなりますか?心不全は、生活習慣や、食事(塩分)の制限したり、薬で、完治しますか?今後、ずっと薬を飲み続ける生活ですか?まだ、54歳で、仕事は、パソコン等デスクワークですが、大丈夫ですか?車の運転はどうですか?今後の生活と、完治について教えてほしいです。
心不全の症状とは?
喋ると息切れがします。(階段登っても) 隠れ心不全のような疑いはありますでしょうか?ちなみに今週、胸部CTを撮る予定です。 CTでそのような兆候はわかるのでしょうか? 異常であれば、血液検査の値は、どのようにあらわれるのでしょうか?
母乳育児による心不全の進行影響有無
幼児の頃にファロー四徴症の心内修復術を受け、現在循環器内科にて年1回程度経過をみています。心雑音はありますが、特に問題はないと言われています。今回出産で大量出血し、ヘモグロビン値が低くなったため輸血を行いました。その後の入院中は点滴で鉄剤を投与され、退院後は内服で処方をされています。 退院時のヘモグロビン値は8とのことですが、母乳育児を続けることで貧血が続き心臓に負担をかけ心不全に繋がらないかを懸念しています。もし母乳育児が心臓に負担をかけるようであればミルク育児に切り替えるべきか教えてください。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「心不全」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。