イメージ:PIXTA
近年、医療技術の進歩は目覚ましく、特に消化管(口から肛門(こうもん)まで続く、消化に関するはたらきを持つ器官)の病気の治療では「内視鏡」がその中心的な役割を担っている。
自覚症状がなくてもがんを早期に発見し、体への負担を最小限に抑えながら治療できる内視鏡は、私たちの健康を守るうえで欠かせない存在だ。
慶應義塾大学病院 内視鏡センター長の加藤 元彦(かとう もとひこ)先生に、内視鏡による検査と治療の最前線について伺った。
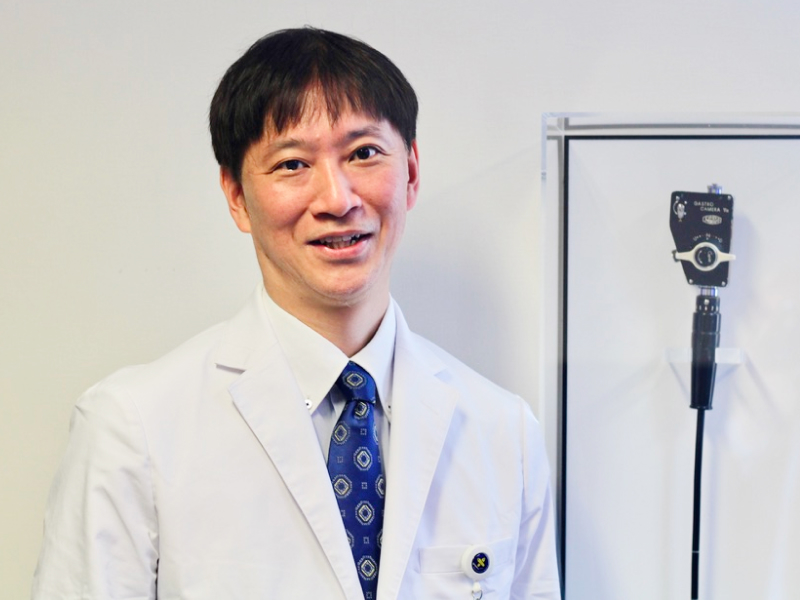
慶應義塾大学病院 内視鏡センター長 加藤 元彦先生
内視鏡検査は「がんの早期発見」が最大の目的
「検診で異常が見つかったらどうしよう」「内視鏡検査は苦しいって聞くけど……」。そうした不安から、内視鏡の検査をためらってしまう方もいらっしゃることでしょう。しかし、消化管の病気の早期発見には、内視鏡による検査が欠かせません。特に、消化管のがんを早期に見つけることに関して、内視鏡はさまざまな面で優れています。
そもそも消化管の初期がんは、組織の表面の粘膜のわずかな色の違いや凹凸といった、まるで皮膚のシミのような変化として現れます。内視鏡はこのようなごく初期の変化を直接観察して見つけ出すことができるのです。一方で、CTやPETといった全身を調べる検査では、ある程度進行したがんでないと見つけることが難しい場合があります。
また、早期のがんはほとんどの場合、粘膜の一番表面にとどまっており、この段階であれば内視鏡によって病変を切除するだけで9割以上の方が治癒できます。
完治が望める段階でがんを見つけられるだけでなく、切除までできることが内視鏡のメリットでしょう。その結果、内視鏡は日本の医療現場へ急速に普及することとなりました。
近年ではこれまで内視鏡では見ることができなかった肝臓、胆道、膵臓(すいぞう)も、十二指腸にある乳頭部という穴から器具を通してアプローチすることが可能になり、内視鏡による検査と治療ができるようになりました。さらには呼吸器である肺へも、空気の通り道へ専用の内視鏡(気管支鏡)を通して検査と治療ができるようになっています。
日本の内視鏡技術が世界に広がった
内視鏡技術は日本が発展させ、世界に広めてきました。現在でも日本は世界の中でも際立った存在になっており、オリンピックで例えるなら柔道や野球のように日本が世界を牽引(けんいん)している種目だといえます。
その背景には、日本がかつて胃がん大国だったという歴史があります。その胃がんを克服するため、第二次世界大戦の終戦後に、飛行機を製造していた技術者などが中心となり内視鏡の開発に尽力しました。それに加え、国が検診制度を整備し、検査を受けやすい仕組みを作りました。
その結果、民間企業が機器を製造し、多くの国民が検査を受け、その際に医師が診断技術を磨く――この官民学一体のサイクルが続けられた結果が、現在の高い技術力につながっています。
技術だけでなく、内視鏡の使い方でも日本は進んでいます。実は、アメリカやヨーロッパでは内視鏡は進行がんの検査と診断補助として使われることが多い状況です。これに対し日本では、内視鏡で早期がんを発見したらその場で治療に進むことができます。早期治療の観点で、日本のやり方が優れているのは明らかでしょう。
ESDの登場で大きな病変にも対応可能に
日本でも、当初は内視鏡は検査のみで用いられていました。その後、診断を目的として内視鏡を使い、その場で消化管の組織の一部を採取することができるようになり、これが発展して病変部の切除まで行うようになりました。
画期となったのは、輪投げの輪のようなワイヤーをかけて病変を切除するEMR(内視鏡的粘膜切除術)という方法が日本で開発されたことです。ただ、EMRは簡便であるものの、ワイヤーのサイズに制限があるため、大きな病変をきれいに切除しきれないことがありました。
そこで1995年ごろから日本で開発が始まったのがESD(内視鏡的粘膜下層剥離術<ないしきょうてきねんまくかそうはくりじゅつ>)です。ESDではワイヤーは使いません。電気メスを使って病変部の周りの粘膜を切り開き、その下の層を少しずつ剥がしていくことで、病変を1つの塊としてきれいに切除します。この方法により、2~3cmといった大きな病変でも内視鏡で切除できるようになりました。EMRが小さな病変に適しているのに対し、ESDは大きな病変や胃の入口・出口といった狭い部位にも対応できる点が優れているといえます。
ただし、ESDには術者に高い技術が求められます。治療を行う消化管の壁は非常に薄いため、ESDよる数百回に及ぶ通電で一度でもミスをすると穴が開いてしまうリスクがあるのです。したがって、ESDによる治療を受ける際は経験が豊かな医師や医療機関を選ぶべきでしょう。
体に優しい内視鏡治療のメリット
内視鏡治療の最大のメリットは、体の表面に傷をつけずに治療できることです。たとえ3cmの病変を切除しても、口から取り出すため、体の表面に傷は残りません。
また、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということわざがあるように、食道より下の消化管粘膜には知覚神経がないため、切除しても痛みを感じることはほとんどありません。臓器の一部を切除することもないので、消化機能への影響や、手術後の合併症(ダンピング症候群など)も起きにくいというメリットもあります。
内視鏡治療は、体への負担が非常に少ないことが最大の特長といえるでしょう。
とはいえ、注意点もあります。がんは進行するとリンパ節や他の臓器に転移することがあります。内視鏡治療の対象は、こうした転移がほとんどない「早期がん」に限られます。万が一転移が見られる場合は、リンパ節を含めて広範囲を切除する外科手術が選択されることになります。
治療の後は病理検査で完治を確認
内視鏡治療で切除した病変は、必ず病理検査に回されます。この病理検査では、切除した病変が本当にがんだったのか、周囲にがん細胞が残っていないかなどを顕微鏡で詳細に確認します。この検査結果によっては内視鏡治療では取りきれなかったと判断され、追加の外科手術が必要となる場合もあります。
病理検査で完全に一括切除できていると確認できれば、たとえば大腸ESDでは局所再発は約1%にとどまると報告されています。内視鏡は精密な検査ができるとともに、有効な治療でもあるのです。
大学病院ならではの強みとAIの活用
大学病院には、内視鏡も新しいものが導入されていることが多いです。たとえば、4Kを超える高解像度の内視鏡や、特殊な光を用いて粘膜表面を詳細に観察できる内視鏡などがあり、リアルタイムで顕微鏡のように拡大して見ることも可能です。
また、十二指腸腫瘍(じゅうにしちょうしゅよう)や再発したがんなど、対応が非常に難しい内視鏡治療を行うこともできます。全国から多くの患者さんをご紹介いただくのは、そのような特別な技術やノウハウが求められる治療に対応できる体制があるからでしょう。
大学病院では、治療だけでなく研究や新しい医療の開発も行います。当院では最近、AI(人工知能)を活用した内視鏡検査の研究開発と、それを使った検査を進めています。人間は集中力が続かなかったり、疲労で見落としをしてしまったりすることがありますが、AIは常に一定の精度で画像を分析します。ポリープなどの病変を見つけ出すうえで、AIは医師の診断を補助する心強い相棒のような存在になっています。
一方で、AIは偽陽性(実際には病気ではないもの)を指摘してしまうことがあり、現段階では不必要な切除につながる可能性もあるため、そこは人の目で見極めています。しかしながらAIの精度は日々向上しているので、今後さらに有用なツールになることが期待されています。
早期発見のために、まずは内視鏡検査を
内視鏡検査は、早期がんの発見と治療に直結します。喉から大腸まで、多くの消化管がんは内視鏡で治療可能であり、早期であれば命に関わることはほとんどありません。
病気が見つかることを過度に恐れる必要はありません。適切に治療すれば完治が見込め、痛みや後遺症も少なく済みます。ぜひ定期的な受診で健康を守っていただきたいと思います。
取材依頼は、お問い合わせフォームからお願いします。
リーダーの視点 その病気の治療法とはの連載一覧
- 運動中の「違和感」は受診すべき? 痛みが出る前に見抜く“オーバーユース”のサイン
- 増えている心不全――パンデミックを防ぐために必要なこととは?
- 大動脈弁狭窄症と閉鎖不全症 働き盛りの治療選択肢として知っておきたい「Ross(ロス)手術」とは
- 「寝言が増えた」「便秘が続く」は危険信号? パーキンソン病“発症10年前”からのサインと治療法
- 息切れや疲れやすさは「年のせい」ではないかも? 見逃されやすい心臓弁膜症とは
- 全身に“肉の塊”ができる指定難病「サルコイドーシス」とは
- 脳の奥が見える――AR(拡張現実)とマルチ・ハイブリッド機能が織りなす、未来型手術室「smart OR」の驚くべき世界
- 心臓のSOSを見逃さないために──狭心症の低侵襲手術「MICS CABG」とは
- 命の最後の砦、「集中治療」──ICUのキャパシティ、日本の強みと弱さとは
- お尻から血が……「痔だろう」と放置は禁物 大腸がんと痔の見分け方と「本当にすべきこと」
- 「痛くないから大丈夫」は間違い? いぼ痔の放置リスクと切らない治療法
- 脳動脈瘤は頭の中の「静かな時限爆弾」 ある日突然命を奪う「くも膜下出血」を防ぐには?
- 動悸、息切れ、夜間頻尿 国内患者100万人超――「心房細動」の見逃してはいけないサインとは
- 膝や股関節の痛みを軽減――手術支援ロボット「CORI」が切り拓く新しい人工関節治療とは
- 前立腺がん治療の新たな選択肢 切らずに機能温存を目指すTULSA治療とは?
- 手のふるえは治療できる――本態性振戦との付き合い方とは
- その膝の痛み、年のせいだと諦めないで――変形性膝関節症の誤解と治療の最前線
- 「休めば治る」症状に潜む危険 心臓が発するSOSサインと受診の目安
- 手のふるえ、実は治療できる――メスを使わない治療法、「FUS」とは?
- 日本発の治療が世界へ――オープンステントグラフト治療の開発の軌跡
- あなたの肩の痛み、四十肩ではないかも? レントゲンでも分かりにくい「腱板断裂」とは
- 「地域の大腸がん手術を守る」―高額な手術支援ロボット導入に踏み切った中規模病院の選択
- 女性がなりやすい痔とは 恥ずかしがらずに早めの受診を
- 「沈黙の病」大動脈瘤――見えないリスクと向き合うためにできること
- 手のふるえは「年齢のせい」だけじゃない 原因と治療法とは
- 日本の内視鏡技術が変えたがん治療 早期発見のための検診の重要性とは
- 喀血治療は「根治」を目指す時代へ――常識を変えた「コイル治療」という希望
- トイレットペーパーに血が――切れ痔を放置するリスクや治療とは
- その腰痛、どこで診てもらうべき? 自分に合った整形外科の医療機関の選び方とは
- 進化する「手術支援ロボット」――ロボット手術が広げる医療の可能性
- その首の痛みや腰痛、本当に手術が必要ですか? ──脊椎脊髄の病気の「早すぎるメス」を考える
- 埼玉県西部のがん治療を強化する―放射線治療装置「リニアック」導入
- 自覚症状ゼロでも進行する胃がん・大腸がん 40歳代からの「見逃さない」検診のすすめ
- 国民病と呼ばれる痔とのより正しい向き合い方―下痢と便秘に要注意
- 国産ロボット「hinotori」が拓く医療の未来―消化器手術はどう変わる?
- その咳、風邪じゃないかも? 「喘息」の正体と新しい治療とは
- 「痔かと思ったらクローン病だった」─若年層に広がる肛門の異変とは
- 「胆石」は日本人の10人に1人――症状がないまま進行する病気の見分け方と対策
- 現代は女性にとって過酷な時代? ライフスタイルの変化で婦人科の病気のかかりやすさが変化
- 「肛門が腫れて痛い……」 知られていないが患者は多い「肛門周囲膿瘍」の症状と治療法とは
- 脳腫瘍の新たな治療選択肢、開頭しない手術とは? 神経内視鏡手術の特徴を解説
- もう我慢するだけの時代ではなくなった片頭痛―新しい薬とその効果とは
- トイレでスマホは危険!? 痔核(いぼ痔)の症状・原因・治療法
- 誰にも言えないお尻の悩みに決着をー痔の3大疾患との正しい向き合い方
- 70代女性の3人に1人が骨折リスク―長寿を満喫するために知っておきたい、骨粗しょう症の予防と治療
- 心臓の低侵襲手術「MICS」とは? 適した症例や病院の選び方を知る
- より正確でより安全な手術が可能に― 人工関節置換術支援ロボットレポート 第1弾
- いぼ痔の再発を繰り返すのは排便に無頓着だから? いぼ痔の治療法や理想的な排便とは?
- 「白内障」は誰でも経験する老化現象-40歳になったら眼科受診を
- 不整脈の1つ「心房細動」新たな治療が登場―心疾患に潜む危険性 第2弾
- 胸の痛み「年のせい……」は禁物!誰にでも起こりうる突然死―心疾患に潜む危険性 第1弾
- 症状が進んだいぼ痔の治し方-切除以外の治療法を選べるのはどんなとき?
- 80歳以上のほぼ全員がかかる白内障の手術には「より安全で適切な時期」がある タイミングの見極め方とは?
- 80代女性の半分がかかる骨粗しょう症―寝たきりの原因にもなる骨折を防ぐために必要なこと
- 肛門の病気だと思ったらクローン病? 早期治療が重要なクローン病の症状と診断とは
- 座りっぱなしは要注意―いぼ痔の症状と受診タイミングとは
- 繰り返す肛門の痛みと膿、実は「痔ろう」かも? 症状・原因・治療法とは
- 患者の負担を減らす放射線治療― ガンマナイフの仕組みやメリット・デメリットを知る

