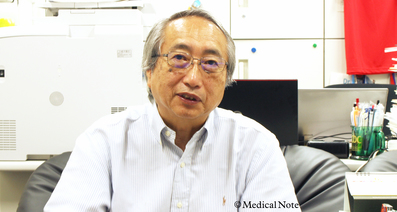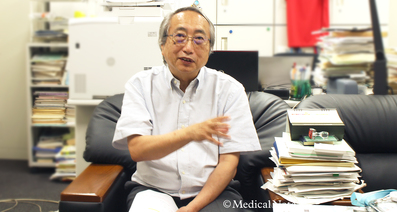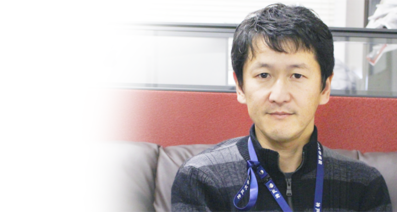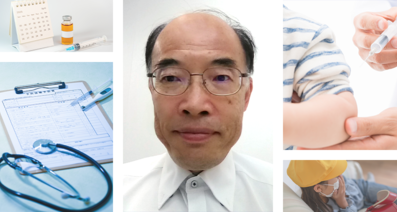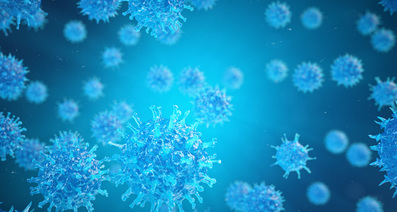感染症とは体が病原体に感染することによって、さまざまな症状が起こる病気です。感染症はその原因となる病原体が、細菌なのかウイルスなのかによって治療方法が異なります。また、体が病原体を排除するためには時間がかかることがあります。治療を行う際には病原体の識別をできる限り行い、適切な治療薬を服用したうえで、時間をかけて療養することが大切です。
今回は感染症の治療と予防方法について、千葉市立海浜病院 小児科部長兼感染症内科の阿部克昭先生にお話を伺いました。
感染症の種類
細菌性感染症、ウイルス性感染症がある
感染症には細菌由来の病気(細菌性感染症)とウイルス由来の病気(ウイルス性感染症)があります。記事1『細菌とウイルスの違いとは?』でも申し上げましたように、細菌とウイルスは生物に感染症をもたらすという共通点はあるものの、根本的に異なるものなので治療方法もそれぞれ違います。
細菌による感染症の治療方法

多くは抗菌薬の投与によって治療
細菌性感染症の多くは抗菌薬で治療します。抗菌薬とは細菌を攻撃したり、細菌のはたらきを邪魔したりすることで殺菌・静菌する薬です。細菌の細胞の多くは*1と呼ばれることが多いのですが、正確には抗菌薬と抗生物質は異なり、抗生物質ではない抗菌薬や、抗菌作用を持たない抗生物質もあります。
細菌感染症であればすべて抗菌薬が必要なわけではなく、対症療法*2で自然治癒を待つこともあります(細菌性腸炎の多くなど)。
1抗生物質……体内に侵入した細菌などの機能を抑制したり、増殖を阻害する作用を発揮したりする、微生物由来の物質。抗菌薬以外にも免疫抑制剤、抗がん剤などがある。
2対症療法……症状を和らげる治療
抗菌薬を使用するうえでの注意点
抗菌薬を処方する際は、その病気が本当に細菌性の病気なのかを見極める必要があります。その理由は大きく分けて2つです。
1つ目の理由は、ウイルス感染症の患者さんに抗菌薬を処方しないようにするためです。抗菌薬は細菌性感染症の治療薬なので、ウイルス感染症の患者さんに処方しても治療の効果はなく、むしろ副作用のみがあらわれてしまいます。しかし、現場では、感染症の原因が細菌性なのかウイルス性なのか明確に鑑別することが難しいケースがあります。その場合には細菌性であることを疑いつつ、必要に応じて抗菌薬が処方されることもあります。
2つめの理由は、抗菌薬を多用してしまうと「耐性菌(AMR*)」の増加が懸念されるからです。耐性菌(AMR)とは、ある特定の抗菌薬に対する耐性を持ち、その抗菌薬では治療できなくなってしまった細菌のことです。近年は耐性菌のなかでも、どの抗菌薬も効き目がないような「多剤耐性菌」の検出例が増えてきています。これは国際的な問題にもなっており、2016年に三重県にて行われた伊勢志摩サミットでも取り上げられました。これを受け、日本では厚生労働省が「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン」を発足し、抗菌薬適正使用を呼びかけています。
またO-157をはじめとするいくつかの細菌性の食中毒は、感染症法によって発見し次第保健所に届け出を提出することが義務付けられています。このように感染症は原因を特定して治療に望むことが大切です。
AMR……Antimicrobial Resistance(抗菌薬に対する耐性)の略
ウイルスによる感染症の治療方法
治療方法はウイルスによって異なる
記事1『細菌とウイルスの違いとは?』でも述べましたように、ウイルスは細胞がなく、自らエネルギーの生産や増殖ができるわけではないので、生物であるとはいい切れません。ウイルスは自ら他の生物の細胞に入り込み、細胞の機能を乗っ取ることで活動します。細胞の機能を止めてしまうとヒトの細胞のほうが強い障害を受けてしまうため、抗菌薬のような一般的な治療効果のある抗ウイルス薬の開発は困難です。
ウイルスのなかにもさまざまな種類があり、それぞれの構造や機能が全く異なります。どのように他の生物の細胞に入り込み、その細胞のなかでどんなはたらきをするかにあまり統一性がありません。インフルエンザや水痘(水ぼうそう)ウイルスなどについては、そのウイルスに特徴的なタンパク質の機能をブロックすることで治療する薬があります。一方、RSウイルスやアデノウイルスなど、ほとんどのウイルス感染症には治療薬がありません。
治療薬のあるウイルス感染症
治療薬のあるウイルスに関しては、その薬を服用することによって治療します。明確な治療薬があるウイルス感染症は下記のとおりです。
<2017年12月治療薬のあるウイルス感染症>
- インフルエンザ
- 水疱瘡(みずぼうそう)
- ヘルペス
- サイトメガロウイルス感染症
- B型肝炎
- C型肝炎
- HIV/AIDS など
治療薬のないウイルス感染症
治療薬のないウイルスに対しては対症療法を行い、体の免疫がウイルスを追い出す自然治癒を待ちます。前述のようにウイルスは構造やはたらきがそれぞれに大きく異なります。そのため、明確な治療薬を開発することが難しいウイルスも多く存在します。2017年12月現在は治療薬のあるウイルスのほうが数は少なく、多くは対症療法が用いられます。
感染症の予防方法
細菌性もウイルス性も予防方法は同じ
感染症は細菌性でもウイルス性でも予防方法に違いはありません。日常生活では主に下記の3点に注意するとよいでしょう。
<感染症の予防方法>
- 手洗い・うがい
- マスクの着用
- 食品の管理
- ワクチンのあるものはワクチンの摂取
感染症予防の基本は風邪予防

感染症予防の基本は、いわゆる風邪予防です。帰宅時、食事前、お手洗いのあとなど、こまめに手洗い・うがいを行うことが大切です。また、人の多いところへ行くときにはマスクの着用も大切です。
食べ物に注意

感染症のなかには食中毒や胃腸炎を引き起こすものもあります。このような感染症を防ぐためには、食品の管理が大切です。具体的には、下記のようなことに注意するとよいでしょう。
<食品管理の注意点>
- 手を洗ってから食品を触る
- 加熱調理が必要なものはきちんと加熱する
- 加熱調理が必要なものを生の状態で触ったあとは、手を洗ってから他の食材を触る
- 料理や食品を常温で保存しない
- 長期間保存せず早めに消費する など
ワクチンが開発されている感染症(VPD)もある
感染症のなかには予防ワクチンが開発されている病気もあります。予防ワクチンが開発されている病気のことを「VPD*」と呼びます。主なVPDは下記のとおりです。
<主なVPD>
ワクチンで防げる感染症は、事前の予防接種でしっかり防ぐことも大切です。
VPD……Vaccine Preventable Diseasesの略
感染症はすぐには治らない

しっかり療養し、免疫をつけることが大切
昨今は多くの病気で「早期発見、早期治療、早期回復」が謳われています。しかし、感染症の場合には早期に発見し治療を行っても、早期回復は難しい病気が多いです。そのため、感染症にかかってしまった場合は、受診後しっかり療養し、完全に細菌やウイルスを排除してから日常生活に戻るということがとても大切です。なぜなら、細菌やウイルスを保有したまま社会復帰してしまうと、周囲の人にうつしてしまう可能性があるからです。
特に子どもは免疫力が未熟で、大人より感染症にかかりやすい傾向があります。予防を心がけることはもちろん大切ですが、それでもすべてを防ぐことは難しいでしょう。また子どもの場合、視点を変えてみれば、感染症にかかりそれを克服することを繰り返すことで感染症にかかりにくい丈夫な体をつくることにもつながります。子どもの病気は急変することもしばしばあるため、変化に注意し、気になることがあれば小児科の受診をおすすめします。
原因を明らかにし適切な治療を受ける
抗菌薬は感染症の治療に大きな功績を残しました。1942年に最初の抗菌薬「ペニシリン」が医療現場で使用されるようになったことで、それまで治療が困難で多くの患者さんが命を落としていた感染症を治療できるようになりました。そのため当時、抗菌薬はあらゆる感染症の治療に用いることができるような存在でした。
しかし、感染症の原因を同定せずむやみに抗菌薬を処方することは危険です。抗菌薬の効かないウイルス性の感染症の患者さんにとっては副作用だけが残ります。さらに、抗菌薬の乱用によって、抗菌薬に耐性を持った抗菌薬の効きにくい耐性菌(AMR)が増加しています。
このようなことを防ぐためにも感染症にかかった際は、できる限り原因を特定し、治療に臨む姿勢が非常に大切です。
鎌ヶ谷総合病院 小児科 部長
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- 受診予約の代行は含まれません。
- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が34件あります
インフルエンザ家族の外出制限に関して
家族にインフルエンザ感染者がおり、自分自身も発症してしまったようです。 自分自身に関しては『発症から5日経過かつ解熱後2日』が外出制限だと認識していますが、接触者である同居家族に関しては、コロナで定めるような外出制限などがありましたでしょうか?
熱が上がったり下がったりを繰り返す
2、3日前から突然38度4分の熱が出て微熱まで下がったと思ったらまた上がってる状態です。喉や鼻はどうもないですが頭痛と寒気がひどく薬を処方していただいたがよくなった感じがしない。再度受診するべきか教えて下さい。
高熱について
三日前から38度以上の熱があります。 1日目、38.9、2日目、40.4、今日、39.7です。 家の中でも動くのがしんどくて病院にも行けてない状態です。 首や脇の下を保冷剤等で冷やしてはいるのですが熱が下がりません。今週末大事な予定があり、それまでに下げたいのですが家で出来ることって何かありますか? あと、なにかの疾患とかの可能性ってあるのでしょうか 咳も酷く呼吸が苦しいです
原因不明のあちこちの痛み
一昨日から、原因不明の身体の痛みと激痛と闘っています。 私の場合は、腕や身体中や腰や背中やたまに目や口が渇いたり症状が重い時や軽い時があります。たまに指の関節も痛いし足の関節痛もあります。睡眠や食事は問題なくです。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「インフルエンザ」を登録すると、新着の情報をお知らせします
「受診について相談する」とは?
まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。
現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。
- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。
- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。