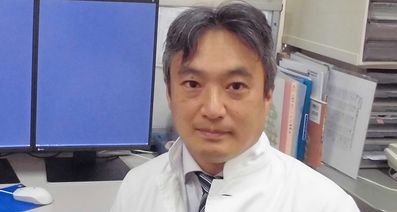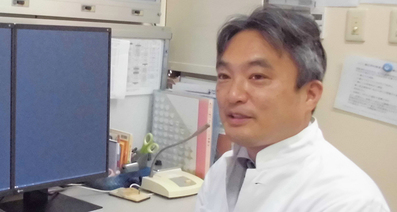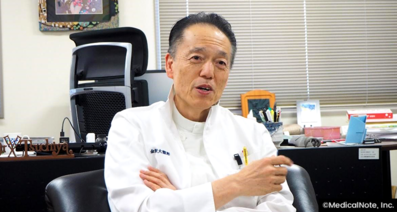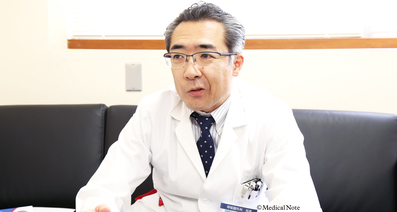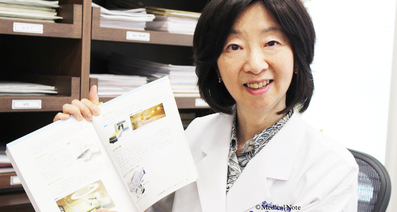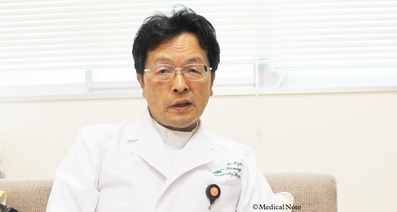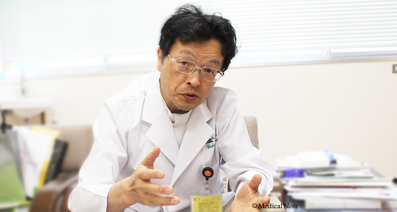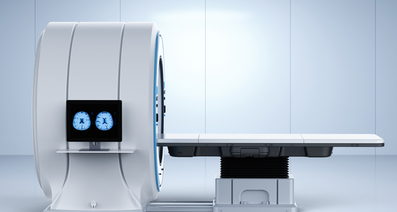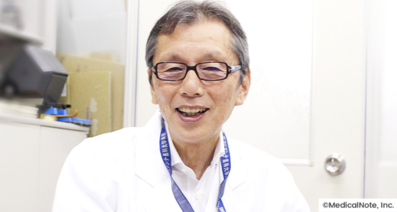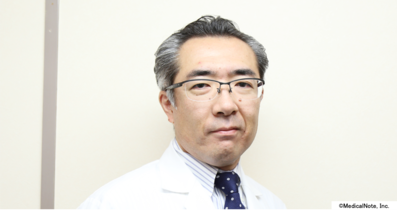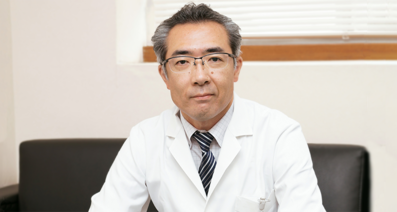肺がんの治療で今最も注目されているのが、免疫療法です。なかでも免疫チェックポイント阻害剤は肺がんの治療成績を劇的に向上させています。
今回は肺がんにおける免疫チェックポイント阻害剤とその適応条件などについて京都大学医学部附属病院 呼吸器内科 助教の金 永学先生にお話を伺いました。
免疫療法とは?
免疫療法にはさまざまな種類がある
がんの免疫療法には、民間療法的な要素の強いものから、医学的に効果が実証されているものまではさまざまなものがあります。今回は、現在肺がん治療の分野で大変注目されている医学的なエビデンスに基づいた「免疫チェックポイント阻害剤」による免疫療法についてご説明いたします。
免疫チェックポイント阻害剤とは?
がん細胞とリンパ球の結合を阻害する薬
がん細胞には体内のリンパ球と結合し、免疫の攻撃から身を守る特性があります。本来リンパ球はがん細胞を異物として認識し攻撃するのですが、がん細胞の表面のPD-L1という分子とリンパ球の表面のPD-1という分子が結合するとリンパ球の攻撃にブレーキがかかってしまうことが明らかにされています。従来の免疫療法ではリンパ球の活性を高めるなど、がん細胞に対する攻撃力を高めようとしてきましたが、思うような効果を出せませんでした。これは車でたとえるなら、ブレーキを思い切り踏んだ状態でアクセルをふかしているようなものです。
免疫チェックポイント阻害剤には、がん細胞表面のPD-L1とリンパ球表面のPD-1が結合するのを防ぐことによりブレーキを解除し、リンパ球が本来の力を発揮してがん細胞を攻撃できるようにする働きがあります。
最初に承認された免疫チェックポイント阻害剤「ニボルマブ」
肺がん治療の分野で最初に承認された免疫チェックポイント阻害剤は「ニボルマブ」です。ニボルマブはリンパ球の表面にあるPD-1という分子と結合することにより、PD-1とPD-L1が結合するのを防ぐことによって効果を発揮します。
肺がんの免疫療法の適応条件
ステージ4の肺がん患者さんの約20%に劇的効果を示す
記事1『肺がんの分子標的薬−適用条件と効果は?』でご説明した分子標的薬と同じく、免疫チェックポイント阻害剤もすべての肺がん患者さんに有効な治療方法というわけではありません。これまでに得られているデータによると、手術のできないステージ4の肺がん患者さん全体のおよそ20%に劇的な効果があるいっぽうで、およそ50%の患者さんにはまったく効果がないことがわかっています。
免疫チェックポイント阻害剤の効果のあるなしを前もって完全に予測する方法は、残念ながらまだありません。しかし、がん細胞の表面にPD-L1が多く発現している患者さんでは効果が高い傾向があることがわかっています。
免疫染色−扁平上皮がん、非扁平上皮がんのどちらの患者さんにも行う
PD-L1ががん細胞の表面にどのくらい発現しているかを調べる方法として、免疫染色による検査があります。免疫染色とは抗体を用いて特定の抗原(この場合はPD-L1)のみを検出、可視化する手法です。
免疫染色による検査は、非小細胞肺がん患者さんであればそれが扁平上皮がんであっても、非扁平上皮がんであっても行われます。ただし、非扁平上皮がんの場合にはまず先に遺伝子変異の検査を行い、分子標的薬の適応があるかどうかを調べ、その適応がなかった場合に免疫染色の検査を行います。扁平上皮がん、非扁平上皮がんの説明については記事1『肺がんの分子標的薬−適用条件と効果は?』を御覧ください。
2017年現在のガイドラインでは、免疫染色による検査でがん細胞上のPD-L1の発現が50%以上認められた場合、診断後すぐに免疫チェックポイント阻害剤*を投与することがすすめられています。一方、PD-L1の発現がそこまで多くはない患者さんの場合には、何らかの抗がん剤による治療効果を行ったあとであれば免疫チェックポイント阻害剤を使用することが認められています。
*PD-L1の発現が50%以上の患者さんに最初から投与が認められているのは、「ペムブロリズマブ」だけです。
免疫チェックポイント阻害剤の効果
長期経過も良好
免疫チェックポイント阻害剤の効果はニボルマブの第一相試験を受けた患者さんの予後によって証明されています。この試験は手を尽くしてあらゆる治療方法を行っても効果がみられず、抗がん剤治療を中心に治療されていたステージ4以降の患者さんを対象に行われました。つまり、ほとんどの患者さんは有効な治療を使い切ってしまっていたわけですが、それにもかかわらずこの第一相試験でニボルマブによる治療を受けた患者さんの5年生存率は16%でした。
もう助からないと考えられていた患者さんのうち16%がニボルマブの治療によって5年以上生存することができたわけです。
肺がんの免疫療法の副作用
副作用が起きる確率は低い
免疫チェックポイント阻害剤は抗がん剤と比較すると、副作用が軽い治療方法といわれています。実際、吐き気や抜け毛、白血球の減少といった抗がん剤特有の副作用はほとんど生じることがありません。
ただし、そこまで頻度は高くないのですが、まれに免疫関連の副作用が認められます。活発化したリンパ球が、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも攻撃を仕掛けてしまうことがあるからです。リンパ球は全身に影響を与えるため、免疫チェックポイント阻害剤の副作用は体のどこにでも起こりえます。
比較的頻度が高いものとして、甲状腺や大腸の障害があります。リンパ球が甲状腺を攻撃してしまった結果甲状腺ホルモンが出にくくなったり、大腸の粘膜を攻撃してしまい酷い下痢や大腸炎に発展したりすることがあります。
また極まれではありますが、急激な筋炎、糖尿病なども引き起こし、発見が遅れると命にかかわることもあります。
副作用がひどいときは
免疫療法による副作用がひどく生じたときはステロイドホルモン剤を処方し、過剰な免疫反応を抑えることでその症状を和らげることができます。免疫チェックポイント阻害剤は副作用が起きる頻度は低いのですが、全身いたるところに症状が現れるおそれがあるため、診療科をまたいだ診療や細かな問診、血液検査等の数値の確認が大切です。これまでと違うと感じることがあったら、必ず医師に相談しましょう。
ちなみに、ステロイドホルモン剤で過剰な免疫を抑えても、がんに対する効果が弱まることはありません。
適応拡大も検討されている免疫療法の課題
免疫チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法は2017年現在、肺がんとメラノーマ(皮膚がんの一種)、腎細胞がんにのみ承認されています。しかし今後は他のがんに対しても適応が拡大されていくことでしょう。また、がん細胞とリンパ球の結合はPD-L1とPD-1だけでなく、他の分子でも起こっているといわれています。それらを解明し、それに対する免疫チェックポイント阻害剤を開発する動きも盛んに行われています。肺がん治療の分野では現在、下記のような課題に取り組み、免疫チェックポイント阻害剤をより適切に使用する方法を検討しています。
治療期間をより短くするために
免疫チェックポイント阻害剤はある一定の期間投与すると、リンパ球ががん細胞を記憶し、みつけただけで攻撃を開始するようになるため、短い治療期間で済むのではないかといわれています。しかし、効果的な治療期間などは現段階で明らかになっていません。免疫チェックポイント阻害剤は価格も比較的高価で、患者さんやご家族への負担が大きいため、より短期間で確実な効果が得られるよう研究を行っています。
PD-L1の発現が少ないがん細胞でも劇的に効くことがある
前述の通り、現在のところ免疫チェックポイント阻害剤は免疫染色による検査でPD-L1の発現が多い患者さんに有効性が高いことがわかっています。しかし、なかにはPD-L1の発現が多くない患者さんであっても、免疫チェックポイント阻害剤が劇的に効果を示す患者さんもいらっしゃいます。つまり、免疫染色による検査で免疫チェックポイント阻害剤の効果を完全に予測することはできません。
そのため現在、免疫療法が劇的に効果を示す患者さんにどのような特徴があるのかを研究し、効果を予測するうえでどのような検査が最も有効なのかが熱心に研究されています。
免疫療法も分子標的薬も効かない患者さんのために
これからの時代、肺がんの新薬といえば免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬が主流になってくることでしょう。しかし現状としては免疫チェックポイント阻害剤も分子標的薬も効果のない患者さんもまだまだいらっしゃいます。
そのような患者さんを治療していくために、免疫チェックポイント阻害剤はさまざまな他の治療方法と組み合わせて使用することも検討されています。たとえば、免疫チェックポイント阻害剤と抗がん剤、免疫チェックポイント阻害剤と分子標的薬、あるいは免疫チェックポイント阻害剤同士を組み合わせるなど、さまざまな研究が行われているところです。今後は更に効果的な治療方法が次々に発見されることが期待されています。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
関連記事
関連の医療相談が26件あります
ガンマナイフ治療効果について
私の治療に関する質問と言うより、治療効果そのものに対する質問です。 ガンマナイフ治療について、その効果について多数の機関が情報を載せていますが、「80%〜90%の治療効果」的な表現が多いかと思います。 大変、効果のある治療と思いますが、反面、「10%〜20%は効果が出ない。」と言う事もあるのかな?と思ってしまいます。 そこで質問ですが、 ①ガンマナイフ治療後の効果判定は治療後どのくらいで実施されるのでしょうか ②残念なことに、期待した効果が出なかった場合の治療方法はどのようなものが考えられますか? 教えて頂ければ幸いです。
高齢者のがん 治療方法について
父が肺がんで、ステージⅢ、他所への転移は見られないが、同肺内での転移は見られると診断されました。高齢のため、手術及び全身への抗がん剤治療は勧めないと医師に言われ、現在、分子標的薬の検査をしている段階です。検査入院から1か月が経ち、治療するとしても、いつから始まるかわからない状態です。本人は、咳、痰の症状以外は、元気の様子ですが、このペースで治療待ちをしていて良いのか、他の治療方法も検討した方が良いのか、教えてください。
CT検査にて、肺がんと診断されました。今後の選択肢について教えて下さい。泣
東京在住、28歳会社員です。 5日前、私の大好きな大好きな広島に住む祖父が肺癌と診断されてしまいました。毎日、涙が止まりません。遠く離れた場所でコロナの感染リスクを考えると、お見舞いに行くことすら許されず、途方に暮れながらも情報収集をしていたところ、このサービスの存在を知り、この度ご質問させて頂きました。 祖父の現在の状況は下記です。 先週、高熱を出し、病院に行きPCR検査を受けたところ陰性でした。しかし、CT検査を実施したところ肺の1/3程度の影があり、肺がんだと診断されました。 詳しい検査をするため、がんセンターの呼吸器内科に転院する予定です。 これまでの病歴として、私が知ってる限りでは、10年ほど前、肺気腫(喫煙者であったが肺気腫と診断され、そこから禁煙)になり、その後、自律神経失調症と診断され、真夏の布団の中で背中が冷たいと感じるようになり、1日のほとんどをベットで過ごすようになりました。また2.3年前には、肺炎で入退院を2回しています。 まだ不確定要素も多く、判断が難しいかとは思いますが、今回は、本当に診断結果が正しいのか?そして肺がんの場合、祖父にとって最善な治療法は何か?(外科的、内科的治療含めて)など、これからの選択肢について教えて頂きたいという一心でご連絡致しました。 祖父が、今まで通り祖母と仲良く家で暮らせる日々を取り戻してあげたいという一心で、今回ご連絡させて頂いています。どうかどうかよろしくお願いいたします。
肺がんの手術と心臓弁膜症
肺がんステージ1との診断があり、来月手術予定ですが、心電図検査で心臓に異常が見つかりました。心臓弁膜症は5段階の3との診断結果ですが、肺がんの手術には問題ないので、薬や治療等何もうけていません。本当に大丈夫でしょうか?息苦しいなどの自覚症状は昨年秋ごろから続いています。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「肺がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします