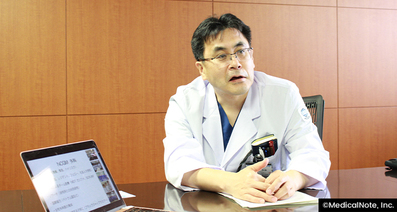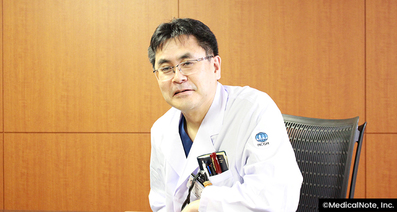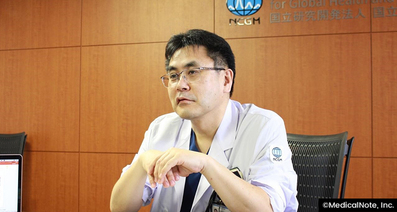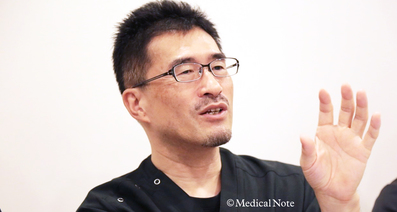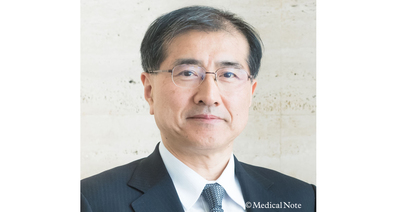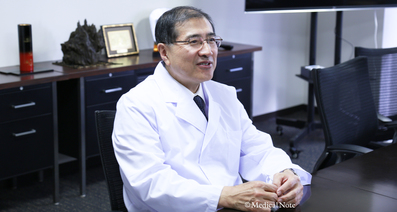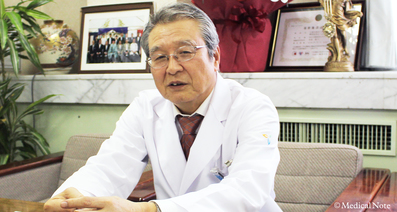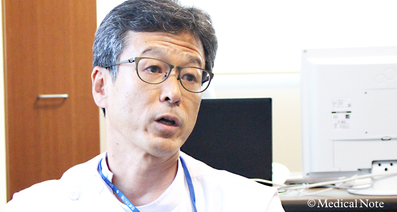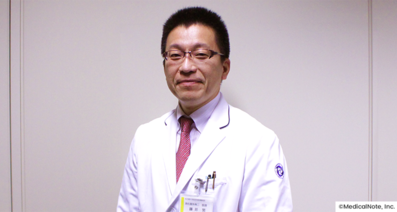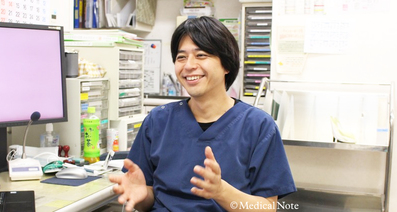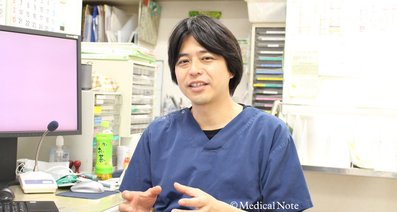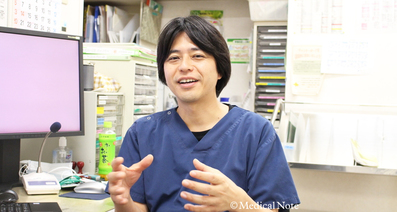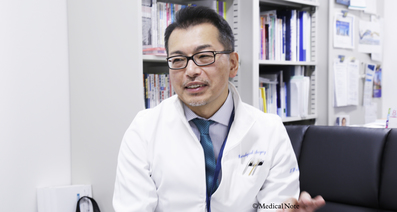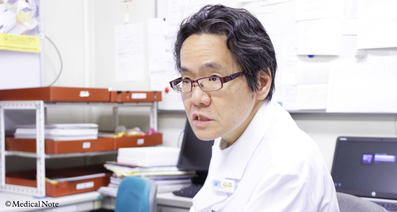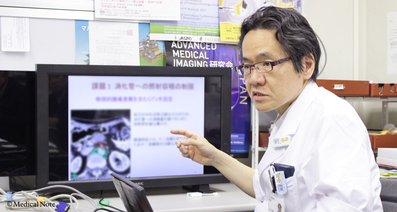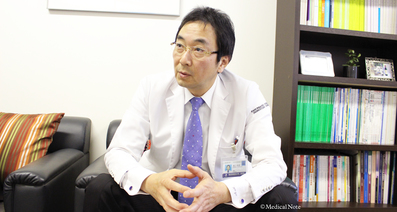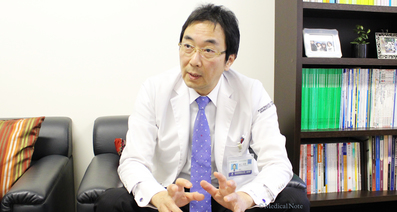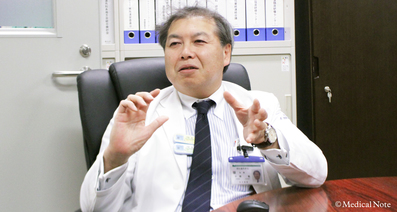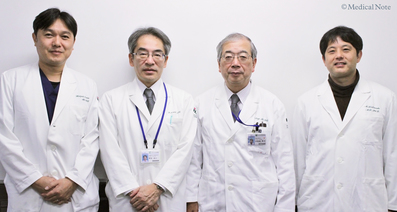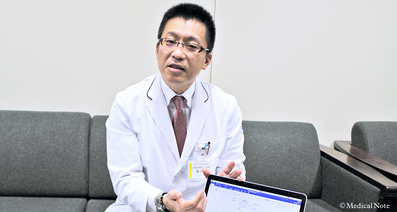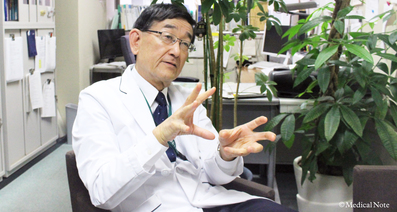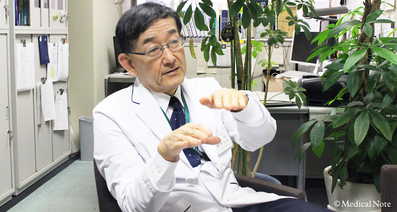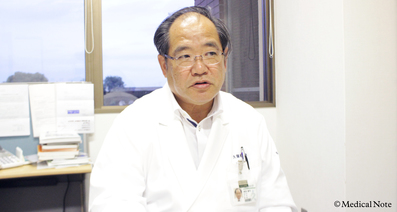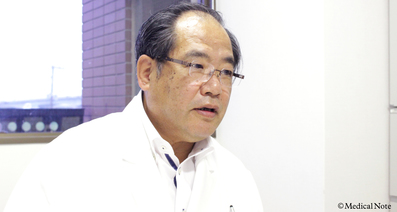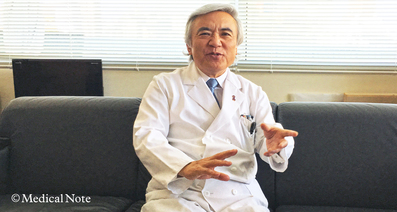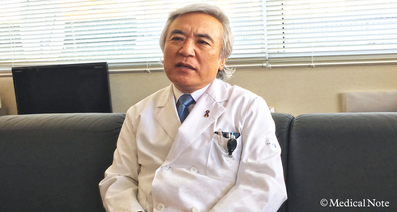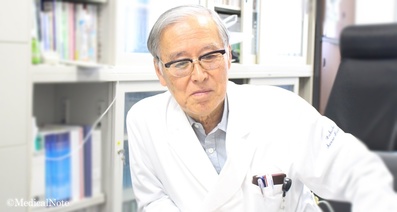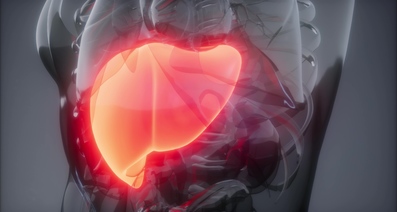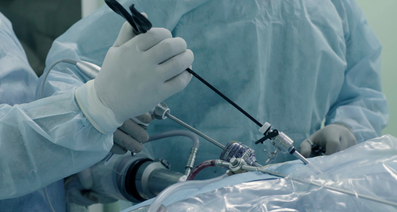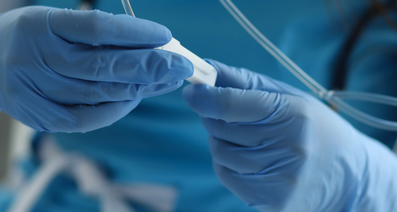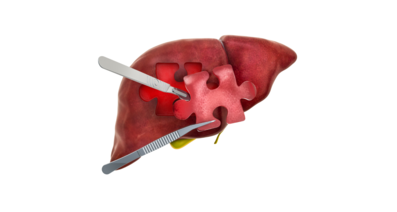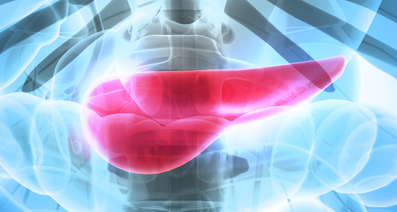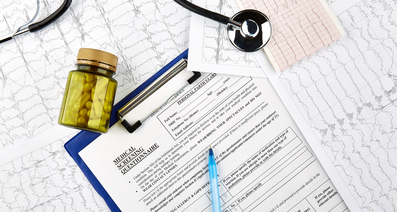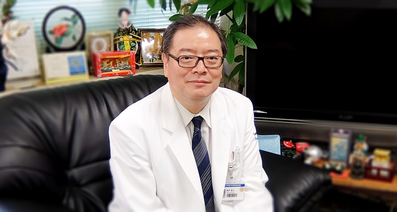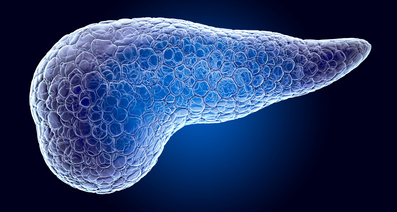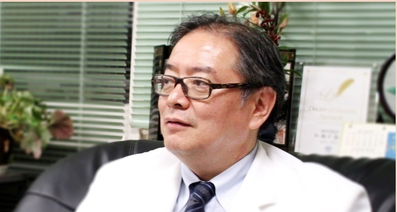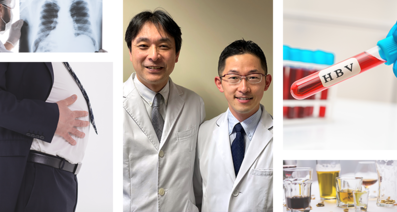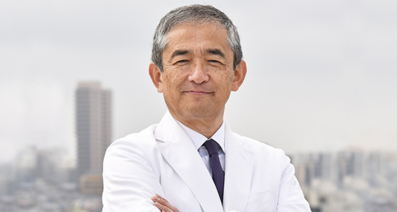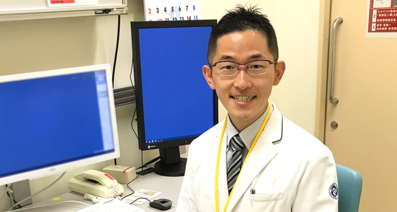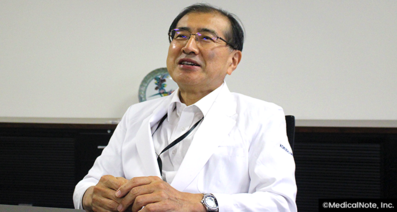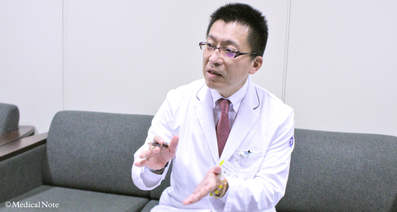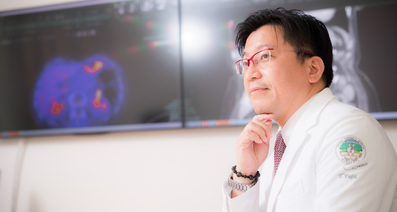がん患者さんに対するリハビリテーションには、手術後に行うものや、抗がん剤治療を行いながら同時並行で進めるものなど様々な種類があります。近年では、がんの外科的手術を受ける前にあらかじめ体力を向上させておく、「プレハビリテーション」という概念も登場し、世界的に注目を集め始めています。国際医療福祉大学三田病院のリハビリテーション科では2016年春、消化器外科とタッグを組み、日本においては先陣を切る形でプレハビリテーションの実施を開始しました。本記事では、国際医療福祉大学三田病院リハビリテーション科教授の角田亘先生に、プレハビリテーションの効果と今後の展望についてお伺いしました。
※角田亘先生は、2018年現在国際医療福祉大学成田キャンパス医学部にてリハビリテーション医学主任教授を務められています。
がん患者さんに対するリハビリテーションにはどのようなものがある?
近年、日本ではがん患者さんに対するリハビリテーションが広く行われるようになりました。一般的にリハビリテーションとは何らかの治療後に行うものを指しますが、がん患者さんに対するリハビリテーションの場合、その時期に合わせて以下の4つの分野に分類されます。
(1)手術や化学療法、放射線治療前に行う予防的リハビリテーション
(2)治療後(もしくは抗がん剤や放射線治療中)に開始される回復的リハビリテーション
(3)進行がん患者さんの運動能力の維持や改善などを目的とした維持的リハビリテーション
(4)積極的な治療を受けられなくなった患者さんの苦痛を取り除き、QOLを向上させる緩和的リハビリテーション
これが他の分野のリハビリテーションと大きく異なる点であり、三田病院でもあらゆるステージにいる患者さんのリハビリテーションを徹底して行っています。
特に、今年2016年3月からは、消化器外科と連携して、手術の前にあらかじめ患者さんの筋量や持久力を向上させる「プレハビリテーション」を開始しました。
プレハビリテーションとは? がんの手術前に「貯筋」をしておく
プレハビリテーションとは、リハビリテーションと接頭辞の“pre-”(ここでは術前の意)を組み合わせたアメリカ発祥の造語です。世界的にも非常に新しい言葉ですので、耳慣れないと感じる方も多いでしょう。
通常、がんの手術後には、体力低下などを防いで体の機能回復を順調なものとするため、早期離床とベッドサイドからの積極的なリハビリテーションが理想とされます。しかしながら、侵襲性の高い手術を受けた後にはダメージの度合いや傷の大きさ、合併症などにより、術前の計画よりも安静期間が長引いてしまうこともあります。
プレハビリテーションとは、このような術後の筋力低下に備え、体が動く時期(術前)に運動を行っていただき、足腰の筋力や持久力を高めて術後の経過を良好なものとすることを目的に行うものです。より噛み砕いていうと、“いざというときに備え、あらかじめ筋肉(と体力)を貯えておく”というものであり、私たちはこれを「貯筋(ちょきん)」と呼ぶこともあります。
実際に術前の身体のコンディションがよいほど、術後の経過もよくなるとされる研究結果も報告されています。また、当院でもプレハビリテーションの有用性は既に数値で確認できています。
がん患者さんに対するプレハビリテーション-具体的にどのような運動を行うのか

ウォーキングなどごく普通の有酸素運動や、ご自宅でもできるような筋力トレーニングを1週間~3週間かけて行っていただきます。
2~3日の運動では大きな変化はみられませんが、1週間以上継続的に実施すれば、高齢の方や体力が低下していた方には目に見える変化が現れます。日ごろ運動習慣がない方々にとっては、1週間強の簡単な運動も非常に大きな意味を成すのです。
消化器がんの手術前には必ずプレリハビリテーションを実施-三田病院の例
現在三田病院では、消化器がんの外科手術を行う患者さん全例にプレハビリテーションを行っていただくという新たな取り組みを実施しています。
スケジュールとしては、まず手術が決定したその日に必ずリハビリテーション科に来ていただき、前項でご紹介した研究報告などを示しながら術前のプレハビリテーションについてお話します。
ほとんどの患者さんは手術を行う2週間~4週間前に当科に来られますので、最低でも1週間以上のプレハビリテーションを行うことが可能です。
このような取り組みを消化器外科と連携して開始した理由は、様々ながんのなかでも消化器がんの外科手術が最も侵襲度が大きく、術後の安静期間も長くなる傾向がみられるからです。特に肝臓や膵臓を切除する手術では体の受けるダメージも大きくなるため、より強度の高いプレハビリテーションが必要となります。
もちろん、同じ消化器外科領域のがん手術でも侵襲度は違いますので、どの程度の運動を処方するかは専門家であるリハビリテーション科の医師が判断・調整します。
このように、プレハビリテーションを行うためには消化器外科とリハビリテーション科など、綿密な他科連携が不可欠です。
プレハビリテーションに対し、前向きに臨まれる患者さんが多い
当科では2016年の4月1日から7月中旬までに、およそ80人弱の患者さんがプレハビリテーションを行っています。
現時点までに当科へ来られた患者さんは、「前向きかつ自主的に運動や筋力トレーニングに取り組んでくださる方が多い」という共通点がみられます。消化器がんの患者さんは手術前には体が弱っていないことも少なくないためとも考えられますが、それ以前に元々「がんを克服しよう/手術を乗り越えて元気になろう」という闘志を持っていらっしゃる方が多いことが、効果的なプレハビリテーションの実施の助けになっていると感じます。ただし、プレハビリテーションを行う患者さんは皆さんがんの手術を控えているわけですから、今後は精神的なケアも取り入れていかねばならないと考えます。
また、私たちが推奨する自主トレが、ご自宅で取り組みやすい強度のトレーニングであることも、患者さんに受け入れていただけている理由のひとつなのではないかと考えます。
包括的なプレハビリテーションのために今後必要なもの-チーム医療による包括的なプレハビリテーション
今後の課題として、まずは消化器がんだけでなく、侵襲性の高い手術を行う場合は診療科の垣根を超えてプレハビリテーションを行えるよう、体制を整えていくことが重要だと考えます。たとえば、肺がんの手術なども種類によっては侵襲度が大きいものとなるため、呼吸器外科の先生方とも手を携えていきたいと考えます。
また、がんの手術前には筋量や持久力を高めておく「貯筋」だけでなく、栄養状態を整えておく「栄養管理」も大切です。
世界ではじめてプレハビリテーションを提唱したグループは、リハビリテーションと栄養管理を併せてプレハビリテーションと述べており、栄養管理は術後の状態をよりよいものとするために欠かせない要素であるとしています。三田病院においても、今後はリハビリテーション科のみならず、栄養士のいる栄養室との協働が必要になるでしょう。
また、プレハビリテーションの対象者は手術を控えたがん患者さんですので、前項でも触れた精神面のケアも大切です。たとえば、患者さんと触れ合う機会の多い看護師の方に、この役割を担っていただくのもよいかと考えます。
海外では(1)体の状態の管理(2)栄養管理(3)心理状態のケアの3つを併せて「包括的なプレハビリテーション」と定義する場合がありますが、日本でもこの3本柱を併せて行えるよう、医療者に対するプレハビリテーションへの認知・理解を広め、施設全体でがん患者さんを支えていける体制を作る必要があります。日本においてその先駆けを務めるのが、当院の役割ではないかと感じています。
以上のことをまとめますと、今後はリハビリテーション科のスタッフだけでなく、栄養士や看護師の方など、多職種と協力して「チーム医療」として包括的なプレハビリテーションを提供していくことが重要であると考えます。
医師の方へ
様々な学会と連携し、日々の診療・研究に役立つ医師向けウェビナーを定期配信しています。
情報アップデートの場としてぜひご視聴ください。
「膵臓がん」に関連する病院の紹介記事
特定の医療機関について紹介する情報が掲載されています。
関連の医療相談が23件あります
手術後の合併症
私の父親なのですが、今月の頭に すい臓がんの手術をしました。 術後、合併症が出なければと早く退院できますよ。と言われていた矢先に液もれを、おこし合併症が出たのでと自宅に電話が来たそうです。 ご飯を食べると、液がもれるようで、現在、点滴と水、お茶しか口に出来ずに、検査づくしの毎日を過ごしている様子。 少し食べたりしている時もあるようですが、液が出たりでなかったりで、いつ治るのかと父も不安のようです。 病室にも入れませんので、本人の様子はメールでしかわからず、母もずーっとモヤモヤ状態。 術後、2週間ぐらい経ちましたが、いつになったらご飯が食べられるようになって、退院の目処がたつのでしょうか? よろしくお願い致します。
膵臓癌の再発による肝不全に伴う腹水への対応について
妻は、昨年の5月初旬にステージ1の膵臓癌が見つかり、6月に標準的外科療法として手術をしました。その後、9月末に退院し、自宅療養をしていましたが、昨年12月に腹水が溜まりはじめ、三月初旬にCT検査をし、膵臓癌が昨年12月頃に再発したことが分かりました。一度は、三月初旬に腹水を三リットル抜いて、それから蛋白質等だけ体内に戻しました。今も腹水が溜まり続けていますが、どのタイミングで再度、腹水を抜いたら良いでしょうか。または、腹水は抜かない方がいいのでしょうか。宜しくご教授下さい。
膵臓癌手術後の癌再発について
初めて相談します。私の妻は、昨年6月に膵臓癌の切除手術をしました。ステージ1でしたが、すぐには回復せず、血栓がてきたりし、血のめぐりが悪く、色々処置し9月末に退院しました。その後、12月頃から腹水が溜まり、肝不全と門脈が詰まっていたようで今月入院しCT検査の結果、膵臓癌が再発していました。担当医は、3ヶ月から1ヶ月の余命ではと言っていました。本当にそのよう余命なのでしょうか?また、セカンドオピニオンを考えた方がよろしいでしょうか?ご教授ください。宜しくお願い致します。
すい臓がんの肝臓への転移
今年の3月にすい臓がんと診断された父親についての2回目の相談になります。 抗がん剤治療を4ヶ月ほど続けていましたが、先週のCTにより肝臓への転移が見つかりました。主治医は治療方針がかわります。とおっしゃいました。今までは抗がん剤でガンを小さくしてから手術に持っていきたいとおっしゃっていたのですがそれが転移となるとできないと。その場合はどのような治療になるのでしょうか?単に延命のための治療になるということでしょうか?すい臓がん事態は2か月前と大きさに代わりはないのに転移するものなのでしょうか?肝臓への転移によって今後どのような症状があらわれるのでしょうか?4日前に胆汁を出すために入れたお腹のチューブが詰まったため緊急で入院し、その時のCT検査で転移がわかりました。今はまだ仮で鼻からのチューブで外に胆汁をだしているためそれが落ち着いたら詳しく治療方針を説明すると言われましたが、不安でご相談させて頂きました。
※医療相談は、月額432円(消費税込)で提供しております。有料会員登録で月に何度でも相談可能です。
「膵臓がん」を登録すると、新着の情報をお知らせします